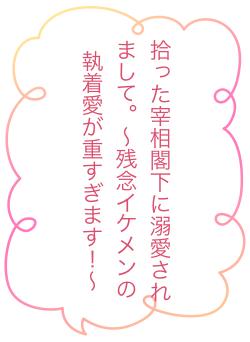(……泣いて、やるものですか)
ぎゅっと手を握りしめ、キャロラインは紫色の瞳を燃え上がらせた。
自分を糾弾してきた三人の令嬢。全員、ダーシー家には少し劣るが、名家の娘たちだ。特に真ん中の娘。彼女はダーシー家と派遣を争うタイウィン家の令嬢、ヘレナだ。ほかの二人はヘレナの取り巻きである。
おそらくキャロラインを突き飛ばしたのは彼女たちだ。騒ぎを起こし、王子の婚約者という立場をキャロラインから取り上げるため、三人で結託したに違いない。
そんなことをする隙を与えたのは、自分の落ち度だ。そして、とっさのことに呆然とし、ここまで追い詰められてしまったのも自分のミス。だが、これ以上好きにさせてなるものか。
笑え、余裕に見えるように。胸を張れ、潔白を証明するために。
ダーシー家に生まれた者として、これしきのことで折れてたまるか。
びしりと巻いた縦ロールを揺らし、キャロラインは勢いよく顔を上げる。そして強い決意を込めて、勝ち誇った顔をする三人組を睨みつけたのだが。
ひゅっと、耳の脇を何かがものすごい勢いで飛んでいく。直後、三人の娘たちの顔に、白いクリームが直撃した。
ぎょっとしてキャロラインは目を瞠り、それから慌てて振り返った。――果たして、三人組にクリームをぶつけた犯人はやはりそこにいた。