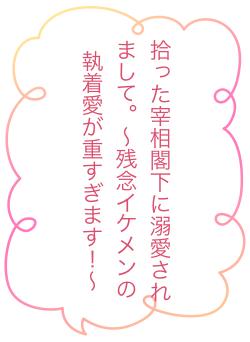「このような事態を招いたのは、たしかに私の不手際です。ですが、わざとではございませんわ! こんなことになったのは、誰かに突き飛ばされたからで……」
「まあ! この期に及んで言い訳ですの?」
「私、一部始終を見ておりましたが、誰もキャロライン様を突き飛ばしてなどおりませんわよ? ねえ? お二人もそうでしょう?」
「ええ。むしろキャロライン様が聖女様に狙いを定めて、わざと転んだように見えましたわ」
「まさか、ありえませんわ! 私、確かに……」
キャロラインは否定をするが、じわじわと嫌な空気が辺りに満ち始める。そんな彼女に追い打ちをかけるように、3人の令嬢たちはジーク王子に訴えかけた。
「私、見てしまいましたの。今宵、パーティの合間に、キャロライン様が何度も恨みの籠った目で聖女様を見つめていらっしゃるのを」
「今夜だけではありませんわ。キャロライン様は、このところずっと聖女様を気にされているんです。このままでは聖女様にジーク殿下を取られてしまうのではないかと。そのような不安を口にされているのを、私、この耳で聞きましたわ」
「よほど、聖女様の存在が我慢ならなかったのでしょう。ですから、わざと聖女様のドレスを汚すという、子供じみた暴挙に出られたのですわ」
「違います! 私は決して、そのようなことを……!」
キャロラインは声を荒げるが、ふと、自分を見つめる人々の目に気付き、すっと心の底が冷える心地がした。人々の目に浮かぶのは欺瞞の色だった。