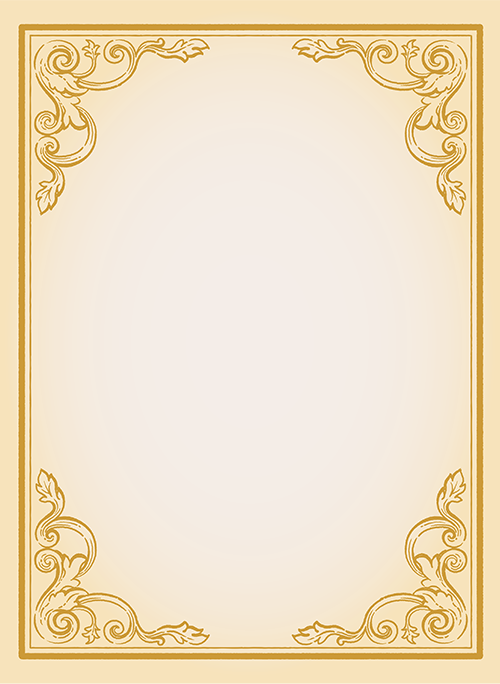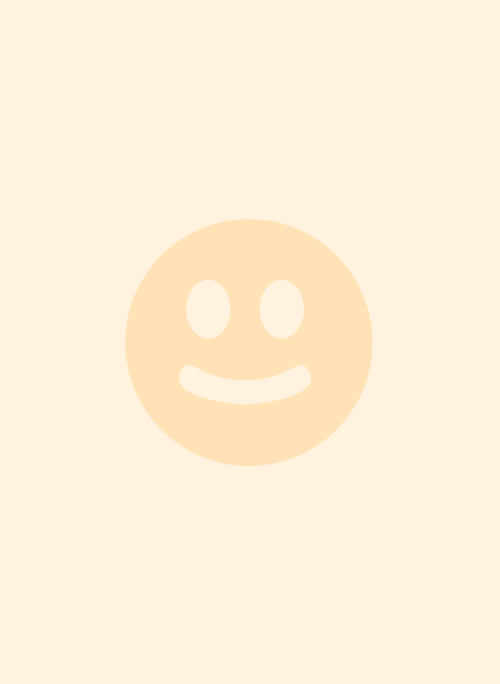この作家の他の作品
表紙を見る
ノベプラに書き溜め中。
小説家になろう、カクヨム、アルファポリス、ベリカフェ、Noraノベルに掲載予定
表紙を見る
ノベプラに読み直しナッシング書き溜め中。
小説家になろう、カクヨム、アルファポリス、ベリカフェ、魔法iらんど、Nolaノベルに掲載予定。
表紙を見る
※R-15は保険です。
※アルファポリス、カクヨム、ベリーズカフェ、Nolaノベルにも掲載します。
続きはないよー。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…
この作品をシェア
悪役令嬢は子ども食堂を始めた模様です!【WEB版】
を読み込んでいます