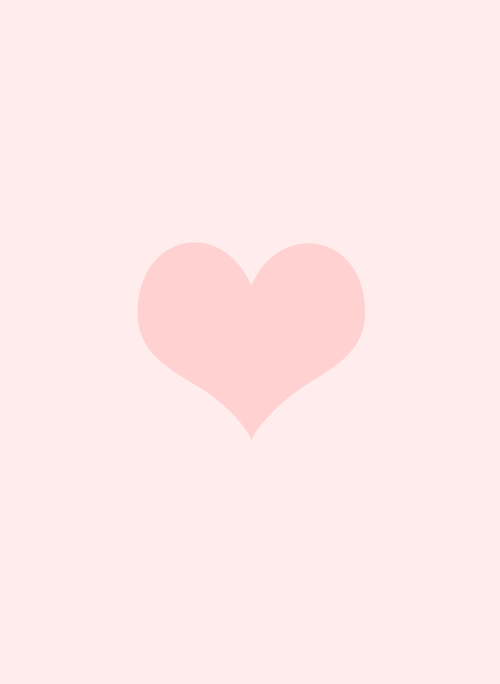赤い屋根の白い一軒家。
そのままばあちゃんを送り届けて、すぐにその場を後にしたんだけど……
あの時の相手、うちの三年だったんだ。
俺の顔もバレてる。
すぐに呼び出されて、因縁付けられた。
喧嘩は好きじゃないけど、不本意ながら場慣れはしてるから弱い方じゃない。
でも、今回は油断した。
落ちてた廃材振り回されて腕と顔に痛みが走った。
血が目に入って視界が塞がれる。
片目だけでなんとか追い払ったけど、今回はさすがに肉体的にも精神的にも辛い………。
そんな時だった。
「小池くん!」
ガラッと窓が開く音がして、自分を呼ぶ声。
辛い身体を動かして声のする方を見ると、保健室の窓を開けてこっち見てるのは、同じクラスの……成宮?
クラスでもあんまり目立たない方の娘。
でも意外にしっかり者だし、色白で髪もフワフワの……俺の中じゃ割と可愛い印象だったりする。
慌てて飛び出して来てしきりに保健室に誘ってくるけど、この時の俺はついて行く気はなかった。
俺に関わるとろくなことないから……………
そんな俺の気持ちを動かしたのは……俺を見上げる成宮の瞳だった。
ドキッ
心配そうに見上げる瞳が潤んでて、なんだかとっても可愛くて。
なんでか、こいつに心配させたくない……そう思った。
身体に力が入らなくて、思わずよろける俺を支えてくれる小さな身体。
柔らかくて細くて……でもしっかり支えてくれる。
俺みたいなのを労ってくれる、その優しさと芯の強さに心惹かれた。
この時から俺は成宮が好きになった―――――
「大輔……ちょっといいか」
親友の木村大輔。
ガキの頃から一緒にいるから気心知れた仲。
俺と違って女子にも人気がある。
「ん~?何?」
「俺、好きな奴できた」
「んごっ!?………ゲホッ、ゲホッ」
大輔の奴、飲んでたイチゴオレ………眺めてた雑誌の上に吐き出した。
それさ…俺のなんだけど。
涙目になりながら、近くにいた女子に貰ったティッシュで雑誌を拭いつつ俺を見上げる。
「ヒナタ~…なんでそんなこと、顔色ひとつ変えないで言えんだよぉ」
「変わってないか?一世一代の、嬉し恥ずかし告白なんだけど」
俺にしたら超恥ずかしい相談。
だって、今まで女の子好きになったことなんか無いから、いわば初恋。
だから当たり前だけど、どうしたらいいかなんてわかんない。
暫く考えた末、大輔に相談しようと思った訳だけどさ。
「もっとこう……ハニかむとか、頬を赤くするとか、色々あるだろ~?」
「こう?」
恥ずかしい気持ちを表そうと、ちょっと笑って見せる。
それを、ジ~ッ……と見てた大輔が残念そうに首を振る。
なんでだよ。
「……それはニヒルな笑みですな。まぁいいや、で?」
「で?って?」
「相手は誰よ」
声を潜めて寄ってくる。
なんでコイツこんなに楽しそうなんだ?
「あいつ」
チョイと俺が指差した先には……廊下側の一番後ろの席で、三人の女子達と楽しそうに笑ってる成宮がいた。
白い肌に笑顔が可愛い。
「どいつよ」
イマイチどの子だかわかってない大輔のネクタイを、おもむろに掴むとグイッと引き寄せた。
「成宮」
「うそ…っ!」
「何がうそだよ、おかしい?」
「いや……タイプ的に意外だったから。あの子すっげー大人しいぞ?」
「そうだな。でも俺のこと恐がらねぇんだ」
俺みたいなのを寄り添って支えてくれて………目と目をちゃんと合わせてくれた。
思い出す、綺麗な瞳。
「ふ~ん、まぁいいや。俺は応援するよ。ヒナタの初恋♪」
「なんか楽しそうだな………やっぱいいや」
「なんでだよぉっ。」
「おっ、何の話~?」
「タケちゃん、聞いて!ヒナタってばさ~ツレないんだよ」
「な~んだ、いつものことじゃん。痴話喧嘩だろ?」
「なんでだよ~!」
「ヒナタ、奥さんがこのように申しておりますが?」
「放っておいていいぜ」
「む~っ……」
この時、途中から会話に混ざった奴らとふざける大輔と俺を見る視線に、この時はまだ気付くことはなかった―――――――――
「うっわ………ヒナタ、外見ろよ。雨凄ぇぜ」
内緒で視聴覚室に持ち込んだ映画の干渉会。
終わって外を見れば、土砂降りの雨。
「朝は降ってなかったのに~……俺傘ないよぉ」
「俺はある」
「まぁじでぇ!ヒナタちゃん、相合い傘お願いしゃっす♪」
ニカッと八重歯を見せ笑う大輔。
調子いい奴~。
「まっ、いっけど」
「いよっしゃ♪ついでに駅前で何か食ってこうぜ……って、あれ?」
昇降口の外に目をやる大輔の視線の先。
見覚えのある後ろ姿。
フワフワの黒髪を揺らして空を見上げてるのは……成宮?
この土砂降りの中、外に出ようとしてるのがわかって、俺も慌てて……つい、その細い腕を掴んでしまった。
ぱっとその身体が振り返る。
フワリと香るシャンプーの甘い香りが鼻をくすぐる。
「小池くん?」
ビックリしたように目を見開いて見つめてくる愛しいその人を前に………どうしたらいいかわからない。
「お~、ヒナタどうした?」
そんな俺の気持ちを察してか、後ろからひょっこり顔を出した大輔は、成宮が居ることに気付かなかったかのようにビックリして見せる。
「あれ~?成宮じゃん」
そんな大輔を見上げながら親しげに喋る成宮(ちょっとヤキモチ)。
でも笑顔がやっぱり可愛くて胸がキュンとする。
成宮が傘を持ってないってわかって、一瞬こっちをチラッて見た大輔……何?
「俺全っ然反対方向に用事あるんだった。じゃ~ね♪」
止める間もなく、パシャバシャかけて行く大輔の後ろ姿を見送る。
つうか、この状況……二人きり!?
どうすれば……どうすればいいの?
「あ~……じゃ私も帰るね」
ふいにかけられた成宮の言葉。
ちょっと待って!
会話なんか思い付かないくせに……掴んだその手をすぐに離す気にはなれなかった。
「……ごめん、帰るね」
ちょっと困ったようにはにかみながら見上げてくる、その表情が超可愛くて。
胸が苦しくなる。
今まで感じたことが無い位の、異性に対する愛おしい気持ち……どうしよう。
「小池…君?」
どの位無言で見つめていたか、ハッと我に返る。
ポン
持っていた傘を開く。
せっかくのチャンスなんだ、まだ一緒に居たい。
咄嗟に思い付いたのは…………
「……送る」
「え……でも私んち、駅とは逆だよ?」
明らかに戸惑ってる。
逆に電車通学の俺の心配してくれて、歩いて帰れる距離だからって言うけど……でも、プライドにかけて引き下がりたくなかった。
「いいから……この前のお礼」
傷の手当のお礼と称して、強引にプッシュ。
少し考えてたみたいだけど、ふわっと成宮の表情が緩む。
「じゃ…お言葉に甘えちゃおっかな」
「ん…」
よっしゃ!大輔のお膳立てもあってか、思ったよりうまくいった♪
異性との始めての相合い傘は好きな人とだぜ?ラッキー過ぎじゃね~?
差し掛けた傘に怖ず怖ず入る成宮に、またもキュン☆となりながら、並んでゆっくりと歩き出す。
そのゆっくりな歩調に合わせて、俺もゆっくり歩くように気も配ったし、彼女が濡れないように傘も余計に傾けてみたりする。
好きな人の事想ってると、こういうことって、割と普通に出来るもんなんだな。
な~んて、意外な発見。
成宮の肩が触れてる腕がほんのり暖かい。
こんなチャンスは滅多にない。今、この時間がもっと長く続けばいいのにと密に祈ったけど……そううまくはいかないもんで。
「うち……ここなの」
あっという間に到着。対した会話も出来なかった自分に若干凹みながら周りを見渡すと。
見たことある景色にはた…となる。
「ここ……」
見覚えある白い壁の赤い屋根。
もしかして………
なんて考えてたら、成宮に俺の肩が雨に濡れてたの、気付かれちゃって。
仕切に家に上がるように進められた。
ウルウル瞳で頼まれると、キュンときちゃうけど。
でもそんな家に上がり込むなんて気はもうとうなくて、とりあえず家に送れたしまぁ濡れたのはいっか…って感じだったから、門口で押し問答。
ガチャッ
玄関が開く音がして、聞き覚えのある声と同時に顔を覗かせたのは…………
「ミュウかい?」
「おばあちゃん!」
やっぱり。あの時助けたばあちゃんだった―――――――
◆◆◆◆
ジャー……
俺は今、好きな人の家でシャワーをあびている。
「はぁ……」
本当はあの時、すぐに帰るはずだった。
それが、なんでこんなことになったかといえば――――――
玄関から出てきたばあちゃん。
すぐにあの時引ったくりから助けた人だってわかった。
それが成宮のばあちゃんだったなんて…………あまりの偶然に超ビックリした。
そしたら急に庭先を歩いてきてたばあちゃんの身体が傾いて………成宮の悲鳴を聞いたら、もう身体が勝手に動いてた。
ナイスキャッチだった。
走り込んで自分が下になり、ばあちゃんの小さい身体を受け止める。
首尾よく受け止めたおかげで、怪我しないで済んだばあちゃんと、その時泥で汚した全身を「綺麗にするまで帰さないから!」って泣きそうな成宮に、問答無用で家の中に引きずり込まれたって訳で。
このありえない展開に、ただ身を任せるしかない。
コンコン
「これ着替え、お兄ちゃんのだけどよかったら着て?」
「ん………」
慌てて閉められる扉を見つめる。
よくわかんないけど、とにかく渡されたTシャツとGパンを身につける。
うわっ……ピッタリじゃん。
借りたタオルで頭を拭きながら廊下に出ると、なんだかワタワタ挙動不振な成宮にリビングに通された。
「飲みなさい」
ばあちゃんが渡してくれたココア。
ふわりといい匂い、俺ココア好きなんだ♪
早速熱いところをフーッと一口。
「あん時助けてくれた兄ちゃんがまさかミュウの彼氏だったなんて……嬉しいじゃないの♪」
「ごふっ」
「ごほっ」
油断した。ばあちゃんのとんでもない爆弾発言に、成宮と俺は……同時にココアを吹き出した。
彼氏!?なんだそれ、なんだそれ、なんだそれ~!!
向かいの席で真っ赤な顔して咳込む成宮………そうだよ、迷惑じゃん。
もしかして好きな奴、いるかもしれないのに。
でもばあちゃんは納得してない風で。
いやいや、早とちりは止めてくれって。
俺の隣にちょこんと座ったばあちゃん、この前の話を大袈裟にして成宮に話す。
話しながら、俺の手をにぎにぎ………なんか、どうすればいいかわかんない。
年寄り特有の、長年家事を頑張ってきたカサカサの、でも暖かい手の平。
嫌いじゃないな、恥ずかしいけど。
「そういうことで。お礼がしたいからご飯、食べていきなさい」
「えっ……」
ふいにその手が、俺の手をがっちり掴んで離さない。
「おっ、おばあちゃん!?何言って…迷惑だよっ」
慌てた成宮が、いくら言っても、ばあちゃんの有無を言わさない。
そのがんとした態度と泣きそうな成宮の顔を見たら………断れないじゃんか。
「……ご馳走になります」
「はいはい、そうでなきゃ♪さて…何作ろうかねぇ☆」
ウッキウキ♪のばあちゃんがキッチンに向かうと、なんでか目の前の成宮が両手を合わす。
「小池くん…ごめんね~」
「別に……」
その可愛い過ぎる仕草が、またも胸を締め付ける。
息苦しい気持ちのやり場に困って、視線を窓の外に向ける。
「あ……」
「どうしたの?」
「雨止んだ」
俺の言葉に席を立った成宮が、カラッと窓を開けた。
「ホントだ」
すっかり暗くなった空にいくつか星が輝いてる。
「ご馳走さまでした」
「おや、もういいのかい?」
ビッグサイズのハンバーグにサラダ、スープ。
ご飯のおかわり進められて頑張ったけど、流石に三杯は無理。
「食が細いからそんなに痩せてるんじゃないのかぃ?それにしたって、同じ痩せてるんでもリュウはもっと食べるのにねぇ」
「お兄ちゃんは特別なの!人それぞれなんだから」
「そうかねぇ………まぁいいさ。これも食べなさい」
ばあちゃんが運んできたのはデザートのケーキ……ヤバイぞ、腹一杯。
◆◆◆◆
「駅まで送るよ」
「いい。もう暗いから」
「自転車だから大丈夫だよ」
外は真っ暗。こんなとこを女の子一人で帰せない。
首を振ったけど、がんとして譲らないのはばあちゃん似か。
「……俺こぐから、後ろ乗って」
もうこうなったら早く帰すほかない。諦めて、後ろを指差す。
まぁ、二人乗りなんて願ってもないチャンスなんだけどさ。
おずおずと後ろに乗る成宮。
肩に感じる小さな手の温もりと自転車にかかる僅かな重さが、なんだかこそばゆい。
「お邪魔しました」
「はいはい、またおいで」
軽く会釈して、上機嫌で手を振るばあちゃんを残して勢いよくペダルを漕ぐ。
「……ちゃんと捕まってて」
「うん」
好きな人とこんな近くにいるなんて信じられない。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
どうしても入りたくて頑張った第一希望の会社になんとか内定貰えた。大学を卒業、新しく始まる社会人生活。
ウキウキ♪………のはずじゃなかったっけ?
最初の方に色々表記ありますが、他意はありません。
表紙を見る
私が好きになったのは―――
隣に住む同い年の幼なじみ高広(たかひろ)。
クラスで一番小さくて…………
勇気と正義感は人一倍…………
そんな小さな巨人に恋してます―――――――
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…