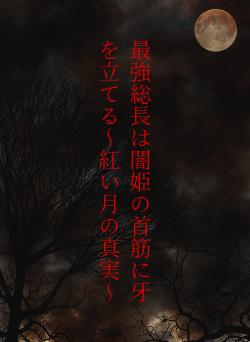「そういうのは彼女にやってあげたほうが……」
「だから、今の彼女は雨音だよ。って、どうしたの?」
「え?」
片桐くんが不思議そうに私の顔を見ていた。
ハッと気がつくと、手には何やら雫らしきものが……って、これは涙?
「安心したら気が抜けたんだね。さっきは怖い思いをさせてごめん」
「片桐くんが謝ることなんてないから」
そっか、私は怖かったんだ。片桐くんに言われて、やっと気付いた。
言われてみれば、複数の女子に囲まれて、ひどい言葉をかけられるのは今まで体験したことなかったし、それが年上だったら、なおさら恐怖は増すわけで。
「今回のことは俺のせいだから。今後は、あんな危険な目に遭わせないように俺が雨音を守るから」
そういって私の頭を撫でる。優しい触り方。まるで壊れものを扱うみたい。
どうしてだろう。撫でられる度に怖かった気持ちが嘘みたいに消えていくのは。
「ありがとう」
朝はすぐに出てこなかった言葉。だけど、今は素直に感謝の気持ちを片桐くんに伝えることができた。
「どういたしまして。でも、忘れてない?」
「な、何を?」
一体なんのこと?と、私は首を傾げた。
「俺は雨音の弱みを握ってるんだよ」
黒い笑みをした片桐くん。私を脅してきたときと同じ顔をしている。
「なっ……!」
「そんなに警戒しないで。フッ……あははっ。雨音は本当に退屈しないね。今まで付き合ってきた女の子とは、また違う魅力があって、こういうのも悪くないかも」
片桐くんがお腹を抱えて笑ってる。なんだか楽しそう。
私のことをからかっていて腹が立つはずなのに、今は片桐くんの笑顔を見て不覚にもカッコいいと思ってしまった。
「だから、今の彼女は雨音だよ。って、どうしたの?」
「え?」
片桐くんが不思議そうに私の顔を見ていた。
ハッと気がつくと、手には何やら雫らしきものが……って、これは涙?
「安心したら気が抜けたんだね。さっきは怖い思いをさせてごめん」
「片桐くんが謝ることなんてないから」
そっか、私は怖かったんだ。片桐くんに言われて、やっと気付いた。
言われてみれば、複数の女子に囲まれて、ひどい言葉をかけられるのは今まで体験したことなかったし、それが年上だったら、なおさら恐怖は増すわけで。
「今回のことは俺のせいだから。今後は、あんな危険な目に遭わせないように俺が雨音を守るから」
そういって私の頭を撫でる。優しい触り方。まるで壊れものを扱うみたい。
どうしてだろう。撫でられる度に怖かった気持ちが嘘みたいに消えていくのは。
「ありがとう」
朝はすぐに出てこなかった言葉。だけど、今は素直に感謝の気持ちを片桐くんに伝えることができた。
「どういたしまして。でも、忘れてない?」
「な、何を?」
一体なんのこと?と、私は首を傾げた。
「俺は雨音の弱みを握ってるんだよ」
黒い笑みをした片桐くん。私を脅してきたときと同じ顔をしている。
「なっ……!」
「そんなに警戒しないで。フッ……あははっ。雨音は本当に退屈しないね。今まで付き合ってきた女の子とは、また違う魅力があって、こういうのも悪くないかも」
片桐くんがお腹を抱えて笑ってる。なんだか楽しそう。
私のことをからかっていて腹が立つはずなのに、今は片桐くんの笑顔を見て不覚にもカッコいいと思ってしまった。