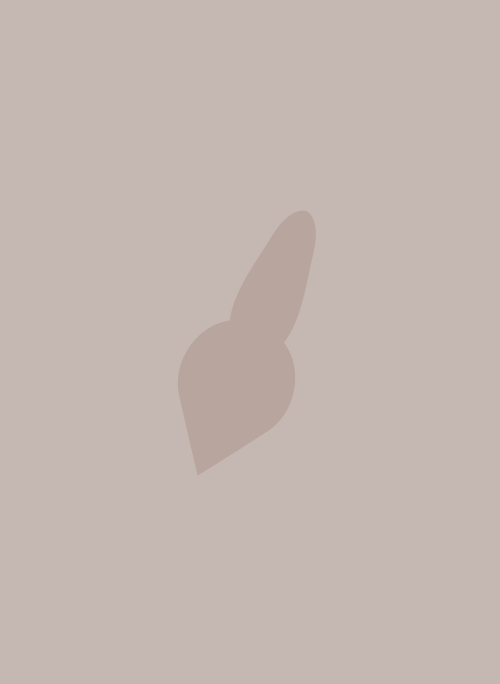第一章 神風とお菓子
俺はまだ生まれたてで兄達はまだ幼い頃,両親は死んだ
死因はトラックに轢かれ即死だったそう
爺ちゃん婆ちゃんが言うには
「とても素敵な人達だった」
だそうだ
俺は全く分からないから涙すら出なかったが寂しさと苦しさとぐちゃぐちゃな感情に包み込まれる
そんな時
一冊の本に出会った
ページを開くとそれはお菓子の本
キラキラ輝いて見えたそれは心を癒してくれた様に感じた
これが俺とお菓子の出会い
「後はコーヒーがいるな」
朝早くから俺は起きるのが習慣で朝食を作るのも俺担当
毎日やっているから慣れてしまったのも事実
「兄貴!起きろってんだろ!」
俺の兄を紹介しよう
「うっせーな!分かっとるわ!」
長男
皇帝都 読み方は すめらぎ・ていと
銀髪ピアスたくさん付けているが地毛が銀髪なので気にすんな
性格はまぁ,優しいな俺とか家族には
「たく,神風~」
そして俺に抱きつくこいつは
次男
皇翡翠 読み方は すめらぎ・ひすい
銀髪ピアスなし
性格は帝都と似ているが甘えん坊だな
「何だ,邪魔なんだが?」
俺は皇神風 読み方は すめらぎ・かみかぜ
銀髪ピアスなし
性格は兄二人を足して甘えを抜いて割った感じだ
俺はスタスタと歩き机に朝食を並べていく
翡翠はむすっとしつつも手伝ってくれる
「ありがとな」
俺は微笑み翡翠の頭を撫でる
まるでどっちが兄か妹かわからない様だな
「おぅ!」
翡翠は嬉しそうに座り待ってくれている
「おい!神風テメェ俺にもしろよ!」
帝都が俺の手を掴み頭に乗っけた
俺は溜息を吐きながらも左右に手を動かす
「仕方ねぇな」
二人は俺の前だと大人しくして優しい兄になる
だが
外に出ると
外見からか怖がられ逆に怖がらしている
俺は学校へ行くがほとんど分かるから授業は出てない分プリントで終わらしているのだ
「今日は帝都の好きな物を作ってみた」
朝食を見て帝都は嬉しそうに
「マジか!」
と言った
「翡翠のはまた明日な」
翡翠の方を見ると翡翠はその言葉に
「おぅ!」
と元気に返事した
俺は祖父母のを呼びに行く
「爺ちゃん,婆ちゃん朝飯だ」
「「おぉ,かー君」」
俺のことをかー君と呼ぶのは爺ちゃんと婆ちゃんだけだ
俺は微笑み二人を待つ
二人はいそいそと片付けこちらへ歩いて来る
「かー君,おはよう」
爺ちゃんの皇善 読み方はすめらぎ・ぜんと言う
「ん,はよ」
「かー君今日は何を作ったんだい?」
婆ちゃんの皇嶺 読み方はすめらぎ・れいと言う
「今日は帝都の好きな物を作った」
俺の言葉に爺ちゃん婆ちゃんは頷きながら俺の頭を撫でる
俺は真っ赤になって
「何すんだよ………」
と言いつつもその手を振り払うことはしない
「今日もお菓子楽しみにしとるよ」
俺を見て微笑む爺ちゃん
「!」
俺はバット顔をあげる
「かー君の作るお菓子は格別よ」
婆ちゃんも嬉しそうに頬に手を当て呟く
「楽しみにしてろよ………絶対美味いから」
俺はワクワクしながら食卓につく
全員で食卓を囲むのが約束だから
俺たちはそうしている
食器を片付け
いよいよ
兄達が慌てる時間になる
「今日会議だってんだろ!」
おいおい,今日大変だな
「知ってるわ!行くぞ!」
帝都が俺に顔を向けて手を振る
「おう!行って来ます!」
翡翠も手を振る
「行って来い」
俺は片手で手を振り見送った
爺ちゃん婆ちゃんが楽しみにしている菓子を作るために
俺は準備をする
今の季節は夏だ
暑くも寒くもない時間だから錦玉羹の基本菓子
さざ波
を作るか
さざ波は寒天と水を煮溶かし砂糖を加えて作る夏の代表菓子
色んなバリエーションができて割と楽だ
ただ砂糖の量で透明感が出なくなったりする
菓子で言うと和菓子だな
ついでにもう一つ作る
醤油で作るフィナンシェ
フィナンシェは卵白だけ使うから割と重宝している
菓子で言うと洋菓子だな
「さざ波を固めている間にフィナンシェか」
まるで動画を見ているかの様に早く,丁寧に作業が終わっていく
俺は慣れているからだと思っているが爺ちゃん達にとっては難しとの事だ
「し!出来た!」
さざ波が固まったのとフィナンシェが焼けたのを見て微笑む
と
同時に二人の声が聞こえる
「「かー君まだかい?」」
俺は嬉しそうに
「出来たぞ!」
と
言った
「召し上がれ」
「「頂きます!」」
パクリと食べる二人
爺ちゃんは洋菓子が好きだからフィナンシェを
婆ちゃんは和菓子が好きだからさざ波を
二人はニコニコと微笑み
「「美味しい」」
と
俺を見て笑った
「良かった」
俺はほっとして笑う
「じゃあ学校行って来るな!」
俺が靴を履いていると後ろから見送る二人
「うむ!行ってらっしゃい」
「気を付けてね?」
「あぁ!」
俺は片手を上げて左右に振る
こうして
俺の1日がやっと始めるのだ
俺はまだ生まれたてで兄達はまだ幼い頃,両親は死んだ
死因はトラックに轢かれ即死だったそう
爺ちゃん婆ちゃんが言うには
「とても素敵な人達だった」
だそうだ
俺は全く分からないから涙すら出なかったが寂しさと苦しさとぐちゃぐちゃな感情に包み込まれる
そんな時
一冊の本に出会った
ページを開くとそれはお菓子の本
キラキラ輝いて見えたそれは心を癒してくれた様に感じた
これが俺とお菓子の出会い
「後はコーヒーがいるな」
朝早くから俺は起きるのが習慣で朝食を作るのも俺担当
毎日やっているから慣れてしまったのも事実
「兄貴!起きろってんだろ!」
俺の兄を紹介しよう
「うっせーな!分かっとるわ!」
長男
皇帝都 読み方は すめらぎ・ていと
銀髪ピアスたくさん付けているが地毛が銀髪なので気にすんな
性格はまぁ,優しいな俺とか家族には
「たく,神風~」
そして俺に抱きつくこいつは
次男
皇翡翠 読み方は すめらぎ・ひすい
銀髪ピアスなし
性格は帝都と似ているが甘えん坊だな
「何だ,邪魔なんだが?」
俺は皇神風 読み方は すめらぎ・かみかぜ
銀髪ピアスなし
性格は兄二人を足して甘えを抜いて割った感じだ
俺はスタスタと歩き机に朝食を並べていく
翡翠はむすっとしつつも手伝ってくれる
「ありがとな」
俺は微笑み翡翠の頭を撫でる
まるでどっちが兄か妹かわからない様だな
「おぅ!」
翡翠は嬉しそうに座り待ってくれている
「おい!神風テメェ俺にもしろよ!」
帝都が俺の手を掴み頭に乗っけた
俺は溜息を吐きながらも左右に手を動かす
「仕方ねぇな」
二人は俺の前だと大人しくして優しい兄になる
だが
外に出ると
外見からか怖がられ逆に怖がらしている
俺は学校へ行くがほとんど分かるから授業は出てない分プリントで終わらしているのだ
「今日は帝都の好きな物を作ってみた」
朝食を見て帝都は嬉しそうに
「マジか!」
と言った
「翡翠のはまた明日な」
翡翠の方を見ると翡翠はその言葉に
「おぅ!」
と元気に返事した
俺は祖父母のを呼びに行く
「爺ちゃん,婆ちゃん朝飯だ」
「「おぉ,かー君」」
俺のことをかー君と呼ぶのは爺ちゃんと婆ちゃんだけだ
俺は微笑み二人を待つ
二人はいそいそと片付けこちらへ歩いて来る
「かー君,おはよう」
爺ちゃんの皇善 読み方はすめらぎ・ぜんと言う
「ん,はよ」
「かー君今日は何を作ったんだい?」
婆ちゃんの皇嶺 読み方はすめらぎ・れいと言う
「今日は帝都の好きな物を作った」
俺の言葉に爺ちゃん婆ちゃんは頷きながら俺の頭を撫でる
俺は真っ赤になって
「何すんだよ………」
と言いつつもその手を振り払うことはしない
「今日もお菓子楽しみにしとるよ」
俺を見て微笑む爺ちゃん
「!」
俺はバット顔をあげる
「かー君の作るお菓子は格別よ」
婆ちゃんも嬉しそうに頬に手を当て呟く
「楽しみにしてろよ………絶対美味いから」
俺はワクワクしながら食卓につく
全員で食卓を囲むのが約束だから
俺たちはそうしている
食器を片付け
いよいよ
兄達が慌てる時間になる
「今日会議だってんだろ!」
おいおい,今日大変だな
「知ってるわ!行くぞ!」
帝都が俺に顔を向けて手を振る
「おう!行って来ます!」
翡翠も手を振る
「行って来い」
俺は片手で手を振り見送った
爺ちゃん婆ちゃんが楽しみにしている菓子を作るために
俺は準備をする
今の季節は夏だ
暑くも寒くもない時間だから錦玉羹の基本菓子
さざ波
を作るか
さざ波は寒天と水を煮溶かし砂糖を加えて作る夏の代表菓子
色んなバリエーションができて割と楽だ
ただ砂糖の量で透明感が出なくなったりする
菓子で言うと和菓子だな
ついでにもう一つ作る
醤油で作るフィナンシェ
フィナンシェは卵白だけ使うから割と重宝している
菓子で言うと洋菓子だな
「さざ波を固めている間にフィナンシェか」
まるで動画を見ているかの様に早く,丁寧に作業が終わっていく
俺は慣れているからだと思っているが爺ちゃん達にとっては難しとの事だ
「し!出来た!」
さざ波が固まったのとフィナンシェが焼けたのを見て微笑む
と
同時に二人の声が聞こえる
「「かー君まだかい?」」
俺は嬉しそうに
「出来たぞ!」
と
言った
「召し上がれ」
「「頂きます!」」
パクリと食べる二人
爺ちゃんは洋菓子が好きだからフィナンシェを
婆ちゃんは和菓子が好きだからさざ波を
二人はニコニコと微笑み
「「美味しい」」
と
俺を見て笑った
「良かった」
俺はほっとして笑う
「じゃあ学校行って来るな!」
俺が靴を履いていると後ろから見送る二人
「うむ!行ってらっしゃい」
「気を付けてね?」
「あぁ!」
俺は片手を上げて左右に振る
こうして
俺の1日がやっと始めるのだ