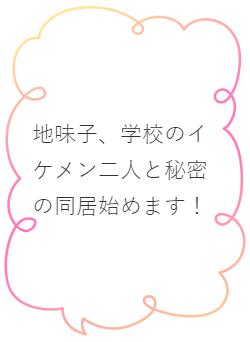『・・・・・・』
『お母さん?体調悪いの?』
流石に俺も母さんのおかしな様子に気づく。
心配になって下からお母さんの顔を覗き込む。
『大丈夫・・・?わっ』
突然母さんにギュッと抱きしめられて声が出た。
強い力で母さんは俺を抱きしめる。
『悠理、ごめんね・・・。本当にごめん・・・』
『おかあ、さ・・・?』
段々ろれつが回らなくなってきた。
そしてそのまま、俺は母さんに抱きしめられたまま眠ったんだ。
どれくらいの時間がたったんだろうか。
『・・・い、おい起きろ!』
『痛っ!』
『なんで酒がねえんだよ!それに樹里はどこだ!』
父に思いっきり蹴られて目が覚める。
状況が理解できないまま、俺は起き上がった。
助けを求めるために母さんを探してきょろきょろと周りを見て・・・俺は絶望した。
『お母、さん・・・?』
『だから、なんで樹里がいねえのかっつってんだろ!耳ついてんのか、あぁ!?』
間髪入れず父の怒号が飛んでくる。
そこには、母さんの姿はなかった。
父の話から推測するに、この家のどこにも母さんはいないんだろう。
どうして・・・?
買い物はいつも俺が帰ってくる前に行ってる。
だから、買い物だとは思えなかった。
俺は混乱するばかり。
そんな俺に、父は怒鳴り続ける。
もう何が何だかわからなかった、脳が理解するのを拒んでいた。
こうして、俺の前から母は消えた。
俺のランドセルには母さんからの手紙が入っていた。
《悠理を置いて私だけ逃げること、本当にごめんなさい。あの人とこれ以上一緒に過ごしていくのはもう限界なんです。貴方と逃げることも考えましたが、それも嫌なんです。貴方のあの人に似てる髪の毛の癖が嫌、貴方のあの人に似てる口元が嫌。こんなこと、とても身勝手だってわかってるんです。だって悠理は何も悪くないから、おかしいのは私なんです。こんな母親でごめんなさい。樹里》
その手紙を読んだ瞬間、俺は後頭部を思いっきり重い鈍器で殴られたかのようなショックを受けた。
目に涙がたまっていく。
「ゔ、うぅ」
意味の分からない嗚咽が口から零れる。
母さんは、俺を置いて逃げた。
それも、最悪の手紙を残して。
俺自身を否定するような手紙を残して。
こんな手紙なら、何も残さず出て行ってくれたほうが良かった。
母さんは、俺が父に似ているという残酷な現実を突きつけて俺の前から去ったんだ。
『お母さん?体調悪いの?』
流石に俺も母さんのおかしな様子に気づく。
心配になって下からお母さんの顔を覗き込む。
『大丈夫・・・?わっ』
突然母さんにギュッと抱きしめられて声が出た。
強い力で母さんは俺を抱きしめる。
『悠理、ごめんね・・・。本当にごめん・・・』
『おかあ、さ・・・?』
段々ろれつが回らなくなってきた。
そしてそのまま、俺は母さんに抱きしめられたまま眠ったんだ。
どれくらいの時間がたったんだろうか。
『・・・い、おい起きろ!』
『痛っ!』
『なんで酒がねえんだよ!それに樹里はどこだ!』
父に思いっきり蹴られて目が覚める。
状況が理解できないまま、俺は起き上がった。
助けを求めるために母さんを探してきょろきょろと周りを見て・・・俺は絶望した。
『お母、さん・・・?』
『だから、なんで樹里がいねえのかっつってんだろ!耳ついてんのか、あぁ!?』
間髪入れず父の怒号が飛んでくる。
そこには、母さんの姿はなかった。
父の話から推測するに、この家のどこにも母さんはいないんだろう。
どうして・・・?
買い物はいつも俺が帰ってくる前に行ってる。
だから、買い物だとは思えなかった。
俺は混乱するばかり。
そんな俺に、父は怒鳴り続ける。
もう何が何だかわからなかった、脳が理解するのを拒んでいた。
こうして、俺の前から母は消えた。
俺のランドセルには母さんからの手紙が入っていた。
《悠理を置いて私だけ逃げること、本当にごめんなさい。あの人とこれ以上一緒に過ごしていくのはもう限界なんです。貴方と逃げることも考えましたが、それも嫌なんです。貴方のあの人に似てる髪の毛の癖が嫌、貴方のあの人に似てる口元が嫌。こんなこと、とても身勝手だってわかってるんです。だって悠理は何も悪くないから、おかしいのは私なんです。こんな母親でごめんなさい。樹里》
その手紙を読んだ瞬間、俺は後頭部を思いっきり重い鈍器で殴られたかのようなショックを受けた。
目に涙がたまっていく。
「ゔ、うぅ」
意味の分からない嗚咽が口から零れる。
母さんは、俺を置いて逃げた。
それも、最悪の手紙を残して。
俺自身を否定するような手紙を残して。
こんな手紙なら、何も残さず出て行ってくれたほうが良かった。
母さんは、俺が父に似ているという残酷な現実を突きつけて俺の前から去ったんだ。