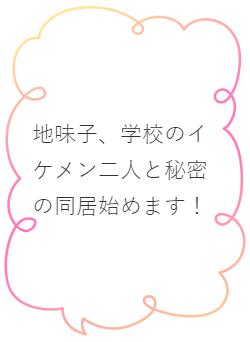「‥‥‥そっか」
また、沈黙が広がる。
私は答えを間違えたのだろうか。
不安になって無意味に視線をさまよわせる。
「これから先のことは僕の独り言だと思って聞いて欲しいんだけど」
やっと千晴くんが口を開く。
私は千晴くんをじっと見つめた。
【千晴side】
「僕、ゲイなんだ」
僕が短く告げると、真紘は目を見開いた。
‥‥‥いつまで経っても、これをカミングアウトするのは怖い。
「ゲイって、あの‥‥‥」
「そう、僕、男の人が好きなの」
真紘は僕をじっと見る。
僕は真紘の目を見つめ返して、昔話をした。
きっかけなんて、なかった。
気づいたときからいつも好きになる相手は男子で。
初恋は、隣の家に住んでいるお兄さん。
その次は、同級生。
僕はまだ小さかったし、自分が周りと違うことに気づいてなかったし、その頃は別に女の子に対して嫌悪感もなかった。
でも、母親は違ったみたいで。
僕が報告することや、相談を聞いているうちに、僕がゲイだってわかったみたい。
それから、母親は僕に冷たくなった。
『どうしてこんなおかしな子を産んだのかしら』
僕を見るたびにそう言っていた。
僕じゃなく、妹を可愛がった。
僕を見れば、『病院に行こう?』といつも言ってきた。
まだ僕は状況が飲み込めてなくて、母親について回った。
さらに母親は僕のことを気持ち悪がる。
妹も、何が起こってるのかわからないのに、それを真似した。
二人は僕を見なくなった。
小さい僕には、一人で家を離れて単身赴任していた父親に報告する術もなかった。
僕は一人になったんだ。
小学校中学年に上がったとき、転機が訪れた。
良い意味とも、悪い意味とも取れる転機。
ママ友達の情報網とはすごいもので、もう殆どのクラスの子に『あの子はおかしいから、関わっちゃダメよ』という言いつけが回っていた。
皆、まだ同性愛異性愛を気にしない、理解できない年だったというのもあって、不思議がられはしたけど、顔だけは人より良かった僕の周りから人がいなくなることはなかった。
そんな時、転校生が来たんだ。
僕とその子は隣の席になった。
明るくて、よく笑う子で、見ているだけでこっちまで笑顔になれるような子で、僕はその子が好きだった。
でも、やっぱりその好きは恋愛対象としての好きではなくて。
僕はその頃には周りと自分が違うということがわかっていた。
また、沈黙が広がる。
私は答えを間違えたのだろうか。
不安になって無意味に視線をさまよわせる。
「これから先のことは僕の独り言だと思って聞いて欲しいんだけど」
やっと千晴くんが口を開く。
私は千晴くんをじっと見つめた。
【千晴side】
「僕、ゲイなんだ」
僕が短く告げると、真紘は目を見開いた。
‥‥‥いつまで経っても、これをカミングアウトするのは怖い。
「ゲイって、あの‥‥‥」
「そう、僕、男の人が好きなの」
真紘は僕をじっと見る。
僕は真紘の目を見つめ返して、昔話をした。
きっかけなんて、なかった。
気づいたときからいつも好きになる相手は男子で。
初恋は、隣の家に住んでいるお兄さん。
その次は、同級生。
僕はまだ小さかったし、自分が周りと違うことに気づいてなかったし、その頃は別に女の子に対して嫌悪感もなかった。
でも、母親は違ったみたいで。
僕が報告することや、相談を聞いているうちに、僕がゲイだってわかったみたい。
それから、母親は僕に冷たくなった。
『どうしてこんなおかしな子を産んだのかしら』
僕を見るたびにそう言っていた。
僕じゃなく、妹を可愛がった。
僕を見れば、『病院に行こう?』といつも言ってきた。
まだ僕は状況が飲み込めてなくて、母親について回った。
さらに母親は僕のことを気持ち悪がる。
妹も、何が起こってるのかわからないのに、それを真似した。
二人は僕を見なくなった。
小さい僕には、一人で家を離れて単身赴任していた父親に報告する術もなかった。
僕は一人になったんだ。
小学校中学年に上がったとき、転機が訪れた。
良い意味とも、悪い意味とも取れる転機。
ママ友達の情報網とはすごいもので、もう殆どのクラスの子に『あの子はおかしいから、関わっちゃダメよ』という言いつけが回っていた。
皆、まだ同性愛異性愛を気にしない、理解できない年だったというのもあって、不思議がられはしたけど、顔だけは人より良かった僕の周りから人がいなくなることはなかった。
そんな時、転校生が来たんだ。
僕とその子は隣の席になった。
明るくて、よく笑う子で、見ているだけでこっちまで笑顔になれるような子で、僕はその子が好きだった。
でも、やっぱりその好きは恋愛対象としての好きではなくて。
僕はその頃には周りと自分が違うということがわかっていた。