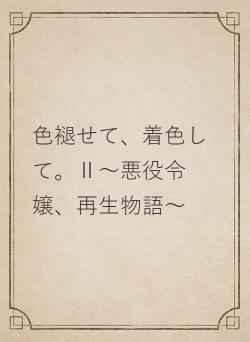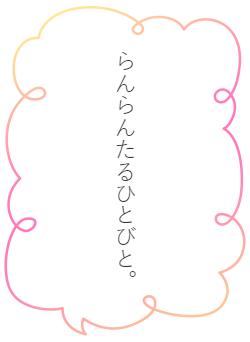走ると言っても。普段運動をしないので。
スピードは出せず、早歩き状態だったと思う。
それでも、屋敷の入口である門の前にたどり着くと。
「ここから出してー」と大声で叫んだ。
心臓はバクバク、額から汗が吹き出す。
ゼーゼーと呼吸をしながら、よじ登ることすらできない高さの門の前。
大声で泣いた。
毎晩泣いているのに。
やっぱり涙が出てくる。
何もかも嫌だ。
全てが嫌だ。
「カレンさん」
振り返ると、シュロさんがコック姿のまま立っていた。
私は涙を拭ったけど。
涙は止まらない。
「お願いだから、蘭のことは嫌いにならないでほしい」
私とは対照的に息が乱れることもなく、汗一つかくこともなく。
シュロさんが涼しげな顔をして言った。
「あいつは、私のことを気持ち悪いってずっと思ってるんですよ? そんな男、好きになんてなれません」
ぐずぐずと鼻をすすって答えると。
シュロさんはじっと私を見た。
「あいつは、昔から…初めて会ったときから私のことキモチワルイって罵ったんですよ? あんな嘘ついて、人の心踏みにじって。ばーか、ばーか」
シュロさんに馬鹿と言っても仕方ないのに。
怒りと悲しみで悪口しか出てこない。
シュロさんは困ったような表情をして、やっぱりこっちを見ている。
「蘭は自分が美男だからって私の顔をずーと侮辱して生きてるんです。小さい頃から…むしろ生まれた頃からアイツは最低な男だ!」
「最低な男?」
当主の悪口を吐き出しているが。
目の前にいるシュロさんは、怒りはしない。
それをいいことに、私は思うがまま蘭の悪口を言ってしまう。
「あいつは、生まれた時から紳士じゃない。私にだけは冷たい。最低男!!」
「えーと…カレンさん。カレンさんが蘭と初めて会ったのっていつ?」
ぐちゃぐちゃの泣き顔を見て。
一歩、シュロさんが後ろに下がった。
シュロさんだって、普段から私のことを気持ち悪い奴だと思ってるはずだ。
「8歳の時です。兄に連れられて、どこかの屋敷の庭で蘭に会いました」
「8歳? ということは、蘭も当時8歳?」
「でしょうね。同い年ですから」
シュロさんは更に私の顔を凝視したので。
私は耐え切れず目をそらした。
「その人は本当に蘭だったのかな?」
ぽつりと言ったシュロさんの言葉は。
私の胸に鋭く刺さった。
「蘭です。絶対に蘭です。そいつは」
「カレンさん。この国に蘭と呼ばれる子ってどれくらいいるんだろうね」
ふぅ…とシュロさんはため息をついて。
腰に手をあてた。
「そんなの、知りませんよ。私は家から出たことがないし。学校にだって行くことを許されなかったんですから」
袖でごしごしと顔を拭く。
「でも、絶対に蘭なんです。その男の子は蘭って呼ばれてました。兄に訊いたら『男の子で蘭って名前は珍しいなあ』と言ったのも覚えてます」
シュロさんは真顔で私を見つめる。
「それに、碧い瞳でした。碧い瞳に蘭という名前は、この国にそんなにいないのでは?」
「…うーん。呼び名なんてコロコロ変わるからなあ」
腕を組んでシュロさんは何かを考えているようだ。
ティルレット王国で出会う人の瞳の色は茶色ばかり。
渚くんのように真っ黒というのも珍しいけど。
蘭のような碧い瞳というのも、見たことがない。
…と言っている自分の瞳の色は、紫なんだけど。
「うん。やっぱり言ったほうがいいな」
独り言のようにシュロさんが呟く。
何かを覚悟したかのようにも見える。
「カレンさん。カレンさんのことを罵ったのは蘭じゃないよ」
「え?」
「だって、蘭は10歳まで女の子として育ったんだから」
スピードは出せず、早歩き状態だったと思う。
それでも、屋敷の入口である門の前にたどり着くと。
「ここから出してー」と大声で叫んだ。
心臓はバクバク、額から汗が吹き出す。
ゼーゼーと呼吸をしながら、よじ登ることすらできない高さの門の前。
大声で泣いた。
毎晩泣いているのに。
やっぱり涙が出てくる。
何もかも嫌だ。
全てが嫌だ。
「カレンさん」
振り返ると、シュロさんがコック姿のまま立っていた。
私は涙を拭ったけど。
涙は止まらない。
「お願いだから、蘭のことは嫌いにならないでほしい」
私とは対照的に息が乱れることもなく、汗一つかくこともなく。
シュロさんが涼しげな顔をして言った。
「あいつは、私のことを気持ち悪いってずっと思ってるんですよ? そんな男、好きになんてなれません」
ぐずぐずと鼻をすすって答えると。
シュロさんはじっと私を見た。
「あいつは、昔から…初めて会ったときから私のことキモチワルイって罵ったんですよ? あんな嘘ついて、人の心踏みにじって。ばーか、ばーか」
シュロさんに馬鹿と言っても仕方ないのに。
怒りと悲しみで悪口しか出てこない。
シュロさんは困ったような表情をして、やっぱりこっちを見ている。
「蘭は自分が美男だからって私の顔をずーと侮辱して生きてるんです。小さい頃から…むしろ生まれた頃からアイツは最低な男だ!」
「最低な男?」
当主の悪口を吐き出しているが。
目の前にいるシュロさんは、怒りはしない。
それをいいことに、私は思うがまま蘭の悪口を言ってしまう。
「あいつは、生まれた時から紳士じゃない。私にだけは冷たい。最低男!!」
「えーと…カレンさん。カレンさんが蘭と初めて会ったのっていつ?」
ぐちゃぐちゃの泣き顔を見て。
一歩、シュロさんが後ろに下がった。
シュロさんだって、普段から私のことを気持ち悪い奴だと思ってるはずだ。
「8歳の時です。兄に連れられて、どこかの屋敷の庭で蘭に会いました」
「8歳? ということは、蘭も当時8歳?」
「でしょうね。同い年ですから」
シュロさんは更に私の顔を凝視したので。
私は耐え切れず目をそらした。
「その人は本当に蘭だったのかな?」
ぽつりと言ったシュロさんの言葉は。
私の胸に鋭く刺さった。
「蘭です。絶対に蘭です。そいつは」
「カレンさん。この国に蘭と呼ばれる子ってどれくらいいるんだろうね」
ふぅ…とシュロさんはため息をついて。
腰に手をあてた。
「そんなの、知りませんよ。私は家から出たことがないし。学校にだって行くことを許されなかったんですから」
袖でごしごしと顔を拭く。
「でも、絶対に蘭なんです。その男の子は蘭って呼ばれてました。兄に訊いたら『男の子で蘭って名前は珍しいなあ』と言ったのも覚えてます」
シュロさんは真顔で私を見つめる。
「それに、碧い瞳でした。碧い瞳に蘭という名前は、この国にそんなにいないのでは?」
「…うーん。呼び名なんてコロコロ変わるからなあ」
腕を組んでシュロさんは何かを考えているようだ。
ティルレット王国で出会う人の瞳の色は茶色ばかり。
渚くんのように真っ黒というのも珍しいけど。
蘭のような碧い瞳というのも、見たことがない。
…と言っている自分の瞳の色は、紫なんだけど。
「うん。やっぱり言ったほうがいいな」
独り言のようにシュロさんが呟く。
何かを覚悟したかのようにも見える。
「カレンさん。カレンさんのことを罵ったのは蘭じゃないよ」
「え?」
「だって、蘭は10歳まで女の子として育ったんだから」