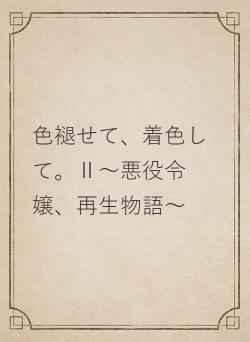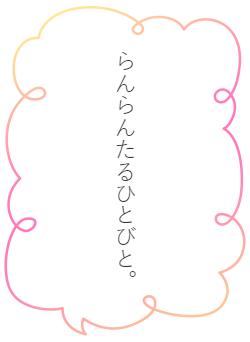蘭とご飯を食べるのは、初めてだ。
しかも、外でサンドイッチって。結構ハードルが高い。
蘭は湖を眺めながら。バクバクとサンドイッチをほおばる。
横顔は、腹立つけど。とても美しいなと思ってしまう。
碧い瞳に褐色の肌。サラサラとなびく黒い髪。
鼻にしても目にしても口にしても。
どうしたら、こんなにバランスのとれた顔になるんだろう…。
「すまなかったな」
「へ?」
急に蘭がしゃべりだしたので。
思わず、サンドイッチを落としそうになってしまう。
「クリスのことだ」
「あ・・・」
「掟は掟だ。おまえには申し訳なかったけど。ああするしかなかった」
「・・・・・・」
急に謝ってくるとは…。
本当に調子が狂ってしまう。
私の中での蘭は嫌な奴だったのに。
「おまえの家だけど」
「え?」
蘭はパクリとサンドイッチを口に入れた。
「おまえが屋敷から逃げ出す一週間前に火事にあって。でも、そこから死体は出てこなかったそうだ」
「したい・・・」
あまりにも生々しい言葉だ。
「だから、おまえの両親はどこかで生きてるはずだ。今、捜させているから安心しろ」
「さがす…?」
「おまえの両親には定期的に賃金を与えていたが、満足出来なかったようだから。もう少し小さい家にでも引っ越したのかもな」
「あ・・・。やっぱり」
ふと、自分の中にある仮説が浮かんだ。
恐らく、両親は自分たちで火を放ったのではないかと…。
没落貴族だなんて、誰もが知っているけど。
プライドだけは高いから、なかなか引っ越せずにいたのかもしれない。
でも、家事で燃えたってことにすれば。必然と引っ越さなければならない。
きっと、母の実家へ行ったのかもしれない。
世間体を気にして誰にも言わず両親は引っ越したのだ。
それなら、合点がいく。
…でも。
「どうした?」
急にうつむいたのを蘭は見逃さなかった。
「いえ…」
…お兄様の帰る家がなくなってしまった。
そう考えると。胸が痛い。
いつお兄様が戻ってきても良いように。
お兄様の部屋はそのままにしてあるってお父様が言っていた。
あの焼け焦げた屋敷を見たら、お兄様はどう思うんだろう。
「心配するな。アズマのこともちゃんと探している」
「え?」
まるで、心を見透かされたのかと思った。
「なんだ、何故おまえは驚いてる?」
むっとした表情で蘭が言う。
蘭はすぐに怒るから嫌なのだ。
「いえ、蘭様はちゃんとお兄様のことを忘れずにいてくださるのですね」
「あったりまえだろうが!」
物凄く大声で蘭が言ったから。
私は驚いて、またサンドイッチを落としそうになった。
「アズマは俺の命の恩人だ。捜すに決まっているだろうが」
「……」
蘭の激しい剣幕に言葉が出ない。
私は蘭から目を放して小さくため息をついて。
サンドイッチを一口食べた。
蘭の前で口を大きく開けるわけにもいかない。
チビチビと食べるしかない。
湖は穏やかだ。
普段のモヤモヤした気持ちを晴らしてくれる気がする。
暫く、お互いが黙っていると。
「なあ、おまえ。様付けは、よせ」
「へ?」
蘭の碧い瞳が私を捕らえる。
「おまえ。俺のいないところでは、俺のこと呼び捨てにしてるんだろ? だったら、それでいい。蘭って呼べ」
「ぅ・・・」
誰が蘭にバラしたのだろうか。
立場的に、蘭様というのがふさわしいから。そう呼んでいたけど。
陰で蘭って呼び捨てにしているのが、バレバレだったとは…。
「ついでに、敬語じゃなくていい」
「いえ、それは流石に」
こんな男でも地位も名誉も背負う方なのだ。
敬語じゃなきゃ駄目に決まってる。
「俺が良いと言ったら、いいんだ。わかったな」
「…はい」
これだから、蘭は嫌いだ。
何様のつもりなんだろう。
立場的には偉いのかもしれないが。
そういう俺様主義なところが、どうしても好きになれない。
「あの、蘭様…じゃなくて蘭」
「何だよ」
「今日はどうして、私を連れてここまで来たのですか…じゃなくて来たの?」
じっと蘭を見つめる。
蘭と渚くんって、やっぱり雰囲気が似ている。
でも、決定的に違うのは。
渚くんはフレンドリーで、蘭はツンツンしているところだ。
蘭は全然、笑わない。
「安心しろ。この湖も俺の領地だ!」
そう言って蘭は立ち上がった。
(質問の答えになってない)
はぐらかされたと思った。
蘭が立ち上がったすきに、サンドイッチを一気に食べ進める。
あー、蘭がいなきゃ口を大きく開けて食べられるのに。
蘭がシュロさんに用意させてくれたであろうサンドイッチはとても美味しい。
ローストビーフと野菜が挟まれている。
「おまえと、ゆっくり話がしたかった」
蘭は湖を見つめている。
「話すならば、屋敷でも出来るじゃないですか」
「屋敷では、誰かに話を聴かれるかもしれないだろ」
蘭は座る。
「ここに、2人で来て大丈夫です…大丈夫なの? そういえば、護衛とか…」
いくら領地とはいえ、目の前は湖。後ろは森。
大丈夫かと急に心配になる。
「大丈夫。俺には護衛がいるから」
「ん?」
そう言って、蘭は頷く。
「しっかし。おまえはやっぱり、素顔のほうがいいな」
(急に何!?)
じっと蘭が私を見つめる。
碧い目に吸い込まれそうになる。
…恥ずかしい。
「ご、ご冗談を」
下を向くが。蘭の鋭い視線を感じる。
この2人だけの時間が無償に、むずかゆい。
恥ずかしいとしか言いようのない。
しかも、蘭はこっちを見ている。
「蘭は、恥ずかしくないのですか?」
敬語じゃなくて、いいと言われたけど。
結局、敬語になってしまう。
「何を?」
「私を妻として迎えて恥ずかしくはないのですか?」
「あ?」
蘭が大声で言う。
「いや、ですから私が妻というのは・・・」
「別に身分など気にしないけどな。俺は」
蘭は飲み物を飲む。
「いえ、そうじゃなくて。いくら兄に頼まれたからといって、私みたいな醜女と結婚してもマイナスになるだけじゃないですか」
「…本気で言ってるのか?」
蘭の形相がみるみると変わっていく。
あー…怒っている。
本気で怒っている。
「じゃあ、おまえは俺のこと。どう思ってる?」
「え!?」
今度は、私が大声を出してしまう。
蘭のことをどう思っているか?
そんなの・・・
急に顔が熱くなるのを感じた。
いやいや、言えるわけがない。
黙り込んでいると、蘭はため息をついた。
「そろそろ、帰るか」
「え、もう!?」
蘭は立ち上がった。
「俺は、忙しいんだよ」
しかも、外でサンドイッチって。結構ハードルが高い。
蘭は湖を眺めながら。バクバクとサンドイッチをほおばる。
横顔は、腹立つけど。とても美しいなと思ってしまう。
碧い瞳に褐色の肌。サラサラとなびく黒い髪。
鼻にしても目にしても口にしても。
どうしたら、こんなにバランスのとれた顔になるんだろう…。
「すまなかったな」
「へ?」
急に蘭がしゃべりだしたので。
思わず、サンドイッチを落としそうになってしまう。
「クリスのことだ」
「あ・・・」
「掟は掟だ。おまえには申し訳なかったけど。ああするしかなかった」
「・・・・・・」
急に謝ってくるとは…。
本当に調子が狂ってしまう。
私の中での蘭は嫌な奴だったのに。
「おまえの家だけど」
「え?」
蘭はパクリとサンドイッチを口に入れた。
「おまえが屋敷から逃げ出す一週間前に火事にあって。でも、そこから死体は出てこなかったそうだ」
「したい・・・」
あまりにも生々しい言葉だ。
「だから、おまえの両親はどこかで生きてるはずだ。今、捜させているから安心しろ」
「さがす…?」
「おまえの両親には定期的に賃金を与えていたが、満足出来なかったようだから。もう少し小さい家にでも引っ越したのかもな」
「あ・・・。やっぱり」
ふと、自分の中にある仮説が浮かんだ。
恐らく、両親は自分たちで火を放ったのではないかと…。
没落貴族だなんて、誰もが知っているけど。
プライドだけは高いから、なかなか引っ越せずにいたのかもしれない。
でも、家事で燃えたってことにすれば。必然と引っ越さなければならない。
きっと、母の実家へ行ったのかもしれない。
世間体を気にして誰にも言わず両親は引っ越したのだ。
それなら、合点がいく。
…でも。
「どうした?」
急にうつむいたのを蘭は見逃さなかった。
「いえ…」
…お兄様の帰る家がなくなってしまった。
そう考えると。胸が痛い。
いつお兄様が戻ってきても良いように。
お兄様の部屋はそのままにしてあるってお父様が言っていた。
あの焼け焦げた屋敷を見たら、お兄様はどう思うんだろう。
「心配するな。アズマのこともちゃんと探している」
「え?」
まるで、心を見透かされたのかと思った。
「なんだ、何故おまえは驚いてる?」
むっとした表情で蘭が言う。
蘭はすぐに怒るから嫌なのだ。
「いえ、蘭様はちゃんとお兄様のことを忘れずにいてくださるのですね」
「あったりまえだろうが!」
物凄く大声で蘭が言ったから。
私は驚いて、またサンドイッチを落としそうになった。
「アズマは俺の命の恩人だ。捜すに決まっているだろうが」
「……」
蘭の激しい剣幕に言葉が出ない。
私は蘭から目を放して小さくため息をついて。
サンドイッチを一口食べた。
蘭の前で口を大きく開けるわけにもいかない。
チビチビと食べるしかない。
湖は穏やかだ。
普段のモヤモヤした気持ちを晴らしてくれる気がする。
暫く、お互いが黙っていると。
「なあ、おまえ。様付けは、よせ」
「へ?」
蘭の碧い瞳が私を捕らえる。
「おまえ。俺のいないところでは、俺のこと呼び捨てにしてるんだろ? だったら、それでいい。蘭って呼べ」
「ぅ・・・」
誰が蘭にバラしたのだろうか。
立場的に、蘭様というのがふさわしいから。そう呼んでいたけど。
陰で蘭って呼び捨てにしているのが、バレバレだったとは…。
「ついでに、敬語じゃなくていい」
「いえ、それは流石に」
こんな男でも地位も名誉も背負う方なのだ。
敬語じゃなきゃ駄目に決まってる。
「俺が良いと言ったら、いいんだ。わかったな」
「…はい」
これだから、蘭は嫌いだ。
何様のつもりなんだろう。
立場的には偉いのかもしれないが。
そういう俺様主義なところが、どうしても好きになれない。
「あの、蘭様…じゃなくて蘭」
「何だよ」
「今日はどうして、私を連れてここまで来たのですか…じゃなくて来たの?」
じっと蘭を見つめる。
蘭と渚くんって、やっぱり雰囲気が似ている。
でも、決定的に違うのは。
渚くんはフレンドリーで、蘭はツンツンしているところだ。
蘭は全然、笑わない。
「安心しろ。この湖も俺の領地だ!」
そう言って蘭は立ち上がった。
(質問の答えになってない)
はぐらかされたと思った。
蘭が立ち上がったすきに、サンドイッチを一気に食べ進める。
あー、蘭がいなきゃ口を大きく開けて食べられるのに。
蘭がシュロさんに用意させてくれたであろうサンドイッチはとても美味しい。
ローストビーフと野菜が挟まれている。
「おまえと、ゆっくり話がしたかった」
蘭は湖を見つめている。
「話すならば、屋敷でも出来るじゃないですか」
「屋敷では、誰かに話を聴かれるかもしれないだろ」
蘭は座る。
「ここに、2人で来て大丈夫です…大丈夫なの? そういえば、護衛とか…」
いくら領地とはいえ、目の前は湖。後ろは森。
大丈夫かと急に心配になる。
「大丈夫。俺には護衛がいるから」
「ん?」
そう言って、蘭は頷く。
「しっかし。おまえはやっぱり、素顔のほうがいいな」
(急に何!?)
じっと蘭が私を見つめる。
碧い目に吸い込まれそうになる。
…恥ずかしい。
「ご、ご冗談を」
下を向くが。蘭の鋭い視線を感じる。
この2人だけの時間が無償に、むずかゆい。
恥ずかしいとしか言いようのない。
しかも、蘭はこっちを見ている。
「蘭は、恥ずかしくないのですか?」
敬語じゃなくて、いいと言われたけど。
結局、敬語になってしまう。
「何を?」
「私を妻として迎えて恥ずかしくはないのですか?」
「あ?」
蘭が大声で言う。
「いや、ですから私が妻というのは・・・」
「別に身分など気にしないけどな。俺は」
蘭は飲み物を飲む。
「いえ、そうじゃなくて。いくら兄に頼まれたからといって、私みたいな醜女と結婚してもマイナスになるだけじゃないですか」
「…本気で言ってるのか?」
蘭の形相がみるみると変わっていく。
あー…怒っている。
本気で怒っている。
「じゃあ、おまえは俺のこと。どう思ってる?」
「え!?」
今度は、私が大声を出してしまう。
蘭のことをどう思っているか?
そんなの・・・
急に顔が熱くなるのを感じた。
いやいや、言えるわけがない。
黙り込んでいると、蘭はため息をついた。
「そろそろ、帰るか」
「え、もう!?」
蘭は立ち上がった。
「俺は、忙しいんだよ」