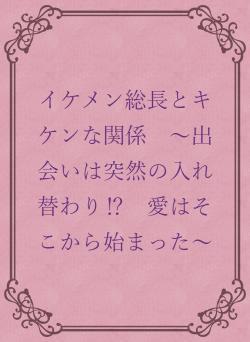十月中旬、だいぶ秋らしくなった、ある日の放課後。
オレと太一は教室の中にいた。
遼祐もいたのだけど、遼祐の周りには相変わらず女子たちが集まっていた。
「いいなぁ、爽やかイケメンくんは。モテモテじゃないですか」
太一は、いつものように遼祐のことを羨ましがっていた。
「そう言うなよ、太一。お前は梓にさえモテればそれでいいんだろ」
「……だって、梓が誰を好きなのかわからないだろ」
太一は、ちょっとふてくされた感じになった。
「……でも、もし梓がオレのことを好きでいてくれるのならオレはそれだけで充分だ」
太一の梓を想う気持ちは健在だ。
「梓がお前のことを想っていてくれるといいな」
「……うん」
太一は願うようにうなずいた。
「きっと大丈夫だろ」
「……隼翔……お前、他人事だと思ってるだろ」
「そんなことないよ」
太一と話しながらオレは一瞬、遼祐の方を見た。
遼祐の周りには、まだ女子たちが集まっていた。