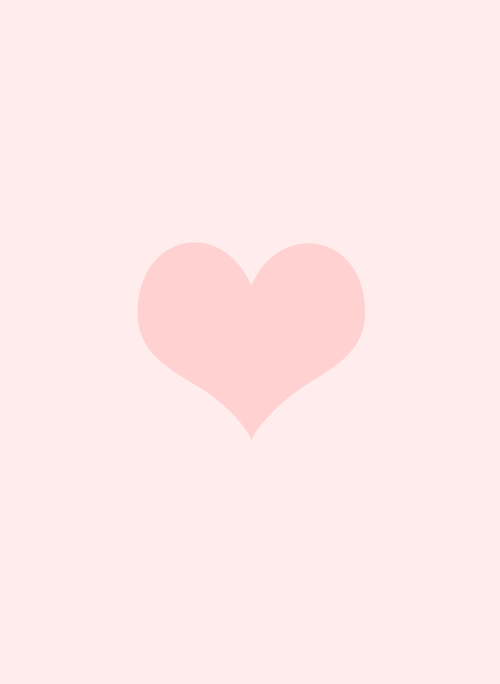「お前が、勇者の息子なんだろ!」
なんだ、この目の前にいるガキは?
と、レオ・アルバートは目を細めた。
自分の前に、まだ親離れもできてないようなガキが喚いていた。
いかにもチャラそうな茶髪に、緑色の大きな瞳。
顔は整っているが、チビ。
まだガキが、なぜ俺の隠れ場所にいる。
こんな不快な気分あったもんじゃない、とレオは内心吐き捨てた。
「何か言えよ、おい!お前がレオ・アルバートだろ!偉大なる勇者ラスカー・アルバートの息子なんだろ!」
「人違いだ」
「うそだ!!!」
小さな男は目を吊り上げて叫んだ。
「俺は聞いたんだ、街の人に!この街の森の奥にでっかい屋敷があって、そこには勇者の息子が住んでるって!俺はそれを信じてここに来た。そしたらお前がいた。つまり…お前が勇者の息子ってことだ!」
「人違いな上に不法侵入だ」
そもそも、とレオ・アルバートは上を向きながら言葉を続けた。
「そこは屋敷の塀だ。塀の上に立つなガキ」
深い緑の森に佇むのは、バロック建築を彷彿とさせる壮大な屋敷だった。
そして、白を基調としたその建物を囲むのは高い高い塀。到底小さな子供が登れるような高さではない。
「靴で家を汚すな」
「俺はガキでもチビでもない!ゼインという名前がある!」
「そうか。ゼイン、消えてくれ」
「お前は勇者なんだろう!!」
ゼインは短い足を肩幅に広げ、塀の上で踏ん張った。
彼の目は真剣に、レオ・アルバートを捉えていた。
「勇者はすごいんだ…俺の憧れなんだ。俺は勇者になりたいんだ」
「そうか。なればいい」
「だから…俺をお前の弟子にしてくれ!!」
「お前さ、俺の声届いてる?」
そうして、レオ・アルバートはゼインという少年に出会ったのだ。
レオ・アルバートはラスカー ・アルバートの息子である。
ラスカー・アルバートはご存知であろうか。
話は20年前に遡る。
ラスカー・アルバートは、世界を滅ぼそうとする大災に打ち勝ったのだ。
大災--その名も魔王。
人間界を支配しようと魔物を操り悲劇を与える、諸悪の根源。
それを倒したのが彼だった。
圧倒的な強さを誇り、魔王を封印することに成功した。
それが、20年前のお話。
そして今、時が経ち、魔王の封印は解かれた。
やはり魔王を消滅することでしか平和は訪れないと証明された瞬間であった。
「偉大なるラスカー・アルバート!目が眩むほど眩しい金髪に、真実を捉える真っ青な瞳!端正な顔立ち!!そして何より、あの強さ!魔王を一撃で封印したんだ、みんなの憧れの勇者さ」
「そうか、ならその勇者に会いに行けばいい。俺じゃなくてな」
「お前は勇者の息子だろ?なんだそのやる気のない目…。魔王に一撃でやられそうな気怠さは」
「年上に対する口の聞き方には気を付けろよ」
顔以外何も似てねえ、というゼインの言葉にレオはシカトを決め込んだ。
「それに、親のことならレオが一番分かるだろ。勇者はもうこの世にいない。俺は勇者には会えない」
「気安く呼ぶな」
「だから俺はレオに会いに来たんだ。どんな人が勇者の息子なんだろうって期待を寄せて…」
ゼインはそこまでいうと、塀の上からレオを見下ろした。その目には何も映っていなかった。
「期待外れだったろ。なら帰れ」
「ほんとにな。俺をチビ呼ばわりするしな」
ゼインのその言葉を聞くと、レオ・アルバートは広大な庭の一角の、塀に最も近い、花も草も生えてない、隅っこであるその場にしゃがみ込み、目をうつ伏せ、最初の体勢に戻った。
そもそも、と、ゼインは心の声が漏れそうになった。
そもそもこの勇者の息子、レオ・アルバートはさっきから何をしているんだ?
ゼインが森の奥を歩み進めると、白を基調とした巨大な屋敷が見えてきて、ここが勇者の息子の居場所であるとすぐに分かった。
しかし、いかんせん広大な土地、それに高い高い塀が立ち上り、とてもじゃないが勇者の息子は愚か、屋敷の住人に出会える確率は低いと思っていた。
ゼインは見た目よりもはるかに身体能力が高く、塀を登ることは容易かったが、頂上から屋敷を眺めても広がるのは大きな庭。
季節ごとの様々な草花が咲き誇り、6段にも連なる巨大な噴水があり、細い一本の道の奥にやっと屋敷が立ちそびえていた。
これは、侵入するのも一苦労だ、とゼインは心の中で舌打ちをし、とりあえず塀を降りようと思い目を下にした。
そこに、彼はいたのだ。
レオ・アルバートがいたのだ。
塀の真下にいた人物が勇者の息子であることはすぐに分かった。
眩しい金髪、青い瞳、整った顔立ち、華奢な体格に隠された鍛え上げられた身体の持ち主。
勇者の息子、レオ・アルバートに違いなかった。
しかし、しかしだ。
いったいこの世の誰が、この広大な屋敷の広大な庭の中で、塀に最も近い隅っこで男が足を抱えて丸まっているなど想像するだろうか。
勇者の息子とあろう男が、膝を抱え自分の真下にしゃがんでようとは誰も想像できまい。
こいつ、本当に勇者の息子なのか?
侵入者を無視し、また下を向くレオを眺めながら、発する言葉と真逆のことをゼインは考えるのであった。
ゼインは塀からぴょんと降りると、徐に、地面に落ちてる小石を拾った。
どこからか微かな風が吹く。
ゼインの髪の毛がふわっと浮いた。
と、同時に、ゼインの持つ小石も、掌の上の宙を舞っていた。
この目の前にいる男が本当に勇者の息子なら--。
それは一瞬の時間。
彼の掌の上、そこに小石はなかった。
ただ、空高くに鷹の声が響くだけだった。
宙に浮いた小石は、目にも見えぬスピードで真っ直ぐに、しゃがんでいるレオ・アルバートの額めがけて飛んで行き、命中し、額からは一筋の血が流れる--はずだった。
勇者の息子に一泡吹かせてやるはずだった。
のだが。
「なあ、ゼイン」
勇者の息子は何一つ表情を変えず、ゼインを真っ直ぐと見上げた。
額には、傷一つも見当たらなかった。
外した?!
そんなはずがない。
俺の命中率は百発百中だ。
なら何故だ。避けた?そんな気配は見えなかった。
一体何が起こったんだ!?
「これ、なんだか分かるか」
「はっ…はあっ?」
動揺のあまりゼインは喉の裏から声が出た。
背中に流れる冷や汗は、決して勘づかれてはならないと思った。
レオはそんなこともいざ知らず、地面に再び視線を落とす。
そこには、小さな穴が開いていた。
「アリの巣…だろ」
「そうだ、これを見ろ」
レオは小さな穴を指差した。
そこからはその穴よりも小さな黒いアリが、せっせと何かを運んでいた。
「このアリはな、俺の大切な家の塀に穴を開け、外に出てっている。…こんなことが許されると思うか。俺の大切な家だぞ」
「……」
嘘だろ、とゼインはたじろいだ。
まさかこの男、アリを観察していたのか?
このだだっ広い敷地の隅の隅っこで、膝を抱えてアリ観察だと?
「お前は一体…何を」
「しっ」
ゼインが口を開くと、レオは指を口に手を当て言葉を遮った。
その目は真剣だった。
「本当ならこんな事許されない…。だが、見てみろ。こんな小さな生命が、必死に何かをせっせと運んでいる。俺はこいつらを邪魔する事はできない。そうだろ?」
「……」
何なんだこいつは。
こんなどうでもいい事を、こんな真剣に語るのか?
ゼインは何が何だか分からなかった。
これが本当に偉大なるラスカー・アルバートの孫なのか?
何かの間違いじゃないのか?
沈黙したままゼインは目を再びアリに向けると、ふと何かに気付いた。
「何だ?こいつらが運んでいるの」
「ん?」
ゼインの視線を追うように、レオもアリに視線を落とす。
「ほら、よく見ろ。こいつらが運んでいるのはただのエサじゃない。何だか黒くて……」
「ほんとだな。不気味だな」
アリが運んでいるのは黒く、禍々しいオーラを放った見たことのない何かであった。
何だろう、とレオはうーんと唸る。
「まぁ、考えても仕方ない。俺はこいつらに手を出さないと決めた。なぁ、ゼイン」
「なっ、なんだよ?!」
急に名前を呼ばれ、ゼインは思わず後退りした。
「折角だ。俺の家を案内してやる」
「はっ……はあっ!?」
「それとな」
レオはゆっくり立ち上がると、屋敷に向けて足を進めた。
ゼインは言葉の続きを待つように、その背中をじっと見た。
大きいけど、小さい。
叩けば倒れてしまいそうなほど弱そうで、しかしそのオーラで魔王さえも蹂躙してしまいそうな程、確かに強い背中を。
「いくら俺が勇者の子といえ、初対面の人に小石を投げるのはやめろよな、危ないから」
勇者の息子、レオの手の中で、真っ二つに割れた先程の小石が弄ばれていた。
「なっ…?!」
ゼインは驚きで目を見開いた。
さっきの俺が投げた石!?
何故だ?!いつ?!
こいつは俺が攻撃しようとした事、気付いていたのか!?
「こねぇの?」
立ちすくむゼインに、レオは首を傾げ問いかけた。
何だこの男、分からねぇ。
勇者の子がどんなもんだと見に来たが、ますます謎が深まるだけだった。
だけど…。
こいつはもしかしたら、相当強いのかもしれない。
あわよくば、俺を弟子にしてくれるかもしれない。
「行く、お前の家、案内してくれ!」
ゼインは内心ニヤリと笑うと、颯爽と先に進むレオの後を追いかけた。
小さな胸に、希望と期待を抱いて。
「はえ〜。それにしてもでっかい庭だな」
「だろ」
ゼインの感嘆した声に、レオは少し嬉しそうに頷いた。
「ここは俺の隠れ家だ。誰かがうちに来るのも、誰かに案内するのも初めてだ」
「街の人はみんな怖がってこないんだろ」
「そんな事はない。俺は好かれている」
おいおいそれを自分で言うのかよ、とゼインは若干引いた。
「人気者ってのは辛いんだ。俺は静かに暮らしたいだけなのに」
「まぁ、かの魔王を一度は倒した息子なんて、人気なのも当たり前だよな」
「俺は全くそういうのに興味がない」
「興味がない?」
レオの言葉に、ゼインは足を止めた。
こいつは何を言ってるんだ?
「今、魔王は復活した!お前は父の後を継ぎたいと思わないのか!?」
「後?」
「魔王の完全消滅だよ!!」
レオは首をかしげる。
その態度に、ゼインは無性に腹が立った。
「お前の父親が魔王をあと一息のところまで追い詰めたんだ!だから、息子としてその後を継いで…」
「あと一息のとこまで追い詰めたって、魔王が復活したんじゃ意味なかったってことだろ。意味がないんだよ、魔王討伐なんて」
「なにっ…!?」