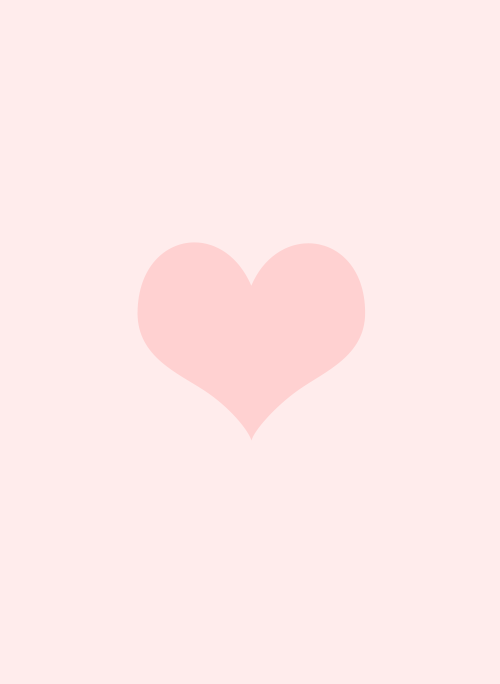「わたしが、演奏する」
「え……?」
「円の代わりにわたしがステージに立つよ」
今度はわたしが円を助ける番。
「いや俺が……」
「わたしが弾く!」
お願い。
今回はゆずってよ。
痛覚は無理だから、その意志と責任を。
プライドごと分けてくれないかな。
「知ってるでしょ?わたしもバイオリンを弾けること」
「だ、だけど……」
「こういうときくらい甘えてよ」
『こういうときくらい甘えろ』
おぼえてる?
前に円が言ってくれたセリフだよ。
「……わ、わかった」
がんこ勝負。
ため息混じりに円が白はたを上げた。
教室に戻ってクラスメイトに事情を説明した。
教室の裏手に置いていた、バイオリンを入れたケースを受け取った。
「大事にあつかえよ」
「もちろん。円の大事なバイオリンだもんね」
「……任せたぞ」
「うん!全力で頑張る!」
休憩時間が終わったら円には右腕にあまり支障のない、入口で案内する仕事を主に担当させることになった。
わたしはクラスと委員会に無理を言って、仕事を他の人に代わってもらった。
楽器は一日弾いてないだけで音色が変わる。
バイオリンは半年触れてない。
長いブランクがあるため、エンディングまでにバイオリンの練習をしなければならない。
エンディングまで時間がない。
文化祭で使われていない音楽室を借り、何回もバイオリンを弾いた。
指の傷が治っていてよかった。
「姫!完成したっす!」
「ほんと!?」
ハルくんにはドレスの作製を頼んだ。
不思議の国のアリス風だったメイド服が、短時間でドレスに変身!
あまったメイド服用の布をつぎ足し、飾りをほどこしてできあがった。
うしろ側の丈が長い、ガーリーかつ大人っぽいドレス。
「かわいい!!」
即席だとは思えない。
技術とセンスが各段に上がってる。
わたしのヨレヨレな縫い跡もうまく隠してくれてる。ありがたい。
「ごめんね、ハルくん。今日はお客さまなのに」
「いいんすよ!姫の力になれてうれしいっす!」
ハルくんにうしろを向いてもらい、早速ドレスを試着する。
うん、サイズもぴったり。
どこもきゅうくつじゃない。
「カンペキだよ!ありがとう!」
「次はヘアメイクっすね!」
「うん、よろしく!」
「任せてください!」
ハルくんの手にかかれば、クセの強いわたしの髪は素直ないい子ちゃんになる。
指どおりがよくて、甘い香りがして。
女子力がアップした気分。
穂乃花ちゃんに貸してもらったメイク道具で、目元を中心に彩っていく。
「できたっす!」
手鏡に映ったのは、お嬢さまのわたし。
この姿になつかしさをおぼえてしまう。
それくらい昔の話。
最終チェックを終えるとちょうどいい時間になった。
もうすぐエンディングが始まる。
ハルくんとともに体育館に移動した。
幕の下りたステージの真ん中にたたずむ。
「まもなくエンディングとなります。今年の体育館ステージのエンディングは、相松円くんによる……えっ?変わった?」
アナウンスにノイズが生じる。
幕の向こう側がざわつく。
「――失礼しました。今年のエンディングは相松円くんから竜宝寧音さんに変更し、バイオリンのソロ演奏をひろうします」
ざわつきが大きくなった。
「えー」
「相松くんじゃないの!?」
「円くんがいい~」
「バイオリンとか興味ねぇし」
「クラシックとかまじ?」
どうして嫌みや文句ばっかり聞こえちゃうんだろう。
手に汗をかく。
心臓がバクバクだ。
緊張と恐怖でどうにかなってしまいそう。
「姫!」
「寧音ちゃん!」
ハルくんとナツくんの声が響いた。
ステージ横で応援してくれてる2人を見据える。
……そうだ。
わたしは独りじゃない。
周りは敵だらけじゃなかった。
「好きです!」
ひと足早く開催された野外ステージのエンディングが、やけに鼓膜を揺らした。
公開告白。
気持ちを伝える企画。
……わたしにもあるよ。
あふれんばかりの「好き」。
音楽が好き。バイオリンが好き。
円の想いの分も、演奏で伝えたい。
ううん、伝えるんだ!
メンテナンスされたバイオリンも、手作りのドレスも
大好きって気持ちも
全部、わたしの味方。
「繰り返し放送します。まもなくエンディングとなります。今年の体育館ステージのエンディングは、竜宝寧音さんによるバイオリンのソロ演奏です」
体育館のステージ前を埋めつくす生徒。
数に比例して高まっていた期待が、徐々に薄れていった。
落胆。
不平。
興ざめ。
生徒の興味が消え失せているのが一目りょう然。
冷めた反応があいつにも届いてないといいけど……。
「相松くん」
体育館の壁によりかかっていた俺に、委員会の仕事を終えた斎藤が近づいてきた。
じゃっかん距離を空けて斎藤も壁に背をつける。
「相松くんはステージ前じゃなくていいの?」
「斎藤こそ」
「あたしはここからでもよく見えるから」
「俺も」
「そっか」
会話がはずまない。
沈黙が多発するのは、どちらも彩希みたいにおしゃべりじゃないのもあるだろうけれど……
斎藤が俺に壁を作ってるせいもあるだろう。
『円、狙われてんじゃね?』
もし本当に狙われてるとしたら
それは好意じゃなくて――。
「……腕」
「え?」
「もう大丈夫?」
「……ああ、平気。もう痛みもない」
「そっか。軽傷で済んでよかったね」
前に一度斎藤を恐れたのはきっと、平等に優しいところしか知らなかったからだ。
今は、もう、ちがう。
「なんであんなことしたんだ」
普通のテンション、普通のトーン。
自然をよそおってなにげなく尋ねた。
「なんの話?」
返事も普通のテンション、普通のトーン。
……微動だにしないんだな。
「看板だよ」
「……看板がどうしたの?」
「アレ倒したの、斎藤だろ」
「ええ、ちがうよ。あたしが倒すわけないじゃん」
「しらばっくれるな。俺は斎藤が倒すところを見たんだ」
更衣室に向かったフリをして、看板をかたむけた。
――俺を狙って。
だが狙いがはずれ、俺ではなく寧音のほうに倒れてしまった。
だから斎藤は悲鳴を上げたんだろ?
「……そう、見てたんだ」
ずっと保っていた微笑が枯れていく。
冷ややかな声に戦りつした。
「俺にうらみでもあるのか?」
「標的が自分だって自覚してるんだね。さすが学年トップ」
「茶化すな。答えろ」
「……うらんではないよ。しいて言うなら、嫉妬?」
嫉妬?
俺に?
なんで……。
疑念が深まる。
けげんそうにすれば、斎藤は上品に一笑した。
「意味わからないって顔してるね」
しょうがねぇだろ。
本当にわからねぇんだ。
俺を好きなわけでもないのに、なんで嫉妬なんかすんだよ。
「当たり前か。誰にも話したことないし」
さらり、とミルクティー色の髪を耳にかけた。
「あたしね、うらやましかったの。相松くんと寧音ちゃんの関係が」
「俺と、寧音の……?」
「小4のころ、バイオリンのコンクールで審査員の娘さんが特別枠として参加者の審査の前に特別に演奏したことがあったの。その子はあたしと同い年なのに、楽しく伸びやかに演奏してた。あれほどすてきな音色を聴いたのは初めてだった」
「……斎藤もバイオリンやってたのか」
「今はやめちゃったけどね。……やっぱりおぼえてないか。そのコンクールに相松くんも出場してたんだよ。1位をとったのも相松くんだった」
小学4年生。バイオリンのコンクール。伸びやかな演奏。
既視感をおぼえた。
まさか。
そんな偶然あるはず……。
『え!?お母さん審査員じゃなかったっけ!?』
脳裏に現れた、忘れられない人。
たしかあの女子がそう言っていったっけか。
審査員の娘……。
偶然にしてはあてはまりすぎている。
「あたし、その子の――寧音ちゃんの演奏に聴き惚れちゃって。すごく、あこがれたの。だからこの学校で再会したときは驚いたし、うれしかった」
だけど、と。
にくらしげに一瞥される。
「寧音ちゃんは相松くんばっかり見てた。相松くんも寧音ちゃんにかまってて、ずるいって思った。相松くんだけ寧音ちゃんを独占して……あたしだって仲良くなりたいのに!」
「……俺は別にかまってもねぇし、独占もしてねぇよ」
「してるの!まさか無自覚?」
「は?」
「自覚してないんだね……。とにかく!あたしは2人の仲がうらやましかったの!」
「……はあ」
「ケガさせたのは悪いって思ってるけど、相松くんも悪いんだよ?寧音ちゃんを独り占めしたりするから。避けられてるくせに」
いやいや、待てよ。
おかしいだろ。
なんで俺が悪いんだよ。
それに最後の一言はよけいだ。黙れよ。
斎藤てめー、1ミリも反省してねぇな?
だんだん腹が立ってきた。
俺もなにか言い返してやろうか。
「……なんで俺にその話をしたんだよ」
いら立ちを抑えこみながら右腕をさする。
「そっちが聞いてきたんでしょ」
「そうだけど……斎藤がやったっていう証拠はねぇし、話さなかったほうが斎藤には都合よかったんじゃねぇの?」
「……都合よくないよ」
「なんで」
「相松くんが寧音ちゃんに告げ口するかもしれないでしょ。そしたらあたしの好感度が下がって、寧音ちゃんと仲良くできない。だったら相松くんに白状して、口止めしておいたほうが確実かなって」
……こっわ。
さらっと口止めって言いやがったぞこの女。
「だからバラさないでね?」
「……言わねぇよ」
「言質とったからね?バラしたら……」
「言わねぇって」
バラしたら俺どうなるんだよ。
怖くて深掘りできねぇ。
笑顔も黒いし。
だけど、あいつは
こんな怖い斎藤のことを信頼してるんだよな。
『ホノカちゃん……?友だちっすか?』
『うん!同じ文化祭実行委員なの』
『そっすか。友だち……できてよかったっすね』
――バラせるかよ。
知ったらあいつが悲しむだろ。
……でもこれからは斎藤に注意しておこう。あいつになにかあってからじゃ遅ぇし。
斎藤をにらんでいると、とうとうステージの幕が上がった。
未だにしらけた微妙な空気感。
おもしろがってブーイングしてるやつもいる。
ステージの中央にライトが集まった
その瞬間
誰もが息をのんだ。
俺も、斎藤も、関心のなかった生徒も、全員がステージにくぎ付けになった。
「……きれー……」
耐えきれず斎藤がささやいた。
あそこにいるのは本当に俺の知る“竜宝寧音”なのだろうか。
光が当たってよりつやめく赤茶の髪。
メイド服をアレンジしたドレス。
緊張や恐怖を感じさせない顔つきは、忘れられないあの子の面影を帯びていた。
ステージの中央で一礼すると、優しく微笑んだ。
バイオリンをかまえる。
まだ演奏していないのに、すでに観客の心をつかんでいた。
息を吸うのもためらうほどの静寂の中。
おもむろに弓が弦に触れた。
心地よい静けさを音色が侵食していった。
これは。
この、曲は。
――パッヘルベルの「カノン」。
昔と全然変わってない。
どこまでも広がる音が、軽やかにはずんでは、胸を焦がす。
淡くておだやかで。
それでいて、鮮やかで力強い。
ようやくわかった。
あのときは気づけなかった、この気持ちの名前。
俺は恋していたんだ。
この音色に。
「……そう、か……本当に……」
寧音が、あの子だったんだ。
何度でもこの音に惹かれるのも、寧音にときめいたのも、忘れられなかった初恋がいつまで経っても過去のものにならなかったから。
「……っ、」
視界がかすむ。
あいつのりんかくがぼやけてよく見えない。
つ、と頬に濡れた感触が伝った。
なんで俺、泣いてんだ。
涙を拭う手は震えていた。
……あぁ、きっと、俺はまた恋をしてしまった。
この作家の他の作品
表紙を見る
「お前に、俺の名をやろう。
今日からお前が――“侍”だ」
♔
□
▼
○
最強暴走族のたまり場は
“女王”の城だった
「ようこそ、“神雷”へ」
空っぽな俺も今日から
気高く美しい“女王”の下僕
○
▲
□
♔
大切なものを見つけたとき
何か失うとも知らずに
俺はただすべてを受け入れた
2019/01/21 表紙作成
2023/12/28 表紙公開
2024/03/01 本編公開
その刃でこの心臓を貫いて
表紙を見る
「ねえねえ」
「ツインテールの、あの子さ」
「――先週までとは、別人みたいだね」
2022/04/01 執筆開始
2022/06/09 執筆終了
2022/06/10 修正開始
2022/10/17 更新開始
2022/12/28 修正終了
表紙を見る
今日も私は
公園にある桜の木の下で
君と交わした約束と共に
君を待ち続ける
*:+゜・。*:+゜・。*:+゜・。*:+゜
二つの切ない約束は
いつしか関係を複雑にして
両思いの赤い糸は
彼との出会いがきっかけで
静かに儚く消えていく
*:+゜・。*:+゜・。*:+゜・。*:+゜
2015/03/12 執筆開始
2015/03/19 執筆終了
2018/07/28 修正開始
2018/08/10 修正終了
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…