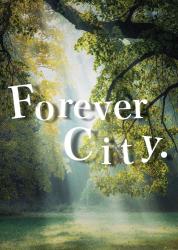喉の乾きを理由に、嫌な程に静かになった部屋を出た。
階段を降りると、リビングの明かりがついていて。ゲームの音が聞こえないし、パソコンの音がする訳でもない。
多分、そこには狂盛がいるんだろう。
そう思いながら中に入ってみると、そこには、ソファーに座る狂盛が居た。
「 あれ、まだ起きてたの? 」
『 …はい。 』
俺がそう声をかけると、狂盛は振り向かずに短くそう言った。
俺はそのままキッチンへ向かい、冷蔵庫の中から冷えた水を取り出す。
喉の乾きと同時に狂盛の背中から妙な何かを感じて、少し焦ってしまっていた。
『 遊んでたんじゃないんですか? 』
ほら、やっぱり聞いてくると思った。
分かっていたとしても、心臓は少しだけ早く動く。
「 ん?んー。 」
立ち上がって俺を見る狂盛に、ニコッと笑いながら適当に返した。
この心情を悟られないように、この気持ちがバレてしまわないように。
いつもの笑顔で、隠すように。
「 わーびっくりした、何急に。 」
すると、急に狂盛が俺の胸ぐらを掴んだ。
狂盛がこんなことをするのは、初めてだった。
表情も、握り締められた拳も、一切震えていないのに。
それなのに、どうしてこんなに苦しそうなんだ。
『 そんなに楽しいんですか?紅苺との遊びは。 』
「 えー、うん。楽しいよ。どうして狂盛がそんなに怒ってるの?珍し〜。 」
嘘つけ、本当は楽しくなんか無い癖に。本当はもう、やめたい筈なのに。
すると、狂盛は微かに眉をピクリとさせた。きっと、俺が言った " 怒ってる " の言葉に対してだろう。
今まで、狂盛から感情や思いを感じ取ったことは一度もなかった。強いていえば、人を殺す時に見せる " 殺気 " に満ちた目だけ。