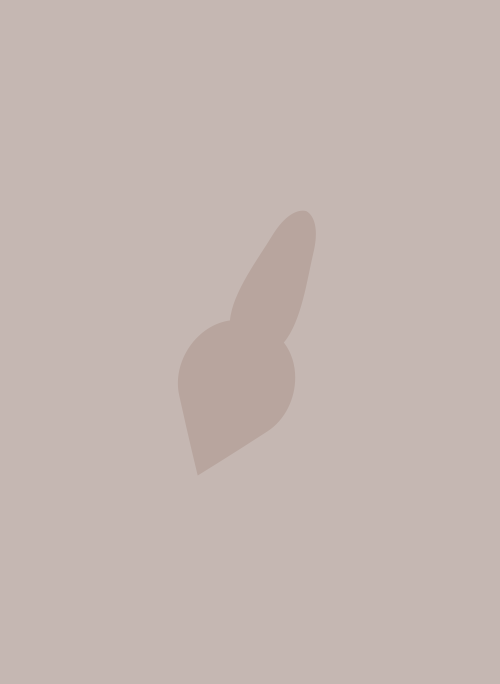『―――少しに前に出せ』
「はい」
若いモンが少し車を前に出し、木村の乗っているミニパトの運転席の窓が、ちょうど俺の横にくる。
俺は少し窓から手を伸ばし、ミニパトの窓を軽く叩く。
木村は此方に目をやり、ウンザリした顔を浮かべながらミニパトの窓を開けた。
俺は木村のウンザリとして、ふてぶてしい顔が、余計におかしくて、含み笑いを浮かべながらミニパトの窓が開ききるのを待つ。
「・・・何だ?」
『きむらぁ~・・・お前、ついに交通課になったのか?』
「・・・借りモンだ」
『なぁ・・・警官刺されたってぇ?死んだのか?』
「・・・テメェには関係無い事だ」
『―――隣の野郎・・・見ねえ面だな?青ざめた顔してるが、大丈夫なのか?』
車が少し流れ、木村は俺の質問を無視して車を前進させる。
俺は若いモンに車を進めるように促すが、車の流れが良くなったのは木村の列の方だけで、コチラの車線は一向に進む気配を見せなかった。
『・・・くっそう』
「ヤマモトさん、アイツは確か総務課だか警務課だかの奴ですね」
面白くなく、シートに深く身を沈める俺に檜山が少し身を此方に向けて言ってきた。
『・・・総務?何で総務だかの奴が生安の木村と一緒なんだ?』
「―――さぁ・・・雑用じゃないですか?」
『ヒ~ヤマ~・・・お前冗談で言ってんのか?』
「いえ、そう思っただけです」
『・・・フンッ』
俺は檜山の答えを鼻で笑い飛ばす。
檜山は表情を変えずに、前を向きなおし、生真面目に窓の外を眺めている。
檜山は良く出来る男だが、いまいち何を考えているのか分からん。
コイツは実は賢いとは対極に居るんじゃねえかと、たまに疑問に思う事がある。
そうこうしてる内に、此方の車線も流れ出し、三台分程前に居た木村のミニパトとまた並ぶ。
「はい」
若いモンが少し車を前に出し、木村の乗っているミニパトの運転席の窓が、ちょうど俺の横にくる。
俺は少し窓から手を伸ばし、ミニパトの窓を軽く叩く。
木村は此方に目をやり、ウンザリした顔を浮かべながらミニパトの窓を開けた。
俺は木村のウンザリとして、ふてぶてしい顔が、余計におかしくて、含み笑いを浮かべながらミニパトの窓が開ききるのを待つ。
「・・・何だ?」
『きむらぁ~・・・お前、ついに交通課になったのか?』
「・・・借りモンだ」
『なぁ・・・警官刺されたってぇ?死んだのか?』
「・・・テメェには関係無い事だ」
『―――隣の野郎・・・見ねえ面だな?青ざめた顔してるが、大丈夫なのか?』
車が少し流れ、木村は俺の質問を無視して車を前進させる。
俺は若いモンに車を進めるように促すが、車の流れが良くなったのは木村の列の方だけで、コチラの車線は一向に進む気配を見せなかった。
『・・・くっそう』
「ヤマモトさん、アイツは確か総務課だか警務課だかの奴ですね」
面白くなく、シートに深く身を沈める俺に檜山が少し身を此方に向けて言ってきた。
『・・・総務?何で総務だかの奴が生安の木村と一緒なんだ?』
「―――さぁ・・・雑用じゃないですか?」
『ヒ~ヤマ~・・・お前冗談で言ってんのか?』
「いえ、そう思っただけです」
『・・・フンッ』
俺は檜山の答えを鼻で笑い飛ばす。
檜山は表情を変えずに、前を向きなおし、生真面目に窓の外を眺めている。
檜山は良く出来る男だが、いまいち何を考えているのか分からん。
コイツは実は賢いとは対極に居るんじゃねえかと、たまに疑問に思う事がある。
そうこうしてる内に、此方の車線も流れ出し、三台分程前に居た木村のミニパトとまた並ぶ。
木村は俺の車が隣に着くと、訝しげな顔で一度こちらを見て、見ていないような素振りで、また前に顔を向ける。
俺は木村のそんな反応が楽しくて、木村の乗ったミニパトの窓をまた叩く。
「―――ったく暇人が・・・」
『木村~そいつ刑事だろ事務方の?・・・なんでそんな野郎と仲良くドライブしてんだよ?』
木村は俺の質問に、訝しげな顔を崩す事なく前を見据え続ける。
隣の脂汗を浮かべた刑事が、目を閉じたまま時折苦悶の表情をコチラにアチラにと向けている。
『―――なぁ隣の脂汗、本当に大丈夫かぁ?』
「なぁ・・・ヤマモト」
木村はうんざりとしながら此方を向き言葉を吐いた。
『何だい?木村ちゃ~ん?』
「・・・コイツはペンキ屋にやられたんだよ」
『・・・なっ?』
木村の言葉に俺は言葉を失う。
「赤いペンキが壁一面に散ってやがったぞ・・・・誰の血なんかねぇ?」
『マジか?!木村っ?!』
「こんな所で俺をかまってる場合じゃねえんじゃねえか?」
木村がそう言うと同時に、木村のミニパトの前方の車が進みだした。
「・・・運命なんだよ・・・俺もお前も」
木村はそう最後に吐き捨てて、流れ出した車の列にミニパトを走らせる。
そして、一向に流れない俺の車の列を横目に流し、十字路を左折して俺の視界から消える。
「ヤマモトさん、確認させます」
檜山が黙り込む俺に気を回し、携帯のアドレスをグルグル巡るように他のモンに電話を掛け始める。
俺はそんな檜山に『おう』とだけ応え、また押し黙る。
名前も覚えてねぇ運転手の若いモンが、チラチラとミラー越しにコチラに送る視線を感じる。
俺は木村のそんな反応が楽しくて、木村の乗ったミニパトの窓をまた叩く。
「―――ったく暇人が・・・」
『木村~そいつ刑事だろ事務方の?・・・なんでそんな野郎と仲良くドライブしてんだよ?』
木村は俺の質問に、訝しげな顔を崩す事なく前を見据え続ける。
隣の脂汗を浮かべた刑事が、目を閉じたまま時折苦悶の表情をコチラにアチラにと向けている。
『―――なぁ隣の脂汗、本当に大丈夫かぁ?』
「なぁ・・・ヤマモト」
木村はうんざりとしながら此方を向き言葉を吐いた。
『何だい?木村ちゃ~ん?』
「・・・コイツはペンキ屋にやられたんだよ」
『・・・なっ?』
木村の言葉に俺は言葉を失う。
「赤いペンキが壁一面に散ってやがったぞ・・・・誰の血なんかねぇ?」
『マジか?!木村っ?!』
「こんな所で俺をかまってる場合じゃねえんじゃねえか?」
木村がそう言うと同時に、木村のミニパトの前方の車が進みだした。
「・・・運命なんだよ・・・俺もお前も」
木村はそう最後に吐き捨てて、流れ出した車の列にミニパトを走らせる。
そして、一向に流れない俺の車の列を横目に流し、十字路を左折して俺の視界から消える。
「ヤマモトさん、確認させます」
檜山が黙り込む俺に気を回し、携帯のアドレスをグルグル巡るように他のモンに電話を掛け始める。
俺はそんな檜山に『おう』とだけ応え、また押し黙る。
名前も覚えてねぇ運転手の若いモンが、チラチラとミラー越しにコチラに送る視線を感じる。
『―――フンッ』
「・・・なんです?」
俺が鼻で笑うと、檜山が空かさず反応し俺の方を向く。
『なに・・・ただ笑っただけさ』
「・・・そうですか」
『なぁ!!若いの!!』
運転手の若いモンが、ビクッと体を強張らせながら「ハイッ」と返事する。
『オメェ名前は?』
「さ・・サイト・・斉藤っす!!」
『そうか・・・なぁ斉藤?メンッドクセぇなぁっ?』
「・・・へっ?」
斉藤はまた間抜けに受け答えをする。
俺が間抜けな斉藤のリアクションにうんざりしだすと、やっと前の車が進みだした。
檜山が斉藤にアゴで合図して「はっはい!!」と斉藤が、また間抜けに返事して、車を走らせ出す。
『運命』だぁ?
木村もふざけた事を抜かしやがる。
『―――残念ながら、俺はそんなモノを感じる程、暇じゃねぇ』
「なんです?」
檜山が俺の独り言に、携帯電話を耳から遠ざけながらイチイチ反応する。
俺は『独り言だ』の一言を吐き出すのも馬鹿らしく、檜山に前を向くようにアゴで合図する。
目の上のタンコブは切り落とせば、それで済むだけの事。
俺は別に悩む必要は無え。
『奴』が、なりを潜めていただけ、そんな事ぁ分かってた事だ。
それ相応の手を打てば済むだけの事・・・
・・・それだけの事だ。
俺はシートに深く身を沈め、ジャケットの内側から携帯を取り出し、アドレスから懐かしい名前を探す。
夏でも無えのに、蒸し暑く感じる。
俺はネクタイをゆるめながら、アドレスの懐かしい名前に電話を掛ける。
―――――ペンキ屋
「―――ここで降りるの?」
女が伏せ目がちに問い掛けて来る。
俺は表情を崩す事無く黙って頷く。
女は一瞬俺の顔を覗き込むようにコチラを向き、少し諦めたように作り笑いをしながら助手席のドアを開けて、シートに手を掛けながらゆっくりと車を降りた。
俺は女が車を降りて、助手席のドアを閉めるのを見届けると、吐いて出る溜息を押し殺し、運転席のサイドポケットからグロックを取り出し車を降りる。
「淋しい所だね・・・工場だったのかな?」
『・・・さぁな、俺はココがこうなってからしか知らねえ』
「こういう所なら・・・誰も来ないね。・・・ね?ペンキ屋」
敷き詰めた砂利が所々剥げたり削れたりして、水溜りが出来ている道を歩きながら、女が相変わらずの愛想笑いを浮かべ聞いてくる。
俺はそんな女の言う事を聞き流す。
迷い?
馬鹿馬鹿しい気持ちが過ぎる。
ここまで来るまでの間、女のおしゃべりを尽く無視して気持ちを固めたつもりだった。
俺は自分の気持ちを確認し、それを女に伝える為に、グロックのマガジンをわざとらしく外し、弾倉数を確認し「カチャリ」と音を立てながら再度装填する。
女はなおも、俺のそんな動作を愛想笑いを浮かべたまま見ている。
俺の子供染みた行為が効果を示さなかった事に、俺は苛立ちを覚える。
「―――ここで降りるの?」
女が伏せ目がちに問い掛けて来る。
俺は表情を崩す事無く黙って頷く。
女は一瞬俺の顔を覗き込むようにコチラを向き、少し諦めたように作り笑いをしながら助手席のドアを開けて、シートに手を掛けながらゆっくりと車を降りた。
俺は女が車を降りて、助手席のドアを閉めるのを見届けると、吐いて出る溜息を押し殺し、運転席のサイドポケットからグロックを取り出し車を降りる。
「淋しい所だね・・・工場だったのかな?」
『・・・さぁな、俺はココがこうなってからしか知らねえ』
「こういう所なら・・・誰も来ないね。・・・ね?ペンキ屋」
敷き詰めた砂利が所々剥げたり削れたりして、水溜りが出来ている道を歩きながら、女が相変わらずの愛想笑いを浮かべ聞いてくる。
俺はそんな女の言う事を聞き流す。
迷い?
馬鹿馬鹿しい気持ちが過ぎる。
ここまで来るまでの間、女のおしゃべりを尽く無視して気持ちを固めたつもりだった。
俺は自分の気持ちを確認し、それを女に伝える為に、グロックのマガジンをわざとらしく外し、弾倉数を確認し「カチャリ」と音を立てながら再度装填する。
女はなおも、俺のそんな動作を愛想笑いを浮かべたまま見ている。
俺の子供染みた行為が効果を示さなかった事に、俺は苛立ちを覚える。
『・・・入れ』
俺は廃工場をグロックの銃口で指し示し女を促す。
女は愛想笑いを浮かべたまま頷き、ゆっくり工場の入り口の方を向き直し入って行く。
「あれ、何の機械かなぁ?」
女は構内に入るなり、目に飛び込んできた大袈裟なチェーンに吊られた機械を指差しながら、相変わらず止めない愛想笑いを浮かべ聞いてきた。
『・・・やめろ』
「え?」
『俺にそうやって笑いかけるな・・・・愛想笑いを浮かべるなら命乞いをしろ』
俺はグロックを女に向けたまま、出来る限り俺の感情が外に出ないように言い放った。
「ペンキ屋・・・アタシ愛想笑いなんかしてないし、命乞いをする気も無いわ」
女は突然真剣な顔で真っ直ぐに俺を見ながら言った。
「ペンキ屋・・・アタシは貴方と過ごせる事が楽しくて笑っていたの」
『馬鹿かお前は?!』
「何度も言ってるでしょ?アタシは馬鹿よ」
『死ぬ事はわかっているんだろう?』
「わかってるわ・・・貴方に殺されるのね?」
女の真っ直ぐな視線が俺を貫く。
真っ直ぐと見据え、決して外す事の無いような視線が俺を激しく動揺させる。
ジャリッと音が響く。
埃だらけの構内で、俺が左足を引いた音だった。
俺はたじろいだ。
女の言葉にたじろいだ。
俺は廃工場をグロックの銃口で指し示し女を促す。
女は愛想笑いを浮かべたまま頷き、ゆっくり工場の入り口の方を向き直し入って行く。
「あれ、何の機械かなぁ?」
女は構内に入るなり、目に飛び込んできた大袈裟なチェーンに吊られた機械を指差しながら、相変わらず止めない愛想笑いを浮かべ聞いてきた。
『・・・やめろ』
「え?」
『俺にそうやって笑いかけるな・・・・愛想笑いを浮かべるなら命乞いをしろ』
俺はグロックを女に向けたまま、出来る限り俺の感情が外に出ないように言い放った。
「ペンキ屋・・・アタシ愛想笑いなんかしてないし、命乞いをする気も無いわ」
女は突然真剣な顔で真っ直ぐに俺を見ながら言った。
「ペンキ屋・・・アタシは貴方と過ごせる事が楽しくて笑っていたの」
『馬鹿かお前は?!』
「何度も言ってるでしょ?アタシは馬鹿よ」
『死ぬ事はわかっているんだろう?』
「わかってるわ・・・貴方に殺されるのね?」
女の真っ直ぐな視線が俺を貫く。
真っ直ぐと見据え、決して外す事の無いような視線が俺を激しく動揺させる。
ジャリッと音が響く。
埃だらけの構内で、俺が左足を引いた音だった。
俺はたじろいだ。
女の言葉にたじろいだ。
女は両手を広げながら俺ににじり寄って来る。
可笑しな話だ。
この女は片手しか無い筈なのに、俺の目には『両手を広げ一歩一歩噛締めるように歩み寄ってくる』確かにそう見えた。
「―――アタシ、毎日つまらなかった・・・不幸せとかなのかも知れないけど、初めて会う男に脚を広げて・・・しゃぶったり、舐められたり、変態野郎は無理な注文したり、アソコに訳の分からないモノ入れられたり・・・寒気がする程に気持ち悪くて辛いのに、辛いってよりも慣れっこになってて、そんな時間が酷く退屈でつまらなかった」
女は言葉を重ねながら歩み寄ってくる。
「アタシね・・・知ってるの。・・・何でこうなったかも全部。・・・アタシね育ちは悪くないのよ、お父さんだってお母さんだっているし、高校までは全寮制の女子高に通ってたんだから。・・・その時も退屈だった。・・・だからかな?変な男に引っかかっちゃって家を出たの」
『止まれ!!俺はオメエの事なんか聞いちゃいねぇ!!』
「いいよ、撃って。・・・アタシは話したいだけなんだから」
女は俺の制止も聞かず、なおも歩み寄ってくる。
「アタシって馬鹿だし、男を見る目が無いのよね。・・・なのに男に縋って・・・本当に馬鹿だよね」
女の顔は遂には俺の構えるグロックの銃口の前まで来る。
『アサガオ・・・・本気だぞ』
「あっ!やっとアサガオって呼んでくれたね」
俺の迂闊な言葉に女は笑顔で応える。
「―――ペンキ屋、何故撃たないの?」
『お前は死にたいのか?』
「・・・フフフ、よっぽどのノイローゼでも無い限り死にたい人間なんて居ると思う?」
『お前はいったい何がしたい?!』
俺は苛立ちから声を荒げる。
「知ってるでしょペンキ屋?・・・アタシ馬鹿なの!!・・・自分でも何がしたいのか、よく分かってないの。・・・でもね、さっきも言ったように今まで退屈で死にそうだったの」
女はそう言いながら、グロックの銃口を右手の指先で押さえながらゆっくりと下げる。
そして自分の左胸のあたりに銃口をつけた。
『どうしたい?』
「・・・わからない、でも不思議とあなたに撃たれるなら・・・いいかもって思ったの」
女はそう言いながら一度グロックに目をやり、まるで銃の質感を確かめるように右手でグロックを二、三度さすった。
そしてそのまま延長線上のグロックを握る俺の右手首を握った。
俺は一瞬反射的に体が強張る。
「ただねペンキ屋」
女はそう言って視線を上げて俺の目を見る。
俺の体の強張りは緊張へと変わる。
「撃つ時は、ちゃんとアタシを見て!!・・・ううん違う!!ちゃんとアナタの目をアタシに見せて・・・お願い」
俺はグロックを握る右手に汗を感じる。
【ッターーーーッン】
俺は女の手を振り払い、グロックを天井に向け一発放つ。
広い構内の中で銃声は共鳴し、色の無い空間に強い光が放たれたような錯覚を覚える。
やがてその響きは止み、コロコロと静かな音を立てながら薬莢が女の足元に転がる。
『次は望み通りにお前の心臓に撃ち込んでやる。ナメたマネはやめろ、何のつもりだか知らんが、お前に情けを掛けるつもりは無い』
「情け?・・・そうだよね情けを求めるのが普通なんだよね?」
女は銃声に怯える事もうろたえる事も無く、ただただ俺の目を見つめたまま言葉を吐く。
「・・・だけど、お願い最後までアナタを見せて」
女は俺の顎先に右の指先を伸ばし、キスを求めるような顔で俺の顔を自分に向ける。
「・・・さぁ撃って」
『何のつもりだ?・・・色仕掛けか?』
「あら、そう見える?」
『・・・さあな』
女は俺の顎先に手を添えたまま、ゆっくりと顔を寄せてくる。
俺は壁を背にし銃口を頭に突き付けられたように動けなくなる。
女が顔を寄せると共に、必然的に女の胸突き立てられたグロックが押され、女の胸の弾力が冷たい銃身を通して伝わってくる。
頭の後ろの方に生暖かい感覚がぼんやりと蘇える。
一瞬視界を失いかけてしまう。
的を絞るように意識の線を鋭く研ぎ澄まし視界を取り戻す。
俺が視界を取り戻した時、目を閉じた女の顔はすっかりと俺の目の前に来ていた。
女の寄せる唇を、まるで処女のように震えながら受け止める。
風が構内を吹き抜ける音が心地よく耳を震わせる。
木漏れ日のように、錆び落ちたトタン屋根から差し込む日差しが、俺の頬を撫でる。
俺の鼻先に女の鼻から僅かに漏れる息が伝う。
音と色の無い世界が目の前に広がり、心音だけが体の中を駆け抜ける、俺はまた視界を失う。
女はゆっくりと唇を離し、ゆっくりと目を開ける。
そして俺の後方に退かれた右手首を持ち、再びグロックを自分の左胸に突き付けた。
「―――撃ってペンキ屋、アタシをこの世界から連れ出して」
俺は無意識に二度首を横に振る。
「駄目・・・ペンキ屋、アタシはやっと出会えた王子様を愛しながら死にたいの」
『馬鹿かお前は?!』
「何度も言わせないでアタシは馬鹿なの。・・・そしてペンキ屋が好き」
迅速な任務遂行の為に、スウェーデンの馬鹿が考えついた結果は、照準を損なう程の軽量化を施した樹脂素材を多用した銃。
そんな、銃の中でも最軽量の部類に入る「グロック18」が俺の右手には酷く重く感じる。
俺は重力に引かれるように、女の左胸に突き立てられた銃口を右手と共にぶらりと落とす。
女の真っ直ぐと見据えた目が、俺の脳裏に「京子」の映像をはっきりと蘇えらせ、そしてそれは女と重なる。
生温かい感覚が後頭部を包む。
「ペンキ屋?・・・撃たないの?」
『俺の前から消えろ』
「消える?」
『俺の目の前から失せろ・・・自分の住む世界に帰れ』
「嫌よ・・・ペンキ屋お願い」
『駄目だ!!』
俺は声を荒げ、女は一瞬ビクリと体を震わせる。
「・・・ペンキ屋?」
女の目線が僅かにズレた。
そして俺の頬に手を添え、その指先をすっと目の方へ引き上げる。
俺はこの時、水気を帯びた感覚を頬に感じた。
女はゆっくりと俺の頬に唇を寄せ、その液体を舐め上げるように頬に舌を這わす。
この作家の他の作品
表紙を見る
『詩作家共和国』
詩作家共和国スレの課題作品を主にアップしております。
少しでも心に響けば嬉しいです
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…