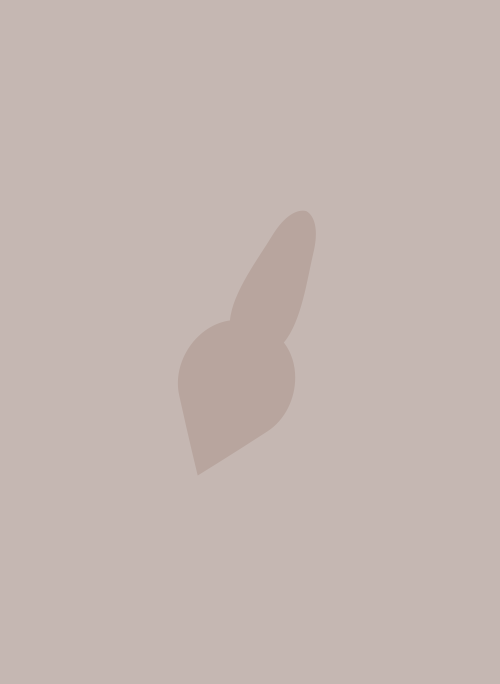「まぁ・・・その組長殺されたってのが、虎心会なんだがね」
『それがいったいどうしたって言うんだ?』
俺は、焦らすように喋る木村の言葉に、腹が立ち更に声を荒げる。
「虎心会の幹部連中は、何とか組長を殺した殺し屋まで調べ上げたんだわ・・・」
『それがペンキ屋か?』
「ああ・・・ところで中島さん、虎心会は解散したの知ってる?」
『当たり前だろ!!』
「・・・じゃぁ何で、あのバカデカイ組織が解散したか・・・知ってるかい?」
『たしか・・・』と一言吐いて、はっとする。
虎心会は、主要幹部が連続して失踪した事により、組織機能を失い、半ば空中分解的に解散した。
「虎心会の幹部連中は、ペンキ屋まで辿り着いた。・・・そしてボンッ!!消えちまった」
木村は、口の前で手を広げ、手品師の真似事をするように言った。
『・・・ペンキ屋がやったって言いてえのか?』
「そう言う噂だよ。・・・最初に都市伝説って言ったじゃねえか」
にわかに信じ難い、俺は4課じゃなかったし、ヤクザ関係には正直疎い。
ただし、虎心会ほどの組織となると、主要幹部はけして少なくない。
そして、そう言った主要幹部を消す事は容易い事では無い。
それぐらいの事は俺にも見当は付く。
木村の言っている事は本当に都市伝説としか思えない。
それに
何故木村は、これをペンキ屋の犯行だと思ったのか?
そもそも、そこが不思議で仕方無い。
『・・・何故、ペンキ屋がやったとわかる?』
「・・・追っていたからだよ。ペンキ屋を」
木村は絵画でも鑑賞するように、壁の血痕をマジマジと眺めながら言葉を吐いた。
俺は木村の言葉に固まる。
―――――アサガオ
ペンキ屋が黙ったまま、暫く経つ。
アタシは少しでも、今を楽しく演出したくて、空元気な笑顔を作り続けたけど、正直そろそろ限界。
いつもそう、アタシは楽しい時間の作り方を知らない。
無理にはしゃいでみたり、無理に笑顔を作ってみたり。
多分アタシは殺されるのに、アタシを殺そうと思ってるペンキ屋との無言の時間が堪えられずに、無理に笑顔を作っている。
拠り所になってる、アイスティーも間も無く、空になる。
お願いペンキ屋、何か言ってよ。
「―――お待たせいたしましたぁ」
拠り所のアイスティーを、アタシが「ズズズ」と底に残った分まで飲み干そうとした時に、ウェイトレスのお姉さんが、料理を運んできた。
「欲張りフライのお客様ぁ」
ペンキ屋が答えないので、アタシが右手でペンキ屋を指して、お姉さんに教える。
ウェイトレスのお姉さんは、ペンキ屋の前に「欲張りフライセット」を置いて、アタシの前に「蟹ピラフ」を一礼して置いた。
ペンキ屋は料理が来ても、黙ったままで煙草を吹かして、外を眺めている。
『・・・食べないの?』
「食えよ・・・」
『食べるけどぉ・・・』
ペンキ屋が、外を眺めたまま、こちらに目線も向けてくれないので、アタシは『いただきます』と溜息のように言って、目の前の蟹ピラフにスプーンを立てる。
最近、ろくに食事自体が疎かな上、2800円もする美味しそうな蟹ピラフが、目の前にあるのに、何故か食欲が湧かなかった。
それでも無言の時間を、少しでも解消するように、上手に炒められて美味しそうにパラパラとちらけるご飯粒を、スプーンですくい口に入れる。
何日もろくな物を食べていないのに、美味しいと思えず、アタシは寂しくなった。
ペンキ屋が黙ったまま、暫く経つ。
アタシは少しでも、今を楽しく演出したくて、空元気な笑顔を作り続けたけど、正直そろそろ限界。
いつもそう、アタシは楽しい時間の作り方を知らない。
無理にはしゃいでみたり、無理に笑顔を作ってみたり。
多分アタシは殺されるのに、アタシを殺そうと思ってるペンキ屋との無言の時間が堪えられずに、無理に笑顔を作っている。
拠り所になってる、アイスティーも間も無く、空になる。
お願いペンキ屋、何か言ってよ。
「―――お待たせいたしましたぁ」
拠り所のアイスティーを、アタシが「ズズズ」と底に残った分まで飲み干そうとした時に、ウェイトレスのお姉さんが、料理を運んできた。
「欲張りフライのお客様ぁ」
ペンキ屋が答えないので、アタシが右手でペンキ屋を指して、お姉さんに教える。
ウェイトレスのお姉さんは、ペンキ屋の前に「欲張りフライセット」を置いて、アタシの前に「蟹ピラフ」を一礼して置いた。
ペンキ屋は料理が来ても、黙ったままで煙草を吹かして、外を眺めている。
『・・・食べないの?』
「食えよ・・・」
『食べるけどぉ・・・』
ペンキ屋が、外を眺めたまま、こちらに目線も向けてくれないので、アタシは『いただきます』と溜息のように言って、目の前の蟹ピラフにスプーンを立てる。
最近、ろくに食事自体が疎かな上、2800円もする美味しそうな蟹ピラフが、目の前にあるのに、何故か食欲が湧かなかった。
それでも無言の時間を、少しでも解消するように、上手に炒められて美味しそうにパラパラとちらけるご飯粒を、スプーンですくい口に入れる。
何日もろくな物を食べていないのに、美味しいと思えず、アタシは寂しくなった。
アタシの寂しさを他所に、ペンキ屋はフライセットに手を付けず、相変わらず窓の外を眺めて、煙草を吹かしている。
アタシは少し意地になって、さも美味しそうに蟹ピラフを食べる。
本当は、楽しく喋りながら食べたいのに、アタシは味の感じられない食事を、ムキになってする。
2800円もする蟹ピラフは、ご丁寧に殻のついた蟹の足が美味しそうに盛られ、事のほかアタシは苦戦する。
フォークも上手く刺さらない殻に、最初は果敢に挑戦していたけど、努力も虚しく、優雅に蟹の身を堪能する事は出来なかった。
「―――ったく、カチャカチャうるせえ」
アタシが犬のように、顔を皿に寄せて蟹の身をほうばろうとした時に、ペンキ屋がアタシの皿を取り上げて言った。
『・・・ごめんなさい』
「犬じゃねぇんだ、そんな食い方するんじゃねえよ!!」
ペンキ屋はそう言って、「おあずけ」をするように、アタシから取り上げた皿を自分の方に寄せた。
アタシは少しバツが悪くなったように俯く。
「一人で食えねえモンを頼むんじゃねぇよ」
そう言ってペンキ屋は、ピラフの上の蟹の足を手で取り、フォークの先で身をほぐしながら、ピラフの上に蟹のほぐし身を散らした。
「―――ほれ」
そう言ってペンキ屋は、蟹のほぐし身を散らしたピラフをアタシに返した。
『あ・・・ありがとう』
アタシは、泣きそうな程嬉しい想いを押し殺し、ペンキ屋の方を見ずに言った。
ペンキ屋は、煙草を灰皿に押し付けるように揉み消し、「仕方ねえな」と言い出しそうな顔で割り箸を割り、スープで顔を洗うように箸をくぐらせて、その流れのままご飯を食べ始めた。
アタシは、ペンキ屋がほぐしてくれた蟹身をピラフとともに口に運ぶ。
『これ以上美味しいものは無い』と思えるくらい、幸せな味が口に広がった。
アタシは単純で馬鹿だから、アタシを殺すかもしれないペンキ屋の、ご飯を食べる姿を見ながら、幸せに蟹ピラフを食べる。
海沿いの温かな正午の日差しが店内に差し込んで、アタシはただ幸せな気持ちになっていた。
―――――中島
『―――そうか、分かった』
同僚からの「キューティー」って店のアサガオは戻っていないと言う報告に、俺は一言だけ応え通話を切り、木村に携帯電話を返した。
鑑識の連中が何人か部屋に入り、血痕や埃まみれの床を調べ始めた。
俺は木村と一緒に部屋の隅に腰掛け煙草を吹かしていた。
『キューティーって店のアサガオって女が、まだ戻っていないらしい・・・』
「アサガオか?片手の?」
『知ってるのか?』
「中島さん、俺は生安だぜ」
『・・・客だからじゃねえのか?』
「良い子なんだよ・・・」
俺が『おしゃぶりがか?』と聞くと木村は鼻で笑うように「ふっ」と言葉とも溜息ともつかない声を発しながら立ち上がり、尻に付いた埃をパタパタと叩いた。
「・・・もう死んじまってるかもしれねえが、アンタも見ればわかるさ」
木村が真剣な目をして諭すように言うので、俺はこれ以上木村をからかうのはやめた。
「―――世の中、不幸なんてもんは何処にでも転がってるもんさ・・・特にこの街はな」
『・・・あぁ』
「中島さん・・・アンタこの街の主要産業は知ってるかい?」
『・・・主要産業?・・・商業とか工業とかか?』
「まぁバカデカイ工業団地もあるし、輸入港もあるから間違っちゃいねえがな・・・」
大げさな荷物を運び込み、パシャパシャと手当たり次第に写真を撮る鑑識の連中を眺めながら、木村は煙草を床に捨て、靴の底で揉み消しながら言葉を続けた。
「―――この街の産業は何にしろ、根幹にあるのはセックスと暴力だよ」
『何だそれ』
「セックスと暴力が金を産み、金がセックスと暴力を引き寄せる・・・因果往訪、この街は人間の性って奴に囚われてるのさ」
『・・・哲学か?』
俺がそう言うと木村はまた鼻で笑い、座っている俺に右手を差し出し「そろそろ限界だろ?」と言って俺を起こした。
「・・・この街じゃ良い子ってのは損するもんなんだよ」
俺は木村の言葉を聞き流すように、ケツに付いた埃を叩き払った。
『―――そうか、分かった』
同僚からの「キューティー」って店のアサガオは戻っていないと言う報告に、俺は一言だけ応え通話を切り、木村に携帯電話を返した。
鑑識の連中が何人か部屋に入り、血痕や埃まみれの床を調べ始めた。
俺は木村と一緒に部屋の隅に腰掛け煙草を吹かしていた。
『キューティーって店のアサガオって女が、まだ戻っていないらしい・・・』
「アサガオか?片手の?」
『知ってるのか?』
「中島さん、俺は生安だぜ」
『・・・客だからじゃねえのか?』
「良い子なんだよ・・・」
俺が『おしゃぶりがか?』と聞くと木村は鼻で笑うように「ふっ」と言葉とも溜息ともつかない声を発しながら立ち上がり、尻に付いた埃をパタパタと叩いた。
「・・・もう死んじまってるかもしれねえが、アンタも見ればわかるさ」
木村が真剣な目をして諭すように言うので、俺はこれ以上木村をからかうのはやめた。
「―――世の中、不幸なんてもんは何処にでも転がってるもんさ・・・特にこの街はな」
『・・・あぁ』
「中島さん・・・アンタこの街の主要産業は知ってるかい?」
『・・・主要産業?・・・商業とか工業とかか?』
「まぁバカデカイ工業団地もあるし、輸入港もあるから間違っちゃいねえがな・・・」
大げさな荷物を運び込み、パシャパシャと手当たり次第に写真を撮る鑑識の連中を眺めながら、木村は煙草を床に捨て、靴の底で揉み消しながら言葉を続けた。
「―――この街の産業は何にしろ、根幹にあるのはセックスと暴力だよ」
『何だそれ』
「セックスと暴力が金を産み、金がセックスと暴力を引き寄せる・・・因果往訪、この街は人間の性って奴に囚われてるのさ」
『・・・哲学か?』
俺がそう言うと木村はまた鼻で笑い、座っている俺に右手を差し出し「そろそろ限界だろ?」と言って俺を起こした。
「・・・この街じゃ良い子ってのは損するもんなんだよ」
俺は木村の言葉を聞き流すように、ケツに付いた埃を叩き払った。
「・・・なぁアンタ本気かい?」
廃ビルの階段を脂汗を流しながら下る俺に、木村は3、4段下から見上げるように聞いてきた。
『・・・何が?』
「何がってペンキ屋だよ」
俺は木村の質問には応えず、歯を食いしばり脂汗を流しながら階段を下る。
正直、手摺りがこれ程有難いと思った事は無いくらいに、手摺りにしがみ付きながら。
「悪い事は言わねえ・・・後悔するだけだぜ」
『・・・アンタは後悔してるのか?』
「あぁ・・・後悔しかしてねえよ」
『俺は・・・アンタとは違う』
そう言って俺は、立ち止まる木村を抜かして階段を下る。
抜かし際に、木村の鼻で笑う声が聞こえたが、俺は気にせず黙々と階段を下る。
「・・・そんな怪我じゃ済まねえし・・・もっと嫌なもんも見るようになるぜ」
『ご心配はありがてえが・・・俺の気は変わらねえ』
「・・・そうか分かったよ、好きにすりゃいいさ・・・・俺は手を貸さないぜ」
『最初っから借りる気はねえよ』
俺は木村から数段進んだ所で、木村の方を向いて言った。
木村は手を焼くガキを見るように、少し困った顔をしながら俺を見ていた。
俺はすぐさま前を振り向き、また黙々と階段を下る。
諦めたような足音で、木村も階段を下り始めた。
廃ビルの階段を脂汗を流しながら下る俺に、木村は3、4段下から見上げるように聞いてきた。
『・・・何が?』
「何がってペンキ屋だよ」
俺は木村の質問には応えず、歯を食いしばり脂汗を流しながら階段を下る。
正直、手摺りがこれ程有難いと思った事は無いくらいに、手摺りにしがみ付きながら。
「悪い事は言わねえ・・・後悔するだけだぜ」
『・・・アンタは後悔してるのか?』
「あぁ・・・後悔しかしてねえよ」
『俺は・・・アンタとは違う』
そう言って俺は、立ち止まる木村を抜かして階段を下る。
抜かし際に、木村の鼻で笑う声が聞こえたが、俺は気にせず黙々と階段を下る。
「・・・そんな怪我じゃ済まねえし・・・もっと嫌なもんも見るようになるぜ」
『ご心配はありがてえが・・・俺の気は変わらねえ』
「・・・そうか分かったよ、好きにすりゃいいさ・・・・俺は手を貸さないぜ」
『最初っから借りる気はねえよ』
俺は木村から数段進んだ所で、木村の方を向いて言った。
木村は手を焼くガキを見るように、少し困った顔をしながら俺を見ていた。
俺はすぐさま前を振り向き、また黙々と階段を下る。
諦めたような足音で、木村も階段を下り始めた。
「なぁ・・・どうするんだい?これから?」
脂汗をタラタラと流しながら廃ビルから出て来た俺は、ミニパトの運転席側に座りエンジンを掛けようとした。
木村はそんな俺に慌てて駆け寄り言葉を吐いた。
『キューティーに行く』
「無茶言うな、病院に戻れよ限界だろ?」
『アンタにゃ迷惑掛けねえよ』
「もぉ・・・わかったよ!!俺がキューティーに行ってくるからアンタは病院に戻れ!!」
『気が変わったのか?』
「今日だけだよ」
木村はそう言って俺を助手席の方へ促した。
俺は痛む体を持ち上げ助手席側へ詰めた。
俺は確信していた。
今俺の中にあるのは悔しさだ。
そして後悔しかしていないと言っていた木村の中に宿るものも悔しさだ。
後悔だけじゃない。
それはさっき階段で見上げた時に、木村の目の中に脈々と生きているのが見えた。
「中島さんよ」
木村はミニパトのエンジンを掛けながら言葉を吐いた。
「・・・ペンキ屋はどんな顔をしてやがった?」
『・・・ニヤけた顔だったよ』
俺がそう言うと木村は「そうかい」と一言吐いて車を走らせ出した。
もう日が高い所まで来ていて、少しばかり蒸し暑く感じる街並みを眺めながら、俺は少しばかり疲れて狭いシートに身を沈め、ゆっくりと目を閉じた。
―――――ペンキ屋
『―――何?』
「だからぁ・・・アサガオって呼んでくれる?」
この女は本当に馬鹿なのか?
それとも何か思い違いをしているのか?
「さっきから・・・オイ女!!とかじゃ、楽しく食べられないじゃん」
どうやら思い違いの甚だしい馬鹿らしい。
残念ながら俺には『この女』にこれ以上付き合う気は無い、悪いが楽しくなくて結構だ。
食事は俺にとって食欲を満たす行為でしか無え。
腹が減る。
食事する。
腹が満ちる。
ただそれだけだ。
ここ何年も一人で食事をしていた。
その行為に楽しさを求めようとも思わねえし、今日久しぶりに誰かと食事するからと言って特別な想いを持とうとも思わねえ。
俺は女のお喋りを無視して、目の前の『食い物』をただ胃に流し込む。
「・・・トマト」
『・・・何?』
「だからぁトマト嫌いなの?」
迂闊にも女の言葉に反応しちまった。
既視感に似た感覚が俺を油断させちまったらしい。
俺は皿の端に除けたトマトを見つめて、女の言葉を頭の中で反芻する。
そして鮮明に頭に浮かんだ映像を振り払うように、トマトから目を離し汗をかいたグラスに残っていたアイスコーヒーを口に含む。
女はそんな俺を見つめながら「トマトが嫌いなのか」と言う質問の答えをニコニコしながら待っていやがる。
似ている
俺の頭の中に馬鹿げた考えが浮かぶ。
『―――何?』
「だからぁ・・・アサガオって呼んでくれる?」
この女は本当に馬鹿なのか?
それとも何か思い違いをしているのか?
「さっきから・・・オイ女!!とかじゃ、楽しく食べられないじゃん」
どうやら思い違いの甚だしい馬鹿らしい。
残念ながら俺には『この女』にこれ以上付き合う気は無い、悪いが楽しくなくて結構だ。
食事は俺にとって食欲を満たす行為でしか無え。
腹が減る。
食事する。
腹が満ちる。
ただそれだけだ。
ここ何年も一人で食事をしていた。
その行為に楽しさを求めようとも思わねえし、今日久しぶりに誰かと食事するからと言って特別な想いを持とうとも思わねえ。
俺は女のお喋りを無視して、目の前の『食い物』をただ胃に流し込む。
「・・・トマト」
『・・・何?』
「だからぁトマト嫌いなの?」
迂闊にも女の言葉に反応しちまった。
既視感に似た感覚が俺を油断させちまったらしい。
俺は皿の端に除けたトマトを見つめて、女の言葉を頭の中で反芻する。
そして鮮明に頭に浮かんだ映像を振り払うように、トマトから目を離し汗をかいたグラスに残っていたアイスコーヒーを口に含む。
女はそんな俺を見つめながら「トマトが嫌いなのか」と言う質問の答えをニコニコしながら待っていやがる。
似ている
俺の頭の中に馬鹿げた考えが浮かぶ。
『・・・食いたくねぇだけだ』
俺は既視感に頭を混乱させられる。
女のおしゃべりに付き合うつもりもねえのに、女の質問に応える。
昔同じ事を言われて、同じ言葉を返した。
ただそれだけの事だが、俺は自然と自分の胸の高鳴りを覚える。
別に恋だの愛だのガキっぽい感情の高鳴りじゃねえ。
女が何て言い返すのかを期待する。
アイツに似ているこの女が何て言い返すのかを
「・・・そうなの?でも食べた方が良いよ」
『・・・フッ』
「何?」
『別に何でもねえよ』
俺は女の言葉に思わず吹き出し、少し気恥ずかしく思って照れくさくなりアイスコーヒーをすする。
「何?何なの?」
『何でもねえよ・・・ただ』
「ただ?」
『・・・ただ何でもねえ』
「何よそれ!!」
女はそう言ってふて腐れた顔を浮かべて俺を睨んだ。
『何処までも似ていやがる』その言葉は俺の口を吐いて出る事は無かった。
そして俺は少しばかり嫌な感情が胸に上がり、外の日差しに目をやる。
俺は既視感に頭を混乱させられる。
女のおしゃべりに付き合うつもりもねえのに、女の質問に応える。
昔同じ事を言われて、同じ言葉を返した。
ただそれだけの事だが、俺は自然と自分の胸の高鳴りを覚える。
別に恋だの愛だのガキっぽい感情の高鳴りじゃねえ。
女が何て言い返すのかを期待する。
アイツに似ているこの女が何て言い返すのかを
「・・・そうなの?でも食べた方が良いよ」
『・・・フッ』
「何?」
『別に何でもねえよ』
俺は女の言葉に思わず吹き出し、少し気恥ずかしく思って照れくさくなりアイスコーヒーをすする。
「何?何なの?」
『何でもねえよ・・・ただ』
「ただ?」
『・・・ただ何でもねえ』
「何よそれ!!」
女はそう言ってふて腐れた顔を浮かべて俺を睨んだ。
『何処までも似ていやがる』その言葉は俺の口を吐いて出る事は無かった。
そして俺は少しばかり嫌な感情が胸に上がり、外の日差しに目をやる。
入り江に近い形になっている海岸線を辿ると、遠くに臨海工業地帯の建物の影が見える、海の先に目をやると薄っすらと水平線のあたりにタンカーらしき物が見える。
夏程でもないが、強い日差しが俺の目に飛び込んでくる。
無機質な物が海にゆらゆらと揺らいでいるようで、俺は自然と目を細める。
俺の頭の中にアイツが浮かんで、俺は外から目を外し顔を正面に戻す。
瞬きがスローモーションのように感じ、その一瞬の暗闇の後目を開けると、目の前に一瞬アイツが現れて、次の瞬きが訪れる。
次の瞬間に俺の目の前に現れたのは、あの女だった。
アイツによく似た左手の無い女だった。
女は本当に美味しそうに、片手でピラフを食べていた。
俺は汗をかいたグラスに注がれたアイスコーヒーを、また一口すすり喉奥に流し込む。
ヒヤリとした物が俺の喉を通り過ぎる時、自分の馬鹿げた事に腹が立ち始めた。
俺は混乱した気持ちを振り切れずにいる。
この女が居る事が俺にとって危険なんだと本能が叫ぶ。
女には悪いが、やはり死んでもらうしかないようだ。
俺は揺ぎ無い自分で居たい。
アイツと同じ事を聞き。
アイツと同じ事を言った。
アイツに雰囲気の似ている「アサガオ」には今日を最後にしてもらう。
この作家の他の作品
表紙を見る
『詩作家共和国』
詩作家共和国スレの課題作品を主にアップしております。
少しでも心に響けば嬉しいです
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…