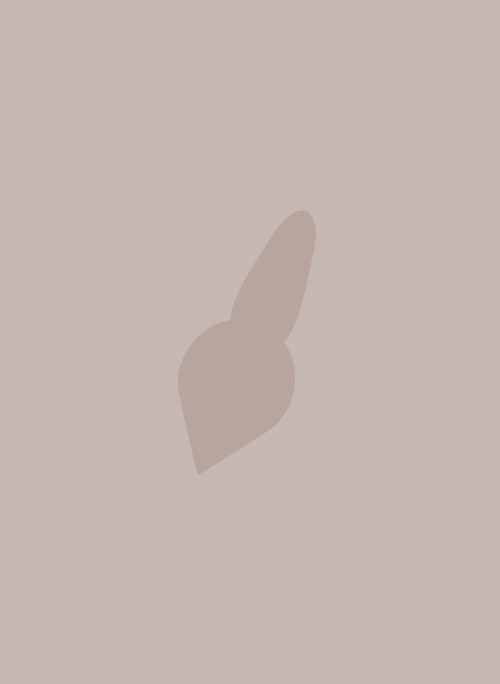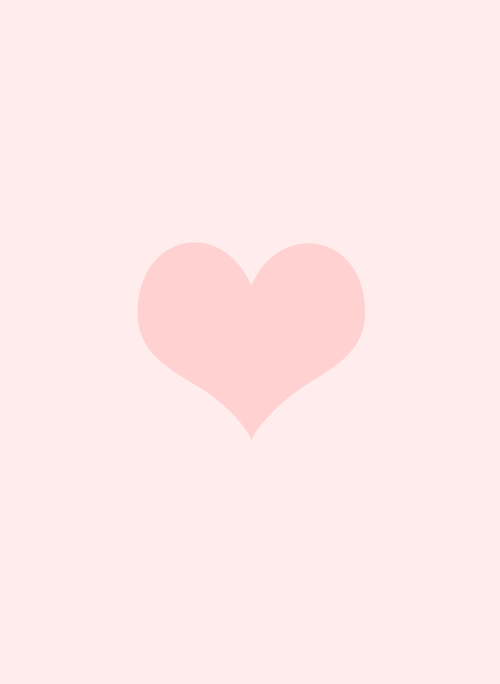―――――ペンキ屋
警察が市街地に向かう国道に検問を張っていた。
通勤時間と重なり国道は流れが悪くなっている。
俺は座り心地の悪いバケット型のミニのシートに時折不快感から体を捩りながら、検問の列の最後尾に車を付ける。
検問の目的はおそらくは俺だろう。
十分もすると俺の乗ってるミニが検問を受ける。
制服警官が頭を下げながら窓を開けるようにジェスチャーで促しながら歩み寄って来た。
「すみません免許証を・・・御協力をお願いします」
『はい』
俺はポケットから免許証を取り出す。
そして素知らぬ顔で『何か?』と付け加える。
「えぇ・・・ちょっと事件がありまして・・・これからお仕事ですか?おおにし・・・大西和樹さん?」
『ええ・・・今日は現場がこっちなもんで』
「現場?・・・あっちょっと免許証かりますよ」
そう言って、その制服警官はもう一人の制服警官に免許証を渡す。
免許証を渡された制服は照合する為に免許証を持ってパトカーへ向かう。
警察が市街地に向かう国道に検問を張っていた。
通勤時間と重なり国道は流れが悪くなっている。
俺は座り心地の悪いバケット型のミニのシートに時折不快感から体を捩りながら、検問の列の最後尾に車を付ける。
検問の目的はおそらくは俺だろう。
十分もすると俺の乗ってるミニが検問を受ける。
制服警官が頭を下げながら窓を開けるようにジェスチャーで促しながら歩み寄って来た。
「すみません免許証を・・・御協力をお願いします」
『はい』
俺はポケットから免許証を取り出す。
そして素知らぬ顔で『何か?』と付け加える。
「えぇ・・・ちょっと事件がありまして・・・これからお仕事ですか?おおにし・・・大西和樹さん?」
『ええ・・・今日は現場がこっちなもんで』
「現場?・・・あっちょっと免許証かりますよ」
そう言って、その制服警官はもう一人の制服警官に免許証を渡す。
免許証を渡された制服は照合する為に免許証を持ってパトカーへ向かう。
『日雇いの工事現場の人足なんですよ』
「そうですか・・・ところでコチラはあなたの車?」
『いや・・・友達のなんです』
「そうですか・・・大西さんはお車は?」
『俺の稼ぎじゃ外車なんか無理ですよ、俺の車は軽です。・・・ただし今車検切れてて』
そうこう話していると、もう一人の制服が免許証を持って戻って来た。
「大西和樹さん・・・問題ありません」
「・・・そうか」
『・・・行ってもいいですか?遅刻したら親方がうるさくて』
「あっはい結構です。・・・あと軽自動車はくれぐれも車検切れで乗らないように」
『あっはいはい』
俺が検問を抜ける時にルームミラーを覗くと、制服警官は俺にしたのと同じジェスチャーを後続の車にもやっていた。
この街では、こう言う場面に多々遭遇する。
その原因が今日の様に、俺の場合もあったりするが、仮にそうじゃないとしても俺はこういった場面に慣れてないとならない。
俺の名前は「大西和樹」でも無いし、免許証の住所に住んでいる訳でも無い。
それに俺の乗っている車が常に俺の車と言う訳では無い。
それと、いつもいつもヤル気の無い。この街の警官共に感謝せざるおえない。
「そうですか・・・ところでコチラはあなたの車?」
『いや・・・友達のなんです』
「そうですか・・・大西さんはお車は?」
『俺の稼ぎじゃ外車なんか無理ですよ、俺の車は軽です。・・・ただし今車検切れてて』
そうこう話していると、もう一人の制服が免許証を持って戻って来た。
「大西和樹さん・・・問題ありません」
「・・・そうか」
『・・・行ってもいいですか?遅刻したら親方がうるさくて』
「あっはい結構です。・・・あと軽自動車はくれぐれも車検切れで乗らないように」
『あっはいはい』
俺が検問を抜ける時にルームミラーを覗くと、制服警官は俺にしたのと同じジェスチャーを後続の車にもやっていた。
この街では、こう言う場面に多々遭遇する。
その原因が今日の様に、俺の場合もあったりするが、仮にそうじゃないとしても俺はこういった場面に慣れてないとならない。
俺の名前は「大西和樹」でも無いし、免許証の住所に住んでいる訳でも無い。
それに俺の乗っている車が常に俺の車と言う訳では無い。
それと、いつもいつもヤル気の無い。この街の警官共に感謝せざるおえない。
居心地の悪いシートに、俺は落ち着かないまま自分の部屋の前に着いた。
自分で言うのも何だが、殺風景な部屋の鍵を開ける。
そして俺は殺風景でブラインドで日差しの遮られた暗い部屋の無愛想な金庫の鍵を開けて金を取り出しテーブルの上に置き、ウォークインクローゼットの中から御あつらえ向けのバッグを探す。
だがクローゼットの中で片手に収まる五百万の束を入れるのに理想的な大きさのバッグがある筈も無い。
俺はTシャツか何かを買った時の洋品屋のビニール袋に五百万を入れた。
俺は今日は仕事が終わったら帰って来て、すぐに眠りに就くつもりでいた。
だが生憎と今日はこの後に用事がある事を思い少し気が落ちた。
俺は渋々とブラインドを開けて部屋に日を入れる。
溜め込んでいた物を吐き出すように光は部屋に差し込んだ。
俺は眩しさに目を細める。
『俺は何をしているんだ?』
俺のバランスが崩れている事に、俺は気付かぬ振りをしていたが、意識を失いそうになる程眩しい日差しが、俺に無理矢理事実を突きつける。
『何故、俺が女と飯を食わなけりゃならない?』
少し浮ついた気持ちになっていた自分に腹が立つ。
そして俺は急にヒドイ喉の渇きを覚えて冷蔵庫に向かう。
冷蔵庫の中を開けて缶ビールを取り出し一気に喉奥に流し込む。
自分の気持ちの整理も付かないまま、イラつきながら俺は部屋を出て車に向かう。
マンションの前に止まっているここまで乗ってきた右ハンドルのミニにもう一度乗るかと思うと俺は更にイラついた。
女と食事をするのも馬鹿らしく腹立たしいが、俺は約束を破るのが嫌いだ。
だから車屋に金を渡し、新しい車を受け取ったら約束通りに女に食事をご馳走しよう。
『殺すのはその後でいいだろう』
あの女は俺のバランスを壊した。
―――――中島
俺は看護師が止めるのも聞かずに点滴を外しベットから這い出る。
病室に残っていた同僚が間抜けな面をしたまま「どうしたんだよ?」「おかしくなっちまったのか?」と俺を止めようと俺に問い掛けてきた。
俺がこの街に来てから一度も見せた事の無い行動に同僚は酷く慌てている様だった。
俺は痛みに耐えながら同僚の腕を振り払う。
『俺の刺された場所に連れてってくれ』
俺の顔を覗き込みながら同僚は間抜けな顔を浮かべたまま黙って頷いた。
「みんな現場や検問にかり出されて空いてる車が無えらしい・・・」
同僚は困った様に携帯を切り、俺をさとす様な口調で言った。
『・・・じゃぁ悪いがタクシー手配してくれるか?』
病室を無理矢理抜けて、俺は総合病院のただっ広いエントランスの長椅子に痛みを堪えながら座り、同僚の顔を見る事無く言った。
「・・・あるにはあるんだが、交通課のミニパトでも良いか?」
『なんでもいい・・・兎に角俺は・・・俺と若造の刺された所へ行けりゃぁいいんだよ』
そう俺が言うと同僚はまた困った顔をしながら携帯をかけて、ミニパトを手配し、面倒な奴から逃げる様に俺をエントランスに残したままそそくさと立ち去った。
俺は看護師が止めるのも聞かずに点滴を外しベットから這い出る。
病室に残っていた同僚が間抜けな面をしたまま「どうしたんだよ?」「おかしくなっちまったのか?」と俺を止めようと俺に問い掛けてきた。
俺がこの街に来てから一度も見せた事の無い行動に同僚は酷く慌てている様だった。
俺は痛みに耐えながら同僚の腕を振り払う。
『俺の刺された場所に連れてってくれ』
俺の顔を覗き込みながら同僚は間抜けな顔を浮かべたまま黙って頷いた。
「みんな現場や検問にかり出されて空いてる車が無えらしい・・・」
同僚は困った様に携帯を切り、俺をさとす様な口調で言った。
『・・・じゃぁ悪いがタクシー手配してくれるか?』
病室を無理矢理抜けて、俺は総合病院のただっ広いエントランスの長椅子に痛みを堪えながら座り、同僚の顔を見る事無く言った。
「・・・あるにはあるんだが、交通課のミニパトでも良いか?」
『なんでもいい・・・兎に角俺は・・・俺と若造の刺された所へ行けりゃぁいいんだよ』
そう俺が言うと同僚はまた困った顔をしながら携帯をかけて、ミニパトを手配し、面倒な奴から逃げる様に俺をエントランスに残したままそそくさと立ち去った。
20分程すると、くたびれた顔をしたオヤジが俺の前に立っていた。
情けない事に、俺は痛みを堪える事に必死になっていたらしく、オヤジが目の前に近付いて来た事すら気が付かなかった。
「中島さんかい?」
『・・・あぁ』
「―――大丈夫かい?アンタ?油汗かいてるぜ」
『大した事じゃ無え』
「・・・そうかい、・・じゃぁ行こうか?」
俺はオヤジに導かれるまま、駐車場に停めたミニパトに向かった。
「悪いねぇ狭いだろう?いつもアンタらの乗ってるセダンとは雲泥の差だろ?・・・あっアンタらはクラウンだったかな?」
『あんた・・・交通課だったか?』
「いや・・・俺は生安だが・・・俺を知ってるのかい?」
『いや、交通課じゃなかった気がしただけだ』
「俺はアンタを知ってるぜ、まっもっとも噂でだけだがな」
『・・・噂?』
「ボロ雑巾・・・アンタが陰で呼ばれてる名前だよ」
オヤジは表情一つ変える事なく、淡々と話しながらシートベルトを締めて、ミニパトのエンジンを掛けた。
『悪いが・・・今日はそんなボロ雑巾に付き合ってもらうぜ』
「あぁ構わんさ」
オヤジは相変わらず表情を変える事無く淡々と車を走らせ始めた。
そして駐車場から道路へ出る時に左右を確認しながら俺の方を見た。
「・・・噂とは違う様だな」
『・・・何がだ?』
「ボロ雑巾にしては気持ちの入った目付きだ」
『・・・そうか?』
「あぁ・・・俺は木村だ生活安全課の木村」
そう言って木村は俺にタバコを差し出した。
情けない事に、俺は痛みを堪える事に必死になっていたらしく、オヤジが目の前に近付いて来た事すら気が付かなかった。
「中島さんかい?」
『・・・あぁ』
「―――大丈夫かい?アンタ?油汗かいてるぜ」
『大した事じゃ無え』
「・・・そうかい、・・じゃぁ行こうか?」
俺はオヤジに導かれるまま、駐車場に停めたミニパトに向かった。
「悪いねぇ狭いだろう?いつもアンタらの乗ってるセダンとは雲泥の差だろ?・・・あっアンタらはクラウンだったかな?」
『あんた・・・交通課だったか?』
「いや・・・俺は生安だが・・・俺を知ってるのかい?」
『いや、交通課じゃなかった気がしただけだ』
「俺はアンタを知ってるぜ、まっもっとも噂でだけだがな」
『・・・噂?』
「ボロ雑巾・・・アンタが陰で呼ばれてる名前だよ」
オヤジは表情一つ変える事なく、淡々と話しながらシートベルトを締めて、ミニパトのエンジンを掛けた。
『悪いが・・・今日はそんなボロ雑巾に付き合ってもらうぜ』
「あぁ構わんさ」
オヤジは相変わらず表情を変える事無く淡々と車を走らせ始めた。
そして駐車場から道路へ出る時に左右を確認しながら俺の方を見た。
「・・・噂とは違う様だな」
『・・・何がだ?』
「ボロ雑巾にしては気持ちの入った目付きだ」
『・・・そうか?』
「あぁ・・・俺は木村だ生活安全課の木村」
そう言って木村は俺にタバコを差し出した。
シートに伝わる小刻みな振動が必要以上に俺に苦痛を与えようとする。
ズキズキと足と腕の傷に舗装の悪い道の凹凸が響く。
俺は路面の凹凸に合わせる様に体を強張らせる。
時折、木村が怪訝そうな顔で俺の方を見ているのが感じ取れる。
「・・・血」
『・・・んぁ?』
「血が滲んでる・・・ダッシュボードにポケットティッシュ入ってるだろうから」
『あぁ・・・悪い』
「俺は構わねぇが、交通課のネェちゃん達が乗る車なんでね。・・・汚ねぇシミつくったら俺が文句言われるからよぉ」
俺は無言でダッシュボードを開けて、ポケットティッシュを取り出し、傷口から繊維を通して滲み出てくる血を含ませる。
「一生懸命になったって得は無えと思うがねぇ」
『・・・だろうな』
俺はそれ以上木村に何も話す気は無い。
木村も端から俺を諭すつもりは無かっただろうが、現場に着くまでにそれ以上何も俺に問いかける事は無かった。
現場に着くと数人の警官と鑑識の人間が、傍から見ても容易に見当が付くほどヤル気の無い顔でヤル気の無い現場検証をしていた。
木村が交通の邪魔にならない様に、ミニパトを歩道に乗り上げて電柱の前に停める。
ミニパトを歩道に乗り上げる時に、木村は何の躊躇も無く段差に踏み込んだので、俺の体にこの上ない痛みが走り、俺は木村の顔を思い切り張りたい気持ちになったが、それ以上に痛みを耐える事に必死だった。
路上に広がるおびただしい血痕。
この場面だけを切り取ったニュース映像が流れたら、尋常じゃない出来事を一般の人間は想像するだろうに・・・
この街の人間は、ただ怪訝そうな顔をして道の端から横目で通り過ぎるだけだった。
別に珍しい事じゃない事くらいは俺にもわかっている。
この通りに関して言えば年間に何度となく、物取りや腐れヤクザ共のイザコザなんかで、こう言った場面には出くわす事が多い。
俺もおそらくは「刺されたのが自分じゃなくて良かった」と安堵しながら横目で会社までの道のりを急いだ事だろう。
ただし今の俺には麻痺しちまった感覚を、無数の針で覚醒させようとする「奴」のニヤケ顔が頭から離れず、この街の人間に嫌悪感すら覚える。
「そっちばかり見てたって仕方ねぇんじゃねぇかい?」
木村が気の抜けた調子で、俺の目線を現場に戻す。
『あぁ』
俺も気の無い返事を木村に返す。
「あんたが連れて来いって言ったんだぜ」
『あぁ』
「じゃぁとっとと済ませてくれよ・・・中島さんよぉ」
『中は調べたか?』
「・・・中って?」
『・・・このビルだよ』
木村はそれ以上は何も聞かず、「ハイハイ」とふて腐れたガキみたいな顔をして二、三度頷き、近くに居た制服警官を呼び寄せた。
この場面だけを切り取ったニュース映像が流れたら、尋常じゃない出来事を一般の人間は想像するだろうに・・・
この街の人間は、ただ怪訝そうな顔をして道の端から横目で通り過ぎるだけだった。
別に珍しい事じゃない事くらいは俺にもわかっている。
この通りに関して言えば年間に何度となく、物取りや腐れヤクザ共のイザコザなんかで、こう言った場面には出くわす事が多い。
俺もおそらくは「刺されたのが自分じゃなくて良かった」と安堵しながら横目で会社までの道のりを急いだ事だろう。
ただし今の俺には麻痺しちまった感覚を、無数の針で覚醒させようとする「奴」のニヤケ顔が頭から離れず、この街の人間に嫌悪感すら覚える。
「そっちばかり見てたって仕方ねぇんじゃねぇかい?」
木村が気の抜けた調子で、俺の目線を現場に戻す。
『あぁ』
俺も気の無い返事を木村に返す。
「あんたが連れて来いって言ったんだぜ」
『あぁ』
「じゃぁとっとと済ませてくれよ・・・中島さんよぉ」
『中は調べたか?』
「・・・中って?」
『・・・このビルだよ』
木村はそれ以上は何も聞かず、「ハイハイ」とふて腐れたガキみたいな顔をして二、三度頷き、近くに居た制服警官を呼び寄せた。
―――――ペンキ屋
『はっ・・・大したオヤジ』
俺は珍しく自分の目を疑う。
俺の仕事を済ませたビルの前に中島とか言った中年刑事が居た。
致命傷とまではいかなかったが、意識を保って歩いていられるような傷じゃ無い筈だ。
それを、わざわざ現場まで赴いて自分の惨劇を確認しているんだから、よっぽどの物好きか、よっぽどのイカレ野郎だ。
俺は敬意を払って、ゆっくりと交通整備の警官に従い現場の横を通過する。
中島は、中島を更にくたびれさせた感じのオヤジに、何か話し込んでいて俺に気付かない。
通勤の群れに混じったミニに乗った俺に、中島が気付かないまま、俺は現場の横を通りきった。
気味の悪い感覚を覚える。
俺は自分の感覚を疑いながら、ルームミラーを覗く。
中島は俺が仕事を済ませた雑居ビルに入ろうとした瞬間だった。
堪らない違和感が鳥肌を立てながら俺の視界に飛び込んでくる。
中島は体を雑居ビルに向けたまま歩みを止めて、ずっと俺の方を見ていた。
俺は敢えて慌てる事無く、ミニをゆっくりと通勤の車の波と共に滑らせた。
そんな俺の車を中島は微動だにせずに見続けていた。
奴が米粒大の大きさになり確認出来なく成る程離れても、俺は奴の視線を背中に感じる事が出来た。
打って出る気配は無かった。
だが奴は確実に俺に気付き、そしてやり過ごした。
『はっ・・・大したオヤジ』
俺は珍しく自分の目を疑う。
俺の仕事を済ませたビルの前に中島とか言った中年刑事が居た。
致命傷とまではいかなかったが、意識を保って歩いていられるような傷じゃ無い筈だ。
それを、わざわざ現場まで赴いて自分の惨劇を確認しているんだから、よっぽどの物好きか、よっぽどのイカレ野郎だ。
俺は敬意を払って、ゆっくりと交通整備の警官に従い現場の横を通過する。
中島は、中島を更にくたびれさせた感じのオヤジに、何か話し込んでいて俺に気付かない。
通勤の群れに混じったミニに乗った俺に、中島が気付かないまま、俺は現場の横を通りきった。
気味の悪い感覚を覚える。
俺は自分の感覚を疑いながら、ルームミラーを覗く。
中島は俺が仕事を済ませた雑居ビルに入ろうとした瞬間だった。
堪らない違和感が鳥肌を立てながら俺の視界に飛び込んでくる。
中島は体を雑居ビルに向けたまま歩みを止めて、ずっと俺の方を見ていた。
俺は敢えて慌てる事無く、ミニをゆっくりと通勤の車の波と共に滑らせた。
そんな俺の車を中島は微動だにせずに見続けていた。
奴が米粒大の大きさになり確認出来なく成る程離れても、俺は奴の視線を背中に感じる事が出来た。
打って出る気配は無かった。
だが奴は確実に俺に気付き、そしてやり過ごした。
相手が警察であったとしても、分は俺にある筈だった。
だが中島の視線には余裕すら感じ取れたように俺は思ってしまう。
満腹のライオンが目の前で、無邪気にはしゃぐインパラの群れをやり過ごすように、中島がまるで俺を余裕でやり過ごしたように俺は感じてしまった。
俺はやっかい事が嫌いだ。
中島の目線を思い返す度に、俺は座り心地の悪いミニのバケットシートに苛立ちを覚え、何度も体を捩る。
『くそっ・・・やっかいだ』
俺は中島にとどめを刺さなかった事を後悔する。
正直見くびっていた自分に腹が立つ。
『・・・だが中島一人に何が出来る?』
仮に奴が俺に辿り着いた所で、俺をどう出来る?
『焦る事は無い』
俺は言い聞かせるように結論付ける。
俺には、まだ済まさなきゃならない事が残っている。
これ以上やっかいな事を増やしたくない。
『まずは女から始末しとかなきゃ・・・な』
俺は居心地の悪いシートも後少しの辛抱と自分に言い聞かせながら、ミニを郊外の車屋の倉庫に走らせる。
この作家の他の作品
表紙を見る
『詩作家共和国』
詩作家共和国スレの課題作品を主にアップしております。
少しでも心に響けば嬉しいです
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…