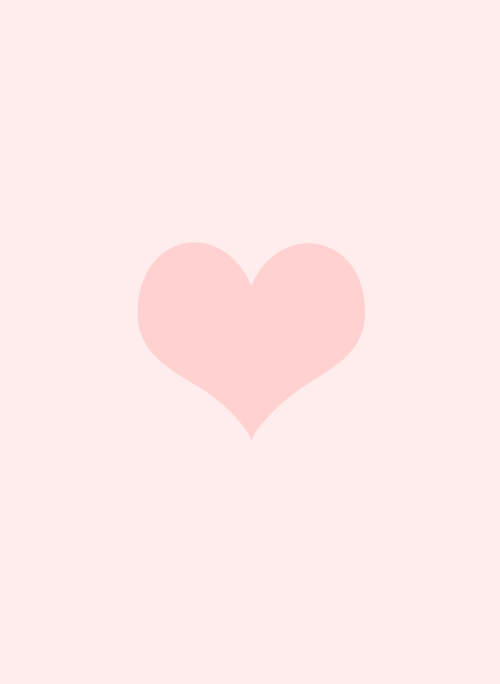「あんた、もう舞台に立たれへんとかゆうとったけど、何も劇場だけが踊る場所やないやろ?」
「せやけど……」
「あんたらの世界の事は、よう判らんけど、あんたがやりたいんは、裸になる事やなくて、踊って何かを表現する事とちゃうの?
たまたまその表現の仕方が、自分の身体を使ってというだけやない」
「うん……」
雅子の言葉で姿月は全てが救われて行くような気持ちになって行った。
「何でも、物事前向きに考えれば何とかなるもんよ」
「うん……」
「元々、前向きなんは、ノリちゃんの専売特許やろ。」
「そやね……」
涙で濡れた姿月の顔に漸く笑顔が浮かんだ。
「散々泣いたからお腹空いたやろ?
昔から、泣いた後はお腹が空くって相場が決まっとるんや」
それ程歳の差が離れてる訳ではないのに、雅子がまるで母親のように思えて来た。
「ママ……」
「何?」
「此処に来て良かった……ありがとう」
「もう、そんな事言われたら照れるやろ。ご飯、ご飯」
そう言って再び台所に立つ雅子の後ろ姿を見ながら、姿月は今言われた事をじっくりと考えてみた。
アタシは舞台をやりたいんや……
来年の五周年でストリップを引退する……
前々からそう自分で決めてはいたが、それはストリップから身を引くという事で、何も踊る事迄やめる気は無かった。
どういう方向に行くかという具体的な計画や進路は、何も決めてはいなかったが、確かな事は、自分はまだ舞台に立っていたいという気持ちがある事だ。
そこのところは全然ぶれていない。
表現する場所……
それをこれから探して行けばいいやんか……
惜しむらくは、ストリップの世界で、この四年近くの間、ストリッパー『姿月』を応援してくれていたファンに、きちんとサヨナラを言えずに去って行かなければならないという事だ。
それだけが心残りと言える。
新たな道へ進むにしても、これ迄の区切りだけはちゃんとしておきたかった。
姿月は、荷物の中からノートパソコンを取り出し、自分のホームページに書き込みを始めた。
「せやけど……」
「あんたらの世界の事は、よう判らんけど、あんたがやりたいんは、裸になる事やなくて、踊って何かを表現する事とちゃうの?
たまたまその表現の仕方が、自分の身体を使ってというだけやない」
「うん……」
雅子の言葉で姿月は全てが救われて行くような気持ちになって行った。
「何でも、物事前向きに考えれば何とかなるもんよ」
「うん……」
「元々、前向きなんは、ノリちゃんの専売特許やろ。」
「そやね……」
涙で濡れた姿月の顔に漸く笑顔が浮かんだ。
「散々泣いたからお腹空いたやろ?
昔から、泣いた後はお腹が空くって相場が決まっとるんや」
それ程歳の差が離れてる訳ではないのに、雅子がまるで母親のように思えて来た。
「ママ……」
「何?」
「此処に来て良かった……ありがとう」
「もう、そんな事言われたら照れるやろ。ご飯、ご飯」
そう言って再び台所に立つ雅子の後ろ姿を見ながら、姿月は今言われた事をじっくりと考えてみた。
アタシは舞台をやりたいんや……
来年の五周年でストリップを引退する……
前々からそう自分で決めてはいたが、それはストリップから身を引くという事で、何も踊る事迄やめる気は無かった。
どういう方向に行くかという具体的な計画や進路は、何も決めてはいなかったが、確かな事は、自分はまだ舞台に立っていたいという気持ちがある事だ。
そこのところは全然ぶれていない。
表現する場所……
それをこれから探して行けばいいやんか……
惜しむらくは、ストリップの世界で、この四年近くの間、ストリッパー『姿月』を応援してくれていたファンに、きちんとサヨナラを言えずに去って行かなければならないという事だ。
それだけが心残りと言える。
新たな道へ進むにしても、これ迄の区切りだけはちゃんとしておきたかった。
姿月は、荷物の中からノートパソコンを取り出し、自分のホームページに書き込みを始めた。
「佐伯さん、姿月さんが自分のホームページに引退の事を書いてたよ」
常連客の一人が、わざわざプリントアウトしたものを僕に見せた。
長い文章の始まりは、応援してくれたファンへのお詫びだった。
そして、最後の舞台と認識せず、結果的に幕引きの舞台となったあの十一日間の事が書かれてあった。
二度、三度と読み返した僕は、最後に書かれてあった、
『……一度観てみたいと思っていた本場のカルメンでも観に行こうかと思います。』
の一文を読んで、
いつか又、舞台に戻ってくれるんだ……
と勝手に想像した。
踊り子が出演予定の劇場に穴を開け、失踪したり、そのまま業界から消えて行くといった事は、別段珍しい事では無い。
日常茶飯事的な出来事で、その時は大きく噂にはなっても、一ヶ月も経てば遠い過去の話しになってしまう。
そういう業界なのだ。
簡単に忘れ去られてしまう業界なのだ。
真っ当に引退興行をし、多くのファンに見送られて舞台を去って行く踊り子の方が、寧ろ少ないかも知れない。
自然消滅的に消えて行く者が多い中、彼女の引退はある意味、小さくない波紋を広げたのではないかと僕は感じていた。
その一方で、観る側の者でさえ、良い踊り子のステージからはストリップを超越した何かを感じ取ってくれるくせに、感動を提供する側が、
たかが裸踊り、若くて可愛い女が素っ裸になりゃあ客は喜ぶんだ。
と、客を舐めている事実。
プライドもへったくれも無い、踊り子をただの道具としか見ない劇場関係者。
そして、悲しい事に舞台に立つ踊り子達の多くが、そういう考えを肯定している。
安くない金を払って足を運んで来る客達が、たかが裸踊りと思う分には構わない。
そう思っている彼等達に、そうじゃないんだと思わせるものを提供すれば、自ずと観る目が変わって行くものなのだ。
現実に、あの十一日間でそういった出会いを体験出来た者が少なくなかった筈だ。
そういった客達の間から、自分達で何とか姿月の引退興行をやれないだろうかという話しが出て来た。
常連客の一人が、わざわざプリントアウトしたものを僕に見せた。
長い文章の始まりは、応援してくれたファンへのお詫びだった。
そして、最後の舞台と認識せず、結果的に幕引きの舞台となったあの十一日間の事が書かれてあった。
二度、三度と読み返した僕は、最後に書かれてあった、
『……一度観てみたいと思っていた本場のカルメンでも観に行こうかと思います。』
の一文を読んで、
いつか又、舞台に戻ってくれるんだ……
と勝手に想像した。
踊り子が出演予定の劇場に穴を開け、失踪したり、そのまま業界から消えて行くといった事は、別段珍しい事では無い。
日常茶飯事的な出来事で、その時は大きく噂にはなっても、一ヶ月も経てば遠い過去の話しになってしまう。
そういう業界なのだ。
簡単に忘れ去られてしまう業界なのだ。
真っ当に引退興行をし、多くのファンに見送られて舞台を去って行く踊り子の方が、寧ろ少ないかも知れない。
自然消滅的に消えて行く者が多い中、彼女の引退はある意味、小さくない波紋を広げたのではないかと僕は感じていた。
その一方で、観る側の者でさえ、良い踊り子のステージからはストリップを超越した何かを感じ取ってくれるくせに、感動を提供する側が、
たかが裸踊り、若くて可愛い女が素っ裸になりゃあ客は喜ぶんだ。
と、客を舐めている事実。
プライドもへったくれも無い、踊り子をただの道具としか見ない劇場関係者。
そして、悲しい事に舞台に立つ踊り子達の多くが、そういう考えを肯定している。
安くない金を払って足を運んで来る客達が、たかが裸踊りと思う分には構わない。
そう思っている彼等達に、そうじゃないんだと思わせるものを提供すれば、自ずと観る目が変わって行くものなのだ。
現実に、あの十一日間でそういった出会いを体験出来た者が少なくなかった筈だ。
そういった客達の間から、自分達で何とか姿月の引退興行をやれないだろうかという話しが出て来た。
一人の踊り子の為に、ファンやその踊り子を慕う別な踊り子も含めて、何とかちゃんとした引退興行をやらせて上げたいという声が沸き上がる事自体、稀有なケースだ。
いかに姿月のステージに魅せられた者が多いかが判る。
だが残念な事に、これは実現しなかった。
元の所属劇場との関係を考えて、わざわざ協力しようなどと言う業界関係者は一人も現れなかった。
もう二度と姿月にライトを当てる事は無い……
悔しさと悲しさが交錯し、気持ちの中に見えない空間が一つ出来た。
新しい感動に出会えれば、それで多少は空いた隙間を埋める事が出来たかも知れないが、姿月の代わりは姿月以外には埋められない。
彼女が与えてくれたものの大きさを僕らは失って初めて気付いた。
あの十一日間の奇跡は、やはり奇跡だったのだ。
真夏の夜の夢……
いや、夢と呼ぶには余りにも鮮烈過ぎる時間だった。
故に、十年以上経った今もそれは色褪せていない。
これから先も褪せる事は無いだろう。
そして、僕はあの時以上の感動を授かる事無く、姿月同様、ストリップの世界から身を引いた。
いかに姿月のステージに魅せられた者が多いかが判る。
だが残念な事に、これは実現しなかった。
元の所属劇場との関係を考えて、わざわざ協力しようなどと言う業界関係者は一人も現れなかった。
もう二度と姿月にライトを当てる事は無い……
悔しさと悲しさが交錯し、気持ちの中に見えない空間が一つ出来た。
新しい感動に出会えれば、それで多少は空いた隙間を埋める事が出来たかも知れないが、姿月の代わりは姿月以外には埋められない。
彼女が与えてくれたものの大きさを僕らは失って初めて気付いた。
あの十一日間の奇跡は、やはり奇跡だったのだ。
真夏の夜の夢……
いや、夢と呼ぶには余りにも鮮烈過ぎる時間だった。
故に、十年以上経った今もそれは色褪せていない。
これから先も褪せる事は無いだろう。
そして、僕はあの時以上の感動を授かる事無く、姿月同様、ストリップの世界から身を引いた。
姿月の引退を知った龍之助は、あの舞台をもう観れないのかと思うと残念で仕方無かった。
描きかけの絵を仕上げるには、もう一度彼女のステージを観るのが一番と思っていたからだ。
あの後、何度か劇場に足を運び、他の踊り子のステージを観た。
プロのダンサー顔負けの踊りを見せてくれる踊り子も居た。
アイドルタレント並に若くて可愛い踊り子とも出会えた。
だがあの時、姿月から受けたような衝撃は、ただの一度も味わえなかった。
この絵は未完のままになってしまうのか……
大きな羽根を手にした裸像の絵は、まさに姿月そのものであった。
龍之助は、そのキャンパスに布を掛け、筆を置いた。
描きかけの絵を仕上げるには、もう一度彼女のステージを観るのが一番と思っていたからだ。
あの後、何度か劇場に足を運び、他の踊り子のステージを観た。
プロのダンサー顔負けの踊りを見せてくれる踊り子も居た。
アイドルタレント並に若くて可愛い踊り子とも出会えた。
だがあの時、姿月から受けたような衝撃は、ただの一度も味わえなかった。
この絵は未完のままになってしまうのか……
大きな羽根を手にした裸像の絵は、まさに姿月そのものであった。
龍之助は、そのキャンパスに布を掛け、筆を置いた。
虚しい日々が続いていた。
姿月が業界から姿を消してから約半年後、僕もストリップの世界を離れた。
あれ程、照明の仕事が自分にとっての天職とさえ思っていたのにだ。
ただ食って行く為だけの生活……
人はパンのみにて生きて行くのではない……
何かに飢えていた。
毎日が渇きの連続。
そんな中、何年振りかで姿月の姿を見た。
何の気無しにコンビニで手にした雑誌に彼女が出ていた。
小さな写真ではあったが、その記事で彼女がイベントやクラブなどを活躍の場としている事が判った。
食い入るようにその記事を読み返した。
自分の生き様を貫ける強さを羨ましく思い、その雑誌を買った。
彼女は足掻くように舞台に立ち続けている。
自分を場末のキャバレー回りと卑下してはいても、ダンサーとしてのプライドと魂は他の誰よりも崇高なものだと感じ取れた。
彼女の足掻く姿を心から羨ましく思い、それに比べて、足掻く事さえしなかった自分の情け無さに、茫然自失となった。
美しき足掻き……
理由も無く、ただぬるま湯に浸るが如くその場に留まる事は足掻きでも何でも無い。
足掻きもせず流されるだけの人間が多い中、改めて彼女の舞台をもう一度観てみたいなと思った。
ストリップ業界を離れてからこの方、僕はただの一度も劇場に行っていない。
個人的に観てみたいなと思える踊り子が居ない訳ではない。
あれから十年……
僕がライトを当てた踊り子の中には、まだ現役で頑張っている子も居る。
たまに名前を雑誌や新聞の紹介記事で見た時には、懐かしさを感じはするが、何故か直接劇場に足を運ぼうとはしなかった。
あれ程、ステージに魅せられていたのに……
今でも、あの十一日間の事を夢に見る。
僕が創り出す光りの中で、姿月は美神の如く恍惚の笑みを浮かべている……
そう、僕の創り出す光りの中で……
姿月が業界から姿を消してから約半年後、僕もストリップの世界を離れた。
あれ程、照明の仕事が自分にとっての天職とさえ思っていたのにだ。
ただ食って行く為だけの生活……
人はパンのみにて生きて行くのではない……
何かに飢えていた。
毎日が渇きの連続。
そんな中、何年振りかで姿月の姿を見た。
何の気無しにコンビニで手にした雑誌に彼女が出ていた。
小さな写真ではあったが、その記事で彼女がイベントやクラブなどを活躍の場としている事が判った。
食い入るようにその記事を読み返した。
自分の生き様を貫ける強さを羨ましく思い、その雑誌を買った。
彼女は足掻くように舞台に立ち続けている。
自分を場末のキャバレー回りと卑下してはいても、ダンサーとしてのプライドと魂は他の誰よりも崇高なものだと感じ取れた。
彼女の足掻く姿を心から羨ましく思い、それに比べて、足掻く事さえしなかった自分の情け無さに、茫然自失となった。
美しき足掻き……
理由も無く、ただぬるま湯に浸るが如くその場に留まる事は足掻きでも何でも無い。
足掻きもせず流されるだけの人間が多い中、改めて彼女の舞台をもう一度観てみたいなと思った。
ストリップ業界を離れてからこの方、僕はただの一度も劇場に行っていない。
個人的に観てみたいなと思える踊り子が居ない訳ではない。
あれから十年……
僕がライトを当てた踊り子の中には、まだ現役で頑張っている子も居る。
たまに名前を雑誌や新聞の紹介記事で見た時には、懐かしさを感じはするが、何故か直接劇場に足を運ぼうとはしなかった。
あれ程、ステージに魅せられていたのに……
今でも、あの十一日間の事を夢に見る。
僕が創り出す光りの中で、姿月は美神の如く恍惚の笑みを浮かべている……
そう、僕の創り出す光りの中で……
「龍さん、今度の個展に出してる作品の中でちょっと変わった絵があったじゃない……」
「変わった絵?」
「そう、こう両手に大きな羽根を持っている裸の女性のやつ」
「ああ、あれか。あれがどうした?」
「一番先に買い手が決まったよ」
「買い手……」
「そう、それで幾ら位の値段を付けたらいいかなと思ってさ」
今回の個展を段取りしてくれた友人が、我が事のように満面の笑みを浮かべて龍之助に聞いて来た。
「あれは、売るつもりは無いんだ」
「売るつもりは無いって……。
そうか、先方はかなり気に入ってたみたいなんだけどなぁ」
「済まないが、どうしてもあれだけは売りたく無いんだ。」
「判った。残念だけど作者本人がそう言うんだから仕方が無いか。
ところでさ、あの絵のモデルって、居るのかい?」
「勿論居るけど」
「何か気になる絵だよなあ。モデルになった女性を直に見てみたいもんだ」
「見れるさ。機会があれば……」
「え?紹介してくれんの?」
「いや、紹介は出来ないけど、何時か機会があれば、あんたも何処かで出会えるかも知れない」
「何だよ、勿体付けちゃって。
あっ、そうか、モデルは実在の人物じゃなく、龍さんの頭の中で想い描いたもの……つまり、バーチャルって事な訳だな。
それならそうと早く言ってくれよ。ふぅん……。
龍さんの趣味が大体読めて来たよ」
実在の人物さ……
俺の頭の中から生まれた女性じゃない……
まあ幻のような人だけど……
舞台上で観た姿月の姿を思い浮かべながら、龍之助はそう呟いた。
未完のまま数年間放置されていたその絵が完成したのは、つい先日の事だ。
今回の個展にぎりぎり間に合った。
ストリップの世界から一旦消えた姿月と再び出会えたのは、たまたま見た彼女のホームページからであった。
彼女は踊る事を辞めていなかった。
あの時と同じ彼女に再び出会えた。
そして、あの絵を完成させた。
キャンパスの中でも彼女は光りを求めているような眼差しを見せていた。
「変わった絵?」
「そう、こう両手に大きな羽根を持っている裸の女性のやつ」
「ああ、あれか。あれがどうした?」
「一番先に買い手が決まったよ」
「買い手……」
「そう、それで幾ら位の値段を付けたらいいかなと思ってさ」
今回の個展を段取りしてくれた友人が、我が事のように満面の笑みを浮かべて龍之助に聞いて来た。
「あれは、売るつもりは無いんだ」
「売るつもりは無いって……。
そうか、先方はかなり気に入ってたみたいなんだけどなぁ」
「済まないが、どうしてもあれだけは売りたく無いんだ。」
「判った。残念だけど作者本人がそう言うんだから仕方が無いか。
ところでさ、あの絵のモデルって、居るのかい?」
「勿論居るけど」
「何か気になる絵だよなあ。モデルになった女性を直に見てみたいもんだ」
「見れるさ。機会があれば……」
「え?紹介してくれんの?」
「いや、紹介は出来ないけど、何時か機会があれば、あんたも何処かで出会えるかも知れない」
「何だよ、勿体付けちゃって。
あっ、そうか、モデルは実在の人物じゃなく、龍さんの頭の中で想い描いたもの……つまり、バーチャルって事な訳だな。
それならそうと早く言ってくれよ。ふぅん……。
龍さんの趣味が大体読めて来たよ」
実在の人物さ……
俺の頭の中から生まれた女性じゃない……
まあ幻のような人だけど……
舞台上で観た姿月の姿を思い浮かべながら、龍之助はそう呟いた。
未完のまま数年間放置されていたその絵が完成したのは、つい先日の事だ。
今回の個展にぎりぎり間に合った。
ストリップの世界から一旦消えた姿月と再び出会えたのは、たまたま見た彼女のホームページからであった。
彼女は踊る事を辞めていなかった。
あの時と同じ彼女に再び出会えた。
そして、あの絵を完成させた。
キャンパスの中でも彼女は光りを求めているような眼差しを見せていた。
高速バスに揺られ、姿月は今日の仕事をぼんやりと振り返っていた。
もう何年も前から仕事を回して貰っているキャバレーだったが、このところの不景気で客の入りが芳しくなく、年内一杯で店を閉めるという。
フロアダンサーといえば聞こえは良いが、やってる仕事の殆どが地方都市のキャバレー回り。
たまにクラブとかのイベントに呼ばれる事もあるが、メインの収入源にはならない。
楽な生活では無い。
プロダクションに所属はしているが、仕事の殆どは自分で管理している。
当てになる仕事先が一つ減るという事は、新しい仕事先を見つけなければならないという事だ。
そろそろかな……
自分なりに引き際は決めている。
ずるずる流されて迄この仕事にしがみつく気持ちは無い。
ここ迄続けて来た原動力ってなんやろ……
最近、そういう事をよく考える。
前に、雑誌のインタビューでこれと同じ質問をされた事があった。
「年に何回もあるわけやないんやけど、舞台やってて背中に電気が走るような感覚になる事があるんです。
自己陶酔なんでしょうけど、舞台と客席、光りと自分がピッタリとマッチして、ああ、やってて良かったなあって心から思えて来るんです。その年に何回もない感覚を追い求めて続けてるのかも」
心底、偽りのない気持ちでインタビューに答えた。
ストリップ業界に居た年数を何時しか越え、一応フロアダンサーとしての姿月というものを確立して来た。
自分が踊れる場であれば、そこがどんなに悪条件の場所であっても文句一つ言わず踊り続けて来た。
ストリップ時代から応援してくれているファンも少なくないが、最近はフロアダンサーになってからのファンの方が多い。
今度は、今度こそは、ちゃんとサヨナラを言うから……
まだ姿月は、あの光りを求めている。
幕は少しずつ降りてはいるが……
2009.2.15(完)
もう何年も前から仕事を回して貰っているキャバレーだったが、このところの不景気で客の入りが芳しくなく、年内一杯で店を閉めるという。
フロアダンサーといえば聞こえは良いが、やってる仕事の殆どが地方都市のキャバレー回り。
たまにクラブとかのイベントに呼ばれる事もあるが、メインの収入源にはならない。
楽な生活では無い。
プロダクションに所属はしているが、仕事の殆どは自分で管理している。
当てになる仕事先が一つ減るという事は、新しい仕事先を見つけなければならないという事だ。
そろそろかな……
自分なりに引き際は決めている。
ずるずる流されて迄この仕事にしがみつく気持ちは無い。
ここ迄続けて来た原動力ってなんやろ……
最近、そういう事をよく考える。
前に、雑誌のインタビューでこれと同じ質問をされた事があった。
「年に何回もあるわけやないんやけど、舞台やってて背中に電気が走るような感覚になる事があるんです。
自己陶酔なんでしょうけど、舞台と客席、光りと自分がピッタリとマッチして、ああ、やってて良かったなあって心から思えて来るんです。その年に何回もない感覚を追い求めて続けてるのかも」
心底、偽りのない気持ちでインタビューに答えた。
ストリップ業界に居た年数を何時しか越え、一応フロアダンサーとしての姿月というものを確立して来た。
自分が踊れる場であれば、そこがどんなに悪条件の場所であっても文句一つ言わず踊り続けて来た。
ストリップ時代から応援してくれているファンも少なくないが、最近はフロアダンサーになってからのファンの方が多い。
今度は、今度こそは、ちゃんとサヨナラを言うから……
まだ姿月は、あの光りを求めている。
幕は少しずつ降りてはいるが……
2009.2.15(完)
この作家の他の作品
表紙を見る
たまには、少しばかり昔を懐かしんで……
出したくても、書く事すら出来なかった手紙
ほのかに残る想い出は 果たして何通の手紙になるのだろう
2009.4.24 一通目
表紙を見る
現実は、小説やドラマの世界みたいに、それほどドラマチックなものじゃない。
でも、時々神様はびっくりするような時間をプレゼントしてくれる事がある。
それは僕に関しても同様だった。
アニータ……
見知らぬ国からやって来た彼女と、僕は一つ屋根の下で暮らす事になった。
以来、僕の中でいろんなものが、シャボン玉のように弾けては飛んだ。
悪戯好きの神様がくれた17歳最後の夏。
僕は新しい扉に手を掛けた……
アクタガワ ナオキ
『こういう小説も、私の中から生まれて来るんだ……
そんな不思議な感覚に包まれながら
書いています
稲葉禎和 』
愛水様
素敵なレビューありがとうございまいた!
表紙を見る
表の世界では生きられない男達がいる。
欲望の赴くままに…
己の力だけでのし上がる…
そんな、ありふれた安っぽいハードボイルド小説のような事は、現実の世界では通じない。
誰しもが持っている力への憧れ…
富と権力…そして、暴力…
ならず者…凶漢、 デスペラードな男達の物語。
*近々こちらを非公開にさせて頂きます。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…