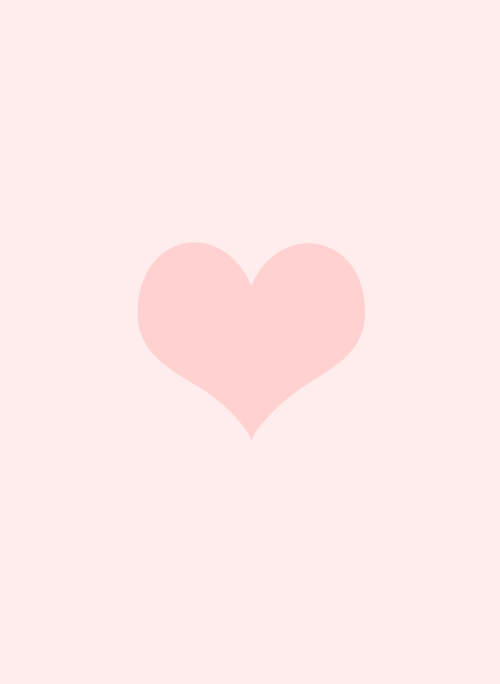客席の片隅で私は涙さえ流していた。
改めて自分がこの世界の奥深さに魅せられた事に気付かされた。
ストリップ……
単なる裸踊り
全裸になり、大勢の男の前で猥褻なポーズを取り見世物になる……
大概の人間はストリップをそういう認識で捕らえるだろう。その通りだ。
だが、そうではない部分を見つけた時、人間は大きな感動を受ける。
そこに理屈は存在しない。
観たままのもの、生に伝わって来るものが、観る者の心を揺り動かし、感動をも与えてくれるのだ。
若くて可愛いとか、綺麗なだけのストリッパーのステージからは、そういったものは生まれない。
いずみリカのステージを観て涙を流す位に感動はしたが、後々考えてみると、それは消え行く者への惜別の情から生まれた涙だった。
彼女のステージは確かに素晴らしかった。
それはストリップというよりも、ダンスそのものであり、本来あるべきエロスはかけらも感じられないものであった。
踊り子達は、その殆どがダンスが上手くなりたいと願い、単なる裸踊りにはしたく無いと思っている。
それはそれで間違ってはいない。
自分を向上させて行く為に日々、ダンスのレッスンに明け暮れる踊り子も少なく無い。
デビューして日の浅い踊り子の深夜レッスンに朝まで付き合い、泣きながら振り付けを覚えようとする姿にカルチャーショックを受けたからこそ、自分は照明というものを疎かに出来ないと感じた訳である。
だが、ストリップに於ける本物の感動は、それ以上の何かが無ければ生まれて来ない。
お金を払う客の反応が全てを物語っている。
酔っ払った勢いで劇場にやって来る客達がそういったステージを観て、自分の想像を超えたものを目にした時、間違い無く押し黙る。
裸になる度に嬌声を上げ、時には非常識な態度を取ろうとする酔客がである。
つまらないからではない。
その姿を照明室から見れた時、共にその時間を共有出来た事に、劇場の照明マンは言葉に表せない喜びに浸り、踊り子との一体感を噛み締める。
だが、なかなかそういうステージに出会う事は少ない。
平成十年八月のお盆興行の出演者が決まったのは、その二週間前の事であった。
改めて自分がこの世界の奥深さに魅せられた事に気付かされた。
ストリップ……
単なる裸踊り
全裸になり、大勢の男の前で猥褻なポーズを取り見世物になる……
大概の人間はストリップをそういう認識で捕らえるだろう。その通りだ。
だが、そうではない部分を見つけた時、人間は大きな感動を受ける。
そこに理屈は存在しない。
観たままのもの、生に伝わって来るものが、観る者の心を揺り動かし、感動をも与えてくれるのだ。
若くて可愛いとか、綺麗なだけのストリッパーのステージからは、そういったものは生まれない。
いずみリカのステージを観て涙を流す位に感動はしたが、後々考えてみると、それは消え行く者への惜別の情から生まれた涙だった。
彼女のステージは確かに素晴らしかった。
それはストリップというよりも、ダンスそのものであり、本来あるべきエロスはかけらも感じられないものであった。
踊り子達は、その殆どがダンスが上手くなりたいと願い、単なる裸踊りにはしたく無いと思っている。
それはそれで間違ってはいない。
自分を向上させて行く為に日々、ダンスのレッスンに明け暮れる踊り子も少なく無い。
デビューして日の浅い踊り子の深夜レッスンに朝まで付き合い、泣きながら振り付けを覚えようとする姿にカルチャーショックを受けたからこそ、自分は照明というものを疎かに出来ないと感じた訳である。
だが、ストリップに於ける本物の感動は、それ以上の何かが無ければ生まれて来ない。
お金を払う客の反応が全てを物語っている。
酔っ払った勢いで劇場にやって来る客達がそういったステージを観て、自分の想像を超えたものを目にした時、間違い無く押し黙る。
裸になる度に嬌声を上げ、時には非常識な態度を取ろうとする酔客がである。
つまらないからではない。
その姿を照明室から見れた時、共にその時間を共有出来た事に、劇場の照明マンは言葉に表せない喜びに浸り、踊り子との一体感を噛み締める。
だが、なかなかそういうステージに出会う事は少ない。
平成十年八月のお盆興行の出演者が決まったのは、その二週間前の事であった。
時間は既に夜中の十二時を過ぎている。
暦が替わり、日付は八月の一日。
新たに始まる十日間の為に、僕はライトのゼラチン(色を変える為のフィルム)を新しいものに交換していた。
それと、少ないライトの数をどうにか効果的にしようと、その角度を変えたりする作業に没頭していた。
盆と正月は劇場にとっての掻き入れ時だ。
どの劇場も普段以上に出演者を豪華にしようと、人気の踊り子の取り合いになる。
AV(アダルトビデオ)というものが世に現れ、その世界からストリップへと流れて来る踊り子が増えて来てからというもの、どの劇場もAV出身の踊り子を客寄せのメインにしようとした。
確かに集客力はある。
だが、それも程度というものがあって、聞いた事も無いような名前のAV嬢なんかが出演しても、それ程の有り難みは無いものだ。
姿月という踊り子も元AVという冠を被されていた。
前日迄出演していた踊り子の中に、二人ばかり姿月の後輩が居た。
彼女達から姿月の事をちらっと聞いていたが、話しから想像した姿月の印象は、
気難しい踊り子……
照明に厳しい踊り子……
であった。
まあ、それ位ならどうって事ないか……
照明の注文がどう煩かろうが、うちの照明じゃ遣れる事が決まってる……
開き直り……
初日を迎える準備というものは、ちょっと不思議な高揚感に包まれる。
まだ半年にも満たない劇場経験だから、初めて出会う踊り子の方が多い。
心の何処かで何かを期待している自分が居る。
楽屋の部屋割も決まり、数時間後には出演する踊り子達が乗り込んで来る。
一足先に荷物だけ送られて来ていた。
姿月のものだ。
「重いなぁ」
若いマネージャーが呟く。
「そう言えば、カンナちゃんが言ってましたけど、姿月さんと百華さんは香盤も部屋も別の方がいいよって」
「面倒クセエなあ」
初対面の前から、従業員の間に於ける姿月の印象はマイナスポイントばかりが累積されていた。
暦が替わり、日付は八月の一日。
新たに始まる十日間の為に、僕はライトのゼラチン(色を変える為のフィルム)を新しいものに交換していた。
それと、少ないライトの数をどうにか効果的にしようと、その角度を変えたりする作業に没頭していた。
盆と正月は劇場にとっての掻き入れ時だ。
どの劇場も普段以上に出演者を豪華にしようと、人気の踊り子の取り合いになる。
AV(アダルトビデオ)というものが世に現れ、その世界からストリップへと流れて来る踊り子が増えて来てからというもの、どの劇場もAV出身の踊り子を客寄せのメインにしようとした。
確かに集客力はある。
だが、それも程度というものがあって、聞いた事も無いような名前のAV嬢なんかが出演しても、それ程の有り難みは無いものだ。
姿月という踊り子も元AVという冠を被されていた。
前日迄出演していた踊り子の中に、二人ばかり姿月の後輩が居た。
彼女達から姿月の事をちらっと聞いていたが、話しから想像した姿月の印象は、
気難しい踊り子……
照明に厳しい踊り子……
であった。
まあ、それ位ならどうって事ないか……
照明の注文がどう煩かろうが、うちの照明じゃ遣れる事が決まってる……
開き直り……
初日を迎える準備というものは、ちょっと不思議な高揚感に包まれる。
まだ半年にも満たない劇場経験だから、初めて出会う踊り子の方が多い。
心の何処かで何かを期待している自分が居る。
楽屋の部屋割も決まり、数時間後には出演する踊り子達が乗り込んで来る。
一足先に荷物だけ送られて来ていた。
姿月のものだ。
「重いなぁ」
若いマネージャーが呟く。
「そう言えば、カンナちゃんが言ってましたけど、姿月さんと百華さんは香盤も部屋も別の方がいいよって」
「面倒クセエなあ」
初対面の前から、従業員の間に於ける姿月の印象はマイナスポイントばかりが累積されていた。
八月一日の朝が来た。
劇場の最上階に住み込んでいた僕は、何時もより一時間ばかり早く階下の事務所に降りた。
クリーニングしたてのワイシャツに着替え、身支度をする。軽く腹拵えをして一階の劇場受付へ行くと、既に客が並んでいた。
数を数えてみる。
七、八、九……
十四、五人は並んでいた。
久し振りだな……
開場迄まだ一時間近くある。
この客達が、全部今日から始まるステージの踊り子達目当てとは思っていなかった。
お盆特別興行として、昼の二回だけAV紛いの企画ステージを組んでいた。
それ目当ての客なんだろうと思いながら、場内をチェックし、乗り込んで来る踊り子達の到着を待ち望んでいた。
十時近くなると一人、又一人と出演する踊り子達がやって来た。
楽屋に案内し、出し物の音を受け取る。
一枚のMDに落としてくれている踊り子も居れば、何枚かのCDを渡し、
「このCDの何曲目と、こっちの何曲目で、最後はこれね」
と、無造作に言い、舞台化粧に没頭する踊り子も居る。
CDやMDを受け取りながら、簡単に照明のポイントを聞き、メモにして行く。
この頃、僕が照明のメインだったから、初日の一回目は必ず担当した。
「あたし、ここで一旦袖に引っ込むから、暗転して欲しいの。ここ、ブラックライトあります?」
「すいません、ブラックライトは無いんです」
「あたしは板付けで、ダンスの時は適当にパキパキした照明にしてくれればいいわ。後は任す」
劇場のキャパや照明設備に限界がある事を踊り子達は良く判っている。
余り期待されてないな……
そう感じる時もあれば、どうせ言った通りには出来ないでしょう的な諦めの空気を感ずる時もある。
姿月が乗り込んで来た。
楽屋に出向く。
少しばかり緊張している自分が居た。
「はじめまして、照明を担当します佐伯と言います」
我ながら随分と堅苦しい挨拶をしたものだと思った。
こちらに向き直った姿月は、一瞬後退りしそうになる位に綺麗だった。
劇場の最上階に住み込んでいた僕は、何時もより一時間ばかり早く階下の事務所に降りた。
クリーニングしたてのワイシャツに着替え、身支度をする。軽く腹拵えをして一階の劇場受付へ行くと、既に客が並んでいた。
数を数えてみる。
七、八、九……
十四、五人は並んでいた。
久し振りだな……
開場迄まだ一時間近くある。
この客達が、全部今日から始まるステージの踊り子達目当てとは思っていなかった。
お盆特別興行として、昼の二回だけAV紛いの企画ステージを組んでいた。
それ目当ての客なんだろうと思いながら、場内をチェックし、乗り込んで来る踊り子達の到着を待ち望んでいた。
十時近くなると一人、又一人と出演する踊り子達がやって来た。
楽屋に案内し、出し物の音を受け取る。
一枚のMDに落としてくれている踊り子も居れば、何枚かのCDを渡し、
「このCDの何曲目と、こっちの何曲目で、最後はこれね」
と、無造作に言い、舞台化粧に没頭する踊り子も居る。
CDやMDを受け取りながら、簡単に照明のポイントを聞き、メモにして行く。
この頃、僕が照明のメインだったから、初日の一回目は必ず担当した。
「あたし、ここで一旦袖に引っ込むから、暗転して欲しいの。ここ、ブラックライトあります?」
「すいません、ブラックライトは無いんです」
「あたしは板付けで、ダンスの時は適当にパキパキした照明にしてくれればいいわ。後は任す」
劇場のキャパや照明設備に限界がある事を踊り子達は良く判っている。
余り期待されてないな……
そう感じる時もあれば、どうせ言った通りには出来ないでしょう的な諦めの空気を感ずる時もある。
姿月が乗り込んで来た。
楽屋に出向く。
少しばかり緊張している自分が居た。
「はじめまして、照明を担当します佐伯と言います」
我ながら随分と堅苦しい挨拶をしたものだと思った。
こちらに向き直った姿月は、一瞬後退りしそうになる位に綺麗だった。
彼女は僕に一枚の紙を差し出し、
「一応、この段取りで照明して欲しいねん。幕ありで、この部分の照明は、お兄さんのセンスに任すけど、暗転のタイミングだけは、ずらさんといて欲しいねん」
姿月は衣装ケースの中からMDを取り出し、これが音と言って僕に手渡して来た。
何時も以上に緊張している自分が居た。
「正直言って、うちの照明はたいして数もないし、フラットな照明ですから満足して貰える出来になるかどうか……」
「それはかまへん。取り敢えずダンスの所をそれなりに派手にしてくれて、頭の部分との差を付けてくれればええから」
彼女の関西弁が何気に心地良かった。
一回目の開演が近付く。
この時の顔触れを十年経った今でもハッキリと覚えている。
トップは新宿の有名劇場所属の『百華』
二番目に同じ劇場所属で、まだデビューして間もない『小室亜美』
三番目は姿月を慕う『小夏』
四番目が、大阪は九条の劇場から来た『河仲美樹』
五番目に千葉の劇場時代にもライトを当てた事のある『向井レイ』
トリ前が東のロック、西の十三と呼ばれた有名劇場所属の人気娘『綾波ナナ』
そしてトリが『姿月』だった。
金の取れる顔触れだった。
実際の話し、シアター アート程度の小屋にしてみれば、かなりの顔触れだった。
一回目の開演時間になった。
何時も以上に客の入りが良いように感じた。
時間が来た。
開演のアナウンスをする。
新しい十日間の始まり。
そして、それは新しい感動の出会いでもあった。
「一応、この段取りで照明して欲しいねん。幕ありで、この部分の照明は、お兄さんのセンスに任すけど、暗転のタイミングだけは、ずらさんといて欲しいねん」
姿月は衣装ケースの中からMDを取り出し、これが音と言って僕に手渡して来た。
何時も以上に緊張している自分が居た。
「正直言って、うちの照明はたいして数もないし、フラットな照明ですから満足して貰える出来になるかどうか……」
「それはかまへん。取り敢えずダンスの所をそれなりに派手にしてくれて、頭の部分との差を付けてくれればええから」
彼女の関西弁が何気に心地良かった。
一回目の開演が近付く。
この時の顔触れを十年経った今でもハッキリと覚えている。
トップは新宿の有名劇場所属の『百華』
二番目に同じ劇場所属で、まだデビューして間もない『小室亜美』
三番目は姿月を慕う『小夏』
四番目が、大阪は九条の劇場から来た『河仲美樹』
五番目に千葉の劇場時代にもライトを当てた事のある『向井レイ』
トリ前が東のロック、西の十三と呼ばれた有名劇場所属の人気娘『綾波ナナ』
そしてトリが『姿月』だった。
金の取れる顔触れだった。
実際の話し、シアター アート程度の小屋にしてみれば、かなりの顔触れだった。
一回目の開演時間になった。
何時も以上に客の入りが良いように感じた。
時間が来た。
開演のアナウンスをする。
新しい十日間の始まり。
そして、それは新しい感動の出会いでもあった。
昼過ぎ辺りから客の入りが一気に増え出した。
何時もの常連は勿論の事、ストリップとは縁の無さそうなタイプの客も入って来ている。
開演してから二時間も過ぎると、ついには場内入口の扉が閉まらなくなった。
舞台袖辺りに陣取っていた踊り子達の追っ掛け達は、後から後からと入って来る客に押し寄せられ、身動きが取れなくなり、トイレにも行けない始末となった。
一人ワンステージ約二十分から二十五分。
無難にそれぞれのステージが進行して行く。
(あのな、今回の出し物は、女郎蜘蛛って言って、デカイ被りもんみたいな衣装やねん。見た目殆どコントやで)
僕にそう告げた姿月の笑顔が浮かんで来た。
トリ前のステージが終わる。
客席は立ち見を含め、照明室から見下ろすと、人の頭しか見えない。
暇な時は数人なんて時もあって、無意識のうちに仕事のやる気も低くなっているものだ。
客の入りが良ければ照明をする自分のテンションも上がる。
照明マンとしては、どんな状況下であっても、常に最高の仕事を目指すのが当たり前なのだが、この辺りの心持ちは正直言って偽ざるところだ。
一呼吸置いて、姿月の名前をアナウンスする。
音出し。
閉められた緞帳の向こうで、舞台中央にスタンバイする姿月の気配を感じた。
緞帳のスイッチに指を掛け、流れ出した音楽と同時に押した。
幕が開く。
舞台中央で黒い塊と化している姿月。
真後ろから淡いブルーのライトを当て、逆光にする。
舞台天井からは細いスポットを落とし、彼女の姿が逆光の中に浮かぶようにした。
蜘蛛を形作った馬鹿でかい衣装を背負うかのように着、ゆったりとした動作で顔を上げ始めた。
顔の動きに合わせ、照明室からピンスポットを開けて行く。
絞りを徐々に開け、光りの輪の中に、女郎蜘蛛がいる。
開演前に見た姿月の姿はそこにはなかった。
僕の背中に軽い電気が走った。
何時もの常連は勿論の事、ストリップとは縁の無さそうなタイプの客も入って来ている。
開演してから二時間も過ぎると、ついには場内入口の扉が閉まらなくなった。
舞台袖辺りに陣取っていた踊り子達の追っ掛け達は、後から後からと入って来る客に押し寄せられ、身動きが取れなくなり、トイレにも行けない始末となった。
一人ワンステージ約二十分から二十五分。
無難にそれぞれのステージが進行して行く。
(あのな、今回の出し物は、女郎蜘蛛って言って、デカイ被りもんみたいな衣装やねん。見た目殆どコントやで)
僕にそう告げた姿月の笑顔が浮かんで来た。
トリ前のステージが終わる。
客席は立ち見を含め、照明室から見下ろすと、人の頭しか見えない。
暇な時は数人なんて時もあって、無意識のうちに仕事のやる気も低くなっているものだ。
客の入りが良ければ照明をする自分のテンションも上がる。
照明マンとしては、どんな状況下であっても、常に最高の仕事を目指すのが当たり前なのだが、この辺りの心持ちは正直言って偽ざるところだ。
一呼吸置いて、姿月の名前をアナウンスする。
音出し。
閉められた緞帳の向こうで、舞台中央にスタンバイする姿月の気配を感じた。
緞帳のスイッチに指を掛け、流れ出した音楽と同時に押した。
幕が開く。
舞台中央で黒い塊と化している姿月。
真後ろから淡いブルーのライトを当て、逆光にする。
舞台天井からは細いスポットを落とし、彼女の姿が逆光の中に浮かぶようにした。
蜘蛛を形作った馬鹿でかい衣装を背負うかのように着、ゆったりとした動作で顔を上げ始めた。
顔の動きに合わせ、照明室からピンスポットを開けて行く。
絞りを徐々に開け、光りの輪の中に、女郎蜘蛛がいる。
開演前に見た姿月の姿はそこにはなかった。
僕の背中に軽い電気が走った。
一回目の照明は、正直言ってどうしようもない出来だった。彼女の動きにライトが追いつかない。
ここで言う追いつかないとは、スポットを外したりとかの意味では無い。
無難にはこなせた。
それだけで終わってしまった事に腹立ちを感じたのだ。
戦い……
僕が作り出そうとする光りに、彼女は舞台の上から無言のダメ出しをしていた。
後に姿月とそんな話しをした時、
「アタシは、そんなん意識した事ないで」
と笑っていたが、間違い無く彼女のステージは照明との戦いだと感じた。
二回目のステージが始まる前に、楽屋にインターホンを繋いだ。
「姿月さん、さっきはちゃんと出来なくてすみませんでした……」
(そうなん?アタシは平気やったよ。まあ、一回目だったから、アタシもグダグダやったし。気にしてへんから、次は頑張ってや)
「すみません。二回目は別な奴が照明やりますから、ポイントはきちんと伝えて置きます」
(なんや、次は違う投光さんなん。お兄さん、今日はもう照明せえへんの?)
「いえ、二回目は僕の休憩時間なんで、残りは全部自分が担当します」
(よかったぁ。ほな頼むね)
彼女の最後の言葉で、僕は漸く気持ちが明るくなった。
自分の部屋に戻り、一回目の舞台を思い返した。
冒頭の女郎蜘蛛で登場する場面。
伏せた顔を徐々に上げ、一点を見据える。
ゆったりとした動作で立ち上がり、そのまま中央でターンを繰り返す。
音楽が変わり、アップテンポなダンスシーンへと移る。
着ていた蜘蛛の衣装は脱ぎ棄てられ、肌を露出した姿で舞台上を踊り回る。
妖艶な表情を浮かべたまま、彼女は客席を挑発する。
姿月は一度も袖に引き込まず、そのまま盆へと来る。
盆……
デベソと言う人も居るが、踊り子や照明をする者は大概ベッドと称している。
舞台の真ん中から花道と呼ばれる細い渡しがあり、客席により近い位置に突き出た形で円形のそれはある。
ここで言う追いつかないとは、スポットを外したりとかの意味では無い。
無難にはこなせた。
それだけで終わってしまった事に腹立ちを感じたのだ。
戦い……
僕が作り出そうとする光りに、彼女は舞台の上から無言のダメ出しをしていた。
後に姿月とそんな話しをした時、
「アタシは、そんなん意識した事ないで」
と笑っていたが、間違い無く彼女のステージは照明との戦いだと感じた。
二回目のステージが始まる前に、楽屋にインターホンを繋いだ。
「姿月さん、さっきはちゃんと出来なくてすみませんでした……」
(そうなん?アタシは平気やったよ。まあ、一回目だったから、アタシもグダグダやったし。気にしてへんから、次は頑張ってや)
「すみません。二回目は別な奴が照明やりますから、ポイントはきちんと伝えて置きます」
(なんや、次は違う投光さんなん。お兄さん、今日はもう照明せえへんの?)
「いえ、二回目は僕の休憩時間なんで、残りは全部自分が担当します」
(よかったぁ。ほな頼むね)
彼女の最後の言葉で、僕は漸く気持ちが明るくなった。
自分の部屋に戻り、一回目の舞台を思い返した。
冒頭の女郎蜘蛛で登場する場面。
伏せた顔を徐々に上げ、一点を見据える。
ゆったりとした動作で立ち上がり、そのまま中央でターンを繰り返す。
音楽が変わり、アップテンポなダンスシーンへと移る。
着ていた蜘蛛の衣装は脱ぎ棄てられ、肌を露出した姿で舞台上を踊り回る。
妖艶な表情を浮かべたまま、彼女は客席を挑発する。
姿月は一度も袖に引き込まず、そのまま盆へと来る。
盆……
デベソと言う人も居るが、踊り子や照明をする者は大概ベッドと称している。
舞台の真ん中から花道と呼ばれる細い渡しがあり、客席により近い位置に突き出た形で円形のそれはある。
俗に言うカブリツキ……
全裸になった踊り子が、様々なポーズを取り、男達の妄想と欲情を掻き立てようとする場所。
ある意味、ストリップの見せ場だ。
この見せ場に至る迄は、綺麗に着飾った衣装を着ている訳だが、脱ぎの見せ方も一つの芸になる筈なのに、多くの踊り子はそれを疎かにしている。
姿月のステージを思い返しながら気付いた。
いつの間に脱いだんだっけ……?
ストリップ……
裸を見世物にした世界だが、かといって最初から素っ裸で登場して来たのでは味も素っ気も無い。
ベテランの踊り子になると、脱ぎの場面で客席をシーンと黙らせる。
デビュー仕立ての若い踊り子ではそうは行かない。
又、脱ぎ方がまるで違う。
色っぽさ、妖艶さ、なまめかしさを表現してくれる踊り子と出会うと、照明自体が無意識のうちに変わる。
踊り子に乗せられるとでも言えばいいのか。
裸になった姿月をもう一度頭の中に思い浮かべる。
情欲……
彼女はそれを全身で表現しようとしていた。
と、僕は勝手にそう受け止め、次のステージへ想い馳せていた。
全裸になった踊り子が、様々なポーズを取り、男達の妄想と欲情を掻き立てようとする場所。
ある意味、ストリップの見せ場だ。
この見せ場に至る迄は、綺麗に着飾った衣装を着ている訳だが、脱ぎの見せ方も一つの芸になる筈なのに、多くの踊り子はそれを疎かにしている。
姿月のステージを思い返しながら気付いた。
いつの間に脱いだんだっけ……?
ストリップ……
裸を見世物にした世界だが、かといって最初から素っ裸で登場して来たのでは味も素っ気も無い。
ベテランの踊り子になると、脱ぎの場面で客席をシーンと黙らせる。
デビュー仕立ての若い踊り子ではそうは行かない。
又、脱ぎ方がまるで違う。
色っぽさ、妖艶さ、なまめかしさを表現してくれる踊り子と出会うと、照明自体が無意識のうちに変わる。
踊り子に乗せられるとでも言えばいいのか。
裸になった姿月をもう一度頭の中に思い浮かべる。
情欲……
彼女はそれを全身で表現しようとしていた。
と、僕は勝手にそう受け止め、次のステージへ想い馳せていた。
シアター アートのお盆興行は連日盛況だった。
AV紛い(男女の絡みがメイン)のハードな出し物目当ての客がかなり多く来た。
客席の空気が何時もとまるで違っていた。
暗く鬱屈した重々しさ……
訳も無くそんな事を思ったりした。
元々、僕自身はその企画には反対で、正直、劇場の雰囲気にそぐわないと考えていた。
だが、経営者サイドはそんな事より数字が問題だった。
乗り気のしない初日を迎えたのであったが、いざ蓋を開けてみれば、最終回迄立ち見が出る程の入りに不満を押し止めるしか無かった。
それと、僕の気持ちを上向きにさせてくれた要因の一つに、出演者達のステージがあった。
メインの姿月は勿論の事、他の出演者達の出来も、照明をやっていて飽きる事が無かった。
休憩無しでこのままぶっ続けで仕事をしてもいいとさえ思った位だ。
シアター アートの照明は、前にも書いたが、全て手動だ。
舞台で踊るストリッパー達のステージも、その時々で微妙に変化するように、僕の照明も変化して行く。
特に素晴らしいステージに出会うとその傾向が顕著になる。
踊り子達の動き、表情を一瞬たりとも見逃すまいとする。
時に、舞台上の踊り子本人と終始視線が合う事がある。
僕の方は当然踊り子そのものを見つめているが、踊り子自身は決して僕を見てるのでは無い。
光りを見ている。
光りの中に入り込む己自身の姿をそこに見つけ出そうとしている。
光りは、彼女達にとっての最も引き立たせる衣装であり、宝石なのかも知れない。
そう気付き、思えるようになったのは、更に暫く後の事になるのだが。
話しを戻す。
初日が終わり、舞台裏を掃除しに行くと、トリのステージを終えた姿月が自分の衣装を片付けていた。
「お疲れ様でした」
「お疲れ様!」
舞台の上で演じている姿月とは別人の彼女が居た。
「あのね、中日替えとかしたいんやけど、かまへん?」
「ええ、構いませんよ。是非お願いします」
彼女は僕の言葉に微笑んだ。
汗が眩しく見える。
AV紛い(男女の絡みがメイン)のハードな出し物目当ての客がかなり多く来た。
客席の空気が何時もとまるで違っていた。
暗く鬱屈した重々しさ……
訳も無くそんな事を思ったりした。
元々、僕自身はその企画には反対で、正直、劇場の雰囲気にそぐわないと考えていた。
だが、経営者サイドはそんな事より数字が問題だった。
乗り気のしない初日を迎えたのであったが、いざ蓋を開けてみれば、最終回迄立ち見が出る程の入りに不満を押し止めるしか無かった。
それと、僕の気持ちを上向きにさせてくれた要因の一つに、出演者達のステージがあった。
メインの姿月は勿論の事、他の出演者達の出来も、照明をやっていて飽きる事が無かった。
休憩無しでこのままぶっ続けで仕事をしてもいいとさえ思った位だ。
シアター アートの照明は、前にも書いたが、全て手動だ。
舞台で踊るストリッパー達のステージも、その時々で微妙に変化するように、僕の照明も変化して行く。
特に素晴らしいステージに出会うとその傾向が顕著になる。
踊り子達の動き、表情を一瞬たりとも見逃すまいとする。
時に、舞台上の踊り子本人と終始視線が合う事がある。
僕の方は当然踊り子そのものを見つめているが、踊り子自身は決して僕を見てるのでは無い。
光りを見ている。
光りの中に入り込む己自身の姿をそこに見つけ出そうとしている。
光りは、彼女達にとっての最も引き立たせる衣装であり、宝石なのかも知れない。
そう気付き、思えるようになったのは、更に暫く後の事になるのだが。
話しを戻す。
初日が終わり、舞台裏を掃除しに行くと、トリのステージを終えた姿月が自分の衣装を片付けていた。
「お疲れ様でした」
「お疲れ様!」
舞台の上で演じている姿月とは別人の彼女が居た。
「あのね、中日替えとかしたいんやけど、かまへん?」
「ええ、構いませんよ。是非お願いします」
彼女は僕の言葉に微笑んだ。
汗が眩しく見える。
中日替え。
週の前半と後半で出し物を替える事を言う。
劇場によっては積極的に奨励する所もあるが、面倒くさがる照明係だと、嫌がられたりもする。
お客さんの中には、十日間の間に何度か足を運ぶ人も少なく無い。
お目当ての踊り子ではないにしろ、違う出し物が十日間の間で観れるというのは、目に見えないファンサービスにもなる。
拒む照明係が居るとすれば、それは自分本来の仕事というものを判っていないのだと晒け出してるようなものだ。
中日替えの演目の打ち合わせを姿月としている間中、どう演出するかを夢中になって語り合っていた。
「先ずは、明日の一回目で実際の雰囲気を掴んで、後は少しずつ手直しして行きましょう」
「ありがとう。とにかく、めり張りだけきちんと付けてくれたらええから」
ボヘミアンバレエと名前を付けられた中日替えの演目と出会えた事は、自分の照明に対する感性の向上になった。
噴き上げるスモーク
無数に交差するライト
激しい動きから一転して、妖艶に、そしてなまめましく演じる姿月に、観客の誰もが見とれていた。
いや、客だけでは無かった。
照明室の中に居た僕自身が、実は一番彼女に夢中になっていた。
片時たりともステージから目を離す事が出来なかった。
自分の照らし出す照明の中に姿月が浮かび上がる度に、僕はこの時間が終わらないでくれと願った。
何日目であったろうか。
彼女から、小倉の劇場の照明が今までで一番良かったという話しを聞き、丁度その時のビデオがあると言われ、僕はそのビデオを彼女から借りる事にした。
仕事を終え、一人そのビデオを観た。
衝撃的であった。
光りを自由に操っている……
踊り子にどういう光りを当てれば一番美しくなるかを、そのライティングは熟知していた。
光りに命があった。
次の日から、僕の照明のライバルは前夜に観たビデオとなった。
姿月が語る小倉の劇場の照明マンに僕は嫉妬した。
この人を本気で演じさせる照明をしなきゃ……
毎回、もう少しという不満感を己の中で感じながら、気が付けば既に楽日を迎えていた。
週の前半と後半で出し物を替える事を言う。
劇場によっては積極的に奨励する所もあるが、面倒くさがる照明係だと、嫌がられたりもする。
お客さんの中には、十日間の間に何度か足を運ぶ人も少なく無い。
お目当ての踊り子ではないにしろ、違う出し物が十日間の間で観れるというのは、目に見えないファンサービスにもなる。
拒む照明係が居るとすれば、それは自分本来の仕事というものを判っていないのだと晒け出してるようなものだ。
中日替えの演目の打ち合わせを姿月としている間中、どう演出するかを夢中になって語り合っていた。
「先ずは、明日の一回目で実際の雰囲気を掴んで、後は少しずつ手直しして行きましょう」
「ありがとう。とにかく、めり張りだけきちんと付けてくれたらええから」
ボヘミアンバレエと名前を付けられた中日替えの演目と出会えた事は、自分の照明に対する感性の向上になった。
噴き上げるスモーク
無数に交差するライト
激しい動きから一転して、妖艶に、そしてなまめましく演じる姿月に、観客の誰もが見とれていた。
いや、客だけでは無かった。
照明室の中に居た僕自身が、実は一番彼女に夢中になっていた。
片時たりともステージから目を離す事が出来なかった。
自分の照らし出す照明の中に姿月が浮かび上がる度に、僕はこの時間が終わらないでくれと願った。
何日目であったろうか。
彼女から、小倉の劇場の照明が今までで一番良かったという話しを聞き、丁度その時のビデオがあると言われ、僕はそのビデオを彼女から借りる事にした。
仕事を終え、一人そのビデオを観た。
衝撃的であった。
光りを自由に操っている……
踊り子にどういう光りを当てれば一番美しくなるかを、そのライティングは熟知していた。
光りに命があった。
次の日から、僕の照明のライバルは前夜に観たビデオとなった。
姿月が語る小倉の劇場の照明マンに僕は嫉妬した。
この人を本気で演じさせる照明をしなきゃ……
毎回、もう少しという不満感を己の中で感じながら、気が付けば既に楽日を迎えていた。
この作家の他の作品
表紙を見る
たまには、少しばかり昔を懐かしんで……
出したくても、書く事すら出来なかった手紙
ほのかに残る想い出は 果たして何通の手紙になるのだろう
2009.4.24 一通目
表紙を見る
現実は、小説やドラマの世界みたいに、それほどドラマチックなものじゃない。
でも、時々神様はびっくりするような時間をプレゼントしてくれる事がある。
それは僕に関しても同様だった。
アニータ……
見知らぬ国からやって来た彼女と、僕は一つ屋根の下で暮らす事になった。
以来、僕の中でいろんなものが、シャボン玉のように弾けては飛んだ。
悪戯好きの神様がくれた17歳最後の夏。
僕は新しい扉に手を掛けた……
アクタガワ ナオキ
『こういう小説も、私の中から生まれて来るんだ……
そんな不思議な感覚に包まれながら
書いています
稲葉禎和 』
愛水様
素敵なレビューありがとうございまいた!
表紙を見る
表の世界では生きられない男達がいる。
欲望の赴くままに…
己の力だけでのし上がる…
そんな、ありふれた安っぽいハードボイルド小説のような事は、現実の世界では通じない。
誰しもが持っている力への憧れ…
富と権力…そして、暴力…
ならず者…凶漢、 デスペラードな男達の物語。
*近々こちらを非公開にさせて頂きます。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…