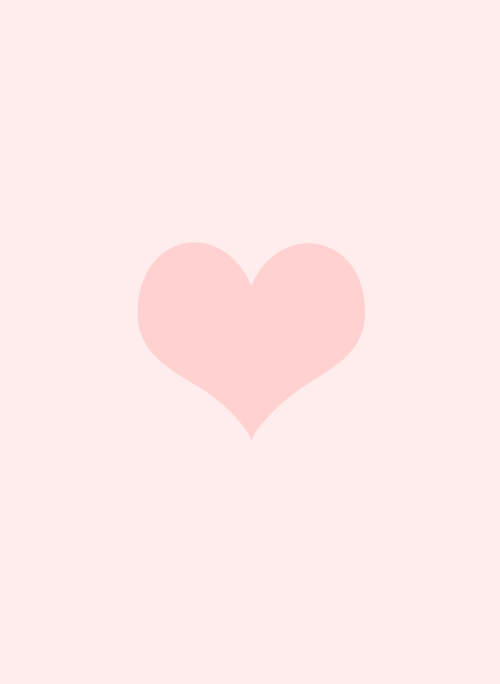(でなあ、面接したその日にいきなりハメ撮り。今考えても信じられへんわあ)
受話器の向こうから聞こえて来る声の明るさと、姿月の話しの内容とが不釣り合いで、僕はどう相槌を打ってよいものかと戸惑っていた。
時計を見ると電話をし始めてから一時間以上経っている。
彼女と電話をすると、毎回長話しになる。
「今の姿月さんからは想像出来ないなあ……」
(百年の恋も醒めたんちゃう?)
「百年の恋って、そんな……」
(あは、あんた何動揺してんの。まあ、そういう事やから、そんなたかが一度や二度、他所の踊り子と出来ちゃった位で気に病む必要無いと思うよ。佐伯君より数段上手のヤリチン男なんか仰山おるから)
「そんなぁ、ヤリチンだなんて……」
(しかしさあ、佐伯君って、あんなんが好みやったん?)
「もう勘弁して下さい。それよりも、話しを戻しますけど、結局はAVに何本か出て、それでストリップといった流れになった訳でしょ?
それも、自分の意志ででしたか?」
(最終的な決断は必ず自分の意志に決まってるけど、踊り子になったきっかけも流れと言えば流れやね。AVの冠ついとれば、ポーンてギャラがアップしとった時代やったし)
「時代って言ってもつい最近でしょ?」
(二年も三年も過ぎたらこの業界はえらい変わりようになるんよ。
アタシかて、デビュー当時は今と違ってブリブリのアイドルストリッパーやったし)
姿月の話しは踊り子になった当時の思い出話しに変わって行った。
半分騙されてAVの世界に身を投じた紀子であったが、当初危惧していた親バレが、何と最初の一本目で現実となってしまった。
母の知り合いが偶然雑誌の広告ページで紀子の主演作品を見つけてしまい、両親の耳に入ってしまったのだ。
それだけではない。
勤めていた会社にまでばれた。
一発目で交通事故に遭ってしもた……
もっと最悪な事に、約束されていた出演料が、期日を過ぎても口座に振り込まれて来なかった。
直ぐさま事務所に電話したが、受話器から聞こえて来たのは、現在この番号は使われておりませんの声であった。
凜子の方も音信が途絶えた。
以前迄は、雅子には何でも相談していた紀子だったが、今回の件以来、何と無く疎遠になっていて、この事も今更という気がして話せ無かった。
AVの仕事もこれで絶ち消えかと思っていた矢先、別なプロダクションから声が掛かって来た。
そのプロダクションこそ、業界では名前の通った事務所で、話しを聞くと、紀子の契約書がその事務所に売り飛ばされていた事が判った。
考えようによっては、その事務所で幸運だったのかも知れない。
取りも直さず、その事務所に所属する事になり、年間十本の作品を撮る事になった。
一本辺りの撮影は大体一日で終わるから、何気に時間が出来る。
勿論、たまに男性誌のヌードなどの撮影が入る時もあるが、自由な時間の方が多い。
暫くは雅子の店を手伝いながら仕事をしていたが、やはり何処と無く居づらくなり、別な店を紹介して貰ったりした。
AVの撮影自体、やってみるとそれ程辛いとは感じ無かった。
滑稽な事に、男優達が必死になって汗だくに腰を振っている様を見上げて、撮影中に笑ってしまった事もある。
辛かったのは、絡みで自分が感じてるふりをしなければならなかった事だ。
本気で感じさせてくれたら楽やのに……
こんなん観て、世間の男はほんまに興奮するんやろか……
ただ金の為……
虚しさを覚え始めた頃、紀子はストリップと出会った。
母の知り合いが偶然雑誌の広告ページで紀子の主演作品を見つけてしまい、両親の耳に入ってしまったのだ。
それだけではない。
勤めていた会社にまでばれた。
一発目で交通事故に遭ってしもた……
もっと最悪な事に、約束されていた出演料が、期日を過ぎても口座に振り込まれて来なかった。
直ぐさま事務所に電話したが、受話器から聞こえて来たのは、現在この番号は使われておりませんの声であった。
凜子の方も音信が途絶えた。
以前迄は、雅子には何でも相談していた紀子だったが、今回の件以来、何と無く疎遠になっていて、この事も今更という気がして話せ無かった。
AVの仕事もこれで絶ち消えかと思っていた矢先、別なプロダクションから声が掛かって来た。
そのプロダクションこそ、業界では名前の通った事務所で、話しを聞くと、紀子の契約書がその事務所に売り飛ばされていた事が判った。
考えようによっては、その事務所で幸運だったのかも知れない。
取りも直さず、その事務所に所属する事になり、年間十本の作品を撮る事になった。
一本辺りの撮影は大体一日で終わるから、何気に時間が出来る。
勿論、たまに男性誌のヌードなどの撮影が入る時もあるが、自由な時間の方が多い。
暫くは雅子の店を手伝いながら仕事をしていたが、やはり何処と無く居づらくなり、別な店を紹介して貰ったりした。
AVの撮影自体、やってみるとそれ程辛いとは感じ無かった。
滑稽な事に、男優達が必死になって汗だくに腰を振っている様を見上げて、撮影中に笑ってしまった事もある。
辛かったのは、絡みで自分が感じてるふりをしなければならなかった事だ。
本気で感じさせてくれたら楽やのに……
こんなん観て、世間の男はほんまに興奮するんやろか……
ただ金の為……
虚しさを覚え始めた頃、紀子はストリップと出会った。
AV出演が両親にばれたとは言え、紀子は辞めるつもりは毛頭無かった。
父親の怒りようは、それは凄まじいまでに激しかったが、しかし、直接紀子に対してそれが向けられる事は無かった。
母親とは、定期的に電話のやり取りをしていたが、その都度愚痴をこぼされた。
最愛の一人娘がAVの世界に入ってしまった事に対する怒りを母親にぶつけているらしい。
父親としてのジレンマも在ったのだろう。
あのまま会社の経営が上手く行っていれば……
高校の学費迄紀子に払わせてしまった……
更には会社の借金返済の負担迄負わせてしまっている。
まとまったお金が送金されて来た時、どうやってその金を作ったのか、と疑問に思う事も無く、喜んでそれを受け取り、会社の借金に充てた。
その金の出所がAVの出演料と判ったあと、当然複雑な気持ちになった。
大手のプロダクションから出された数本のビデオは、特別売れた訳では無かったが、この頃は、取り敢えず出せば赤字にはならなかった時代であったから、そこそこ会社も紀子にまとまったギャラを振り込んで来た。
最初の時は、一円にもならず、結局数人の男達の慰みものになっただけのようなものであった。
この世界も、やってみると意外な面を多く見れ、仕事に関わっている時はそれなりに刺激的だった。
しかし、それも長続きはしなかった。
『エル·ドラド』で働いていた時には、まだ心の中に充足感を持つ事が出来たが、この世界は刺激は与えてくれても精神的な満足感は得られない。
日が経つにつれ、その思いは強くなって行く。
家族との葛藤も、紀子の心の水瓶から水気を吸い上げていた。
何かを欲していた。
その何かが見つからない。
自分が男一途に己の心を充たせられる女では無いと気付き始めた。
アタシは大人しく家庭に納まる女やないのかな……
男の都合の良い女になってまで生きたくはない……
心の揺れが、紀子に舞台を引き合わせた。
父親の怒りようは、それは凄まじいまでに激しかったが、しかし、直接紀子に対してそれが向けられる事は無かった。
母親とは、定期的に電話のやり取りをしていたが、その都度愚痴をこぼされた。
最愛の一人娘がAVの世界に入ってしまった事に対する怒りを母親にぶつけているらしい。
父親としてのジレンマも在ったのだろう。
あのまま会社の経営が上手く行っていれば……
高校の学費迄紀子に払わせてしまった……
更には会社の借金返済の負担迄負わせてしまっている。
まとまったお金が送金されて来た時、どうやってその金を作ったのか、と疑問に思う事も無く、喜んでそれを受け取り、会社の借金に充てた。
その金の出所がAVの出演料と判ったあと、当然複雑な気持ちになった。
大手のプロダクションから出された数本のビデオは、特別売れた訳では無かったが、この頃は、取り敢えず出せば赤字にはならなかった時代であったから、そこそこ会社も紀子にまとまったギャラを振り込んで来た。
最初の時は、一円にもならず、結局数人の男達の慰みものになっただけのようなものであった。
この世界も、やってみると意外な面を多く見れ、仕事に関わっている時はそれなりに刺激的だった。
しかし、それも長続きはしなかった。
『エル·ドラド』で働いていた時には、まだ心の中に充足感を持つ事が出来たが、この世界は刺激は与えてくれても精神的な満足感は得られない。
日が経つにつれ、その思いは強くなって行く。
家族との葛藤も、紀子の心の水瓶から水気を吸い上げていた。
何かを欲していた。
その何かが見つからない。
自分が男一途に己の心を充たせられる女では無いと気付き始めた。
アタシは大人しく家庭に納まる女やないのかな……
男の都合の良い女になってまで生きたくはない……
心の揺れが、紀子に舞台を引き合わせた。
僕が横浜の『シアター·アート』に戻ったのは、平成十年の四月であった。
半年振りに戻った僕をみんな心良く迎えてくれた。
「他の劇場の子と出来ちゃった位で何も飛ぶ事なかったのに。
でもまあ、お兄さんが戻って来たから又此処に来るのが楽しみになった。」
そう言ってくれたのは、何度か一緒に仕事をした踊り子達であった。
それ以上に嬉しかったのは常連客から同じ言葉を聞いた時であった。
再びこの世界に戻って来れた。
狭い照明ブース。
幾つものスイッチ。
ピンスポットから伸びる一本の光りの帯。
煙るスモークの中から浮き上がる踊り子。
舞台に釘付けになる観客。
拍手とどよめき。
幾筋もの光りに輝く踊り子達の汗。
僕の居場所は此処なんだ……
直ぐさま姿月に電話をした。
(そう、戻ったんや。アタシ、ゴールデンウイークは野毛に乗るんよ)
野毛の劇場は『シアター·アート』から歩いて5分程の場所にある。
うちよりも小さな場末の劇場だ。
「野毛なんですか?ゴールデンウイークなのに?」
姿月はそこそこ客を呼べる踊り子だ。
野毛のような場末の劇場に乗るなんて……
そんな思いを抱いた。
(アタシ、あれ以来シアター·アートには呼ばれてへんのよ。
出し物が何時も暗いやつやからそこの小屋主さんに嫌われてるんやろか……)
「そんな事無いですよ。きっとたまたまだと思います」
(どうせ同じ横浜なら野毛じゃなくそっちに乗りたかったなあ……)
「僕も一緒に仕事したかったです。姿月さん、自分で暗い出し物って言ってますけど、昔からなんですか?」
(ううん、最初はな、他の子達みたいなブリブリのアイドル路線やったんよ……)
姿月はデビューの頃を懐かしむように語り始めた。
半年振りに戻った僕をみんな心良く迎えてくれた。
「他の劇場の子と出来ちゃった位で何も飛ぶ事なかったのに。
でもまあ、お兄さんが戻って来たから又此処に来るのが楽しみになった。」
そう言ってくれたのは、何度か一緒に仕事をした踊り子達であった。
それ以上に嬉しかったのは常連客から同じ言葉を聞いた時であった。
再びこの世界に戻って来れた。
狭い照明ブース。
幾つものスイッチ。
ピンスポットから伸びる一本の光りの帯。
煙るスモークの中から浮き上がる踊り子。
舞台に釘付けになる観客。
拍手とどよめき。
幾筋もの光りに輝く踊り子達の汗。
僕の居場所は此処なんだ……
直ぐさま姿月に電話をした。
(そう、戻ったんや。アタシ、ゴールデンウイークは野毛に乗るんよ)
野毛の劇場は『シアター·アート』から歩いて5分程の場所にある。
うちよりも小さな場末の劇場だ。
「野毛なんですか?ゴールデンウイークなのに?」
姿月はそこそこ客を呼べる踊り子だ。
野毛のような場末の劇場に乗るなんて……
そんな思いを抱いた。
(アタシ、あれ以来シアター·アートには呼ばれてへんのよ。
出し物が何時も暗いやつやからそこの小屋主さんに嫌われてるんやろか……)
「そんな事無いですよ。きっとたまたまだと思います」
(どうせ同じ横浜なら野毛じゃなくそっちに乗りたかったなあ……)
「僕も一緒に仕事したかったです。姿月さん、自分で暗い出し物って言ってますけど、昔からなんですか?」
(ううん、最初はな、他の子達みたいなブリブリのアイドル路線やったんよ……)
姿月はデビューの頃を懐かしむように語り始めた。
月一本のペースでAVに出演していた紀子にストリップの話しが舞い込んで来たのは、平成七年の春であった。
事務所の社長から、何度かその話しをされていたが、毎回はっきりした返事をしていなかった。
気乗りがしなかったから、何時も適当に返事をごまかしていた。
スタッフだけの仕事現場で自分の全裸をさらけ出す事は、この一年余りで慣れては来たが、何十、何百というぎらつく視線にとなると、さすがに抵抗がある。
そうこうしている時、同じ事務所に所属する子でストリップデビューする子が居て、浅草のスター座に出演する事になった。
浅草スター座。
ストリップ界のトップに君臨する老舗の劇場である。
踊り子の全てが、此処の舞台に乗れたらと夢を見る。
ストリップの聖地と表現してもいいだろう。
そこでデビュー出来る踊り子は、ほんの一握りに過ぎないし、何年踊り子をしていても、生涯この劇場から呼ばれない子も居る。
デビューする子とは何度か事務所で顔を合わせた事がある。
スラリとした長身で、可愛いというより清楚な美人といったタイプだ。
何処か引き合うものがあったのか、初対面からその子とは打ち解ける事が出来た。
浅田かおりというAVでの芸名のまま、ストリップ界にデビューする事になった彼女の初舞台を紀子は事務所の社長と一緒に観に行く事になった。
行ってみて驚いたのは、ステージの広さと客席の多さであった。
そしてもう一つは、想像していたのとは違って、舞台そのものがいやらしさのかけらも感じなかった事であった。
紀子の頭の中に在ったストリップのイメージは、もっとおどろおどろした淫靡なものであったが、目の前で繰り広げられていた舞台は、宝塚のレビューを想わせるようなもので、少しばかり驚いた。
「こんな感じのステージなら別に問題無いだろ?
ダンスのレッスンとかは初めのうちはきつく感じるかも知れんが、そんなもん適当に身体くねらせとけば大丈夫さ。どうだ、やってみるか?」
紀子は即答しなかった。
が、既に答えは出ていた。
事務所の社長から、何度かその話しをされていたが、毎回はっきりした返事をしていなかった。
気乗りがしなかったから、何時も適当に返事をごまかしていた。
スタッフだけの仕事現場で自分の全裸をさらけ出す事は、この一年余りで慣れては来たが、何十、何百というぎらつく視線にとなると、さすがに抵抗がある。
そうこうしている時、同じ事務所に所属する子でストリップデビューする子が居て、浅草のスター座に出演する事になった。
浅草スター座。
ストリップ界のトップに君臨する老舗の劇場である。
踊り子の全てが、此処の舞台に乗れたらと夢を見る。
ストリップの聖地と表現してもいいだろう。
そこでデビュー出来る踊り子は、ほんの一握りに過ぎないし、何年踊り子をしていても、生涯この劇場から呼ばれない子も居る。
デビューする子とは何度か事務所で顔を合わせた事がある。
スラリとした長身で、可愛いというより清楚な美人といったタイプだ。
何処か引き合うものがあったのか、初対面からその子とは打ち解ける事が出来た。
浅田かおりというAVでの芸名のまま、ストリップ界にデビューする事になった彼女の初舞台を紀子は事務所の社長と一緒に観に行く事になった。
行ってみて驚いたのは、ステージの広さと客席の多さであった。
そしてもう一つは、想像していたのとは違って、舞台そのものがいやらしさのかけらも感じなかった事であった。
紀子の頭の中に在ったストリップのイメージは、もっとおどろおどろした淫靡なものであったが、目の前で繰り広げられていた舞台は、宝塚のレビューを想わせるようなもので、少しばかり驚いた。
「こんな感じのステージなら別に問題無いだろ?
ダンスのレッスンとかは初めのうちはきつく感じるかも知れんが、そんなもん適当に身体くねらせとけば大丈夫さ。どうだ、やってみるか?」
紀子は即答しなかった。
が、既に答えは出ていた。
姿月がその頃の事を笑いながら話すのを僕は不思議な気持ちで聞いていた。
あっけらかんとしている。
強いな……
(そりゃあ辛い事も沢山あったけど、後ろばっかり見てたら死にたくなってしまうやろ。アタシ、嫌やもん。アハハって笑ってしもうた方が楽やん。だから言うて、その辺の脳天気なオネーチャンと一緒にされたらかなわんけどな)
「前に、デビューから暫くはブリブリのアイドルしてたって言ってましたけど、きっかけって何だったんですか?」
(アタシの知らんうちにそういう路線敷かれてた……。
衣装かて、自分でなんか選んだ事無かったんよ)
「ほんとですか?」
(そう……)
何故か姿月の声のトーンが落ちた。
(あん時の事を思い出すと顔から火が出るわ。とにかく、あれよあれよという間にデビューさせられてな、もうその時点でうちの事務所とは反目になったんよ)
「それで路線変更を?」
(まあね。元々アタシって、他人に自分の生き方を決められるのって嫌いなんよ。自分の道位、自分で探して歩くわ)
「強いな……」
(何が?)
「僕なんかこの歳になってもこんな有様だし、それに比べたら……」
(勘違いしたらあかんよ。アタシにしたって毎日頭悩ませてるもん。
まあ、アタシの場合はプライベートから仕事からいろいろ有り過ぎるんやけど)
そう言って笑う彼女の声が、僕の耳元で心地良く響いた。
「何だか姿月さんのステージ、観たくなって来たなぁ……」
(来て来て、盆の上からアンタの姿見つけたら抱き着いてあげる)
「冗談でも止めて下さいね。」
(シアター·アートの照明係、今度は姿月に手を出す……てネットに出るやろな)
「勘弁して下さい……」
(うそ、うそ、ゴールデンウイーク、野毛で待ってるからね)
そして約束通り、僕は彼女のステージを観に行った。
あっけらかんとしている。
強いな……
(そりゃあ辛い事も沢山あったけど、後ろばっかり見てたら死にたくなってしまうやろ。アタシ、嫌やもん。アハハって笑ってしもうた方が楽やん。だから言うて、その辺の脳天気なオネーチャンと一緒にされたらかなわんけどな)
「前に、デビューから暫くはブリブリのアイドルしてたって言ってましたけど、きっかけって何だったんですか?」
(アタシの知らんうちにそういう路線敷かれてた……。
衣装かて、自分でなんか選んだ事無かったんよ)
「ほんとですか?」
(そう……)
何故か姿月の声のトーンが落ちた。
(あん時の事を思い出すと顔から火が出るわ。とにかく、あれよあれよという間にデビューさせられてな、もうその時点でうちの事務所とは反目になったんよ)
「それで路線変更を?」
(まあね。元々アタシって、他人に自分の生き方を決められるのって嫌いなんよ。自分の道位、自分で探して歩くわ)
「強いな……」
(何が?)
「僕なんかこの歳になってもこんな有様だし、それに比べたら……」
(勘違いしたらあかんよ。アタシにしたって毎日頭悩ませてるもん。
まあ、アタシの場合はプライベートから仕事からいろいろ有り過ぎるんやけど)
そう言って笑う彼女の声が、僕の耳元で心地良く響いた。
「何だか姿月さんのステージ、観たくなって来たなぁ……」
(来て来て、盆の上からアンタの姿見つけたら抱き着いてあげる)
「冗談でも止めて下さいね。」
(シアター·アートの照明係、今度は姿月に手を出す……てネットに出るやろな)
「勘弁して下さい……」
(うそ、うそ、ゴールデンウイーク、野毛で待ってるからね)
そして約束通り、僕は彼女のステージを観に行った。
五月の連休、『シアター·アート』は久々に客足が良かった。
活気のある場内というものは、照明ブースから見ていても感じが良いものだ。
自然、ステージに上がる踊り子達の気持ちも高揚する。
反対に、客が少ないとテンションが下がってしまうのは、ある程度は仕方が無い事だと同情出来る。
しかし、現実には満席の状況ばかりに出会える訳では無い。
余程、本人自身に客を呼び込めるだけの魅力や人気があれば別物だが、劇場自体に客を引き寄せる力がなければ、閑古鳥の日々が続くのは致し方無いものだ。
二、三人の観客を相手に不機嫌そうに踊る踊り子。
ほら、勝手に観な……
そんな空気が伝わる場面を何度か見た事がある。
自分の贔屓客が少ない日には不機嫌さがより増す踊り子。
中にはそうではない踊り子も居る。
本物のプロフェッショナル。
姿月もその一人であった。
その日、僕は劇場から半休を貰い、近くの花屋で買った花束を手にして姿月の出演する劇場へ向かった。
夕方くらいだったが、劇場の待合室でうちにも良く来てくれている常連客と一緒になった。
「姿月さんのステージ、観に来たんだね」
彼は去年のお盆興行で、彼女のステージを初めて観てファンになった客だ。
「電話で観に行きますって約束したんで。それに、今の出し物って確か新作だって聞いてたから」
彼女の出番は次だ。
時間を見て、その客と場内に入る。
観客は僕を入れて総勢四人。
それだけじゃない。
照明と呼べるライトなんて一つも無かった。
場末の安キャバレー以下かも知れない。
やる気の感じられない照明係のアナウンスが流れ、姿月のステージが始まった。
ナチの軍服を思わせる衣装を纏った彼女がいきなり舞台中央の盆にツカツカと来て片膝を付いた。
暗転の状態とはいえ、スタンバイの状態は判る。
数メートル先に佇む彼女から気が伝わって来た。
入り込んでいる……
音が流れ暗闇の中に一本の光りが走った。
浮かび上がる彼女の視線には、僕ら等まるで無かった。
活気のある場内というものは、照明ブースから見ていても感じが良いものだ。
自然、ステージに上がる踊り子達の気持ちも高揚する。
反対に、客が少ないとテンションが下がってしまうのは、ある程度は仕方が無い事だと同情出来る。
しかし、現実には満席の状況ばかりに出会える訳では無い。
余程、本人自身に客を呼び込めるだけの魅力や人気があれば別物だが、劇場自体に客を引き寄せる力がなければ、閑古鳥の日々が続くのは致し方無いものだ。
二、三人の観客を相手に不機嫌そうに踊る踊り子。
ほら、勝手に観な……
そんな空気が伝わる場面を何度か見た事がある。
自分の贔屓客が少ない日には不機嫌さがより増す踊り子。
中にはそうではない踊り子も居る。
本物のプロフェッショナル。
姿月もその一人であった。
その日、僕は劇場から半休を貰い、近くの花屋で買った花束を手にして姿月の出演する劇場へ向かった。
夕方くらいだったが、劇場の待合室でうちにも良く来てくれている常連客と一緒になった。
「姿月さんのステージ、観に来たんだね」
彼は去年のお盆興行で、彼女のステージを初めて観てファンになった客だ。
「電話で観に行きますって約束したんで。それに、今の出し物って確か新作だって聞いてたから」
彼女の出番は次だ。
時間を見て、その客と場内に入る。
観客は僕を入れて総勢四人。
それだけじゃない。
照明と呼べるライトなんて一つも無かった。
場末の安キャバレー以下かも知れない。
やる気の感じられない照明係のアナウンスが流れ、姿月のステージが始まった。
ナチの軍服を思わせる衣装を纏った彼女がいきなり舞台中央の盆にツカツカと来て片膝を付いた。
暗転の状態とはいえ、スタンバイの状態は判る。
数メートル先に佇む彼女から気が伝わって来た。
入り込んでいる……
音が流れ暗闇の中に一本の光りが走った。
浮かび上がる彼女の視線には、僕ら等まるで無かった。
ステージを見終え、僕は気持ちの高揚を噛み締めると同時に、やるせ無さを感じていた。
もっとちゃんとした照明がある舞台に立たせたい……
立ち見が出る位の大勢の観客が見守る中で……
そして、そのライトを当てるのは……
数日後、彼女に電話をした。
「あんな寒い舞台でもよくテンションが下がりませんね」
(まあな、無い物ねだりしてもしゃあないから。
アタシ、結構ああいうしょぼい明かりで踊るの嫌いやないんよ。ただな、やれるのにやってくれへんかったりしたら腹立つけど、あの劇場じゃ無理やし)
「ですね……」
(でも、あんな野毛なんかにうちの事務所コース入れるんやったら、なんでアンタんとこに乗せへんのやろ……)
「さあ……その辺の事は余り詳しく判りませんが……」
(事務所に嫌われてるからな……)
自嘲気味に笑う彼女の声には、余り何時もの明るさは感じられなかった。
自ら所属する事務所と、このところ小さなトラブルが続いているらしい。
彼女自身は、その辺の話しをさらりと話してはいるが、かなり複雑な感情が入っている事が言外に臭う。
(潮時かな……)
「えっ!?」
(アタシな、来年の五月でデビュー五周年になるんよ。でな、その時に引退しようかなって考えてるんよ)
「引退、ですか……」
(ストリップとは違う形で、何かやれたらええけど、今はまだ模索中)
「引退興行、やるんでしたら、その時は是非うちで。
もし、ご自分の劇場でされるのでしたら、その時だけ照明当てに行きます」
(アタシもそうなったらええなって思うよ。どうせなら、自分が一番楽しく踊れる舞台で幕退きたいし……。
まあ、うちの劇場ではアタシの引退興行なんてやらせてくれへんやろけどな)
虚し気に言葉を吐き出した姿月と僕は、この電話の二ヶ月後、再び一緒に仕事をする機会に恵まれた。
お互いにそれが最後になるとは露とも感じていない平成十一年の春の事であった。
もっとちゃんとした照明がある舞台に立たせたい……
立ち見が出る位の大勢の観客が見守る中で……
そして、そのライトを当てるのは……
数日後、彼女に電話をした。
「あんな寒い舞台でもよくテンションが下がりませんね」
(まあな、無い物ねだりしてもしゃあないから。
アタシ、結構ああいうしょぼい明かりで踊るの嫌いやないんよ。ただな、やれるのにやってくれへんかったりしたら腹立つけど、あの劇場じゃ無理やし)
「ですね……」
(でも、あんな野毛なんかにうちの事務所コース入れるんやったら、なんでアンタんとこに乗せへんのやろ……)
「さあ……その辺の事は余り詳しく判りませんが……」
(事務所に嫌われてるからな……)
自嘲気味に笑う彼女の声には、余り何時もの明るさは感じられなかった。
自ら所属する事務所と、このところ小さなトラブルが続いているらしい。
彼女自身は、その辺の話しをさらりと話してはいるが、かなり複雑な感情が入っている事が言外に臭う。
(潮時かな……)
「えっ!?」
(アタシな、来年の五月でデビュー五周年になるんよ。でな、その時に引退しようかなって考えてるんよ)
「引退、ですか……」
(ストリップとは違う形で、何かやれたらええけど、今はまだ模索中)
「引退興行、やるんでしたら、その時は是非うちで。
もし、ご自分の劇場でされるのでしたら、その時だけ照明当てに行きます」
(アタシもそうなったらええなって思うよ。どうせなら、自分が一番楽しく踊れる舞台で幕退きたいし……。
まあ、うちの劇場ではアタシの引退興行なんてやらせてくれへんやろけどな)
虚し気に言葉を吐き出した姿月と僕は、この電話の二ヶ月後、再び一緒に仕事をする機会に恵まれた。
お互いにそれが最後になるとは露とも感じていない平成十一年の春の事であった。
野毛でのステージを観た後、僕は姿月のビデオを何回も観た。
以前、彼女から貰った物で、自分が照明を当てた出し物と、小倉の劇場で撮られたものがダビングされている。
もう一度、彼女にライトを当てたい。
そんな想いが強く湧き起こって来た。
様々な姿を見せてくれる姿月を僕の差し出す光りの中に包み込めたら……
一年前、初めて姿月にライトを当てた時に味わった身震いするような感覚を僕は求め続けていた。
消化不良のようなステージばかり続いたりしていたせいか、僕は仕事抜きの刺激を求めていたのかも知れない。
漸く僕の願いは通じた。
七月の最終週に姿月が来演する事になったのだ。
決まったのはかなり瀬戸際になってからだったように記憶する。
七月二十日の夜、僕は劇場の若いマネージャーともう一人の従業員とで居酒屋に行っていた。
その週の楽日も終え、慰労を兼ねた飲み会。
ほろ酔い加減で互いの愚痴をこぼしあったりしながら、明日からの新しい出会いに想いを馳せていた。
僕の携帯が突然鳴った。
こんな時間に誰からだろう。
姿月からだった。
(お疲れぇ、明日から宜しくな。あっ、もう今日か。で、佐伯君アタシの他に誰が乗るん?)
僕は出演者全員の名前を伝え、楽屋の部屋割も教えた。
「出し物は野毛の時に観たやつですか?」
(ああ、『愛の嵐』な。あれともう一つ中日替えでやろう思うんやけど)
「だったら、これ迄姿月さんの出し物で評判の良かったやつ、日替わりメニューでやっちゃいませんか?
『夜叉』も観てみたいし……」
酔いと、彼女への気安さのせいか、僕は大胆な事を口にしていた。
(アンタ日替わりメニューて、アタシの出し物その辺のランチとちゃうでぇ)
言葉とは裏腹に楽しそうな笑い声が携帯越しに伝わって来た。
以前、彼女から貰った物で、自分が照明を当てた出し物と、小倉の劇場で撮られたものがダビングされている。
もう一度、彼女にライトを当てたい。
そんな想いが強く湧き起こって来た。
様々な姿を見せてくれる姿月を僕の差し出す光りの中に包み込めたら……
一年前、初めて姿月にライトを当てた時に味わった身震いするような感覚を僕は求め続けていた。
消化不良のようなステージばかり続いたりしていたせいか、僕は仕事抜きの刺激を求めていたのかも知れない。
漸く僕の願いは通じた。
七月の最終週に姿月が来演する事になったのだ。
決まったのはかなり瀬戸際になってからだったように記憶する。
七月二十日の夜、僕は劇場の若いマネージャーともう一人の従業員とで居酒屋に行っていた。
その週の楽日も終え、慰労を兼ねた飲み会。
ほろ酔い加減で互いの愚痴をこぼしあったりしながら、明日からの新しい出会いに想いを馳せていた。
僕の携帯が突然鳴った。
こんな時間に誰からだろう。
姿月からだった。
(お疲れぇ、明日から宜しくな。あっ、もう今日か。で、佐伯君アタシの他に誰が乗るん?)
僕は出演者全員の名前を伝え、楽屋の部屋割も教えた。
「出し物は野毛の時に観たやつですか?」
(ああ、『愛の嵐』な。あれともう一つ中日替えでやろう思うんやけど)
「だったら、これ迄姿月さんの出し物で評判の良かったやつ、日替わりメニューでやっちゃいませんか?
『夜叉』も観てみたいし……」
酔いと、彼女への気安さのせいか、僕は大胆な事を口にしていた。
(アンタ日替わりメニューて、アタシの出し物その辺のランチとちゃうでぇ)
言葉とは裏腹に楽しそうな笑い声が携帯越しに伝わって来た。
この作家の他の作品
表紙を見る
たまには、少しばかり昔を懐かしんで……
出したくても、書く事すら出来なかった手紙
ほのかに残る想い出は 果たして何通の手紙になるのだろう
2009.4.24 一通目
表紙を見る
現実は、小説やドラマの世界みたいに、それほどドラマチックなものじゃない。
でも、時々神様はびっくりするような時間をプレゼントしてくれる事がある。
それは僕に関しても同様だった。
アニータ……
見知らぬ国からやって来た彼女と、僕は一つ屋根の下で暮らす事になった。
以来、僕の中でいろんなものが、シャボン玉のように弾けては飛んだ。
悪戯好きの神様がくれた17歳最後の夏。
僕は新しい扉に手を掛けた……
アクタガワ ナオキ
『こういう小説も、私の中から生まれて来るんだ……
そんな不思議な感覚に包まれながら
書いています
稲葉禎和 』
愛水様
素敵なレビューありがとうございまいた!
表紙を見る
表の世界では生きられない男達がいる。
欲望の赴くままに…
己の力だけでのし上がる…
そんな、ありふれた安っぽいハードボイルド小説のような事は、現実の世界では通じない。
誰しもが持っている力への憧れ…
富と権力…そして、暴力…
ならず者…凶漢、 デスペラードな男達の物語。
*近々こちらを非公開にさせて頂きます。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…