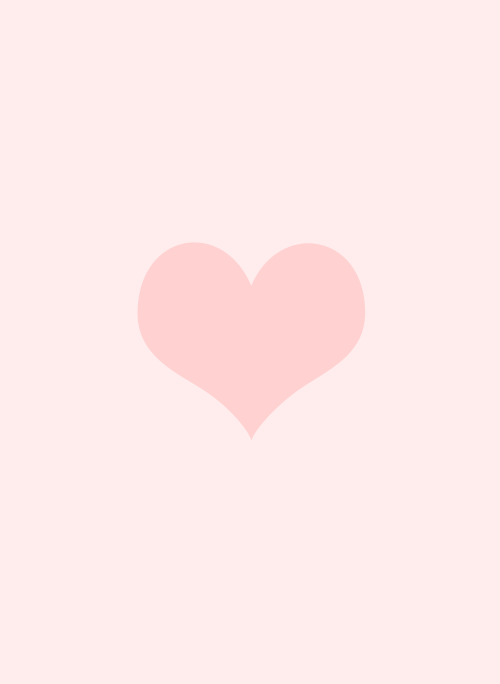初日を迎える時の気持ちは、何時も複雑な感情が入り混じったものになる。
前日迄の興行が特に印象深いものであったりすれば尚更の事だ。
通り過ぎた十日間の熱が、まだ自分の身体の中で余熱として燻っているところへ、新たな熱が加わる。
冷めて欲しく無い……
そんな気持ちと、新たな出会いへの期待……
余熱を消し去ってくれるには、新たな出会いが、より熱を帯びたものでなければならない。
余熱の燻りが余りにも鮮烈過ぎたりすると、それを消し去ってくれるには余程の舞台に出会わなければ残り続けてしまうものだ。
姿月(しづき)との一年振りの仕事は、余りにも鮮烈過ぎた。
そのせいだったのか、僕は初日の一回目の照明を終えると、無意識のうちに彼女へ電話を掛けていた。
今日から和歌山の劇場の筈だ。
三回……
五回……
七回……
十回以上鳴らしたかも知れない。
諦めて切ろうとした時、彼女とやっと繋がった。
「お疲れ様です」
意味も無く電話を掛けてしまった事を少しばかり後悔しながら、彼女の天真爛漫な何時もの声を待っていた。
ほんの少し、本当に僅かばかりの沈黙を感じた。
「そっちの初日はどうですか?」
もとからこれといった用事があって掛けた電話では無かったから、彼女の沈黙に慌ててそんな事を聞いた。
「……アタシ、飛んだの」
返って来た返事は、意外な言葉であった。
そして、その後に続いたのは彼女の涙混じりの声だった。
姿月との出会いは丁度一年前になる。
平成十年八月のお盆興行に彼女は来た。
横浜市内にある小さなストリップ劇場。
「シアター アート」
洒落た横文字で呼ばれていたその劇場は、元々はSM専門の劇場だった。
僕がこの劇場に来たのは、その年の三月で、SM専門の劇場からオーナーが変わり、多くあるような一般的なストリップ劇場へとリニューアルされて半年程した頃だった。
住む所も職も無く、ただぶらぶらするだけの生活を三ヶ月ばかり続けていて、いよいよ明日からの生活に困っていた時に、私はその劇場の前を通り掛かった。
入口脇に従業員募集の貼紙を見、次に出演者のポスターを眺めた。
ストリップ劇場であると判ると、一瞬躊躇したが、住み込み可と書いてあった文字に惹かれて私は受付の前に立った。
実のところ、ストリップの仕事は以前もした事があった。
千葉の劇場に僅か一ヶ月ばかり勤めていただけであったが。
スーツ姿の年配の劇場員に働きたい旨を伝えると、オーナーが一時間後に来るからその時に直接面接をしてくれると言ってくれた。
近くのコンビニで履歴書を買い、喫茶店のランチで腹拵えをしながら、履歴書を書いた。
劇場での経験を約半年と経歴に水増しをし、時間が来る迄隙を潰した。
面接はアッサリとしたもので、早速その日から働く事になった。
それから五ヶ月が過ぎ、照明係として働いていた私は、姿月という踊り子と出会ったのである。
「シアター アート」に入ったその日から照明をやらされた。
狭い照明室に入り、先輩の従業員にスイッチや照明器材の使い方を聞く。
やたらスイッチが多いなと最初は感じたのだが、小一時間ばかり先輩の操作を横で眺めてみると、思った程ではないなと少しばかり胸を撫で下ろした。
照明室から舞台を見る。
かなり小さいな……
客席も、三十人ばかりが座れる程。
立ち見が出ても五、六十人が限界か……
数ヶ月後、姿月の興行では、百人近くが入り、入口の扉が閉まらなくなったのだが、この時点でそれを想像出来る要素は皆無だった。
その週の香盤は六香盤。
自分の劇場からデビューさせた新人をトップにし、ラストのトリは前年にデビューした他の劇場の所属タレントだった。
香盤とは、出演するタレント(ストリッパー)の出演順を言う。
ストリップ劇場の一週は、基本的に十日間。
三十一日ある月の最後の週は十一日興行となったり、劇場によっては休みにする所もある。
話を戻す。
初めての劇場での仕事。
経験があるのだからと、一時間余りの説明だけで直ぐさま照明をやらされた。
初めはスイッチの位置に戸惑いを感じたが、実際に何人かのステージに照明を当ててみると、直ぐに慣れた。
びっくりする程のステージには出会わなかった。
二年前、初めてストリップ業界に入り、カルチャーショックを受けた時に比べると物足りなさを感じてしまった。
踊り子の動きに、自分のイメージするライティングが追いつかない……
そんなもどかしさばかりを感じ、ストリップというものを何処か舐めていた自分にショックを憶えていた事を思えば、随分と余裕が出たものだ。
数える程しかないライトの色と数。
代わり映えしないステージ。
演じる踊り子は別でも、内容は皆一緒だった。
私が照明係として働くようになって三ヶ月ばかり過ぎた頃、あるベテランの踊り子が新宿の劇場で引退興行を行う事になった。
その踊り子とは面識は無い。
前の月にシアター アートに乗ったある踊り子さんから、
「その姐さんのステージを観る最後のチャンスだよ」
と言われ、六月の中旬、休日を利用して私は新宿の劇場へ出掛けた。
観に来なさいと言った踊り子本人が、その興行ではトップの出番で、シアター アートに出演した事のある踊り子も他に何人か居た。
興味自体は正直な所、引退興行の主では無かった。
自分が当てる照明とどう違うか……
劇場によってライトの種類が大分違う。羨ましくなる位にいい器材を使っている。
だが殆どが使いこなせていない。
コンピュータでプログラミングされた大劇場の照明ならいざ知らず、手動の照明ならば感性でライティングというものはある程度変わるものだ。どの劇場の照明も、単に踊り子をライトで追っているだけだった。
当てるライトの角度、色……何でも光を当てればいいというものでもない。
ライティング一つで舞台は生きもし、死んだりもする。
が、本物の舞台を演じてくれる踊り子は、そんなものを超越してしまう。
しょぼい一本のピンスポットだけでも、客を虜にしてしまうものなのだ。
話しが又逸れた。
引退興行を行っていた踊り子は、下に何人もの妹分を枝葉のように作り、自分の名前を冠にした軍団なる一団を形成していた。
狭い縦社会の一面……
そう受け止めるだけでは理解出来ない繋がりが彼女達にはあった。
劇場の待合室や廊下に沢山の花輪や花束が飾られていた。
『いずみリカ姐さんへ 〇〇より』
そんな中に姿月の名前を見た。
誤解の無いように言う。
こののち二ヶ月後に出会う迄、僕は姿月という踊り子の事を何一つとして知らなかった。
しかし、どうしてなのかこの時に見た花輪の中の名前をその後もずっと記憶していたのである。
理由……
今もって判らない。
引退興行の主であるいずみリカのステージは、素晴らしかった。
客席の片隅で私は涙さえ流していた。
改めて自分がこの世界の奥深さに魅せられた事に気付かされた。
ストリップ……
単なる裸踊り
全裸になり、大勢の男の前で猥褻なポーズを取り見世物になる……
大概の人間はストリップをそういう認識で捕らえるだろう。その通りだ。
だが、そうではない部分を見つけた時、人間は大きな感動を受ける。
そこに理屈は存在しない。
観たままのもの、生に伝わって来るものが、観る者の心を揺り動かし、感動をも与えてくれるのだ。
若くて可愛いとか、綺麗なだけのストリッパーのステージからは、そういったものは生まれない。
いずみリカのステージを観て涙を流す位に感動はしたが、後々考えてみると、それは消え行く者への惜別の情から生まれた涙だった。
彼女のステージは確かに素晴らしかった。
それはストリップというよりも、ダンスそのものであり、本来あるべきエロスはかけらも感じられないものであった。
踊り子達は、その殆どがダンスが上手くなりたいと願い、単なる裸踊りにはしたく無いと思っている。
それはそれで間違ってはいない。
自分を向上させて行く為に日々、ダンスのレッスンに明け暮れる踊り子も少なく無い。
デビューして日の浅い踊り子の深夜レッスンに朝まで付き合い、泣きながら振り付けを覚えようとする姿にカルチャーショックを受けたからこそ、自分は照明というものを疎かに出来ないと感じた訳である。
だが、ストリップに於ける本物の感動は、それ以上の何かが無ければ生まれて来ない。
お金を払う客の反応が全てを物語っている。
酔っ払った勢いで劇場にやって来る客達がそういったステージを観て、自分の想像を超えたものを目にした時、間違い無く押し黙る。
裸になる度に嬌声を上げ、時には非常識な態度を取ろうとする酔客がである。
つまらないからではない。
その姿を照明室から見れた時、共にその時間を共有出来た事に、劇場の照明マンは言葉に表せない喜びに浸り、踊り子との一体感を噛み締める。
だが、なかなかそういうステージに出会う事は少ない。
平成十年八月のお盆興行の出演者が決まったのは、その二週間前の事であった。
時間は既に夜中の十二時を過ぎている。
暦が替わり、日付は八月の一日。
新たに始まる十日間の為に、僕はライトのゼラチン(色を変える為のフィルム)を新しいものに交換していた。
それと、少ないライトの数をどうにか効果的にしようと、その角度を変えたりする作業に没頭していた。
盆と正月は劇場にとっての掻き入れ時だ。
どの劇場も普段以上に出演者を豪華にしようと、人気の踊り子の取り合いになる。
AV(アダルトビデオ)というものが世に現れ、その世界からストリップへと流れて来る踊り子が増えて来てからというもの、どの劇場もAV出身の踊り子を客寄せのメインにしようとした。
確かに集客力はある。
だが、それも程度というものがあって、聞いた事も無いような名前のAV嬢なんかが出演しても、それ程の有り難みは無いものだ。
姿月という踊り子も元AVという冠を被されていた。
前日迄出演していた踊り子の中に、二人ばかり姿月の後輩が居た。
彼女達から姿月の事をちらっと聞いていたが、話しから想像した姿月の印象は、
気難しい踊り子……
照明に厳しい踊り子……
であった。
まあ、それ位ならどうって事ないか……
照明の注文がどう煩かろうが、うちの照明じゃ遣れる事が決まってる……
開き直り……
初日を迎える準備というものは、ちょっと不思議な高揚感に包まれる。
まだ半年にも満たない劇場経験だから、初めて出会う踊り子の方が多い。
心の何処かで何かを期待している自分が居る。
楽屋の部屋割も決まり、数時間後には出演する踊り子達が乗り込んで来る。
一足先に荷物だけ送られて来ていた。
姿月のものだ。
「重いなぁ」
若いマネージャーが呟く。
「そう言えば、カンナちゃんが言ってましたけど、姿月さんと百華さんは香盤も部屋も別の方がいいよって」
「面倒クセエなあ」
初対面の前から、従業員の間に於ける姿月の印象はマイナスポイントばかりが累積されていた。
八月一日の朝が来た。
劇場の最上階に住み込んでいた僕は、何時もより一時間ばかり早く階下の事務所に降りた。
クリーニングしたてのワイシャツに着替え、身支度をする。軽く腹拵えをして一階の劇場受付へ行くと、既に客が並んでいた。
数を数えてみる。
七、八、九……
十四、五人は並んでいた。
久し振りだな……
開場迄まだ一時間近くある。
この客達が、全部今日から始まるステージの踊り子達目当てとは思っていなかった。
お盆特別興行として、昼の二回だけAV紛いの企画ステージを組んでいた。
それ目当ての客なんだろうと思いながら、場内をチェックし、乗り込んで来る踊り子達の到着を待ち望んでいた。
十時近くなると一人、又一人と出演する踊り子達がやって来た。
楽屋に案内し、出し物の音を受け取る。
一枚のMDに落としてくれている踊り子も居れば、何枚かのCDを渡し、
「このCDの何曲目と、こっちの何曲目で、最後はこれね」
と、無造作に言い、舞台化粧に没頭する踊り子も居る。
CDやMDを受け取りながら、簡単に照明のポイントを聞き、メモにして行く。
この頃、僕が照明のメインだったから、初日の一回目は必ず担当した。
「あたし、ここで一旦袖に引っ込むから、暗転して欲しいの。ここ、ブラックライトあります?」
「すいません、ブラックライトは無いんです」
「あたしは板付けで、ダンスの時は適当にパキパキした照明にしてくれればいいわ。後は任す」
劇場のキャパや照明設備に限界がある事を踊り子達は良く判っている。
余り期待されてないな……
そう感じる時もあれば、どうせ言った通りには出来ないでしょう的な諦めの空気を感ずる時もある。
姿月が乗り込んで来た。
楽屋に出向く。
少しばかり緊張している自分が居た。
「はじめまして、照明を担当します佐伯と言います」
我ながら随分と堅苦しい挨拶をしたものだと思った。
こちらに向き直った姿月は、一瞬後退りしそうになる位に綺麗だった。