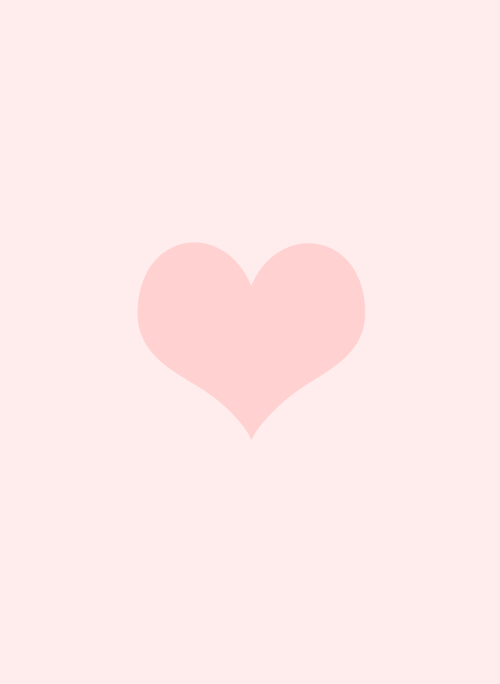母は、情緒不安定になった私を見て、ひどい言葉を投げつけました。汚いものを見るような目を向けました。何を言われたのか、それは覚えていません。きっと、深く傷ついて記憶が抜けてしまったんだと思います。
父は、まだ味方になってくれました。そして、私に部活を休むように言いました。
「部活をしばらく休みたい」
そう言った時も、私は泣いていました。みんなが何も言わなかったことが、唯一の救いだったような気がします。
私が泣いている時、私を支えてくれた人がいました。それは、莉亜ちゃんです。
莉亜ちゃんは、私が落ち着くまでいつもそばにいてくれました。家で吐き出すことのできない気持ちを聴いてくれました。
抱きしめてくれた温もりが、「大丈夫」だと言ってくれたことが、どんな贈り物よりも嬉しかったです。
部活はいつも賑やかです。ふざける時はふざけて、真面目な時もふざける人がいて、休憩中はそれ以上に賑やかで……。
しかし、私は孤独感を感じていました。みんなとの間に、大きな透明な壁を感じていました。
「……消えたい……」
一人ぼっちなら、この寂しさに耐えられます。でも、周りに人が多くいるのになぜ孤独を感じなければならないのでしょうか。
父は、まだ味方になってくれました。そして、私に部活を休むように言いました。
「部活をしばらく休みたい」
そう言った時も、私は泣いていました。みんなが何も言わなかったことが、唯一の救いだったような気がします。
私が泣いている時、私を支えてくれた人がいました。それは、莉亜ちゃんです。
莉亜ちゃんは、私が落ち着くまでいつもそばにいてくれました。家で吐き出すことのできない気持ちを聴いてくれました。
抱きしめてくれた温もりが、「大丈夫」だと言ってくれたことが、どんな贈り物よりも嬉しかったです。
部活はいつも賑やかです。ふざける時はふざけて、真面目な時もふざける人がいて、休憩中はそれ以上に賑やかで……。
しかし、私は孤独感を感じていました。みんなとの間に、大きな透明な壁を感じていました。
「……消えたい……」
一人ぼっちなら、この寂しさに耐えられます。でも、周りに人が多くいるのになぜ孤独を感じなければならないのでしょうか。
同じ頃、あまりに情緒不安定な私を見て、莉亜ちゃんが私を保健室に連れて行ってくれました。
そこで私は、保健室の先生から精神科に行くことを勧められました。
精神科と聞いた時、私の頭の中には恐ろしい光景が浮かんでいました。
身体拘束されるかもしれない、変な薬を飲まされるかもしれない、無理やり何か検査を受けさせられるかもしれない……。
不安と恐怖で、私は先生に何度も「怖いことされませんよね?」と訊きました。
精神科なんて行ったこともなく、テレビで患者が押さえつけられる映像を見てそれが恐怖となっていました。
しかし、みんなに説得され、私は精神科に行くことになりました。
これが私の真実を知ることになるとは、全く疑うこともなく…。
両親とともに訪れた精神科は、先生が猫好きなのか待ち合い室には猫の置物などがたくさん置かれていました。
精神科の先生は、女性でした。少し緊張しながら私は最近の出来事を話しました。
先生は私の話を聞いた後、紙を一枚取り出しそれを見ながら、私にいろいろ質問をしました。
そこで私は、保健室の先生から精神科に行くことを勧められました。
精神科と聞いた時、私の頭の中には恐ろしい光景が浮かんでいました。
身体拘束されるかもしれない、変な薬を飲まされるかもしれない、無理やり何か検査を受けさせられるかもしれない……。
不安と恐怖で、私は先生に何度も「怖いことされませんよね?」と訊きました。
精神科なんて行ったこともなく、テレビで患者が押さえつけられる映像を見てそれが恐怖となっていました。
しかし、みんなに説得され、私は精神科に行くことになりました。
これが私の真実を知ることになるとは、全く疑うこともなく…。
両親とともに訪れた精神科は、先生が猫好きなのか待ち合い室には猫の置物などがたくさん置かれていました。
精神科の先生は、女性でした。少し緊張しながら私は最近の出来事を話しました。
先生は私の話を聞いた後、紙を一枚取り出しそれを見ながら、私にいろいろ質問をしました。
「忘れ物が多い?」
「集中すると、何も聞こえなくなる?」
その質問に、私は嘘をつくことなく素直に答えました。そして、先生はこう言いました。
「あなたは、ADHDです」
それは、発達障害の一種だと先生は説明してくれました。そのあと、私の両親が呼ばれ、私は退室しました。
発達障害は、小学生のうちに見つかることが多いのですが、私の場合、注意力の欠如ということで発見が遅れたと父が言っていました。
薬を薬局でもらい、母が「よかったね、見つかって」と言っていました。
私はその時、「うん」と頷きました。自分のことがわかった、そう思いたかったのです。
しかし、私の心は思ったようには進んではくれませんでした。人と違う、自分は違う、そんな思いが私を支配していったのです。
ADHDのことを障害とマイナスなイメージでしかとらえないまま、私はマイナスな方向へ落ちていきました。
「集中すると、何も聞こえなくなる?」
その質問に、私は嘘をつくことなく素直に答えました。そして、先生はこう言いました。
「あなたは、ADHDです」
それは、発達障害の一種だと先生は説明してくれました。そのあと、私の両親が呼ばれ、私は退室しました。
発達障害は、小学生のうちに見つかることが多いのですが、私の場合、注意力の欠如ということで発見が遅れたと父が言っていました。
薬を薬局でもらい、母が「よかったね、見つかって」と言っていました。
私はその時、「うん」と頷きました。自分のことがわかった、そう思いたかったのです。
しかし、私の心は思ったようには進んではくれませんでした。人と違う、自分は違う、そんな思いが私を支配していったのです。
ADHDのことを障害とマイナスなイメージでしかとらえないまま、私はマイナスな方向へ落ちていきました。
私は、普通ではないということを、莉亜ちゃんや部活のみんなに話しました。
しかし、情緒不安定が完全に治ったわけではわけではなく、悲しみを感じてはいました。
精神科の薬はカプセルでした。とても苦くて、まずくて、私はジュースやココアで飲んだりしていました。
それでも薬を飲むのを忘れて、母がカンカンに怒ったことがあります。精神科の薬はとても高いのです。
カプセルの薬は、最初のうちは副作用で気持ち悪くなりました。何のための薬なのかわからず、私は飲んでいました。
それでも、これで普通に近づけられるなら、頑張ろうと思っていました。でも、そんな思いもある人によって壊されてしまうのです。
あれは、六月のことでした。
剣道部には、一年生の弟が入部していました。弟は小学生の時から剣道をしていて、そこそこ実力もありました。中学生になる前から、弟と同じ時期に剣道を始めた父と部活に足を運んでくる時がありました。
その時に、「お前より弟の方が頼りになる」そう言われて傷ついたのを覚えています。
しかし、情緒不安定が完全に治ったわけではわけではなく、悲しみを感じてはいました。
精神科の薬はカプセルでした。とても苦くて、まずくて、私はジュースやココアで飲んだりしていました。
それでも薬を飲むのを忘れて、母がカンカンに怒ったことがあります。精神科の薬はとても高いのです。
カプセルの薬は、最初のうちは副作用で気持ち悪くなりました。何のための薬なのかわからず、私は飲んでいました。
それでも、これで普通に近づけられるなら、頑張ろうと思っていました。でも、そんな思いもある人によって壊されてしまうのです。
あれは、六月のことでした。
剣道部には、一年生の弟が入部していました。弟は小学生の時から剣道をしていて、そこそこ実力もありました。中学生になる前から、弟と同じ時期に剣道を始めた父と部活に足を運んでくる時がありました。
その時に、「お前より弟の方が頼りになる」そう言われて傷ついたのを覚えています。
私の学校の剣道部は、とても弱くみんな弟が入って来てくれたことを喜んでいました。
でも、弟は羽目を外して問題行動ばかり起こします。柔道場の壁を登って遊んだり、竹刀で遊んだり、誰も弟を咎めることはなかったと思います。
そのたびに、私が注意していたのです。
その日は、心の状態も穏やかで久しぶりに面をつけて練習ができると思っていました。あんなことを体験してしまうなんて、想像すらしていませんでした。
体操と、素振りが終わった後、十分間の休憩中でした。
私の左には扇風機が置かれ、涼しい風を届けてくれています。右には、里奈ちゃんが座っていました。
弟が扇風機の前にやって来ました。涼みに来たのかと思いましたが、違いました。
弟は扇風機でふざけ始めたのです。私が「ちょっとあんたね!」と言ったその時でした。
「うるっせぇんじゃ!!」
隣から大きな怒声が聞こえ、びくりと私の体が震えました。右手は小刻みに震えていて、私はそれを必死で左手で押さえつけようとしました。しかし、震えは止まりません。
でも、弟は羽目を外して問題行動ばかり起こします。柔道場の壁を登って遊んだり、竹刀で遊んだり、誰も弟を咎めることはなかったと思います。
そのたびに、私が注意していたのです。
その日は、心の状態も穏やかで久しぶりに面をつけて練習ができると思っていました。あんなことを体験してしまうなんて、想像すらしていませんでした。
体操と、素振りが終わった後、十分間の休憩中でした。
私の左には扇風機が置かれ、涼しい風を届けてくれています。右には、里奈ちゃんが座っていました。
弟が扇風機の前にやって来ました。涼みに来たのかと思いましたが、違いました。
弟は扇風機でふざけ始めたのです。私が「ちょっとあんたね!」と言ったその時でした。
「うるっせぇんじゃ!!」
隣から大きな怒声が聞こえ、びくりと私の体が震えました。右手は小刻みに震えていて、私はそれを必死で左手で押さえつけようとしました。しかし、震えは止まりません。
目の前はぼやけて、今にも泣いてしまいそうでした。
心を支配していたのは、恐怖一色だったのです。
隣を見れば、里奈ちゃんが私を睨んでいました。後輩に怒鳴られたのです。
「なら、向こうに行けばいいじゃない」
私は冷静を装って、そう言いました。里奈ちゃんは何も言わずに隣から去りました。
それを見届けた後、私の目から涙があふれて止まらなくなりました。手は震え、私は泣いていることがバレないように面をつける時にかぶる布を顔に当て、静かに泣き続けました。
異変に気付いたのは、あっという間のことでした。
私は、自分の息がまるで全力で走った後のように荒くなっているのに気づきました。次第に手足が痺れ、息をしているはずなのに、呼吸ができなくなっていきました。苦しくて、このままでは死んでしまうのではないか、そう何度も思いました。
すると、異変に気付いた人が「大丈夫か?莉亜のところに行け」と言ってくれました。私はそれに答えることもできないまま、部室へと急ぎました。
莉亜ちゃんだけが頼りでした。莉亜ちゃんにしか頼れないのです。
部室の扉を開けると、莉亜ちゃんがこちらを振り向きました。そして、驚いた様子を見せました。
心を支配していたのは、恐怖一色だったのです。
隣を見れば、里奈ちゃんが私を睨んでいました。後輩に怒鳴られたのです。
「なら、向こうに行けばいいじゃない」
私は冷静を装って、そう言いました。里奈ちゃんは何も言わずに隣から去りました。
それを見届けた後、私の目から涙があふれて止まらなくなりました。手は震え、私は泣いていることがバレないように面をつける時にかぶる布を顔に当て、静かに泣き続けました。
異変に気付いたのは、あっという間のことでした。
私は、自分の息がまるで全力で走った後のように荒くなっているのに気づきました。次第に手足が痺れ、息をしているはずなのに、呼吸ができなくなっていきました。苦しくて、このままでは死んでしまうのではないか、そう何度も思いました。
すると、異変に気付いた人が「大丈夫か?莉亜のところに行け」と言ってくれました。私はそれに答えることもできないまま、部室へと急ぎました。
莉亜ちゃんだけが頼りでした。莉亜ちゃんにしか頼れないのです。
部室の扉を開けると、莉亜ちゃんがこちらを振り向きました。そして、驚いた様子を見せました。
「……助けて……。息が……」
私はそう言うのが精一杯でした。莉亜ちゃんは私を椅子に座らせ、落ち着くまで背中をさすってくれました。
その温もりが、何よりも温かくて安心しました。
呼吸がもとに戻った後、莉亜ちゃんに「何だったんだろ、これ…」と呟くと、「過呼吸じゃないかな」と莉亜ちゃんが教えてくれました。
過呼吸なんて、この時だけのことだと思っていました。
私は、何も知ろうとしていなかったのです。ADHDのことも、過呼吸のことも…。
だから、長く苦しむはめになったのだと思います。
過呼吸を、一度起こしたあの日から何度も私は過呼吸を起こすようになりました。
悲しい時、親と喧嘩をした時、苦しくなって過呼吸を起こしました。
親は、私の過呼吸を見て心配することは一度もありませんでした。親どころか、弟や妹すらも過呼吸を起こした私を「気持ち悪い」と言いました。
「演技やめろよ!」
「構ってほしいだけだろ!」
「お前のは過呼吸じゃない!」
何度も過呼吸を繰り返していると、息をコントロールすることができるようになっていったのです。それを見て両親は「演技だ」と言いました。
「本当に過呼吸なら、紙袋を使わないと戻らない」
私はそう言うのが精一杯でした。莉亜ちゃんは私を椅子に座らせ、落ち着くまで背中をさすってくれました。
その温もりが、何よりも温かくて安心しました。
呼吸がもとに戻った後、莉亜ちゃんに「何だったんだろ、これ…」と呟くと、「過呼吸じゃないかな」と莉亜ちゃんが教えてくれました。
過呼吸なんて、この時だけのことだと思っていました。
私は、何も知ろうとしていなかったのです。ADHDのことも、過呼吸のことも…。
だから、長く苦しむはめになったのだと思います。
過呼吸を、一度起こしたあの日から何度も私は過呼吸を起こすようになりました。
悲しい時、親と喧嘩をした時、苦しくなって過呼吸を起こしました。
親は、私の過呼吸を見て心配することは一度もありませんでした。親どころか、弟や妹すらも過呼吸を起こした私を「気持ち悪い」と言いました。
「演技やめろよ!」
「構ってほしいだけだろ!」
「お前のは過呼吸じゃない!」
何度も過呼吸を繰り返していると、息をコントロールすることができるようになっていったのです。それを見て両親は「演技だ」と言いました。
「本当に過呼吸なら、紙袋を使わないと戻らない」
それについて私は調べました。口に袋を当てて呼吸を戻す方法は、以前はよく使われていましたが、実は危険な行為だそうです。亡くなった人もいるそうです。
私はこのことを親に言いましたが、聞く耳を持ってくれませんでした。
三年生の時は、親とたくさん喧嘩をしました。その多くは、弟や妹を叱った時の飛び火なのですが、私はそのたびに泣いて過呼吸になるを繰り返しました。
精神科に行くことも、だんだんと辛くなっていきました。先生が嫌だったわけではありません。
母が、「薬代が高い。何で、こんなに払わなきゃいけないの」と言ったからです。
それを言われることが嫌で、私は先生に嘘をつきました。
先生はいつも、「大丈夫だった?」と訊いてきます。私は、どんなに辛くても笑顔を作って「はい、大丈夫でした」と答えるようにしました。
そう何度も言っていると、病院に行かなくてもいいようになりました。この時に母はとても喜びました。
心に傷がまだ深く残ったまま、私は放り出されたのです。
私はこのことを親に言いましたが、聞く耳を持ってくれませんでした。
三年生の時は、親とたくさん喧嘩をしました。その多くは、弟や妹を叱った時の飛び火なのですが、私はそのたびに泣いて過呼吸になるを繰り返しました。
精神科に行くことも、だんだんと辛くなっていきました。先生が嫌だったわけではありません。
母が、「薬代が高い。何で、こんなに払わなきゃいけないの」と言ったからです。
それを言われることが嫌で、私は先生に嘘をつきました。
先生はいつも、「大丈夫だった?」と訊いてきます。私は、どんなに辛くても笑顔を作って「はい、大丈夫でした」と答えるようにしました。
そう何度も言っていると、病院に行かなくてもいいようになりました。この時に母はとても喜びました。
心に傷がまだ深く残ったまま、私は放り出されたのです。
それからは、毎日泣いていました。大切な試合が控えているというのに、莉亜ちゃんにそばにいてもらっていました。莉亜ちゃんの時間を奪ってしまったことは、今でもとても後悔しています。
自分が普通ではないこと、自分の存在がみんなに迷惑をかけてしまっていること、それが苦しくてたまりませんでした。
死のうと何度思ったかわかりません。リストカットしようと、引き出しを開けてカッターを取り出しました。刃を出すと、キチキチと気持ち悪い音が室内に響きました。
肌に刃を突き立てたらどうなるのか、それは想像がついていました。血があふれ、体や服、床を汚してしまうのでしょう。
リストカットは、結局怖くてできませんでした。
リストカットの代わりに私が選んだのは、自分の首を自分で締めるということでした。
最初は手で力いっぱい締めました。苦しくて、手を離した後咳き込みました。すると、さっきまで胸にあった悲しみが少し薄れているような気がしたんです。
私はそれが嬉しくて、何度も首を締め続けました。しかし、だんだん苦しみを感じなくなっていきました。そこで、今度は紐を使うことにしたのです。
自分が普通ではないこと、自分の存在がみんなに迷惑をかけてしまっていること、それが苦しくてたまりませんでした。
死のうと何度思ったかわかりません。リストカットしようと、引き出しを開けてカッターを取り出しました。刃を出すと、キチキチと気持ち悪い音が室内に響きました。
肌に刃を突き立てたらどうなるのか、それは想像がついていました。血があふれ、体や服、床を汚してしまうのでしょう。
リストカットは、結局怖くてできませんでした。
リストカットの代わりに私が選んだのは、自分の首を自分で締めるということでした。
最初は手で力いっぱい締めました。苦しくて、手を離した後咳き込みました。すると、さっきまで胸にあった悲しみが少し薄れているような気がしたんです。
私はそれが嬉しくて、何度も首を締め続けました。しかし、だんだん苦しみを感じなくなっていきました。そこで、今度は紐を使うことにしたのです。
この作家の他の作品
表紙を見る
とある国家に所属するスパイの青年。彼にはとある秘密があった。
「今度の任務は、ここの会社のデータを盗むことか……。頑張らないと!」
普段はあまり仕事を好まず、争い事を避けようとする。しかし、自身が危険に陥った際、彼の中に眠るもう一人が目を覚ます。
「全員まとめてぶっ潰す!」
表紙を見る
20××年、ついに日本も同性婚が認められることになった。これに歓喜した同性カップルは多く、同性カップルも結婚式を挙げられるようになった。
「結婚式、とっても楽しみ!」
「ええ。準備を頑張って、素敵なものにしましょう!」
これは、とあるカップルが結婚式を挙げるまでの物語ーーー。
表紙を見る
「一生あなたを好きでいます!」
「俺の隣にいてください」
「絶対、あなたを楽しませ続けます」
「ずっと幸せにします」
こんな甘い甘い告白、何て答えるべきなんでしょうか……。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…