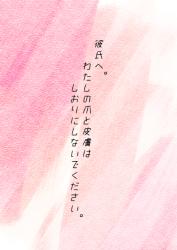バタバタと足音をたてながら走り、靴を履く。
振り返って、いま通った道である廊下をまじまじとながめた。
深みのある、緑がかった茶色の床。時代を感じさせるような濃くて古い色なのに、引っ越してきてから数年しか経っていないから、まだまだ新しい。
おとなしくみえるけれど、どこかで強い力を抱くそれにむかってうなずく。
ギィと悲鳴をあげる扉。1歩外に出ると、眩しさにやられてしまいそうだった。
ぎゅっと目を閉じることは、しない。
負けてしまうみたいで、悔しいから。
パタンと静かな音を響かせながら扉を閉めると、ひどく小さな、猫の声がした。