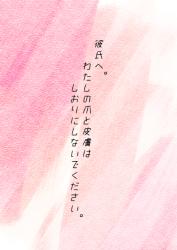「栗林くん、だーいすき」
「俺も好きに決まってるだろ」
くーちゃんの名前があがって、思わず、その方向をみてしまう。
茶髪を高い位置でひとつに結んだ、活発そうな女の子と、手を繋いで歩くのは……紛れもない、くーちゃんだった。
「彼女より?」
「当たり前。彼女のこと、別にたいして好きじゃないし」
「うわー、そういうこと言っちゃう?」
ふたりはカップルのように、ならんで歩いている。
「いたらいいやってだけかな」
くーちゃんの言葉に、失望と、悔しさが溢れてくる。
「ねぇ、ちゅー、して?」
女の子が可愛くおねだりすると、くーちゃんはキスをした。
すごく深くて、とても甘そう。