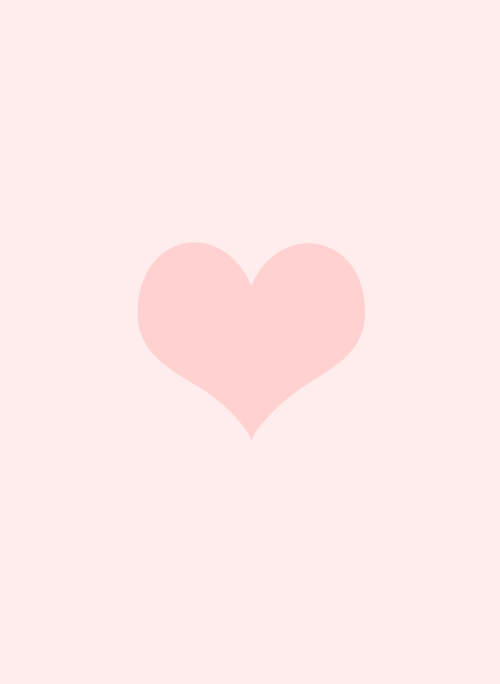「この……鬼っ! 悪魔っ! イケメンならなに言っても許されるなんて思わないでよねっ!」
二月三日、節分。誰もいない夜のオフィスで、私はひとり豆を投げていた。
そう、にっくき高築課長の椅子めがけて。
椅子の背には、豆を買ったときにおまけでついていた鬼のお面をテープで貼り付けてある。
「鬼は~外!」
ただひたすら悔しい思い、腹立たしい気持ちを込めて、紙のお面に豆を投げつける。
パチン、パチン、と豆が紙を打つ小気味いい音に、ほんの少しだけ慰められて、私は大きく息を吐いた。
数時間前、高築課長に言われた言葉が耳に蘇る。
私がデスクでパソコンに向かっていたら、課長が紙の束を無造作にデスクに置いた。私が一週間かけて練り上げた、渾身のイベント企画書だ。
「ダメだ。ボツ」
開口一番、投げられた厳しい言葉に、私は泣きたい気分になった。一週間、寝る間も惜しんで考えたのに。
「……どこがいけなかったんでしょうか」
「全部だな」
課長が低い声で続ける。
「おまえがこの製品を好きだということはよく伝わってくる。だが、それだけだ。こんなのはただの独りよがりだ。なんのためのイベントか、誰のための企画か。そのくらい考えられないで、この課でやっていけると思うなよ」
課長の言葉を思い出したせいで、目に涙が浮かび、手の甲で拭った。
私の六歳上、三十一歳でイベント企画課の課長を務めるエリート上司。ほかの部署にはファンも多いけど、この課長のファンになるなんて、それは絶対彼の本性を知らないからだ。実際はこんなにも鬼なのに。みんな課長の整った顔に騙されている。
「……鬼課長は外。優しいイケメン新課長は内」
ぽつりとつぶやいて、掴んだ豆を口に入れ、怒りを込めてバリボリかみ砕いた。
完全にスッキリした、とは言いがたいけど、袋の中の豆がなくなってしまった以上、ひとり豆まきはこれで終わりだ。
撒いた豆を拾い集めようとしゃがんだとき、パーティションの向こうから低い声が聞こえてくる。
「鬼課長とは俺のことか」
ギクッとして、一瞬で額に嫌な汗が浮かぶ。
まさかまさか課長が残っていたなんて!
慌てて立ち上がると、パーティションを回って、当の鬼課長、もとい高築課長が姿を現した。ゆっくり歩いて私の目の前で足を止め、丸めた紙を持った右手を腰に当てる。二十センチ以上上から切れ長の目で見下ろされ、私はあわあわしながら口を開く。
「あ、あのっ、か、か、課長のことではなくてですねっ、その、節分だし、日頃のストレスを晴らそうと思って~……まあ、そのぅ……」
「日頃のストレスは俺、というわけか」
課長は私の横をゆっくり歩いて、自分のデスクに浅く腰かけた。そうして床を見回す。
私が投げつけた豆がそこら中に散らばっていて、課長の椅子の背には鬼のお面が貼ってある。これは……どう見たってバレバレだ。たっぷり怒られるか……悪くすればクビ、とか。
そんな想像にぞっとしたとき、課長がふっと笑みをこぼした。
「見事に豆だらけだな」
そう言っておかしそうに笑う。お小言を覚悟していた私は、予想外の反応にぱちくりと瞬きをした。
「お、怒らない……んですか?」
おずおず問いかけると、課長は丸めて持っていた紙で、私の頭をポンと叩いた。
「おまえが出した修正案をチェックしていたんだ。この線で修正すれば、GOサインを出してやれる」
ええと。つまり、課長はパーティションの向こうで、私が帰る間際に提出したイベントの修正案を見てくれていたというわけで。ということは、やっぱり私の言葉は聞かれていたはずで。
「あのぅ、課長」
謝ろうとするより早く、課長が言う。
「浅井、おまえにとって俺は鬼上司なのかもしれない。だが、おまえに厳しくするのは、おまえに伸びしろがあると思っているからだ。やる気のないヤツ、見込みのないヤツに、いちいち構ったりしない」
課長が顔を近づけて私の目を覗き込んだ。整った顔と距離が近づき、しかもその顔が予想外に優しくて、ドギマギしてしまう。
「わかるな?」
念を押すように言って、課長が立ち上がった。
「さて、豆を片づけるか」
課長は立てかけてあるコードレス掃除機の方に向かっていく。
普段の課長からしたら、想像できない行動だ。
だって、私、課長を鬼に見立てて豆を投げたのに!
挙げ句の果てに、「鬼課長は外!」なんて言ったのに!
「か、課長!」
慌てて呼び止めると、課長が肩越しに私を見た。
「どうした?」
「どうして……怒らないんですか? 私、課長のことを……」
「鬼って言ったのに?」
「はい」
課長はゆっくりと私に向き直った。
「浅井の持論でいくと、イケメンならなに言っても許されるってわけではないんだよな。だが、俺の持論では、かわいい部下ならなにをしても許してしまうだろうな」
課長は私に背中を向けて、「特に浅井なら」と言った。
付け加えられたその一言にドキッとする。
そ、それって、私のことをかわいいって思ってくれてるってこと?
あ、いや、『かわいい部下』って言ってたから! ただの部下だから!
鬼上司からの想定外の言葉にひとりで赤面していると、いつの間にか課長がクリーナーを手にして、こっちに歩いてきていた。
「浅井は甘やかしてくれる『優しいイケメン新課長』の方がいいんだったな。俺が異動になった後、お望み通りの上司が来るといいな」
「いえ! とんでもない!」
課長が私に厳しくする本当の理由がわかったのだから、そう簡単に異動してほしくはない。厳しいことは厳しいけれど、それ以上に課長から学べることは本当に多いのだ。
「わ、私は高築課長がいいですっ」
真剣な顔で言うと、課長はいたずらっぽく微笑んだ。
「俺も浅井がいい」
その笑みと言葉に、不覚にも心臓が大きく跳ねた。鼓動がどんどん高くなって、顔が勝手に熱くなっていく。
「だから、ずっと俺のそばにいろ」
それって部下として? それともそれ以上の意味があるの……?
ぐっと近づいた課長の顔には、艶めいた甘い笑みが浮かんでいて……。
どうしよう。鬼課長を頭の中から退治するはずだったのに、心を奪われてしまった気がする……。
【END】