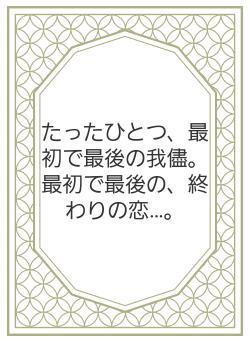ふわり。
もう、神々しいくらいの笑顔を残して、彼女は俺をそっと起こした後、その場を去っていこうとする。
そして、もう一度俺の方に微笑みを投げ掛けると、そのまま電車を降りていく。
「あっ!ま、待って…っ!」
俺はそんな彼女にお礼が言い足りないのと、もっと話がしたいので、急いでその後ろ姿を追っていった。
さっきまでの気分の悪さなんて、微塵も感じさせないくらいのスピードで…。
「ねぇ!キミ!」
駅の改札を出て、彼女も背中をとんっと小さく叩くと、さらりとした長い黒髪を風にそよがせながら、彼女は振り向いてくれる。
ドキンと胸が高鳴った気がしたのが、自分でもはっきりと分かる。
カァーッ!と熱くなっていく頬。
彼女はそんな俺の言葉を、少しだけ小首を傾げるようにして待ってくれていた。