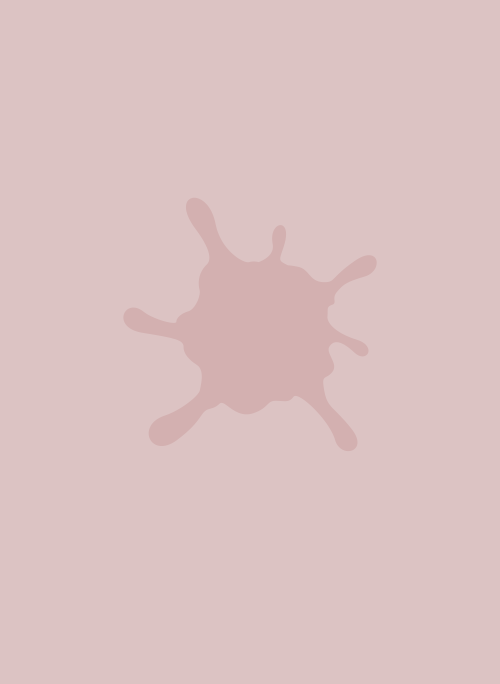三人は面白がるようにしてその場を去っていく。
その三人の楽しそうに逃げる後ろ姿を見てため息を吐くと、持っていたランドセルを地面に置いて少年の身体を起こした。
「"章ちゃん"...大丈夫?」
「"ちぃちゃん"....ぐすん...ありがとう。助けてくれて...」
少年は次々に溢れてくる涙を砂埃の袖で拭くが、涙は止まらず両目をずっとごしごしと拭いていた。
少女は砂埃の少年の背中を叩き、砂埃を落としていた。
「あいつら...許せない!明日一緒に先生に報告しよ?」
「ちぃちゃん。僕...大丈夫だから...そんな事したらお母さん悲しむし、迷惑掛けちゃうから...」
「でも章ちゃん。このままだったらずっとイジメられちゃうんだよ?いいの?」
少し落ち着いたのか、少年は拭くのを止め、首を横に振った。
「良くないけど、とにかく言わないで欲しいんだ。...僕、頑張るから。」
すぐに壊れそうな作り笑顔を少年は作った。それを見て少女は自分も泣きそうな顔をして、それを誤魔化すように少年を立たせた。
「だ、だけど章ちゃん。章ちゃんはなんでやり返さないの?あんなやつら、全員ぶっ飛ばしちゃえばいいのに。」
「そんなこと出来ないよ....僕、力も無いし運動も出来ない。僕よりおっきくて強い三人に勝てるわけないよ...」
「そんなのやって見ないと分かんないじゃん!それなら私も...」
「それに!...僕...」
少女の言葉を遮ってまで出た少年の答え。その優しすぎるが故に出てくる弱々しい回答。
これを聞いた少女は少年という人間を改めて認識したのだった。
笑い声が飛び交い、朝日が眩しく照らせる賑やかな教室。男子は馬鹿な事をして遊び、女子は友達と話していた。
だが、そんな中一人スマホをいじっていた女子高生がいた。ロングの黒髪を垂らしながらボーッと画面を見ている。
彼女はゲームやSNSをしているわけでもなく、意味もない操作を何となくやっていた。
彼女に構ってくれる友達が居ない訳では無い。彼女自身みんなと楽しく喋りたかった。だが、そんな気も失せる程彼女は心の中のモヤモヤに支配されていた。
「依奈〜。おはよう〜。」
「あっ、美苗。おはよ...」
依奈に声を掛けてきた、茶髪のロングヘアーで美人顔な人物、八栗 美苗。彼女の身体から漂う鼻が折れそうな香水の匂いは、まだ依奈は耐性が着いていなかった。
少し顔を顰め、それを誤魔化すようにスマホに目を移した。
「依奈って本当にスマホ依存症だよね〜。朝来たら絶対にスマホばっか見てるじゃん。」
「ははっ.....何か癖になっちゃってさ。スマホ見るの...」
「そういうのを依存症って言うんだよ〜。そんなんじゃ彼氏出来ても嫌われちゃうよ?」
「で、出来たことないから何とも言えないけど...」
高テンションの美苗に対して低リアクションの依奈。何故こんなにもテンションの差があるのかは依奈に問題があったのだ。
寄り添ってくれているのは分かるが、直感的に美苗とは距離を感じていた。
だがそれだけではなかった。依奈にはまだ慣れてないことがあった。直接目で見ることはほぼないが、心の中で締め付けられるような罪悪感で常に押し潰されそうになっている。
だから依奈は毎度、「しょうがない」「無理だ」といって言い聞かせ、少しでも楽になるようにする。こんな事を一ヶ月少しやっているが、段々負担が蓄積されてきているのか毎日気分が悪かった。
「ん?どうしたの?気分悪いの?」
美苗が心配そうに顔を覗き込むと、教室のドアが凄い勢いで開いた。
その音にビクッと教室内の生徒は身体をはね、視線を一斉にドアの方へ向ける。
ドアには制服をだらしなく着こなし、楽しそうに話している三人組の男子がいた。
その三人組の姿が目に映った瞬間、さっきまで賑やかだった教室はその三人組の声しか響かなかった。
「おう!デブ助!おはようさん!」
「あっ...お、おはよう....」
三人組の先頭にいた黒髪で高身長イケメンな男子が、ドアから一番近くで話していたポッチャりな男子に声をかける。
デブ助と呼ばれた男子生徒は出来るだけ目線を合わせないよう、下の方を見てモジモジしていた。
「おいデブ助、お前まぁ〜たこんなメンツとだべってたの?こんなオタク集団と話して何が楽しいんだ?」
イケメン男子は肩に手を回して、そう言った。デブ助はずっと下を見ていた。
そうすると金髪で髪を後ろに上げている男子生徒が、ケラケラ笑いながら話しかける。
「おいおい京吾。そのデブもオタクだろうがよ〜。オタクと話してんのはオタクだけなんだぜぇ〜?」
「え!?そうなの?お前オタクなの?きっしょ〜。」
そう二人にゲラゲラと笑われていたが、デブ助は下を見て、ははっと苦笑いだけをしていた。
そこで京吾はある事を思い出し、少し声のトーンを低くした。
「あっ、そういえばデブ助...今日は忘れてねぇよな?昨日忘れちゃったもんな?今日忘れてたら〜....次のターゲット先お前だけど...大丈夫か?」
その一言にデブ助はダラダラと汗を流し、震える手でポケットから財布を出して、一万円を差し出した。
「だ、大丈夫だから...ちゃ、ちゃんと持ってきたから...こ、これでいいでしょ?」
京吾はデブ助から一万円を取ると、ポケットの中にしまって更にトーンを低くして睨み付けた。
「あ?
"いいでしょ"だと?"いいですか"だろ!?クソデブが!!」
デブ助は顔を真っ青にして悟った。すぐに謝ろうとしたが遅く、謝罪より早く京吾からの拳が腹にめり込んだ。
拳は丁度鳩尾にめり込み、デブ助は腹を抱えながら椅子から転がり落ちた。
「うっ!...がっ....はぁ...」
「立場を弁えろや豚が!次倍にすんぞ!?」
「ご...ごめんなさい...ごめんなさい...」
京吾は舌打ちをし、オタク集団と罵られたグループの一人に声を掛けた。
「おい。アイツは?」
「え?へ?あ、あの...」
突然の事で硬直してしまったのか上手く喋れずにいると、京吾はその生徒の顔に拳を振りかざした。
椅子と机はその生徒一緒に倒れ、大きな音を奏でる。
この出来事を呆然と見ていたオタク集団のもう一人に、京吾は更に顔を険しくして聞いた。
「アイツは?もう来たのか?」
「あっ...き、来てないです....」
「チッ...またお迎えに行かねぇとダメじゃねぇか...めんどくせぇ〜。おい来希。これ何回目だっけ?」
そう聞くと、三人組のもう一人の茶髪の男子生徒がスマホを操作した。
「あぁ〜四回目...うん、四回目だわ。」
「特典は?」
「いつものやつ二セットと害虫の食事かな?ってかアイツ、後一回で泡吹くまで締め上げるやついくじゃん。」
「おっ、マジか〜。滅多に出来ねぇからな〜。楽しみだなぁ〜。
まぁ死んでも仕方が無いよな〜。うん、しょうがない。だって休んじゃったんだもん。」
そう言うと三人組は教室の一番後ろの席に移動して、さっきまでの事は無かったように楽しそうに話し始めた。
さっきの騒動は終わったはずなのに、教室内には緊張感が漂い、誰も喋ろうとはしなかった。
殴られたオタク集団は机や椅子を静かに戻していた。
これを見た教室内の生徒は誰も非難の声をあげない。あげられないのだ。
まるで暴漢の王に逆らえない村人のように、全員が身を小さくしている。
一年の頃はこの三人はそれ程大きな問題を起こすような事をしていなかった。学校自体大きく、クラスも多いので三人はバラバラだった。
だが、二年になってから科によって別れるため、三人は一緒のクラスになり、こんな騒動が起き始めた。
そのまま三人組が話すだけで時間は過ぎていき、教室に先生が現れた。
ハゲ気味の太った中年男性、案の定女子生徒からの批判は絶大な先生だ。
先生はいつもより暗い表情で、拳を握り締めているのが見えた。
さっきの騒動に先生の様子で教室内は重々しい雰囲気で満たされた。
「.......皆、聞いてくれ...朝のHR始める前に悲しい知らせがある...
うちのクラスの...佳川 章太が自宅で首吊り自殺で亡くなった....」
その言葉で一気にクラスはザワつく。全員が顔を真っ青にし、このクラスで唯一空席の机をチラチラ見た。
この先生の言葉にさっきの三人組の内二人は顔をポカーンとしていた。
特に金髪の男子生徒、清都は「まじかよ」と口パクで驚愕していた。
だが、京吾に関しては無表情で先生の話を腕を組んで聞いていた。
一方、依奈はというと机に顔を押し付け、両手で胸を抑えていた。
呼吸が荒くなり、心臓がちぎれる程の締め付け、足をガクガクと震わして死ぬ寸前のように感じた。
...."章ちゃん"が....?嘘....
先生は拳を更に強く握り、額に汗を垂らしながら三人組を睨み付ける。
「....お前らだろ?....お前らがあの子を追い詰めた....お前らが!」
先生の怒りの声に、来希と清都は圧倒された。だが、京吾は涼しんだ顔をして立ち上がる。
「先生〜。なんの事っすか?俺達はなぁ〜んにもしてない。証拠でもあるんすか?」
「なっ!あるに決まってるだろ!?今までお前達がしてきたこと!佳川以外にしてきたこと!証言なんていくらでも」
「じゃあなんですか?"俺達が章太と他の奴らをイジメていたのを黙って見てた"って警察に説明します?"見殺しにしてた"って。」
「そ、それは....」
京吾は先生に圧倒されるどころか、涼しんだ顔をしてニコニコしながら先生に近付き、肩にポンッと手を置く。
「あんただって見逃してたのバレたら不味いだろ?あんた達は証言だろうが、こっちにはあんたらが黙認してたっていう証拠の動画がある。
俺達三人組を少年院に送るのは別にいいけど、このクラス全員道連れ。もれなく特典で身内全員に素敵なプレゼント。この年齢だから刑務所じゃなくて少年院。すぐ出れる。
...どう考えたって黙ってた方が良くない?所詮他人じゃんか。」
京吾の言葉に先生は何も言えなかった。ギリギリと歯を食いしばるしか出来ていなかった。
「だから、な?知らなかったで通せばいいんだよ。少なくとも、あんただけ落ちても俺達を巻き込まなければ、身内には何も手を出さない。約束だ。」
「.......今から職員会議だ。自習してろ。」
そう言うと先生は逃げるように教室を後にした。
京吾はスタスタと元の席に戻り、圧倒されてた二人の手に肩を置いた。
「おいおいお前ら。大丈夫か?あんな事でビビんなって。余裕だよ余裕〜。」
「お、おう。やっぱすげぇな京吾は。な、来希?」
この作家の他の作品
表紙を見る
楽しい修学旅行になるはずだった。
クラス全員、前々から楽しみにしていた学校生活最大の想い出になるであろう修学旅行。
和気藹々としていたクラスメイト達が今では疑いの目をチラつかせている。
血の匂いが鼻を刺激し、恐怖に晒される。友達も、恋人さえも信じられないこの状況。
耐えられない...私には耐えられない....
人間の本性が見え隠れるするこの施設にはとても耐えられない。
恐怖、悲しみ、憎しみ、怒り、負の感情が空気中に漂い、私達を汚染する。
何を信じていいか私には分からない。
何で?...何でそんなことをするの?....
......信じてたのに!!
※ルール等更新しながら変更する場合がありますのでご了承ください。
※グロテスク要素がありますので、苦手な方は閲覧注意してください。
よろしかったら是非レビュー・カンタン感想の方をよろしくお願いします!!
表紙を見る
ここはとてもいい村だ
自然豊かで空気が気持ちよく、ご飯もとても美味しい
外から来た私達を村全体で温かく歓迎してくれる
村人一人一人が優しくて、困った時は全員で手を貸してくれる
何一つ不自由を感じさせない村
幸せになれる村
だけど私はそんな幸せは望んでいない
あの仮面だけはつけたくない
表紙を見る
恋は色んな感情を呼び寄せる
想い人に会える楽しさや嬉しさ
一緒にいれない悲しさや切なさ
もしかしたら嫌われているかもしれないという恐ろしさや不安
他の異性と話しているだけで沸き起こる嫉妬や苛立ち、そして憎しみ
それらを制御するのは難しい。人は欲から出てくる感情を制御するのは抗えない。
これらの数多の感情の中、"狂気"が出てきたのなら
狂気に支配された恋する人はどうなってしまうのか
その道の辿り着く先を想像するのはそう難しくないだろう
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…