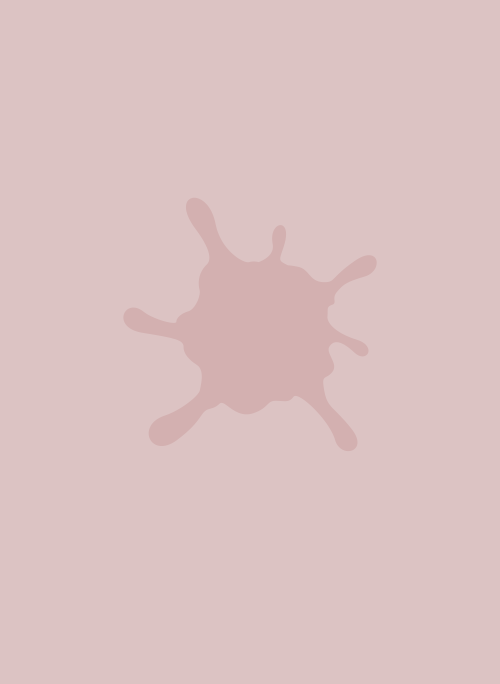「う...うう....うううううううぅぅぅぅ!!....」
章太は依奈の言おうとしたことを察していた。自分も同じ気持ちだから、章太は分かった。
そしてその言葉を聞いた時、章太は依奈の側から離れることが出来なくなると確信した。自分が今一番聞きたい言葉を聞くことを、愛する者の為に拒んだ。
それは依奈自身も感じていた。章太の行動の意味を察していた。だからこそ悲しかった。
声は届くのに自分の気持ちを伝えられない、近いようで遥かに遠いその距離感。
依奈は自分のワガママを通せないと感じた。ここまで覚悟を決めた章太の意志を無下にすることは出来ないと。
「....グスン...もう....章ちゃんのバカ....」
依奈は透明な涙を流しながら精一杯の笑顔を章太に向けると、章太の顔に自分の顔を近付け、抱き締めながら唇を合わした。
自然と身体はポカポカと温かくなり、章太の体温を唇からだけではなく、身体全体で感じていた。
章太は目を見開いていたが、キスを噛みしめるかのように、目を瞑り抱き返した。
たった数秒だが、依奈と章太は幸福感で満ちていた。二人は身体ではなく、心ではなく、魂が合わさっていくような感覚になった。
依奈は唇をそっと離し、章太を見つめた。
「....見ててよ。章ちゃんよりずっといい男を掴まえて、絶対に幸せになるから。
あの世で後悔しても、もう遅いんだからね。」
章太は押し殺していた自分の感情が少しだけ漏れた。依奈の笑顔と言葉で、絶対に目の前ではしないと封印していた鍵が解かれた。
章太は涙を流しながら、依奈に笑い返した。
「あはは...残念だなぁ〜....僕、嫉妬しちゃうよ....」
二人はお互い笑いながら、切なそうに見詰めていた。だが、言葉はもう交わさなかった。交わさなくても全て分かっているから。
章太は片手を顔付近まで上げて、掌を向けながら左右にゆっくりと振った。
「....じゃあねちぃちゃん。また今度。」
「うん。じゃあね章ちゃん。」
依奈が振り返すと、章太はカクンと頭を下げた。章太の身体が善子のように、光の玉となって分裂していく。そしてそれは依奈の目の前を通り過ぎ、上の方へと消えていった。
光の玉が消えていくと、そこには頭を下げている静華の姿があった。
静華は目を開くと、章太が流していた涙を拭いた。
「終わったよ...静華。全部....全部終わった。」
「そう....そうね。章太君のオーラはもうない。本当に逝ってしまったのね。」
「うん。でも、章ちゃんと会話出来て....本当に良かった。ありがとう、静華。」
静華は小さく頷くと深呼吸をした。そして、なぜだかまるで小馬鹿にしているかのように口角を上げた。
「それにしても依奈って大胆だったのね。キスしちゃうなんて...」
「え!?え?嘘でしょ!?え?全部知ってたの?...」
顔がトマトのように真っ赤になり、頭からマグマが出そうになるくらい暑くなった。
「あなたの一生懸命章太君を引き留めようと泣いてたのも全部知ってるわよ〜。あんなに必死になっちゃって、羨ましいわ〜。」
「ちょ!そういう事なら事前に説明を」
「いいじゃない。結局思い切って話せたんだし。それにしても、章太君に訂正しなくていいの?いい男じゃなくて....いい女を掴まえるって」
「や、やめてよ!!恥ずかしいじゃん!!もう!!」
依奈が頬を膨らませると、静華はプッと笑いをこぼし、涙を流すくらいに笑った。
「ちょ、何笑ってんの!?」
「だってあなた...頬を膨らませると....本当に梅干しみたいで....あはははは」
「ちょ...もう、やめてよ....プッ....全くもう....」
静華の笑い声につられて依奈も笑った。依奈は心の底から笑った。
章太を見捨ててから冷たく凍ってしまっていた依奈の心は、多くの歳月と苦難によって解けていった、
レンガ色で覆われている建物から、二人の男が外へ出た。陽の光が世界を照らし、中庭にある植物や虫が生き生きとしていた。
二人の男はその光を目で遮りながら、中庭を歩いていた。
「いやぁ〜マジで講義クソだるいわ....あんなの人間が理解しようにも無理だって....」
「いや、本当にそれは同感だわ。あんなのもし理解出来たとしても絶対に社会じゃ使わないって。」
「だよな?そんなのは入社した会社でやれってぇんだ。」
金髪の男と茶髪の男はそんな愚痴を垂らしながら大広場へと歩いていく。
ここはマンモス校の大学。至る所に人がいて、出入り口に接している大広場には沢山の人がいる。
友達と話していたり、サークルの勧誘をやっている人、カップルがイチャつく所を見るのは普段通りの日常。
だが、その大広場の隅では普段通りでは見かけることもないのを見つけ、二人は愚痴を吐くのをやめて監視していた。
それは一人の女性に向かって男性が握手を求めながらお辞儀をしていた。男はラフな格好と言ってしまえば収まるが、女性の方は白いロングスカートで黒いシャツ。シンプルだが清楚な印象に金髪は少し見惚れた。
告白なのは一目瞭然。二人の男はニヤニヤしながら気付かれないように近付いた。
「お願いします!俺と付き合って下さい!」
男性がそう言うと、女性は嬉しそうな表情を見せるも、少し言いづらそうな顔をした。後ろに束ねている髪を揺らし、綺麗な色をした唇を人差し指で触りながら、空を見上げながら「あー」っと小さく声を漏らしていた。
心が決まったのか、その女性は男性と握手をすることはなく、頭を下げ返した。
「ごめん!今藤君とは付き合えない。」
今藤はガッカリした表情を見せながら頭をあげる。今藤は二人の目から見ても中々にイケている男だったため、二人は目を見開いた。
「えぇ?....マジか....な、なんでなのかな?理由だけでも教えてくれない?俺のどこが悪かった?」
「あっ、いや...別に悪いことはないんだけど....なんて言うのかな...」
告白された女性は手をパタパタさせながら困り果てていると、今藤は目に涙を浮かべながら唾を飲み込んだ。
「...もしかして...俺以外に好きなやつが...」
「あっ....えっと....」
返答に困っている女性を見て、今藤は涙を流しながら走り去って行った。女性は引き留めようと手を伸ばすが、後を追わないで小さくため息を吐いた。
その状況を見ていた男二人はニヤニヤしていた。他人の不幸は蜜の味とはまさにこの事だった。
「うわ〜フラれちゃったよあいつ....辛いだろうな〜」
「まぁそうだろうな〜。俺だったらもう一週間は立ち直れねぇ。」
「だよな。だけど、俺だったらすぐ立ち直っちゃうかな〜。だってあんなに可愛い人だぜ?釣り合わないって妥協するわ〜。俺、ちょっとアタックしようかな?」
金髪がヘラヘラしながら言うと、茶髪は首を横へ振った。
「やめとけお前。あいつのこと知らないのか?」
「あ?何だよ?なんかあんの?」
「千澤 依奈。そいつと同じ高校卒業のやつに聞いたんだけどよ、なんでもいじめっ子に反抗したりしてたんだけど、そのいじめっ子が死んじまったんだとよ。
そしたらなんだ?その姿に惚れたとか抜かして何人かに告白されたけど付き合わず、大学にきても告白はされるもののやっぱり付き合わないんだとよ。」
「なんじゃそりゃ。でも、あいつがフリーだから告白してるんだろ?もしかしてレズ?」
「本人は否定してるそうだが、実際どうだかな。もしレズじゃなかったら単に男が苦手か好きな人でもいんじゃねぇの?」
「好きな人の線はないだろ。告白されたのがいつからなのかは知らないけど、一・二年経ってる。あんな美人なのに好きな人と付き合えないのはねぇだろ?
男が苦手なパターンで決定だな。」
男二人はその場から離れて、校舎の方へと戻って行った。
依奈は今の話は全て聞こえており、フッと鼻で笑いながら空を見上げた。
だが、清々しい顔とは裏腹に依奈の内心は荒れていた。
ああああああああ!!付き合えないぃぃぃぃ!!告白されてるから付き合えない訳では無いけど、無理だァァァァ!!
依奈は大きなため息を吐くと、近くのベンチに座り込み、頭を抱えた。
章ちゃんに宣言してから三年...チャンスはいっぱいある....だけど、どうしても章ちゃんの顔が思い出して踏み出せない!あんなに堂々と言ったくせに進歩がないのはどういうことよ私!
「はぁ〜言えないよね〜。三年前に死んじゃった男の子が忘れられないって...
重いよね〜....絶対に重い女って思われる...
空の上の章ちゃんも絶対に苦笑いだって....」
心の声がポロポロと言葉になって出てきて、依奈は自問自答を繰り返していた。
ふと、腕時計の時刻を見て依奈は焦った。
「うわ!やば!もうこんな時間!?急がなきゃ!」
依奈はすぐに立ち上がり、大学を後にした。
走る事二十分、依奈は喫茶店に入店した。荒い息を整えながら店内をジックリ見回すと、四人席で座っている女性が依奈をジッと見ていた。
長い髪の毛にキラキラと光るピアスをぶら下げ、紺色のニットを着用していた。例えるなら大人の女性、色気があって女でも見惚れてしまうような女性は依奈に向かって手招きをした。
依奈はその女性の元へ駆け寄り、正面に座ると鞄を隣の椅子に置いて、女性の目の前で両手を合した。
「ごめん静華、ちょっと遅れちゃった。」
「そうね、約束より十分の遅刻。この珈琲を飲み終わる前に来てくれて良かったわ。」
「いや...本当にごめん....ちょっと野暮用が...」
静華は少し困った顔を作った依奈を見逃さず、顔を覗かせながらニヤニヤしていた。
「当ててあげましょうか?あなた、誰かに告白されてたわね?」
「え?なんで分かるの!?」
「分かるわよ。あなたって本当に正直だもの。それにこんなことも分かる。告白されたけど、章太君の事を忘れられずにふったでしょ?もう手に取るように分かるわ。」
依奈はしょんぼりとして、静華が用意してくれていた珈琲を片手で持ってズズっと啜って飲んだ。すると、静華はあからさまに咳をして、依奈はムスッとしながら両手に持ち替え、音を出さないようにして飲んだ。
「全く....モテるような仕草を教えてあげた私の苦労が無駄じゃない。どうするつもりよ?このままだと未来永劫に章太を引きずって、誰とも付き合えず孤独死よ?」
「うっ...何も言い返せないです....」
「それに仕草もこう簡単に解けちゃうとはね...ダメよ?どんな時でもそういうことしなきゃ。」
「でも、こんな時くらいよくない?毎回毎回気を使ってると頭が痛くなってくる....」
「身体が覚えるまでは我慢しなさい。それに、こういう時でも目を光らせてる男はいるのよ?ほら、あそこのテーブルの男達を見てみなさいよ。」
静華に言われて、斜め後ろのテーブルから見ていた三人の男を見た。目があわさった瞬間、三人はあからさまに目線を外し、携帯をいじっていた。
「.......あれは静華目当てじゃないの?私は静華に比べたら全然だし。」
「何言ってるのよ。自信を持たないとやっていけないのよ?私の方が遥かに美人だとしても、負けん気でいかなくちゃ。」
「静華....自分で言ってて恥ずかしくないの?」
「全く恥ずかしくないわ。自分を認めないとダメよ?人の感じでそれ相応の行動パターンが決まってくるのよ。地味目の子は控えめな行動しながら接触すればいいだろうし、逆にイケイケな子は積極的に動けばいい。
あなたも自分を評価してみなさい?まぁ、それ以前の問題を直してからけど。」
静華は依奈を言葉でボコボコにすると、珈琲を一口飲む。依奈は笑いで誤魔化しながら、心のダメージに耐えていた。
「ねぇ静華、静華の大学どう?結構偏差値高いよね?」
「まぁね。でも、ついていけそうだから単位を落とすことはあんまりないと思うわ。」
「そっかぁ〜。私なんて静華よりレベルは低いのに全然ついてけないよ〜...やっぱり私立卒と公立卒じゃあ頭の作りが違うよねぇ〜。」
「そんな言い訳する暇あったら勉強するか、自分を磨くことに集中しなさいよ。章太君に笑われるのは確定ね。」
依奈は何も言えず黙っていると、あることに気がついて、少し声量を落とした。
この作家の他の作品
表紙を見る
楽しい修学旅行になるはずだった。
クラス全員、前々から楽しみにしていた学校生活最大の想い出になるであろう修学旅行。
和気藹々としていたクラスメイト達が今では疑いの目をチラつかせている。
血の匂いが鼻を刺激し、恐怖に晒される。友達も、恋人さえも信じられないこの状況。
耐えられない...私には耐えられない....
人間の本性が見え隠れるするこの施設にはとても耐えられない。
恐怖、悲しみ、憎しみ、怒り、負の感情が空気中に漂い、私達を汚染する。
何を信じていいか私には分からない。
何で?...何でそんなことをするの?....
......信じてたのに!!
※ルール等更新しながら変更する場合がありますのでご了承ください。
※グロテスク要素がありますので、苦手な方は閲覧注意してください。
よろしかったら是非レビュー・カンタン感想の方をよろしくお願いします!!
表紙を見る
ここはとてもいい村だ
自然豊かで空気が気持ちよく、ご飯もとても美味しい
外から来た私達を村全体で温かく歓迎してくれる
村人一人一人が優しくて、困った時は全員で手を貸してくれる
何一つ不自由を感じさせない村
幸せになれる村
だけど私はそんな幸せは望んでいない
あの仮面だけはつけたくない
表紙を見る
恋は色んな感情を呼び寄せる
想い人に会える楽しさや嬉しさ
一緒にいれない悲しさや切なさ
もしかしたら嫌われているかもしれないという恐ろしさや不安
他の異性と話しているだけで沸き起こる嫉妬や苛立ち、そして憎しみ
それらを制御するのは難しい。人は欲から出てくる感情を制御するのは抗えない。
これらの数多の感情の中、"狂気"が出てきたのなら
狂気に支配された恋する人はどうなってしまうのか
その道の辿り着く先を想像するのはそう難しくないだろう
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…