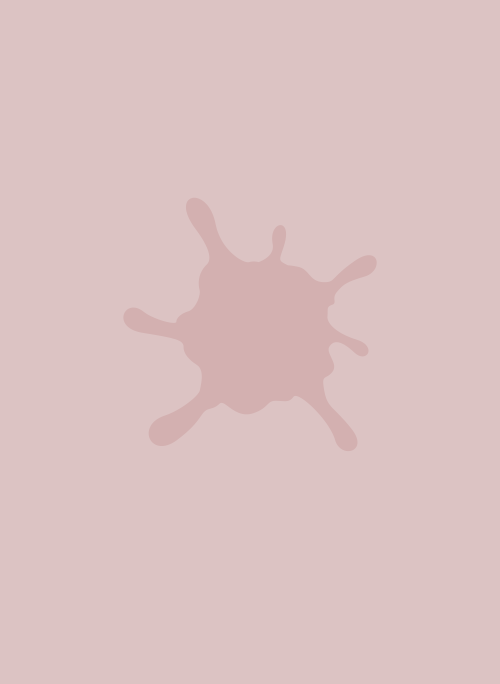日がゆっくりと沈み空はオレンジ色に染まっていく。それは次第に町にも染めわたり、真っ白の障子や草木、ボロボロの電柱もみるみると空と同じ色になっていく。
そんな中、公園で小さい男の子数人が楽しそうにはしゃいでいた。
子供が元気に遊んでいる、とても微笑ましい状況、子供の笑い声は世の中の平和の象徴にも思える。そういう風に思わせられる力がある。
たが、その子供達の笑いは効果と全く反対のことを指していた。
三人の男の子は自分達より一回り小さい男の子を囲んで、あらゆる方向から蹴りをくらわしていた。
「おい!"へにょへにょ章太"!なんで学校に来るんだよ。お前みたいな気持ち悪い奴が学校来てんじゃねぇよ!」
「そうだそうだ!悔しかったら殴り返してみろよ〜。まっ、そんなこと出来ないだろうけどね〜。」
その一言で三人はまた笑う。先程より高く楽しく、空に向かって笑った。
土埃だらけの少年は、乾いた土に涙を零しながら弱々しく蹲っていた。
立ち向かう気力は感じられず、背中を丸めて小さくなっていく。消える寸前の灯火、少年の心はズタボロだった。
「お前みたいな弱くて気持ち悪いやつはさっさと死ねばいいんだよ〜。だ〜れも悲しまないからさっさと死んじゃえば?」
「そうだよ!さっさと死んじゃえ!し〜ね!し〜ね!し〜ね!し〜ね!」
拍手と共に延々と続くように思われる残酷すぎるコール。少年のボロボロの心に、また深く言葉の攻撃が突き刺さる。
ボロボロと大粒の涙を流し、我慢していた泣き声も徐々に溢れてくる。
その様子を見て三人は手を休めるどころか、もっと声を大きくする。その三人の子供にとって少年は、生き物ではなく玩具として見えていたに違いなかった。
「うぅ....ぅぅぅ...」
「あはは!こいつ泣いてやんの!だっせぇ〜。」
「泣くくらいならさっさと死ねばいいじゃん!よし!もう一回やろうぜ。せーのっ!し〜」
再び悪魔のコールが開始されようとした瞬間、ある人物が飛び出し、掛け声をかけようとした男の子に体当たりする。
男の子はよたよたとバランスを崩したが、体勢を立て直して自分に当たってきた人物に目線を合わせる。
そこにいたのは一人の少女。可愛らしいピンクの服装に髪型はポニーテール。だが、ランドセルを片手で肩に乗せ、三人に引けを取らない睨み付きは正に男の子の様だった。
「あんた達!何やってんの!!」
「お前、"ゴリラ女"!!ゴリラに殺されるぞ〜!逃げろ〜!!」
三人は面白がるようにしてその場を去っていく。
その三人の楽しそうに逃げる後ろ姿を見てため息を吐くと、持っていたランドセルを地面に置いて少年の身体を起こした。
「"章ちゃん"...大丈夫?」
「"ちぃちゃん"....ぐすん...ありがとう。助けてくれて...」
少年は次々に溢れてくる涙を砂埃の袖で拭くが、涙は止まらず両目をずっとごしごしと拭いていた。
少女は砂埃の少年の背中を叩き、砂埃を落としていた。
「あいつら...許せない!明日一緒に先生に報告しよ?」
「ちぃちゃん。僕...大丈夫だから...そんな事したらお母さん悲しむし、迷惑掛けちゃうから...」
「でも章ちゃん。このままだったらずっとイジメられちゃうんだよ?いいの?」
少し落ち着いたのか、少年は拭くのを止め、首を横に振った。
「良くないけど、とにかく言わないで欲しいんだ。...僕、頑張るから。」
すぐに壊れそうな作り笑顔を少年は作った。それを見て少女は自分も泣きそうな顔をして、それを誤魔化すように少年を立たせた。
「だ、だけど章ちゃん。章ちゃんはなんでやり返さないの?あんなやつら、全員ぶっ飛ばしちゃえばいいのに。」
「そんなこと出来ないよ....僕、力も無いし運動も出来ない。僕よりおっきくて強い三人に勝てるわけないよ...」
「そんなのやって見ないと分かんないじゃん!それなら私も...」
「それに!...僕...」
少女の言葉を遮ってまで出た少年の答え。その優しすぎるが故に出てくる弱々しい回答。
これを聞いた少女は少年という人間を改めて認識したのだった。
笑い声が飛び交い、朝日が眩しく照らせる賑やかな教室。男子は馬鹿な事をして遊び、女子は友達と話していた。
だが、そんな中一人スマホをいじっていた女子高生がいた。ロングの黒髪を垂らしながらボーッと画面を見ている。
彼女はゲームやSNSをしているわけでもなく、意味もない操作を何となくやっていた。
彼女に構ってくれる友達が居ない訳では無い。彼女自身みんなと楽しく喋りたかった。だが、そんな気も失せる程彼女は心の中のモヤモヤに支配されていた。
「依奈〜。おはよう〜。」
「あっ、美苗。おはよ...」
依奈に声を掛けてきた、茶髪のロングヘアーで美人顔な人物、八栗 美苗。彼女の身体から漂う鼻が折れそうな香水の匂いは、まだ依奈は耐性が着いていなかった。
少し顔を顰め、それを誤魔化すようにスマホに目を移した。
「依奈って本当にスマホ依存症だよね〜。朝来たら絶対にスマホばっか見てるじゃん。」
「ははっ.....何か癖になっちゃってさ。スマホ見るの...」
「そういうのを依存症って言うんだよ〜。そんなんじゃ彼氏出来ても嫌われちゃうよ?」
「で、出来たことないから何とも言えないけど...」
高テンションの美苗に対して低リアクションの依奈。何故こんなにもテンションの差があるのかは依奈に問題があったのだ。
寄り添ってくれているのは分かるが、直感的に美苗とは距離を感じていた。
だがそれだけではなかった。依奈にはまだ慣れてないことがあった。直接目で見ることはほぼないが、心の中で締め付けられるような罪悪感で常に押し潰されそうになっている。
だから依奈は毎度、「しょうがない」「無理だ」といって言い聞かせ、少しでも楽になるようにする。こんな事を一ヶ月少しやっているが、段々負担が蓄積されてきているのか毎日気分が悪かった。
「ん?どうしたの?気分悪いの?」
美苗が心配そうに顔を覗き込むと、教室のドアが凄い勢いで開いた。
その音にビクッと教室内の生徒は身体をはね、視線を一斉にドアの方へ向ける。
ドアには制服をだらしなく着こなし、楽しそうに話している三人組の男子がいた。
その三人組の姿が目に映った瞬間、さっきまで賑やかだった教室はその三人組の声しか響かなかった。
「おう!デブ助!おはようさん!」
「あっ...お、おはよう....」
三人組の先頭にいた黒髪で高身長イケメンな男子が、ドアから一番近くで話していたポッチャりな男子に声をかける。
デブ助と呼ばれた男子生徒は出来るだけ目線を合わせないよう、下の方を見てモジモジしていた。