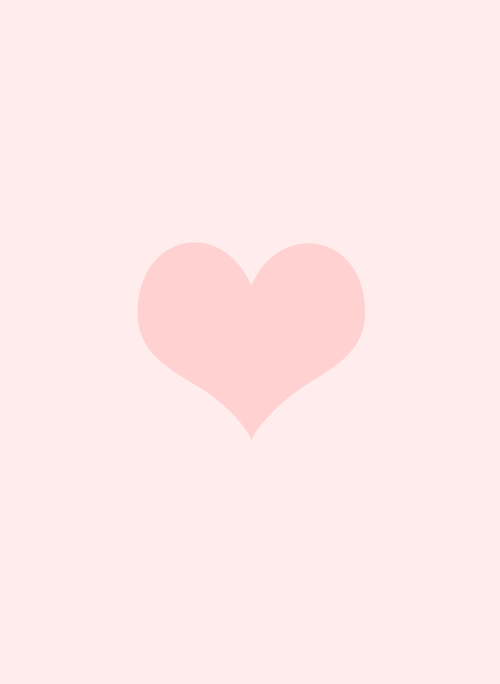しかし彼女は、そんなあなたに臆することなく、スムーズに答えたのです。
「最終目的は、自宅に帰りたいんです。下沢というバス停から町に出ると、屋代という駅があります。そこからさらに二回くらい乗り換えると、地元に戻れるはずなんです。でも携帯の電源が切れていて、手持ちのお金もありません。コンビニのATMでお金をおろして、タクシーに乗ったら、下沢へ行けます。携帯用充電器も買いたいんです」
あなたは少し呆気にとられましたが、そこはさすが、簡単に相手のペースには飲まれません。冷たい眼差しのまま、彼女に返しました。
「町へ行くバスの始発は、休日は昼の十二時ですよ。あと、先のコンビニはローカルのものなのでATMがあるかは分かりませんし、さらに屋代駅からの電車は二時間に一本しかありません」
あなたは問題を提起するばかりなので、彼女は乏しい知識で解決策を考えねばなりませんでした。正解が出せそうにないと分かっているので、黙り込み、しかしあなたに助けを求めようとはしません。あなたもあなたで、解決策を提示したらそれに手を貸さなければならない気がして、言い出さないのでしょう。
そのとき、一台だけ、このオープンカーの横をミントカラーの軽自動車が追い越していきました。乗っていたのはおそらく女性です。この時間にここを走る車は、もうないでしょう。
彼女は数秒、その車を目で追います。ええ、そちらの車に乗せてもらったほうが、彼女にとって良かったはずです。
「まあ……解決策は、いくつかありますが」
あなたは責任を感じたのでしょう。ヒッチハイクを無視していれば、先ほどのミントカラーの車が、彼女を助けたのかもしれませんから。
拾ってしまったのだから、最後まで面倒を見なければならない、あなたは自分が彼女を助ける理由を得たので、やっと本気になりました。
理由を探していたあなたには、ちょうど良かった。
「最終目的は、自宅に帰りたいんです。下沢というバス停から町に出ると、屋代という駅があります。そこからさらに二回くらい乗り換えると、地元に戻れるはずなんです。でも携帯の電源が切れていて、手持ちのお金もありません。コンビニのATMでお金をおろして、タクシーに乗ったら、下沢へ行けます。携帯用充電器も買いたいんです」
あなたは少し呆気にとられましたが、そこはさすが、簡単に相手のペースには飲まれません。冷たい眼差しのまま、彼女に返しました。
「町へ行くバスの始発は、休日は昼の十二時ですよ。あと、先のコンビニはローカルのものなのでATMがあるかは分かりませんし、さらに屋代駅からの電車は二時間に一本しかありません」
あなたは問題を提起するばかりなので、彼女は乏しい知識で解決策を考えねばなりませんでした。正解が出せそうにないと分かっているので、黙り込み、しかしあなたに助けを求めようとはしません。あなたもあなたで、解決策を提示したらそれに手を貸さなければならない気がして、言い出さないのでしょう。
そのとき、一台だけ、このオープンカーの横をミントカラーの軽自動車が追い越していきました。乗っていたのはおそらく女性です。この時間にここを走る車は、もうないでしょう。
彼女は数秒、その車を目で追います。ええ、そちらの車に乗せてもらったほうが、彼女にとって良かったはずです。
「まあ……解決策は、いくつかありますが」
あなたは責任を感じたのでしょう。ヒッチハイクを無視していれば、先ほどのミントカラーの車が、彼女を助けたのかもしれませんから。
拾ってしまったのだから、最後まで面倒を見なければならない、あなたは自分が彼女を助ける理由を得たので、やっと本気になりました。
理由を探していたあなたには、ちょうど良かった。
「本当ですか?どんな?」
「住宅地の中に入れば朝六時からやっているATMがあります。そこで金をおろして、駅へ行く。そこまでなら付き合えます」
「いいんですか?」
あなたは携帯を取り出し、片手で電車のアプリをタップします。少し近づいて覗きこむ彼女からは、濃い潮の香りがしましたが、ここ一帯の匂いと混じっているので、気にはなりませんでした。
「ただ、電車の時間があるのか微妙ですね。自宅の最寄り駅はどこですか」
「屋代から……色々乗って、最寄りの立川まで帰りたいんです」
あなたの手が止まります。アプリに駅名を入力している途中でしたが、あなたは画面を消しました。
「それって、東京の立川」
「はい」
携帯をしまい、エンジンをかけます。プランを決めたあなたの様子に、彼女は怪訝そうでした。
「……なら、このまま、俺の車で立川まで帰るって方法もあります」
「え?」
あなたはハザードランプを消し、後方を確認すると、思い切りハンドルを切りました。運転は昔から上手です。あなたの運転中の冷静さ、丁寧さは、オープンカーを乗りまわす男としては珍しいものです。
ハンドルを三回転させてからアクセルを踏み、彼女の体を揺らさず、しかし素早く、何もない車線でUターンをしてみせました。そのまま戻り車線に沿って、来たときと同じように綺麗な走行を始めるのです。
「え、あの、立川までって、どういうことですか?ここから二時間くらいかかると思うんですけど」
「俺も立川から来たんです。もう帰ろうとしていたところなので、かまいません」
「え、え……」
「住宅地の中に入れば朝六時からやっているATMがあります。そこで金をおろして、駅へ行く。そこまでなら付き合えます」
「いいんですか?」
あなたは携帯を取り出し、片手で電車のアプリをタップします。少し近づいて覗きこむ彼女からは、濃い潮の香りがしましたが、ここ一帯の匂いと混じっているので、気にはなりませんでした。
「ただ、電車の時間があるのか微妙ですね。自宅の最寄り駅はどこですか」
「屋代から……色々乗って、最寄りの立川まで帰りたいんです」
あなたの手が止まります。アプリに駅名を入力している途中でしたが、あなたは画面を消しました。
「それって、東京の立川」
「はい」
携帯をしまい、エンジンをかけます。プランを決めたあなたの様子に、彼女は怪訝そうでした。
「……なら、このまま、俺の車で立川まで帰るって方法もあります」
「え?」
あなたはハザードランプを消し、後方を確認すると、思い切りハンドルを切りました。運転は昔から上手です。あなたの運転中の冷静さ、丁寧さは、オープンカーを乗りまわす男としては珍しいものです。
ハンドルを三回転させてからアクセルを踏み、彼女の体を揺らさず、しかし素早く、何もない車線でUターンをしてみせました。そのまま戻り車線に沿って、来たときと同じように綺麗な走行を始めるのです。
「え、あの、立川までって、どういうことですか?ここから二時間くらいかかると思うんですけど」
「俺も立川から来たんです。もう帰ろうとしていたところなので、かまいません」
「え、え……」
あなたは彼女が遠慮しようと、もう立川まで乗せて帰る決心をしていました。彼女にとってあなたの案が一番良いに決まっていますし、Uターンを終えた今では、住宅地のATMへ寄ってから駅へ向かう方があなたも手間だからです。
むしろ、躊躇されることが面倒だから、先にUターンをしたのでしょう。
彼女はまだ自分の身なりの汚さを気にしていました。隣のあなたは潔癖そうに見えますし、実際のところ潔癖です。先ほどから携帯電話の画面を逐一拭きますし、運転席と助手席の間にあるドリンクホルダーには、埃ひとつ、手垢ひとつ付いていません。
しかし、あなたは、彼女のことを、汚いといって嫌ってはいないはずです。あなたが嫌うのは、あなたが潔癖であることに気付かず、悪意なく汚していく人間ですから。
あなたにとって重要なのは、現在の身なりを綺麗にしているかどうかではなく、雑菌と自分の体との距離感を意識できているかどうかなので、シートと素肌の間にハンカチを敷いた彼女なら、それができていると判断できました。
「立川まで……本当に、いいんですか?」
「色々と寄って駅へ送り届けるより、俺はその方が楽です」
「すみません。では……お願いします」
「はい」
早朝の海辺をドライブする趣味を続けて三年、あなたはこのコースの最中に、初めて女性を乗せました。そしてふたりとも不本意な顔をしていますが、朝陽はのぼり、風は爽やかに吹いています。
あなたと彼女の奇妙なドライブが始まったのです。
むしろ、躊躇されることが面倒だから、先にUターンをしたのでしょう。
彼女はまだ自分の身なりの汚さを気にしていました。隣のあなたは潔癖そうに見えますし、実際のところ潔癖です。先ほどから携帯電話の画面を逐一拭きますし、運転席と助手席の間にあるドリンクホルダーには、埃ひとつ、手垢ひとつ付いていません。
しかし、あなたは、彼女のことを、汚いといって嫌ってはいないはずです。あなたが嫌うのは、あなたが潔癖であることに気付かず、悪意なく汚していく人間ですから。
あなたにとって重要なのは、現在の身なりを綺麗にしているかどうかではなく、雑菌と自分の体との距離感を意識できているかどうかなので、シートと素肌の間にハンカチを敷いた彼女なら、それができていると判断できました。
「立川まで……本当に、いいんですか?」
「色々と寄って駅へ送り届けるより、俺はその方が楽です」
「すみません。では……お願いします」
「はい」
早朝の海辺をドライブする趣味を続けて三年、あなたはこのコースの最中に、初めて女性を乗せました。そしてふたりとも不本意な顔をしていますが、朝陽はのぼり、風は爽やかに吹いています。
あなたと彼女の奇妙なドライブが始まったのです。
*******
秋になりかけた季節、早朝は冷たい風が吹くようになりました。彼女は疲れきって寒さを感じていないようですが、あなたは一応、声をかけました。
「寒ければ、座席の裏にブランケットが入っているので出せますが、大丈夫ですか」
「ありがとうございます。大丈夫です」
彼女が断ってくれて、ホッとしたでしょう。貸せば膝掛けが砂だらけになります。
彼女の荷物は、コンパクトなボストンバッグと、小さなハンドバッグで、どちらもシートの上には置かず、土足の足元に並べていました。
「携帯の機種、なんですか」
あなたの質問は突然でした。
「機種、ですか……?なんだっけ……なんとかセブン……」
「グローブボックス開けてもらえますか。鍵穴はついていますが、鍵は閉まっていないので」
次にあなたは、彼女に収納の取っ手を引くよう目線で示します。すると彼女は「はい」と返事をして、素直にそこを開けました。
そこには黒い革のカバーに入った車検証やサングラス、カーナビの説明書などが綺麗なパズルのように収納されています。
「そこに赤い充電器とアダプターが入っていますから、ソケットに差して使ってください」
ジッパーのついた小袋に入ったそれらを彼女はすぐに発見しました。小さい機材に戸惑う様子はなく、使い勝手も分かっているようです。
「すみません……使わせていただきます」
彼女は器用に一度でソケットに差し込み、ハンドバッグから携帯電話を取り出すと、そこへアダプターを繋ぎます。真っ暗だった画面は息を吹き返し、白く光り出しました。
秋になりかけた季節、早朝は冷たい風が吹くようになりました。彼女は疲れきって寒さを感じていないようですが、あなたは一応、声をかけました。
「寒ければ、座席の裏にブランケットが入っているので出せますが、大丈夫ですか」
「ありがとうございます。大丈夫です」
彼女が断ってくれて、ホッとしたでしょう。貸せば膝掛けが砂だらけになります。
彼女の荷物は、コンパクトなボストンバッグと、小さなハンドバッグで、どちらもシートの上には置かず、土足の足元に並べていました。
「携帯の機種、なんですか」
あなたの質問は突然でした。
「機種、ですか……?なんだっけ……なんとかセブン……」
「グローブボックス開けてもらえますか。鍵穴はついていますが、鍵は閉まっていないので」
次にあなたは、彼女に収納の取っ手を引くよう目線で示します。すると彼女は「はい」と返事をして、素直にそこを開けました。
そこには黒い革のカバーに入った車検証やサングラス、カーナビの説明書などが綺麗なパズルのように収納されています。
「そこに赤い充電器とアダプターが入っていますから、ソケットに差して使ってください」
ジッパーのついた小袋に入ったそれらを彼女はすぐに発見しました。小さい機材に戸惑う様子はなく、使い勝手も分かっているようです。
「すみません……使わせていただきます」
彼女は器用に一度でソケットに差し込み、ハンドバッグから携帯電話を取り出すと、そこへアダプターを繋ぎます。真っ暗だった画面は息を吹き返し、白く光り出しました。
充電のメーターが三十パーセントに回復するまで、彼女は海を見て呆けていました。
あなたは仕事以外で人と話すことは大嫌いですから、都合が良かったでしょう。しかし、これから二時間彼女を乗せて黙っているには、彼女に謎が多すぎました。だからでしょうか、珍しくあなたから、会話を始めたのです。
「ここへは、何をしに?」
彼女は大きな瞳をあなたに向けました。おそらく、彼女のほうは、それほど人と話すことが嫌いではないはずです。あなたが話しかけたことで、かすかに笑顔になりました。
あなたは仕事以外で人と話すことは大嫌いですから、都合が良かったでしょう。しかし、これから二時間彼女を乗せて黙っているには、彼女に謎が多すぎました。だからでしょうか、珍しくあなたから、会話を始めたのです。
「ここへは、何をしに?」
彼女は大きな瞳をあなたに向けました。おそらく、彼女のほうは、それほど人と話すことが嫌いではないはずです。あなたが話しかけたことで、かすかに笑顔になりました。
「勝間が母の故郷なので、見に来たんです。昨日一日いて、バス停がある下沢に行くところだったんですけど、タクシーになぜかこの海岸に連れてこられてしまって……。寝ていた私も悪いのですが、戻るほどの手持ちがなくて、とりあえず降りて、さ迷っていたんです。お恥ずかしい……」
「ああ、たしかに町にも下沢というバス停がありますが、この海岸自体を下沢海岸とも言うんですよ」
「そうなんですか?知りませんでした」
「ドラマのロケ地だったそうですよ。若い人が見る恋愛物の。ですから、タクシーを使って下沢へ行きたい、という人は、ここへ来る人が圧倒的に多いでしょうね」
「それでタクシーの運転手さんは勘違いをしたんですね。良かった、騙されたんじゃなくて……」
あなたはピンときていないようです。
騙されたか騙されていないかは関係なく、目的地とは違う場所に来た結果は変わりませんから。
「こちらがご実家ということではないんですか」
実家というわりには、土地勘がなさすぎると、あなたは不思議に思っていました。母の故郷、というのは、どういった場所なのか、あなたは自分にそのような場所があるか思いを巡らしましたが、思い付きませんでした。
それか、知らないだけかもしれません。
「母が高校生まで暮らしていた場所なんです。今はゆかりはなくて、母の実家も別の場所にあります」
「へぇ、そこへ、今回はひとりで」
「はい。一人旅です。なんて言うんでしょうか……巡礼、ですかね」
「あー」
察しのいいあなたは、すぐに、彼女の母親は遠くない過去に亡くなったのだと理解しました。
しかしそれには言及しませんし、顔色も変えません。
「ああ、たしかに町にも下沢というバス停がありますが、この海岸自体を下沢海岸とも言うんですよ」
「そうなんですか?知りませんでした」
「ドラマのロケ地だったそうですよ。若い人が見る恋愛物の。ですから、タクシーを使って下沢へ行きたい、という人は、ここへ来る人が圧倒的に多いでしょうね」
「それでタクシーの運転手さんは勘違いをしたんですね。良かった、騙されたんじゃなくて……」
あなたはピンときていないようです。
騙されたか騙されていないかは関係なく、目的地とは違う場所に来た結果は変わりませんから。
「こちらがご実家ということではないんですか」
実家というわりには、土地勘がなさすぎると、あなたは不思議に思っていました。母の故郷、というのは、どういった場所なのか、あなたは自分にそのような場所があるか思いを巡らしましたが、思い付きませんでした。
それか、知らないだけかもしれません。
「母が高校生まで暮らしていた場所なんです。今はゆかりはなくて、母の実家も別の場所にあります」
「へぇ、そこへ、今回はひとりで」
「はい。一人旅です。なんて言うんでしょうか……巡礼、ですかね」
「あー」
察しのいいあなたは、すぐに、彼女の母親は遠くない過去に亡くなったのだと理解しました。
しかしそれには言及しませんし、顔色も変えません。
話は一旦区切れました。
そこから沈黙しても良かったのですが、あなたは頭が良いので、彼女の疑問だらけの話を流すことができません。
「さ迷っていた、というのは、どれくらいのことですか」
「え……」
「今は朝ですから、昨夜は宿をとっていないんですよね。海岸へ来たのは昨日の話で……それで、一晩歩いていた、と」
「そうなんですよね。恥ずかしい……本当に、何やってるんだか、ですよね……」
「別にそうは思いませんが、まあ、大変だったんですね」
嘘です。何をやってるんだか、そう顔に出ていましたよ。
彼女にもバレています。
あなたは女というものを神経の少ない生き物だと思っていますが、それは間違いです。あなたの前では神経の少ないふりをしなければ身が持たないから、彼女たちはそうするのですよ。
気付いていないのは、あなただけです。
彼女も同じく、神経を減らして、無愛想なあなたに合わせています。しかし、あなたが今まで付き合ってきた女性たちよりは、彼女は本当に神経の数が少ないのかもしれません。
あなたが何を言っても、顔を歪めませんから。
「あの……私は藍川(あいかわ)と申します。お名前を聞いてもいいですか?」
名前を聞いた彼女に嫌な気はしませんでした。
あなたもちょうど、名前を知らないままでは会話がしにくいと思っていたところでしたから、彼女もそれを感じてのことだと分かったのです。
「ああ、はい。碓氷(うすい)です」
「字は何て書くんですか?」
「“氷”を使う碓氷です。説明しにくいんですが……」
「あ、“碓氷峠”の碓氷ですか?」
あなたは久しく碓氷峠を思い出しました。
「ああ、それです。……よく知ってますね」
「行ったことがあります」
仕事で自分の漢字を説明するのに、今後は碓氷峠を使おう、あなたはそう思いつきましたが、もしかしたら彼女のようには伝わらないかも、とも思い直しました。
そこから沈黙しても良かったのですが、あなたは頭が良いので、彼女の疑問だらけの話を流すことができません。
「さ迷っていた、というのは、どれくらいのことですか」
「え……」
「今は朝ですから、昨夜は宿をとっていないんですよね。海岸へ来たのは昨日の話で……それで、一晩歩いていた、と」
「そうなんですよね。恥ずかしい……本当に、何やってるんだか、ですよね……」
「別にそうは思いませんが、まあ、大変だったんですね」
嘘です。何をやってるんだか、そう顔に出ていましたよ。
彼女にもバレています。
あなたは女というものを神経の少ない生き物だと思っていますが、それは間違いです。あなたの前では神経の少ないふりをしなければ身が持たないから、彼女たちはそうするのですよ。
気付いていないのは、あなただけです。
彼女も同じく、神経を減らして、無愛想なあなたに合わせています。しかし、あなたが今まで付き合ってきた女性たちよりは、彼女は本当に神経の数が少ないのかもしれません。
あなたが何を言っても、顔を歪めませんから。
「あの……私は藍川(あいかわ)と申します。お名前を聞いてもいいですか?」
名前を聞いた彼女に嫌な気はしませんでした。
あなたもちょうど、名前を知らないままでは会話がしにくいと思っていたところでしたから、彼女もそれを感じてのことだと分かったのです。
「ああ、はい。碓氷(うすい)です」
「字は何て書くんですか?」
「“氷”を使う碓氷です。説明しにくいんですが……」
「あ、“碓氷峠”の碓氷ですか?」
あなたは久しく碓氷峠を思い出しました。
「ああ、それです。……よく知ってますね」
「行ったことがあります」
仕事で自分の漢字を説明するのに、今後は碓氷峠を使おう、あなたはそう思いつきましたが、もしかしたら彼女のようには伝わらないかも、とも思い直しました。
「私も、読みは普通なんですが、漢字は珍しいかもしれません。藍色の“藍”です」
「あー、草冠の……」
「はい。“青は藍より出でて藍より青し”の」
「噛まずに言えましたね」
「ふふ、こういう話になるたびに使っていますから。意味もご存知ですか?」
「弟子が師匠を上回る、って話ですね」
「そうです」
あなたは仕事でも、プライベートでも、意味のない自己紹介を嫌います。今後使う必要のない情報を仕入れることが苦痛なのです。それも、興味のあるふりをしなければならないことが、特に。
彼女としているのはその意味のない自己紹介に違いありませんが、あなたは苦痛には思いませんでした。
彼女の使うどこかで聞いたけれど忘れていた言葉は、まるでスパイスのようだったのです。
「碓氷さんは、どうしてここへ?」
あなたへの質問の順序も適切でした。
「俺は休日、いつもここへ運転しに来ます。三時に立川を出て、まあ、ありがちですが、朝陽を見に来るんでしょうね」
「ストレス発散、ですか?」
「発散できているつもりはないですが、三年もやめられないんですから、そういうことなのかもしれません」
「あー、草冠の……」
「はい。“青は藍より出でて藍より青し”の」
「噛まずに言えましたね」
「ふふ、こういう話になるたびに使っていますから。意味もご存知ですか?」
「弟子が師匠を上回る、って話ですね」
「そうです」
あなたは仕事でも、プライベートでも、意味のない自己紹介を嫌います。今後使う必要のない情報を仕入れることが苦痛なのです。それも、興味のあるふりをしなければならないことが、特に。
彼女としているのはその意味のない自己紹介に違いありませんが、あなたは苦痛には思いませんでした。
彼女の使うどこかで聞いたけれど忘れていた言葉は、まるでスパイスのようだったのです。
「碓氷さんは、どうしてここへ?」
あなたへの質問の順序も適切でした。
「俺は休日、いつもここへ運転しに来ます。三時に立川を出て、まあ、ありがちですが、朝陽を見に来るんでしょうね」
「ストレス発散、ですか?」
「発散できているつもりはないですが、三年もやめられないんですから、そういうことなのかもしれません」
彼女は頷き、そこでまた会話は途切れました。
それから五分ほど走ったところで、彼女はもう一度あなたに声を掛けました。
「碓氷さん、あの」
「はい」
「すみません。先に見えている自動販売機で停まってもらってもいいですか?喉が乾いてしまって……」
彼女が指をさした先には、左側に車を寄せるスペースがあり、そこには三台の自動販売機が向かい合って立っています。
「ああ、すみません、気づきませんでした。寄りましょうか。それか、そろそろATMもあるコンビニがありますので、他に必要なものがあればそちらにも行けますが」
「あ、良いですね。コンビニの方に寄りたいです」
「わかりました」
「……コンビニで着替えたら怒ります?」
「は?」
あなたはハンドルに右手を乗せたまま、不可思議なことを言う助手席の彼女を見ました。彼女はこれから怒られる子どものように肩をすぼめています。
女性が子どもっぽく振る舞うことに対しては全くそそらないあなたは、眉を寄せました。
「……着替えはあるんですか」
「はい。一応、海に入るかもしれないと思って、ジャージを持ってきてるんです……。でも、着替える場所がなくて……」
「まあ、いいですけど……」
あなたは何人かの女性と細切れな付き合いをしてきましたが、自分の前でジャージになる女性など見たことがないでしょう。
週に二回通っている会員制のフィットネス・ジムでも、そこの女性たちが着ているのは“ジャージ”ではなく洗練された“スポーツウェア”のはずです。
そもそも、あなたと一晩一緒にいるとしても、女性たちはジャージ姿になって気を抜くことなどなかったのでしょうから、彼女にこれからジャージ姿になると宣言されて、あなたは正直“引いている”のです。
それから五分ほど走ったところで、彼女はもう一度あなたに声を掛けました。
「碓氷さん、あの」
「はい」
「すみません。先に見えている自動販売機で停まってもらってもいいですか?喉が乾いてしまって……」
彼女が指をさした先には、左側に車を寄せるスペースがあり、そこには三台の自動販売機が向かい合って立っています。
「ああ、すみません、気づきませんでした。寄りましょうか。それか、そろそろATMもあるコンビニがありますので、他に必要なものがあればそちらにも行けますが」
「あ、良いですね。コンビニの方に寄りたいです」
「わかりました」
「……コンビニで着替えたら怒ります?」
「は?」
あなたはハンドルに右手を乗せたまま、不可思議なことを言う助手席の彼女を見ました。彼女はこれから怒られる子どものように肩をすぼめています。
女性が子どもっぽく振る舞うことに対しては全くそそらないあなたは、眉を寄せました。
「……着替えはあるんですか」
「はい。一応、海に入るかもしれないと思って、ジャージを持ってきてるんです……。でも、着替える場所がなくて……」
「まあ、いいですけど……」
あなたは何人かの女性と細切れな付き合いをしてきましたが、自分の前でジャージになる女性など見たことがないでしょう。
週に二回通っている会員制のフィットネス・ジムでも、そこの女性たちが着ているのは“ジャージ”ではなく洗練された“スポーツウェア”のはずです。
そもそも、あなたと一晩一緒にいるとしても、女性たちはジャージ姿になって気を抜くことなどなかったのでしょうから、彼女にこれからジャージ姿になると宣言されて、あなたは正直“引いている”のです。
この作家の他の作品
表紙を見る
──これからどんな人が現れても、今夜一緒にいてくれたあなたには、もう誰も敵わない──
雪永光莉(25)は大学時代、
人気者の先輩・檜山水樹が実は不遇な生い立ちで劣悪な暮らしをしていると偶然知ってしまい、秘密の関係となる。
しかし、家庭の事情により光莉が大学中退を余儀なくされ、彼を遠ざけて関係は終わった。
それから、五年。
幸せとは程遠い空っぽの毎日を送る光莉の前に、再び水樹が現れる。
彼は名字が変わり、なぜか大企業の御曹司になっていた。
◇重く切ないダークラブストーリー◇
2020.10 完結
*godisdora様、結城ひなた様、みやのもり様、マイマイ。様、海月三五様、素敵なレビューをありがとうございました!*
表紙を見る
※前作『恋するオフィスの禁止事項』を読んでからお楽しみください
ふたりの出会い、エピソード・ゼロ編!
桐谷先輩が恋に落ちるまでを、
桐谷先輩の目線で。
2017.11 完結
*みなの。様、素敵なレビューをありがとうございました!*
表紙を見る
2020.08
マカロン文庫より書籍化しました。応援して下さった皆様、ありがとうございました。
書籍には本編後のストーリーを収録しておりますので、是非ご覧下さい。
◇◇◇◇◇
デザイン事務所「株式会社K.Works」
秘書として働く【有村 莉央(27)】は、社長兼デザイナーの【都筑 京(28)】に振り回される毎日を送っていた。
憧れる気持ちがありつつも、もう限界。
気持ちに区切りをつけ、この恋をおしまいにしたのに……
「俺に断りもなく恋愛していいわけないだろ」
突然、独占欲をむき出しにしてきて……!?
2020.04 完結
*すう!!様、聖凪砂様、みやのもり様、素敵なレビューをありがとうございました*
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…