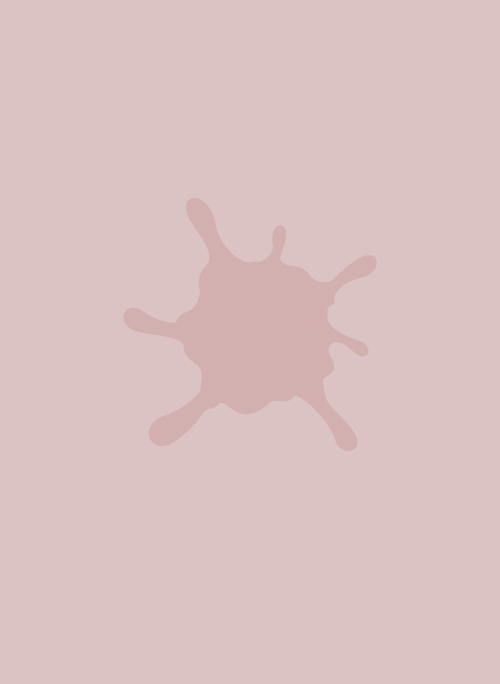「四方さん、今日は本当にありがとうございました」
ひと気のない自動販売機の前で、わたしは深々と頭を下げた。
「いやあ、そんな、ぼくなんて、なんにもしてないですし」
四方はちょっと疲れたような顔に、いつもの笑みをたやさず、パタパタと手を横にふる。
「そんなことはありあません。四方さんがいなかったら今ごろはどうなっていたか」
それはわたしの偽らざる気持ちだった。
「いやあ、照れちゃうな。なんか飲みましょうよ。なんにします?」
四方が小銭を出そうとするのを、わたしは制した。
「それで、あの」
言いづらくて、一瞬、口ごもってしまった。
でも、今のうちに、今のうちだからこそ言わなければ、と思った。
今日は本当に四方という男を見なおした。これからも仕事の上でいろいろ助けを借りたい。だからこそ、昼間のプロポーズの件で尾を引きたくなかった。
「四方さん、昼間の、その……プロポーズのことなんですが」
「あっ、はいっ」
「あの、わたし、とっても嬉しかったんです。こんなわたしに結婚を申しこんでいただけるなんて」
と、一応、心にもない前口上を述べる。
もちろん続けて、ありがたいお話ではあるのですがお断りさせていただきたいと思います、と言うつもりだった。