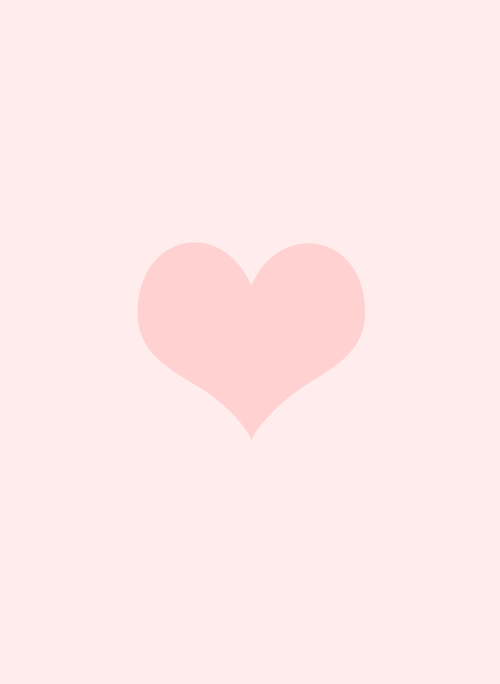なんて男なんだろう、なんて人と付き合っていたのだろう。と、最近私は再びそう思うようになった。
その理由は至って単純なものである。
去年の今頃、私の隣には恋人と呼べる人間が居たからだ。
“恋は盲目”という言葉通り、付き合っていた当時は彼が世界で一番素敵な異性に見え、彼が私の世界の中心だった。
去年のこの時期は、いつもよりも奮発した豪華なデートを計画していた記憶がある。
お洒落なホテルで食事だとか、プチ旅行だとか、ペアリングだとか。
なんて、そんな事をこの時期に思い出したのは、やはり独り身が寂しいからだろうか。
クリスマスイブを直前に控えた今日は、街のどこを歩いても恋人だらけだ。
その中をトボトボと歩く私は、人々から見ればさぞ寂しい人間だろう。
この煌びやかな街の中を歩く人間には似つかわしくない気持ちが芽生える。
幸せそうに笑う恋人、笑い合う家族とすれ違う度に、私の心が灰白に染まっていく気がしてならない。
ちらほらと降り始めた雪のように、積もっても、いつかは融けて消えるものだけれど。
ふと立ち止まり、空を見上げればいつの間にか暗くなっていた。
昼間の白い冬空は何処(いずこ)へ消え、真っ暗な空に星を散りばめている。
真ん丸に輝く月が、目の前にある巨大なクリスマスツリーのライトアップに負け、なんだか寂しげだった。
(…帰ろう)
独身の女がひとり、こんな場所で立ち尽くしていても虚しくなるだけだ。
早く家に帰って、温かいお風呂に浸かって、お気に入りの毛布に包まって眠ろう。
恋人がいなくたって、いいじゃないか。
男なんて、私とは真逆な人間である、可愛くて素直で従順な女の子ならば誰でも良いのでしょう。
私には彼しかいなかったけれど、彼にはたくさんの人がいる。
振り向けば羨望の眼差しを送る女がたくさんいるのだ。
彼を必要とする人は、私を含めてたくさんいるのだ。
この広い世界で、私を必要とする人はもういない。
このちっぽけな存在が消えようとも、誰も気にしはしない。気付きもしないのだ。
降り積もっていく雪のように、遊ばれ、退かされて終わる人生なのだ、私は。
冷たい空気に晒していた手をポケットに突っ込み、マフラーに顔を埋めた。
肩に乗った雪を落とし、クリスマスツリーに背を向ける。
12月24日は、聖なる夜だ。私はこの場から退散し、独り寂しい夜を送ろう。
これ幸いに、部屋にあるカレンダーは23日のままだ。
このまま捲らずに新年を迎え、新しいカレンダーを買えばいい。
そうすれば、私の中からクリスマスというものが消える。そう信じて。
私は足先を自宅の方角へ向け、深い吐息をこぼしながら歩き始めた。
ーーーその時、
「………な…」
人混みの中から、誰かの声が鮮明に聞こえた。
何て言っていたのかは分からないけれど、私の名前を呼んでいないことは確実だ。
普段の私なら気にも留めないのに、一体どうしたのだろうか。
「……帰ろう」
今度こそ、と。 そう胸の内で呟き、歩き出そうとしたが、またもその声は聞こえる。
「……ひいな…」
今度ははっきりと聞こえた。“ひいな” と。
私は何かに導かれたかのように、その場から走り出した。
ーーーふと聞こえた声が紡いだ名は、私の名前ではないけれど。
滴る雫のように降った声音は、私の耳に焼き付いて消えない。
人混みの中をひた走り、あの声の主の元へ。
私は正気だろうか。呼ばれたわけでもないのに、何かに引き寄せられるかのように走って。
向かった先で何をするのかなんて分からない。
何のために向かっているのかさえ分からない。
ただひたすらに走り、声の主の元へと向かう。
「……っ、居たっ…」
私に向けられている好奇心に満ちた眼差しなんて気にも留めずに、肩で息をしながらその存在を見つめる。
私と同じく、ひとりきりで。
煌々と輝くクリスマスツリーの前に、彼は居た。
私の胸の奥から、高鳴る鼓動が聞こえている。
緊張に酷く似ている気がするが、それとは少し違う感情が芽生えた。
話し掛けるつもりはない。声の主がどんな人なのかなんて興味もない。
ただ、その背中を一目見てみたいと思っただけなのだ。
背中に突き刺さる視線に気がついたのか、彼は此方を振り向いた。
視線が交わった瞬間に、私と彼だけこの世界から切り離された場所に飛ばされたかのような錯覚がする。
周りの景色も、冷たい空気も、体温を奪う雪も何も変わっていないけれど。
ただ、その存在に惹かれてやまない。
吸い寄せられるように、彼のことを見つめてしまう。
「……なに?」
端正な顔立ち。まるで人形のようだ。
彼の綺麗な眉が不快に歪む。
「…えっと」
可笑しいな。私は話しかけていないのに。
ただ、見つめていただけなのに。
「見てたでしょ、俺のこと」
そう言われて、私は言葉を失った。
彼は呆れたように肩を落とすと、溜息を吐いた。
私は何を言えば良いのか分からず、視線を泳がせる。
自分が何のために、何をするためにここに来たのかが分からなくなってしまった。
だって、透明な糸のような何かに繋がれていたようなものだったから。
「…すみません」
慌ててその場を後にしようと、体を反転させたのだが。
容赦無く冷たい温度が、私を引き止めるように捕らえた。
「貴女は誰?…まだ質問の答えを貰ってないんだけど」
芸術品のように綺麗な顔が、私の目の前にある。
息の仕方を忘れそうになるくらいに綺麗過ぎて、私は目を逸らした。
こんなに綺麗な男性が世界には居るのだ。
私から彼を奪ったあの女の子が世界の何処かから現れたように。
「ただの通行人です。…ツリーの前に佇む貴方が、綺麗だったので…つい」
嘘は言っていない。全てが本当かと訊かれたら、首を横に振るが。
彼は気のない返事をすると、ポケットに手を突っ込んだ。
「…じゃあ、通行人さん。これから予定はあるの?」
「生憎、寂しいクリスマスを過ごす予定です」
吐き捨てるように言えば、彼は戯けたように笑った。
くるりと私の方を向くと、柔らかく目を細める。
「じゃあさ、今日だけ俺に付き合ってよ」
何を言い出すのかと思いきや、お誘い?
パチパチと瞠目すれば、彼は渇いた笑みをこぼした。