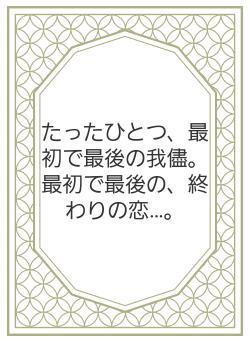だから、俺は彼女をいつものように隣に抱き寄せると、意を決してから一呼吸置いて、耳元に囁いた。
「愛してるよ…りん。付き合って欲しい、ちゃんと」
その途端、サッと引かれた身。
驚いたような顔をして、瞳を見開いた彼女からは、まるで見たこともないモノを見た、という恐怖が垣間見れた。
「……どうして……?」
暫くの沈黙の後で、彼女はか細い声でそう訴えてきた。
彼女は泣くのを必死で我慢していた。
薄っすらと浮かぶ、透明な液体。
それが溢れる前に、俺は告げる。
「傍に、いて欲しいんだ」
可笑しいくらいに、喉元に引っ掛かってしまった言葉。
すると彼女は、真正面から俺を捉え、俺のシャツに両手を掛けた。
少しだけ力を込めて…。
「私、『奥さん』にはなれないんだよ?私は私でしかないの。それでも…私なんかでいいの……?」
その言葉で、あぁなんて自分は勝手な私憤の中で生きてきて、彼女を『此処』に置き去りにしたままだったんだろうと、恥じた。
きっと、ずっと俺から送られない言葉に、悩んで来たに違いない。
それは、苦しそうに歪められた彼女の表情から伺えた。
だから、俺はもう一度だけ彼女のシャツに絡められた手を取ってから、彼女を見つめた。
「りんじゃないとだめなんだ。りんがいいよ」