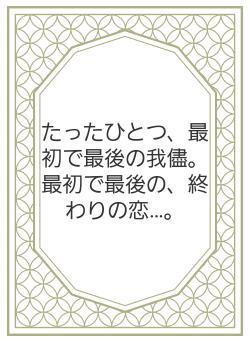そこからお互いに、けして告白なんてしないままの状態で…少しずつ…ほんの少しずつ軽めのボディタッチは増えてゆき…抱き締め合ったりキスをするような関係に発展するのに、さほど時間は掛からなかった。
彼女は拒まない。
そう、どこかで願っていたのかもしれない。
自分の中の腹黒い物が、そう、思わせていたのかもしれない。
「りん…」
想いを出来るだけ込めてそう呼べば、彼女は泣くような顔をしていて、俺の名前を繰り返す。
「りゅうさん…熱い…」
それでも一線を越えないでいるのは、自分が彼女よりも断然余裕があるから、というわけじゃなく…更には彼女にそう言った魅力がないわけでもなくて…。
ただ、越えてしまったら、後はどうなるんだろう?という焦りだけが胸の中に、渦を巻いていたからだ。
欲しい。
全部欲しい。
願うのに、堰き止めてしまうんだ。
突き上げられる熱情を…。
捻じ曲げて、ジリジリと焦がして…年甲斐もなく地団駄を踏み鳴らす。
「好き…だけじゃな…」
ぽつりと呟いた。
そんな陳腐な言葉だけじゃ、足らなかった。
二人の世界はそんなものだけでは広がらない。
それなのに、自分の視界に入り込んで離れない、彼女の肌に触れたくて堪らない。