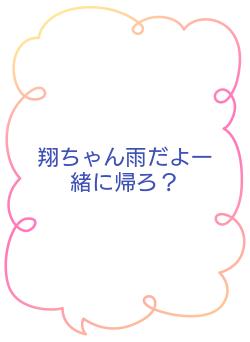悠君は泣き虫だったよね。
生まれも育ちもニューヨークってだけで、生意気だなんていじめられることも多かった。
2月、学校にやってくる節分の鬼を怖がって、いつも私の後ろに隠れてた。
豆を投げて退治するのは私の係で、悠君は鬼が退散してもまだ泣いてる。
「大丈夫、もうやっつけたよ!」
フンフンと、戦いのあとで私は鼻息荒め。
悠君のキャラメル色のふわふわな髪
よしよししてあげなくちゃ。
そしたら、涙に濡れた目でじっと私を見つめて
悠君は言ったの。
「さらちゃんがいなくなったら、ぼくどうしたらいいの?」
だから私は胸を張って言ったのだ。
「さらはずっとここにいるよ!」
って。
「じゃあけっこんしてくれるってこと?」
「まぁ、それもあり」
「ぼくのことずっとまもってくれる?」
「まかせといてっ!」
当時7歳だったけど、私と悠君は結婚を誓いあった仲。
子供の口約束だもん。
だから悠君はそんなこと覚えてないはず。
ずっとそう思っていた。
生まれも育ちもニューヨークってだけで、生意気だなんていじめられることも多かった。
2月、学校にやってくる節分の鬼を怖がって、いつも私の後ろに隠れてた。
豆を投げて退治するのは私の係で、悠君は鬼が退散してもまだ泣いてる。
「大丈夫、もうやっつけたよ!」
フンフンと、戦いのあとで私は鼻息荒め。
悠君のキャラメル色のふわふわな髪
よしよししてあげなくちゃ。
そしたら、涙に濡れた目でじっと私を見つめて
悠君は言ったの。
「さらちゃんがいなくなったら、ぼくどうしたらいいの?」
だから私は胸を張って言ったのだ。
「さらはずっとここにいるよ!」
って。
「じゃあけっこんしてくれるってこと?」
「まぁ、それもあり」
「ぼくのことずっとまもってくれる?」
「まかせといてっ!」
当時7歳だったけど、私と悠君は結婚を誓いあった仲。
子供の口約束だもん。
だから悠君はそんなこと覚えてないはず。
ずっとそう思っていた。