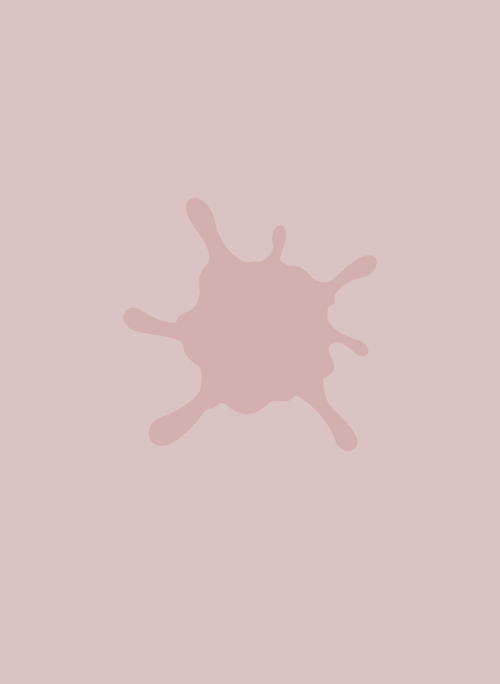怪訝そうに、御崎は眉間に皺をよせていた。
きゅっ、と胸が苦しくなる。
いきなりクラスメートの出現。
急いでいるのに足止めをくらう。
そりゃあ誰でも嫌な気持ちになるだろう。
「明日、なんでもいうこと聞くから! だから、だからお願い! 今日だけでいい!」
だけど、ごめんね。
わたしだって御崎のことを助けようと必死なんだ。
だから、今日だけ、わたしのいうことを聞いて。
声を張り上げて、御崎に訴えた。
わたしに明日なんてないのだけど、だから約束なんてできないのだけど。
「しっかたねえなぁ」
もう駄目かもしれないと諦めかけた矢先、御崎の優しそうな声が降ってきた。
驚いて顔を上げると、呆れたような笑顔を浮かべた御崎がいた。
「そんな必死な顔でお願いされちゃ、俺も断れないぜ?」
「う、うん」
「特に見たかった映画じゃないし、後で友達に電話かけとくわ。でも、約束だからな。明日、俺のいうこと聞くんだぞ」
わたし、御崎を救えた?
あの笑顔を、守れた?
御崎の命を、繋ぎとめることができた?
「別のルートで映画館行くとかなしだからね。本当に家に帰るんだよ」
「分かってる、分かってるって」
「本当? 約束だよ?」
何度も何度も確認するしつこいわたしに呆れたのだろうか。
御崎は分かってるよと適当に言って、ゆっくりと立ち上がった。
「俺はお前のいうこときいて、大人しく家に帰る。だからお前も、ちょっと休んだらすぐに家に帰るんだぞ」
そんな優しい言葉にうんと頷く。
普段通りの御崎に少しどぎまぎしながら控え目に手を振ってみると、御崎もこちらを振り向いて手を振ってくれた。
去っていく背中を見つめていると、急に力が抜けた。
安心したからだろうか、今度はどっと疲れが出て、わたしは電信柱に寄り掛かった。
まるで電源が抜けてしまったロボットのように、わたしはその場に崩れ落ち、完全に電信柱に体を預けた。
腕の時計を確認すると、長針は十一を指していた。
確かわたしが起きたのは八時で、それから満足に朝食も食べずに御崎の家へ向かった。
そして御崎も十分もかからずに見つけられた。
たぶん、一時間くらいしか動いてなかっただろう。
ということは、わたし二時間も寝ていたんだ!
「うわあ、あと少ししか時間はないっていうのに! 緊張感なさすぎだよわたし!」
周りに誰もいないのをいいことに、わたしはそう叫びながら、地面から飛び起きた。
だけどコンクリートの上で寝ていたからか、体の節々がずきずきと痛んだ。
自業自得だと溜め息をつく。
慌てふためき混乱する自分の頭を、幾回か叩き落ち着かせる。
そしてゆっくりとあの男の言った言葉を思い出した。
〔あなたが存在できるのは正午まで〕
すなわち、あと一時間でわたしは消えてしまうというのだ。
あと一時間。六十分。三千六百秒。
短い。短すぎる。
混乱して、脳の中の細い糸が絡まっていくのを感じた。
確かわたしが起きたのは八時で、それから満足に朝食も食べずに御崎の家へ向かった。
そして御崎も十分もかからずに見つけられた。
たぶん、一時間くらいしか動いてなかっただろう。
ということは、わたし二時間も寝ていたんだ!
「うわあ、あと少ししか時間はないっていうのに! 緊張感なさすぎだよわたし!」
周りに誰もいないのをいいことに、わたしはそう叫びながら、地面から飛び起きた。
だけどコンクリートの上で寝ていたからか、体の節々がずきずきと痛んだ。
自業自得だと溜め息をつく。
慌てふためき混乱する自分の頭を、幾回か叩き落ち着かせる。
そしてゆっくりとあの男の言った言葉を思い出した。
〔あなたが存在できるのは正午まで〕
すなわち、あと一時間でわたしは消えてしまうというのだ。
あと一時間。六十分。三千六百秒。
短い。短すぎる。
混乱して、脳の中の細い糸が絡まっていくのを感じた。
あ……御崎。
御崎は、ちゃんと家に帰ったかな。
だけど御崎の存在を思い出しただけで、雁字搦めになっていた糸はすんなりと解けた。
胸の中を清々しい風が吹いているような感覚に見舞われる。
御崎が無事なら、怖くない。
こんなわたしでも御崎の役に立てたと、嬉しくなるから。
もう死ぬとしても、消えてしまうとしても、すっきりとした気持ちで逝ける。
「……わたしは、大丈夫」
怖くないし、寂しくない。
御崎を失うよりも、心は軽い。
「全然、平気」
呪文のようにそう呟いて。
かちかちに固まってしまった足を一歩ずつ動かす。
体育のせいでなってしまった筋肉痛の痛みと、コンクリートの上で寝たせいでなった痛みが重なり合い、体がぎしぎしときしんだ。
死ねば、この痛みも消えるのだろうか。
そんなことを考えながら、わたしは足を踏み出した。
しばらく歩いていると、心もすっかり落ち着き、恐怖などといった感情も消え失せていた。
照り付ける太陽。
人で賑わう商店街。
遠慮がちに肩を寄せ合うカップル。
玩具を強請る子供とそれに困り果てる親。
ぎこちない態度でいらっしゃいませというデパートの定員。
全てが普段通りで、それが優しくて。
わたしのマイナスな感情は、日曜日を満喫している人のプラスの感情に照らされ、蒸発してしまったかのように。
だからわたしも前を行く人たちの話に耳を傾けたり、商店街の本屋で雑誌を立ち読みしたりと、普段と変わらないことをした。
だけどもう終わり。
こんな優しい光景を見ていられるのは、今日で終わり。
だから周りの景色を目に焼き付けておこうと思った。
「……もう終わり、ねえ。」
だけどあまり実感がわかない。
もうすぐで消滅――つまり死ぬといわれても、ピンとこなかった。
照り付ける太陽。
人で賑わう商店街。
遠慮がちに肩を寄せ合うカップル。
玩具を強請る子供とそれに困り果てる親。
ぎこちない態度でいらっしゃいませというデパートの定員。
全てが普段通りで、それが優しくて。
わたしのマイナスな感情は、日曜日を満喫している人のプラスの感情に照らされ、蒸発してしまったかのように。
だからわたしも前を行く人たちの話に耳を傾けたり、商店街の本屋で雑誌を立ち読みしたりと、普段と変わらないことをした。
だけどもう終わり。
こんな優しい光景を見ていられるのは、今日で終わり。
だから周りの景色を目に焼き付けておこうと思った。
「……もう終わり、ねえ。」
だけどあまり実感がわかない。
もうすぐで消滅――つまり死ぬといわれても、ピンとこなかった。
不思議な気分でなおも街をぶたぶたしていると、耳に小さな機械音が届いた。
最初は自分の腕時計からした音だなんて気付かなく、一体どこからこの音は、なんてきょろきょろしていた。
そういえば、昨日十二時にアラームをセットしたんだっけ。
この時計は、予定の時間の三十分前になると鳴るんだったなぁ。
……あと三十分なんだ。
思わず足が止まる。
死ぬという実感はなかったけど、そのことは知っていた。
だから、やっぱり、少しだけ怖くなったのだ。
思考を振り飛ばそうと周りの景色に目をやる。
すると、なぜだかその風景に見覚えがある。
「あ、ここは……」
三十分前と同じ場所。
自分の行動がおかしくって、思わず笑いが漏れた。
ここは御崎と最後に喋った場所。
やっぱりわたしは御崎のことが好きなんだなぁと思い知らされた。
再び電信柱に寄り掛かる。
電信柱に頬を寄せると、ひんやりとしていて心地よい。
ゆっくりと目を閉じると、まぶたの裏で御崎が笑っていた。
いつも、いつでも、目を伏せればすぐそこに御崎がいた。
御崎はわたしのすべてで、大袈裟にいえばわたしの世界を支配していた人だった。
わたしが今彼に望むこと。
今彼に思うこと。
それは、告白したいとかそういう後悔じゃなくて。
ていうかもう告白なんてどうでもいいから。
もっと生きて。
そんなシンプルなものだ。
わたしのものにしたいとかそういう醜い独占欲なんてどっか飛んでいってしまった。
一番大切なのは、彼が笑っているということ。
生きていることを幸せだと思い、毎日が楽しいと笑っていること。
最初は自分の腕時計からした音だなんて気付かなく、一体どこからこの音は、なんてきょろきょろしていた。
そういえば、昨日十二時にアラームをセットしたんだっけ。
この時計は、予定の時間の三十分前になると鳴るんだったなぁ。
……あと三十分なんだ。
思わず足が止まる。
死ぬという実感はなかったけど、そのことは知っていた。
だから、やっぱり、少しだけ怖くなったのだ。
思考を振り飛ばそうと周りの景色に目をやる。
すると、なぜだかその風景に見覚えがある。
「あ、ここは……」
三十分前と同じ場所。
自分の行動がおかしくって、思わず笑いが漏れた。
ここは御崎と最後に喋った場所。
やっぱりわたしは御崎のことが好きなんだなぁと思い知らされた。
再び電信柱に寄り掛かる。
電信柱に頬を寄せると、ひんやりとしていて心地よい。
ゆっくりと目を閉じると、まぶたの裏で御崎が笑っていた。
いつも、いつでも、目を伏せればすぐそこに御崎がいた。
御崎はわたしのすべてで、大袈裟にいえばわたしの世界を支配していた人だった。
わたしが今彼に望むこと。
今彼に思うこと。
それは、告白したいとかそういう後悔じゃなくて。
ていうかもう告白なんてどうでもいいから。
もっと生きて。
そんなシンプルなものだ。
わたしのものにしたいとかそういう醜い独占欲なんてどっか飛んでいってしまった。
一番大切なのは、彼が笑っているということ。
生きていることを幸せだと思い、毎日が楽しいと笑っていること。
わたしはそれだけでじゅうぶんだから。
御崎の笑顔さえ見られればもういいから。
御崎、聞いて?
トラックに轢かれるなんてばかみたいなこと、二度と起こさないでよね。
もうわたしはいないんだから。
自分の命を犠牲にしてまであんたを助けようとするばかはわたしくらいなんだから。
そして、また同じような毎日に戻るんだよ。
まあわたしがいないから前と同じじゃないけど、御崎はわたしがいなくなっても別に平気だよね?
わたしがいなくなっても、御崎には代わりがいっぱいいるもの。
代わりじゃなくたって、御崎の周りにはたくさんの人がいるもの。
だから寂しくないよね。
「御崎……ありがとう」
今までありがとう。
生きるってことがこんなに楽しいって教えてくれて、ありがとう。
生きるのが辛いと思いながら死んでいくはずだったのに、御崎が救ってくれた。
御崎の笑顔さえ見られればもういいから。
御崎、聞いて?
トラックに轢かれるなんてばかみたいなこと、二度と起こさないでよね。
もうわたしはいないんだから。
自分の命を犠牲にしてまであんたを助けようとするばかはわたしくらいなんだから。
そして、また同じような毎日に戻るんだよ。
まあわたしがいないから前と同じじゃないけど、御崎はわたしがいなくなっても別に平気だよね?
わたしがいなくなっても、御崎には代わりがいっぱいいるもの。
代わりじゃなくたって、御崎の周りにはたくさんの人がいるもの。
だから寂しくないよね。
「御崎……ありがとう」
今までありがとう。
生きるってことがこんなに楽しいって教えてくれて、ありがとう。
生きるのが辛いと思いながら死んでいくはずだったのに、御崎が救ってくれた。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
「君たちは実験台なんだよ。世界のための大切な人材だ」
不気味な笑みを浮かべる白衣の男たち
「……何も悪いことなんかしてないのに、なんで、なんでこんな仕打ちに合わないといけないの。もう嫌だ。こんなことなら、生まれてきたくなかった」
泣き崩れるクラスメート
「早く殺してよ。殺せ、殺せ。わたしを、殺せよ!」
狂い始める親友
ねえ、わたしたちがなにをしたっていうの
望まれるように生きるわ
ちゃんといい子にしているわ
だから、お願い
元の世界――平和な毎日に戻らせて
謎の薬
仕方のない発狂
逃げ場のない世界
TAKE MEDICINE
この世界で誰が正常でいられると?
*
執筆:三月上旬くらい~七月二十八日
これから文章直したり増やしたりしていきます
表紙を見る
貴方は自分の最も信頼する人を殺すことはできますか
「健太くん、ごめん。これも、僕の為」
貴方は自分の最も愛しき人を殺すことはできますか
「無理だよ、お前を失くすなんて、考えられない……!」
けれど、殺さないと――
――貴方の命が危ないです
僕は一体何を望んでいたの
いじめに打ち勝つ力を欲しかっただけ
人を殺したかったわけじゃないのに
- - - - -
読者500人、PV数は30万突破!
ご愛読(なのか?)有り難う御座いますw
表紙を見る
陥落した感情
歪んだ愛情
間違った正義
崩れる友情
汚行に満ちたこの時代に俺らは産まれ
恋に落ちた
◇
「俺は頭を撫でてやることもできない。手を繋ぐことも、抱き締めてやることも」
それでもいいのか
そう問う俺に、こくりと頷く彼女
「愛してる」
俺は確かめるようにそう呟いた
◇
接吻も抱擁も
触れることすらできないけれど
愛を語らうことくらいはできる
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…