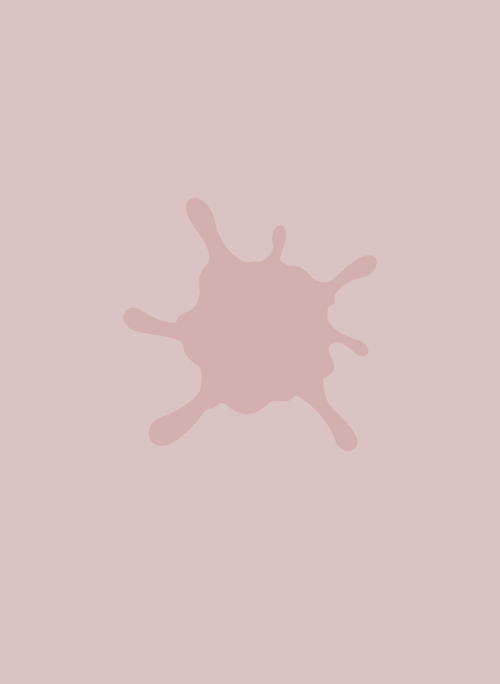「あなたが過去に行き触れ合ったもの全ての運命が変わります。あなたにその意思がなかろうと。その対価に値するものは、あなたの持っているものの中では一番大切な「命」なのです」
「……どういうこと?」
「例えば、あなたが歩いているとき、小石が足に当たったとします。すると小石はさっきとは異なった位置へ飛ぶ。そしてその数分後、その小石に少女が躓いてしまう。角を曲がってきたトラックは少女に気付かなく、少女を轢いてしまった」
「……わたしのせい?」
「直接的ではないのであなたのせいとは言い切れませんが、あなたがその少女の、そしてトラックの運転士の運命を変えたのです。つまり、あなたが過去に行くことにより様々な人、物の運命が変わってしまう。その対価にはあなたの命が必要、ということです」
「……へえ」
男の言葉には妙に信憑性があり、思わず頷いてしまう。
だけどそれはとてもおぞましいことだと思った。
だって、過去に行くということで、わたしは様々な人の運命を変えてしまうのだ。
たったそれだけのことで。
たくさんの人の運命が変わる。
「人の人生とはそんなものです」
一オクタープほど低い声で男が呟いた。
「……どういうこと?」
「例えば、あなたが歩いているとき、小石が足に当たったとします。すると小石はさっきとは異なった位置へ飛ぶ。そしてその数分後、その小石に少女が躓いてしまう。角を曲がってきたトラックは少女に気付かなく、少女を轢いてしまった」
「……わたしのせい?」
「直接的ではないのであなたのせいとは言い切れませんが、あなたがその少女の、そしてトラックの運転士の運命を変えたのです。つまり、あなたが過去に行くことにより様々な人、物の運命が変わってしまう。その対価にはあなたの命が必要、ということです」
「……へえ」
男の言葉には妙に信憑性があり、思わず頷いてしまう。
だけどそれはとてもおぞましいことだと思った。
だって、過去に行くということで、わたしは様々な人の運命を変えてしまうのだ。
たったそれだけのことで。
たくさんの人の運命が変わる。
「人の人生とはそんなものです」
一オクタープほど低い声で男が呟いた。
まさに、その通り。
ひどく儚くひどく虚しい。
それを一生懸命に生きようとするのが人間だ。
「さあ、余談はこれくらいにしておきましょう」
段々と下がっていた男の手に気合が入る。
しおれていた指は生き返ったようにぴんと張り詰める。
わたしはごくりと口の中の唾液を嚥下した。
「本当にいいですね」
「さっきからしつこいわね」
「これであなたの運命が変わってしまうんです。それくらいしつこくないと」
「あら、わたしがあなたの手をとろうととるまいと、あなたが出会ったことでわたしの人生は大きく変わってしまったと思うけど」
「……そうですね」
悪戯っぽく言ってやると、男は苦虫を噛み潰したような顔をした。
ひどく儚くひどく虚しい。
それを一生懸命に生きようとするのが人間だ。
「さあ、余談はこれくらいにしておきましょう」
段々と下がっていた男の手に気合が入る。
しおれていた指は生き返ったようにぴんと張り詰める。
わたしはごくりと口の中の唾液を嚥下した。
「本当にいいですね」
「さっきからしつこいわね」
「これであなたの運命が変わってしまうんです。それくらいしつこくないと」
「あら、わたしがあなたの手をとろうととるまいと、あなたが出会ったことでわたしの人生は大きく変わってしまったと思うけど」
「……そうですね」
悪戯っぽく言ってやると、男は苦虫を噛み潰したような顔をした。
「それでは」
男が低い声でつぶやく。
それを合図にわたしは全身の力を抜いた。
「いってらっしゃいませ」
心地のよい低音で見送られ、わたしはゆっくりと目を伏せた。
瞬間、頭の中が蛍光色のラインで彩られる。
さっきまで全身を取り巻いていただるさや疲れがどこかへ飛んでいってしまった。
足もついているはずなのにどこか浮いているような感覚だ。
麻薬をやったらこんな風なのかな。
ふわふわとした不思議な感覚を味わいながら、そんなばかみたいなことを考える。
そんな中ふと目を開くと、あの男の姿が見えた。
最後に見えた男の顔は、ひどく悲しそうなだった。
体を取り巻く異様なほどの倦怠感。
目を開けても視界はぼやけて、焦点は定まらない。
数秒後やっと分かる。
わたしはベッドの中にいた。
「うう……」
奇妙な呻き声をあげて、わたしはのそのそと起き上がった。
まず、周囲を確認する。
ここがどこか、本当に自分の家なのか、などとどうでもいいことを。
だけどいくら見てもそれは自分の部屋に変わりなくって。
ベッドの上でぽかんと口を開けて、脳内に浮かんだ言葉を呟いてみる。
ああ、もしかして。
「あれは、夢?」
御崎が死んだことも。
あの男と出会ったことも。
全部、夢?
時刻は八時十分。
いつもより少し遅い起床となった。
まあ今日は日曜日だから関係ないことなのだけど。
あたしはベッドから降りると適当に選んだ服に着替えて、一階へと降りる。
眠い目をこすりながらテーブルにつくと、目の前には母が用意した朝食がずらりと並んでいる。
「ねえお母さん。今日何日?」
「やあね、二十五日でしょ? 六月二十五日」
確認のためお母さんに尋ねると、ばかにしたような微笑と共に返された。
日付は昨日の日付。
だけど「明日」というものが嘘だったとしたら?
悶々とそんなことを悩みながら目玉焼きに醤油をかける。
みんなはソースとか塩とか変なこと言うけれど、わたしは断然醤油派だ。
ちなみに御崎も醤油らしい。
おそろいだ。
いつもより少し遅い起床となった。
まあ今日は日曜日だから関係ないことなのだけど。
あたしはベッドから降りると適当に選んだ服に着替えて、一階へと降りる。
眠い目をこすりながらテーブルにつくと、目の前には母が用意した朝食がずらりと並んでいる。
「ねえお母さん。今日何日?」
「やあね、二十五日でしょ? 六月二十五日」
確認のためお母さんに尋ねると、ばかにしたような微笑と共に返された。
日付は昨日の日付。
だけど「明日」というものが嘘だったとしたら?
悶々とそんなことを悩みながら目玉焼きに醤油をかける。
みんなはソースとか塩とか変なこと言うけれど、わたしは断然醤油派だ。
ちなみに御崎も醤油らしい。
おそろいだ。
「あら、美里」
「ん?」
「その目、どうしたの」
そう言われ目元に手をやる。
だけど何も違和感はない。
どうしたというのだろう。
「腫れてるわよ。どうしたの」
心配そうな顔をしたお母さんがわたしに手鏡を渡した。
わたしは素直にそれを受け取ると、自分の顔を映す。
「……本当、だ」
わたしの目は見るも無残なほどに腫れていた。
そういえば、心なしか目元が空気に触れてひりひりしているような気がする。
恐る恐る目元を触れ、その腫れ具合を確かめる。
「ん?」
「その目、どうしたの」
そう言われ目元に手をやる。
だけど何も違和感はない。
どうしたというのだろう。
「腫れてるわよ。どうしたの」
心配そうな顔をしたお母さんがわたしに手鏡を渡した。
わたしは素直にそれを受け取ると、自分の顔を映す。
「……本当、だ」
わたしの目は見るも無残なほどに腫れていた。
そういえば、心なしか目元が空気に触れてひりひりしているような気がする。
恐る恐る目元を触れ、その腫れ具合を確かめる。
「どうしたの、美里。泣いたの? それともただ単に寝不足?」
「あー……たぶん、寝不足。昨日寝たの遅いし。ほ、ほらっ、テストもうすぐだし!」
「そう、お勉強頑張っているのね。だけど体調を崩すのはよくないから、十二時までには寝なさいね」
お母さんはそう言うとテーブルから離れキッチンの方へ向かった。
勉強したなんて嘘だ。
この目の腫れは、明らかに泣き腫らしたものだ。
それは、今日――いや、厳密にいうと「明日」、御崎を失ったわたしが泣いてなってしまったものだ。
わたしは過去に戻ってきたのだ。
御崎が死んだのは本当で、怪しげな男の言っていたことも本当で。
御崎が死んだ。
その事実が明瞭になり、再び曇り始める心。
だけどまだ助けられるという希望が、心の中に舞い戻る。
そうだ。
まだ御崎は生きている。
早く助けなきゃ。
わたししかいないんだから。
御崎を助けられるのは!
たくさんの感情がせめぎあう。
そんなとき、ふとあの男の言葉が頭に浮かんだ。
〔あなたが過去にいられるのは四時間です。今から「昨日の午前八時」にあなたをおくります。ですから、あなたが過去に存在していられる時間は十二時まで。十二時になったらあなたの命は消滅します〕
わたしはここに四時間しかいられない。
そして十二時になったらわたしという存在は消えてしまう。
いつもの習慣で手首につけている腕時計の長針は二十を指している。
焦燥感がわたしの中にあふれてきて、わたしは勢いよく立ち上がった。
いきなりのわたしの行動に驚いたのか、お母さんが何なのよと声をあげた。
まだ御崎は生きている。
早く助けなきゃ。
わたししかいないんだから。
御崎を助けられるのは!
たくさんの感情がせめぎあう。
そんなとき、ふとあの男の言葉が頭に浮かんだ。
〔あなたが過去にいられるのは四時間です。今から「昨日の午前八時」にあなたをおくります。ですから、あなたが過去に存在していられる時間は十二時まで。十二時になったらあなたの命は消滅します〕
わたしはここに四時間しかいられない。
そして十二時になったらわたしという存在は消えてしまう。
いつもの習慣で手首につけている腕時計の長針は二十を指している。
焦燥感がわたしの中にあふれてきて、わたしは勢いよく立ち上がった。
いきなりのわたしの行動に驚いたのか、お母さんが何なのよと声をあげた。
「わたし、行ってくる!」
「何よ、いきなり。どうしたっていうの」
そのまま玄関に突進して、靴を履くためにしゃがむ。
靴を履き終え、立ち上がろうとすると、お母さんがエプロンで手を拭きながらわたしの傍に歩いてきた。
思わず振り向くと、心配そうな、呆れたような、よく分からない顔をしているお母さんと目があった。
御崎を助けなくてはいけない。
そしてそれには時間が限られている。
だから早くしなくては。
早く、早く早く。
急かす気持ちが、わたしを動かした。
そしてドアノブに触れた瞬間、後ろからお母さんの声がした。
いつもどおりの、それは妙に優しくて。
「いってらっしゃい、美里」
思考がストップした。
そのせいで不要な感情がたくさんはいってくる。
〔二時になったらあなたは消滅する〕
あの男の言葉が頭の中でくるくると踊っていた。
そう、わたしの人生はもう終わってしまったといっても過言ではない。
わたしは御崎のために自分の人生を捨てたのだ。
「何よ、いきなり。どうしたっていうの」
そのまま玄関に突進して、靴を履くためにしゃがむ。
靴を履き終え、立ち上がろうとすると、お母さんがエプロンで手を拭きながらわたしの傍に歩いてきた。
思わず振り向くと、心配そうな、呆れたような、よく分からない顔をしているお母さんと目があった。
御崎を助けなくてはいけない。
そしてそれには時間が限られている。
だから早くしなくては。
早く、早く早く。
急かす気持ちが、わたしを動かした。
そしてドアノブに触れた瞬間、後ろからお母さんの声がした。
いつもどおりの、それは妙に優しくて。
「いってらっしゃい、美里」
思考がストップした。
そのせいで不要な感情がたくさんはいってくる。
〔二時になったらあなたは消滅する〕
あの男の言葉が頭の中でくるくると踊っていた。
そう、わたしの人生はもう終わってしまったといっても過言ではない。
わたしは御崎のために自分の人生を捨てたのだ。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
「君たちは実験台なんだよ。世界のための大切な人材だ」
不気味な笑みを浮かべる白衣の男たち
「……何も悪いことなんかしてないのに、なんで、なんでこんな仕打ちに合わないといけないの。もう嫌だ。こんなことなら、生まれてきたくなかった」
泣き崩れるクラスメート
「早く殺してよ。殺せ、殺せ。わたしを、殺せよ!」
狂い始める親友
ねえ、わたしたちがなにをしたっていうの
望まれるように生きるわ
ちゃんといい子にしているわ
だから、お願い
元の世界――平和な毎日に戻らせて
謎の薬
仕方のない発狂
逃げ場のない世界
TAKE MEDICINE
この世界で誰が正常でいられると?
*
執筆:三月上旬くらい~七月二十八日
これから文章直したり増やしたりしていきます
表紙を見る
貴方は自分の最も信頼する人を殺すことはできますか
「健太くん、ごめん。これも、僕の為」
貴方は自分の最も愛しき人を殺すことはできますか
「無理だよ、お前を失くすなんて、考えられない……!」
けれど、殺さないと――
――貴方の命が危ないです
僕は一体何を望んでいたの
いじめに打ち勝つ力を欲しかっただけ
人を殺したかったわけじゃないのに
- - - - -
読者500人、PV数は30万突破!
ご愛読(なのか?)有り難う御座いますw
表紙を見る
陥落した感情
歪んだ愛情
間違った正義
崩れる友情
汚行に満ちたこの時代に俺らは産まれ
恋に落ちた
◇
「俺は頭を撫でてやることもできない。手を繋ぐことも、抱き締めてやることも」
それでもいいのか
そう問う俺に、こくりと頷く彼女
「愛してる」
俺は確かめるようにそう呟いた
◇
接吻も抱擁も
触れることすらできないけれど
愛を語らうことくらいはできる
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…