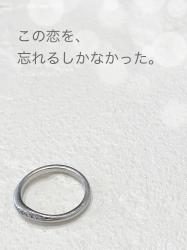「…」
だから慣れてないんだってば、そういうのに。
でも夏休みは40日間もあるーーー毎日宿題する訳でもないし、そのうちの何日かを誰かと一緒にいるのも、たまにはいいかもね。
めずらしくそんな風に思ったあたしは、少しだけ迷ってから、佐久田くんに《了解》と返信した。
《ゆかた着てこいよ!》
《ゆかたなんか持ってないよ》
《え〜っ、持ってないのかよー。夢希は絶対水色のゆかたが似合うと思ったのにー》
「…ふふっ」
ぶーぶー文句を言っている佐久田くんの顔が目に浮かぶようで、想像していたら可笑しくなってきた。
浴衣か…もう何年も着ていない、だいたいあたしには必要ないアイテムだと思っていたし。
夏祭りだなんて、何年ぶりだろう。
「あ…!」
あたしはハッとして、慌ててリビングに戻った。
「お母さんっ…!」
「どうしたの?夢希ちゃん」
カチャカチャと音を立てて洗い物していたお母さんが、ゆっくりと顔をあげた。
だから慣れてないんだってば、そういうのに。
でも夏休みは40日間もあるーーー毎日宿題する訳でもないし、そのうちの何日かを誰かと一緒にいるのも、たまにはいいかもね。
めずらしくそんな風に思ったあたしは、少しだけ迷ってから、佐久田くんに《了解》と返信した。
《ゆかた着てこいよ!》
《ゆかたなんか持ってないよ》
《え〜っ、持ってないのかよー。夢希は絶対水色のゆかたが似合うと思ったのにー》
「…ふふっ」
ぶーぶー文句を言っている佐久田くんの顔が目に浮かぶようで、想像していたら可笑しくなってきた。
浴衣か…もう何年も着ていない、だいたいあたしには必要ないアイテムだと思っていたし。
夏祭りだなんて、何年ぶりだろう。
「あ…!」
あたしはハッとして、慌ててリビングに戻った。
「お母さんっ…!」
「どうしたの?夢希ちゃん」
カチャカチャと音を立てて洗い物していたお母さんが、ゆっくりと顔をあげた。