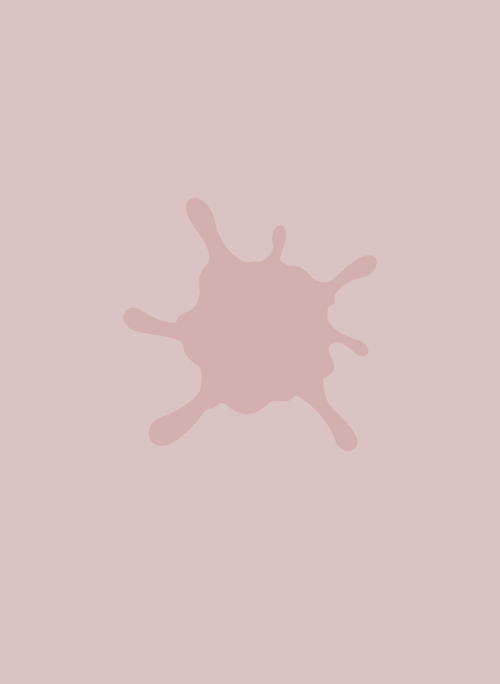――――――――――――――――――――
冷たい風が俺の肌を刺激してくる。それが嫌でもあったが同時に良くも感じる。今俺の右手には買ったばかりの暖かい缶コーヒーが握られている。外が寒いおかげでこの缶コーヒーを握っていると幸せさえ感じてくるし、"今日の学校が終わり"としみじみと思う。
校門の所に背もたれして、普段なら携帯か本でも読んでいるところを俺は空に映る、綺麗な星空を眺めていた。
やはり絶景を見ると心を落ち着ける。そこに深い感情は無いがついつい時間を忘れてぼーっと見る。その何気ない時間が俺にとっては楽しいものだ。
「おーい。待たせたな。」
「遅いんだよ。早く帰ろうぜ。」
「いや〜。コーヒーご馳走様でした。すっげえあったけぇ〜」
俺が買ってやった缶コーヒーを敦は恋人のを抱いているように、両手で持ちながら頰に当て、幸せそうな表情を見せた。
「...そういえば何で奢ったりしてくれたんだ?珍しいじゃねぇか。」
敦は歩きながらそんな事を聞く。俺は敦が隣へ来ると同時に返答し、歩いた。
「ほら、もうそろそろ学園祭だろ?"練習お疲れ様"ってやつだ。練習は厳しくて頭から離れてるが、俺達は学園祭を楽しめるのはあと二回だけってことだ。千恵どうこうより学園祭を楽しむのがいいと思うんだ。」
「おぉ。またまた珍しく栄治が人間っぽい台詞を吐いたな。だけど栄治、俺に缶コーヒーを奢ってくれたのと結構話がズレたな。」
俺が折角奢った上、こいつはタダでさえテンションが下がっているのを気にして言ったらこのザマだ。敦は湯気が立つ缶コーヒーを啜りながらニヤニヤとしていた。
「うるせぇな〜。とにかく明後日は楽しもうってことだよ。」
「んなの無理に決まってんだろ?俺のアイドルである里沙ちゃんが来てないんだぞ?あぁ....今思うとコーヒーがゲロ不味く感じてしまう....」
俺が必死に避けてきたキーワードをこいつは意図も簡単に口にし、一人勝手にテンションを落としやがった。
俺はため息を吐きながら渋々敦の背中を叩いた。
「大丈夫だって。里沙も学園祭参加したいに決まってるって。もしかしたら当日か明日になったら来るかもしれないだろ。」
「...そうかもな....ありがとな"本煩悩"」
最後の言葉に引っかかってキレそうになったが何とか抑えた。
流石に四日も学校に来ていないとなると、話したこともないのにタダのクラスメイトな俺でも多少心配する。
俺はコーヒーを啜りながら空に輝く星を見上げながら、想像もつかない里沙の現状を悟るように考えた。
俺が折角奢った上、こいつはタダでさえテンションが下がっているのを気にして言ったらこのザマだ。敦は湯気が立つ缶コーヒーを啜りながらニヤニヤとしていた。
「うるせぇな〜。とにかく明後日は楽しもうってことだよ。」
「んなの無理に決まってんだろ?俺のアイドルである里沙ちゃんが来てないんだぞ?あぁ....今思うとコーヒーがゲロ不味く感じてしまう....」
俺が必死に避けてきたキーワードをこいつは意図も簡単に口にし、一人勝手にテンションを落としやがった。
俺はため息を吐きながら渋々敦の背中を叩いた。
「大丈夫だって。里沙も学園祭参加したいに決まってるって。もしかしたら当日か明日になったら来るかもしれないだろ。」
「...そうかもな....ありがとな"本煩悩"」
最後の言葉に引っかかってキレそうになったが何とか抑えた。
流石に四日も学校に来ていないとなると、話したこともないのにタダのクラスメイトな俺でも多少心配する。
俺はコーヒーを啜りながら空に輝く星を見上げながら、想像もつかない里沙の現状を悟るように考えた。
――――――――――――――――――――
アレが見えなくなってからもう数十時間になる。私はちょっと前までは考えられないような薄暗い自分の部屋の隅で縮こまっていた。
アレが見えなくなると、自分の部屋の有り様が良く見えて自分自身ビックリしてしまった。
部屋は物で埋め尽くされて床なんて見えたものではない。いつも丁寧に閉まっていた漫画や小説などの本棚は倒れ、本は散乱している。
机も本の上で倒れ、ペンなどは何本か折れてすっぽかされている始末。飾ってあった写真やポスター、賞状もどれがどれか分からないほど破り散っていた。
壁もでこぼこしており、かつて綺麗な白い壁は戦場の家のような有り様だった。
こうなったのは全てアレのせい。アレは私を弄んでいるように目の前に現れた。
アレが最後に現れた時なんて酷かった。目の前がありもしない幻覚で包み込まれ、アレがとった行動があまりにも異常で私は発狂しながら気絶した。
そして気がついた時からアレの姿は一度も見ていない。逆に恐ろしくはあるがここまで見えなくなったのは初めてだ。もしかしたら消えたのかもしれないと思ってきた。
人の死を目撃しアレが見えるようになってから実に五日間、本当に壮絶で辛かった分今の時間が天国のように感じ、ボロボロと涙が零れてくる。
前のような視線を感じるような感覚は無くなったし、不可解な現象も無くなった。
今まで嬉しいことはいっぱいあったが、ここまで日常が有難いと思ったことは無い。親や友人に言ったら気味が悪いと言われそうで言えなかった恐怖が消えた。
自分が安全と今感じてきた。ふと、すぐ上に視線を向けると、半分破り捨ててあるカレンダーがぶら下がっていた。明後日の日にちには赤い文字で"学園祭"とデカデカと書いてあった。
一瞬血かと思いゾワっとしたが、マジックで書いてあって安堵のため息を漏らす。
学園祭...とても楽しみにしていた行事。アレを見るようになる前までは猿のようにはしゃいでいたのを思い出す。だが、アレを見ている内はそんな事を考えれる暇は無かった。
学園祭....朝起きた時までにアレが居なかったら、学校行こうかな...
時間を見ると夜の七時。少し早いが数十時間アレが姿を表さないかと緊迫状態が続いたので、疲れは出ていたのですぐに寝ることにした。
布団にゆっくり入ると意識がスグに遠のいていく。私は完全に意識が消える直前までアレが再び姿を現さないことを願った。
俺の朝は基本早い。七時半少し過ぎには学校へ着くようにし、教室に入ると誰もいない空間で読書をする。家でゆっくり読めばいいと思うが、家の中では他にやりたい事がある。
登校の時には敦は一緒ではない。入学当時は一緒ではあったが、あいつが寝坊したせいで何度か先生に怒られるハメになった事があり、今では登校は俺が朝早く行き敦が馬鹿を見るという感じだ。
こんな学校生活が何百日も続いているので、朝の学校の変化が良くわかる。
例えばグランドを見ると朝早くからサッカー部が練習をしている。恐らく大会が近いのだろう....
すぐ外にある木下を見ると綺麗なコンクリートが見える。昨日の掃除当番はしっかりとした生徒がやったのだろう....
そんな事を頭の端で考えながら俺は読書を楽しんだ。その内ゾロゾロとクラスメイトが教室へ入ってきた。教室の時計を見るとあまり時間は経ってはいない。明日の学園祭のことも影響しているか分からないが、いつもは遅く来る生徒も見かけられた。
俺はそれをあまり気にせず、すぐに読書へ戻った。少しいつもと違って朝から賑やかだったが、俺の耳にはその雑音はあまり入ってこなかった。
それから数十分後にあくびをして頭を掻きながら教室へ入ってきた。それを確認すると本をゆっくりと閉じた。
敦が来ると読書どころではなく、逆にイライラしてしまって読書が嫌いになってしまいそうだったからだ。
敦も皆と同じで少し早い登校で、周りを見渡すと敦が最後らしい。
敦は眠気と戦いながらヨロヨロとしていて、鞄を机に置くと椅子に座り込んだ。
「...おはよう栄治。」
「お、おう。おはよう。」
俺が少し戸惑ったのは敦の目を見たからだ。敦の目には気力が感じられなかった。眠気に襲われているのもあるが、やる気というか気力を無くしている。どこか遠くを見ているようで、里沙が来ていないのが大きいと感じた。
里沙の事で周りに何か変化があるんじゃないかとふと思い、周りを見渡すと人それぞれの行動をしていて、少し面白くもあった。
千恵は本番ではないのに少し緊張して顔が強張っていたし、どこか落ち着きがなかった。
青山に関しては学園祭間近なのに勉強していた。受験生じゃないくせに何でそこまでするのか良く分からないが、彼なりに何か事情があるのだろう。
加奈は静かに読書をしていた。周りに騒いでいるクラスメイトとはまるで別空間で読んでいるかのような集中力、そこの辺りは凄いと本心で思った。
吉永は携帯を見たり力なくうつ伏せになったりなどを繰り返していた。
恐らく里沙に連絡を入れたが一向に返ってこないのだろう、顔が疲れ果てていた。
ガラガラ
俺の片耳で聞こえた教室のドアが開く音。分かってはいるものの反射的にそこを向いてしまう。
ドアの方へ目線を合わせると俺は二つの事に気付いて衝撃を受けた。
まず一つ目は....
「里沙!?」
そう。一つ目は矢野里沙が登校してきたことだ。それに気付いた吉永は飛び跳ねるように机から立つと、そのまま体当たりをする勢いで里沙へ抱きついた。
「里沙!何で返信してくれなかったの!?私心配で心配で....」
「う、うん。ごめんね愛香。」
吉永の行動をきっかけに主に女子が次々と里沙の方へ集まっていく。
「里沙〜久しぶりじゃん!」
「里沙大丈夫なの?もう平気なの?」
里沙を中心にゾロゾロと女子の群れが集まった。もうここからでは里沙の姿が見えない程になった。
チラッと隣を見ると疲れ果てながらも嬉しそうにしていた敦の姿が目に映る。多分敦は今にでも吉永と同じように飛びつきたい気持ちで一杯なのだろうが、そんな勇気があるならとっくの前に話せているから、グッと堪えていた。
でも敦や他の皆の反応からすると、まだ気付いていないらしい。
俺は吉永の前に里沙に気付いたからこそ分かったのだ。
それは里沙は相変わらずのサラっとした髪の毛をしているし、清潔感が漂っていた。だが、彼女の目にはクマがあったのだ。
それが二つ目に驚いた事だ。タダのクマなら寝不足だったりと思える。だが、俺はあのクマにはまた別の意味を感じ取った。何か良からぬ事のように思えてならない。
里沙は少し減った女子の軍団を引き連れて自分の席へゆっくりと座った。周りの女子も段々と減ってきているので、その間から里沙がチラッと見える。
里沙の目は何処と無く生気を感じられず、周りをキョロキョロとしていた。それは近くの女子に向けられたものではなく、何か別の恐怖に怯えていると言った感じだ。
そして前よりか目線が下であまり皆と目を合わせたがらない。まるで加奈のような、加奈より酷いキョドり方。
里沙はちょくちょく手で目をみんなに隠す行為をした。このクマに関しては里沙も自覚しているらしく、いつもの自分に戻ろうとしたが、クマは取れなかったという推測が一番あっているのかな?
俺はこんなに違和感を感じたのにも関わらず、皆は笑顔で里沙を出迎えた。里沙がいつも通りに学校へ来てくれた嬉しさや、心配が解れたからなのか、歓喜で胸がいっぱいらしい。
逆に言えばこんな事に気付いてしまった俺は、敦の言う通り人間性が少し欠けているのかもしれない。
すると後頭部から鋭い痛みが走った。俺はその勢いに逆らえず、思いっ切りおでこが机に激突した。
「おい栄治。何チラチラ里沙ちゃんのこと見てんだよ。もし下心あったら俺がその性根叩き潰してやるからな。」
冷たく鋭い声でボソッと耳元で話し掛けてきた敦。本来、ここで下心があったのなら身震いするような場面だが、生憎俺は下心何て全く無いし、逆に推測で殴られた怒りが込み上げてきた。
「ってめぇ..!!.....はぁ。何もねぇよ。ただまだ休んでた方がいいんじゃないのか?って思っただけだ。」
「あ?何でそう思うんだ?」
「前みたいな元気がねぇし、何処と無く控えめだ。学園祭だからって無理してねぇのかな?って思わねぇのか?」
「うーん...確かにな。だけど、もし今回の件がトラウマになったのなら、それを少しでも忘れる為に参加したんじゃないのか?
あぁ...でもお前の言うことにも一理あるんだよなぁ〜」
敦は頭を机に擦り付けながら必死に悩んでいた。
俺は敦が推測で殴った事を謝らない事に怒りを感じていた。
この作家の他の作品
表紙を見る
楽しい修学旅行になるはずだった。
クラス全員、前々から楽しみにしていた学校生活最大の想い出になるであろう修学旅行。
和気藹々としていたクラスメイト達が今では疑いの目をチラつかせている。
血の匂いが鼻を刺激し、恐怖に晒される。友達も、恋人さえも信じられないこの状況。
耐えられない...私には耐えられない....
人間の本性が見え隠れるするこの施設にはとても耐えられない。
恐怖、悲しみ、憎しみ、怒り、負の感情が空気中に漂い、私達を汚染する。
何を信じていいか私には分からない。
何で?...何でそんなことをするの?....
......信じてたのに!!
※ルール等更新しながら変更する場合がありますのでご了承ください。
※グロテスク要素がありますので、苦手な方は閲覧注意してください。
よろしかったら是非レビュー・カンタン感想の方をよろしくお願いします!!
表紙を見る
時間を戻せたらとこれ程思うことは無い。
私が犯してしまった罪
裏切り、見捨て、見殺した私の罪
許されないのは分かってる
殺してやりたいと思う程憎まれているのは分かっている。
許されなくてもいい
憎まれてもいい
殺されても何も文句は言わない
私はただ.......
※少々グロテスク表現がありますので、苦手な方は閲覧する際に注意してください
もし良かったら自分の励みにもなりますので、レビュー・カンタン感想、感想ノートの方をよろしくお願いします!!
Sayoさん、レビュー書いて頂きありがとうございます!
表紙を見る
ここはとてもいい村だ
自然豊かで空気が気持ちよく、ご飯もとても美味しい
外から来た私達を村全体で温かく歓迎してくれる
村人一人一人が優しくて、困った時は全員で手を貸してくれる
何一つ不自由を感じさせない村
幸せになれる村
だけど私はそんな幸せは望んでいない
あの仮面だけはつけたくない
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…