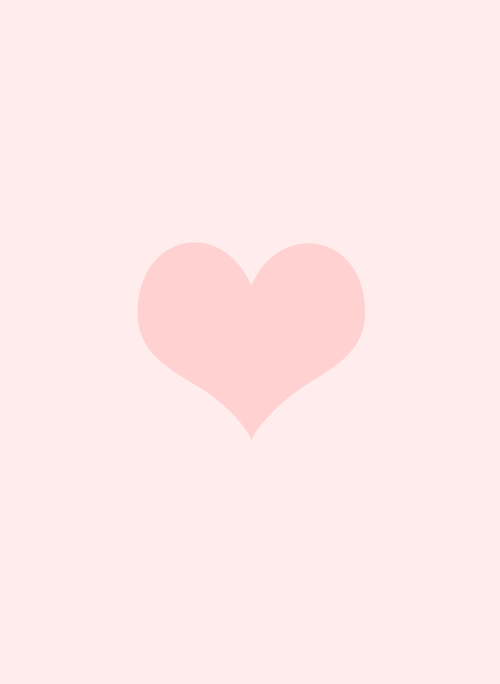「だからね…
まだ出会ったばかりなのに、もう別れる事を考えるのはやめにしようと思って。
ミンジュンさんは韓国を拠点として仕事を展開してて、私は日本でお店を守らなきゃならなくて、でも、今の韓国と日本は、国内を旅行するより簡単に行き来できる。
ミンジュン王子のおかげで、ソウル東京間の飛行機なんて何便も飛んでるし、飛行機代も格安だし、日帰りだって余裕でできる」
「何だよ… ミンジュン王子のおかげって」
ミンジュンは自分の功績には全く気付いていない。
でも、詠美はそれでいいと思った。
これは詠美とテヒの秘密の話に出てくる、いい話の一つだから。
「だから、しばらくはそういう付き合いをしていこう…?
一年後か、二年後には、状況が変わってくるかもしれないし」
「状況が変わるって、例えば?」
ミンジュンは水を止めた。
温いお湯のままの方が穏やかに寛容に詠美の話を聞けるから。
「例えば…
うちのお兄ちゃんがお店を継ぐ事になるかもしれないし、もしかしたら、ミンジュンんさんの会社が日本で大成功して、ミンジュンさんが日本に住めるかもしれないし…
あ、でも、後の方はないか…
それは私のただの願望だった、ごめんね…」
ミンジュンはその事には何も触れず、詠美をまた優しく抱きしめる。
「俺は…
一年も二年も待てない…
でも、詠美の言うように、急いで結論は出さないようにする。
でも…」
詠美はミンジュン見上げて笑った。
「でもが多いぞ、ミンジュンさん」
ミンジュンも困ったように笑って、また話し出す。
「でも、決めたんだ…
俺の導き出す結論に、別れるという選択はない。
俺の結論は、必ず詠美と結婚すること。
その結論は変わらなくて、その過程を一生懸命考える。
とにかく俺は詠美と離れて暮らすのは耐えられないから、どうにかしてそうならない方法を考える。
結婚に向かって努力するよ。
だって、俺達のゴールはもう決まってるんだから」
詠美が一生懸命に考えてそうしたいと思うのなら、俺もそれに合わせるだけだ。
俺は詠美のしたいようにさせてあげたい。
でも、さっきまでは、詠美の思いは、俺と別れる事だと思っていた。
韓国に嫁ぐ事ができないのなら、今ここで別れる選択をするのだと思っていた。
オンマと話したからか詠美の考えが変わったのなら、俺はそれを喜んで受け入れる。
でも、これはスタートで、二人の結婚までの道のりは厳しく長いはずだ。
でも、でも…
その前に、俺は詠美と離れて生活ができるのだろうか…?
詠美は何も言わずに俺の胸にもたれかかっている。
でも、せっかく結婚の話をしたのに、何のコメントもないなんて…
「詠美…?」
「…あ、ごめん…
なんか、のぼせたみたい…」
ミンジュンは詠美を抱き上げ立ち上がった。
顔を真っ赤にした詠美の大きな目は半分とろんと閉じている。
「詠美、水風呂に入るぞ」
「え、あ、それは、いいです…」
のぼせているのにはっきりと断る詠美は、よっぽど水風呂が嫌いなのだろう。
ミンジュンは軽く笑いながら、詠美の足先に水を優しくかける。
「…気持ちいい」
ミンジュンは詠美の足元にゆっくりと水をかけながら、さっきのプロポーズの事を考えた。
多分、のぼせ上がっていた詠美には、半分も伝わっていない。
ま、いいか…
あとで、ゆっくり、ちゃんとプロポーズをしよう。
俺と結婚してくださいと…
そして、死ぬまで何があっても離さないと…
ミンジュンと詠美は、空港にジノ達を見送るために来ている。
最初の計画より仕事がスムーズに進んだという事で、ミンジュン以外のスタッフは一週間前倒しで韓国へ帰る事になった。
最初はミンジュンもジノ達と一緒に帰るつもりだった。
でも、ジノの計らいで、あのホテルのスウィートルームは予定通りの日程まで使う事ができ、ホテルの代金も前払いで支払い済みだった。
ジノはミンジュンの母親がホテルに立ち寄った次の日に、詠美の給料の事で事務所として使っている部屋へ詠美を呼び出した。
でも、詠美と世間話をしていると、どうやらミンジュンから帰国が早まったという要件を聞かされていないらしく、普通に明るく話をしている。
ジノは機転を利かせて、とりあえずその件は伏せておいた。
「詠美のお給料の件なんだけど、詠美がミンジュンについて24時間体制で仕事をしてくれた事に本当に感謝して、最初の条件とは違う金額で支払いたいと思ってるんだ」
ジノは詠美の驚く顔が意外だった。
でも、ジノはそんな詠美を横目で見ながら、給料明細書を詠美に渡した。
「ジノさん… あの…」
詠美はもらった給料明細書を見ようとしない。
「うん? 何?」
詠美はジノへ給料明細書を返した。
「これは受け取れません…
とういうか、お給料は辞退させていただきます。
もちろん、最初は仕事としてミンジュンさんの元へやってきたけど、でも、今では仕事ではなく、自分の意思です。
私は多分、早い段階からミンジュンさんに心惹かれていて、ミンジュンさんへしてきた事は自分のためでもあって、仕事じゃないんです。
だから、お給料なんてもらえないし、もらいたくない…
ごめんなさい… わがまま言って」
ジノはわざと大きくため息をついた。
「いいのか? こんな大金なのに」
詠美はその大金という言葉に恐れをなして、要らない要らないと首を横に振った。
「分かった。
でも、この事は、社長であるミンジュンには報告しないとならないから。
あいつがどう反応するかだな。
俺は了承した。
詠美は、本当にいい子だな…」
ジノは詠美と話した後、すぐにミンジュンと話した。
詠美が給料を辞退した話を聞いて涙ぐんでいるミンジュンを見て呆れて鼻で笑ってしまったが、二人の愛は確実に育っている事をしっかりと認識できた。
「ミンジュン、お前はまだ東京にいろよ。
俺達に合わせて急いで帰る必要はない。
お金という報酬を受け取らないのなら、お前というご褒美を俺は詠美にあげたいと思うんだけど。
俺達が帰った後の一週間は、お前は詠美のためにだけ時間を過ごせ。
別れられないんだろ…?
顔にそう書いてあるぞ」
ミンジュンはムカついたふりをしている。
見透かしたみたいに何言ってんだ?と俺の顔を睨みながら。
「お前に言われなくてもそうするよ。
あと、ジノ…
俺は詠美と結婚する。
でも、今すぐにはできない事情があるんだ。
俺が韓国に帰ったら、仕事の事でお前に相談がある。
ま、今までも、不可能を可能にしてきたジノ様だから、俺はお前を信頼してる、心から」
ジノは嫌な予感がしたが、とりあえずミンジュンに笑みを見せた。
ガキの頃から、俺はミンジュンをずっと守ってきた。
孤独と戦う小さな戦士のようだったミンジュンは、いつも危なっかしくて、でも心を許した人間には命を差し出しても構わないくらいの深い愛情で包み込んだ。
子供の時から漠然と思っていた。
俺は、きっと、ミンジュンを守るために生まれてきたのだと。
「詠美、短い間だったけど、楽しかったよ。
でも、韓国にも遊びに来るんだろ?
いつでも歓迎するから、待ってるよ…
あ、それと、あいつにも優しい言葉をかけてやってくれ。
何だか失恋した気分になってるみたいだからさ」
空港は夜の最終便ということもあり、人がまばらだった。
ジノは詠美にそう言うと、隅っこで煙草を吸っているテヒョンを指さした。
詠美がテヒョンに近づくと、テヒョンはすぐに気が付いて困ったように笑った。
「詠美、日本語を教えてくれてありがとう…
あと、詠美はミンジュン兄さんと上手くいってるみたいだね」
詠美はコクンと頷いた。
「テヒョンは、映画のオーディションを頑張って。
私と一緒に頑張った日本語は、もうテヒョンのものにちゃんとなってる。
だから、絶対、合格できるから、自信を持ってね」
詠美はテヒョンの手を握った。
テヒョンの存在は、詠美にとっては欠かせないものだった。
友達として、これからもずっと応援していきたい。
ミンジュンと詠美は、搭乗口に入って行く皆を見送った。
詠美は胸の奥から涙がこみ上げる。
ミンジュンはそんな詠美の肩を抱き寄せた。
空港から外へ出ると、白い雪が降っている。
関東地方に押し寄せた大寒波は、ミンジュンと詠美の上に雪を降らせた。
「詠美、知ってる?
韓国では、初雪の降る日は特別な日だって。
初雪に出逢った人と結ばれるとか、初雪にデートした恋人達は幸せになれるとか。
若い頃はくだらないって思ってたけど、今、なんかワクワクしてる。
東京で今日は初雪だよな?
あ~、やっぱり俺達は、何があっても結ばれる運命なんだ~」
詠美のセンチメンタルな気分はあっという間に吹き飛んだ。
ミンジュンと一緒に両手を広げて、舞い落ちる雪を全身で受け止める。
可笑しくて何度も笑った。
ミンジュンとの日々は、詠美にたくさんの幸せをもたらしてくれる。
ミンジュンは詠美の実家に何度も足を運んだ。
一週間という短い期間に一番したい事は、やはり詠美の家族と打ち解けたい。
煎餅屋の仕事が終わる頃に、ミンジュンと詠美はたくさんのご馳走を買い込んで遊びに行った。
お酒が好きな詠美の父親につき合って、ミンジュンは夜まで飲み明かした。
詠美をどれほど愛しているか、詠美の父さんの思いが胸を突くほど伝わってくる。
でも、詠美の父さんは、亡くなった妻の話は一切しない。
それがただただ苦しかった。
詠美の父さんは、まだ、永遠に詠美のお母さんを愛している。
でも、それが幸せなのか不幸せなのか、今のミンジュンには何も分からなかった。
ミンジュンが韓国へ帰る日の前日、ミンジュンは詠美の父さんに告白をした。
ちょうど詠美は美沙とコンビニまで買い物に行ったため、その時間はミンジュンと詠美の父さんと二人っきりだった。
「あの、お父さん、聞いて下さい…
僕は、詠美さんと結婚したいと思っています。
でも、お父さんやこの家族に悲しい思いはさせたくない。
だから、僕の中でちゃんと準備が整ったら、その時また改めてお父さんに挨拶に来ます。
どうぞ、どうぞよろしくお願いします」
ミンジュンはそう言って、深々と頭を下げた。
「…ミンジュンさん、そんなに色々な事を抱え込まなくてもいいんだよ。
詠美がミンジュンさんと一緒になりたいと思っているのなら、私達は反対はしない。
詠美が幸せになる事が、それが一番だから…」
ミンジュンはまだ頭を下げている。
詠美の幸せを誰もが願っているのは百も承知で、そして、その幸せの中にはお父さんの幸せもお店の繁盛も入っている。
ミンジュンは全てを受け入れ、全てを叶えたいと思った。
いつになるかは分からないけれど、必ず笑顔で、詠美を迎えにここへ帰って来る。
その日の夜、ミンジュンは初めて経験する寂しさに戸惑った。
詠美の実家からホテルへ帰ってくると、急激に寂しさが押し寄せてきた。
ミンジュンの頭の中では、詠美と結婚するための準備と整理のために少しの間離れ離れになるとしっかり納得したはずなのに、心と体はその少しの間が我慢できないと叫んでいる。
詠美の様子もおかしかった。
明らかに泣くのを我慢している。
「詠美、お風呂に入ろうか…?」
詠美は笑顔で頷くが、涙がポロポロと零れている。
この作家の他の作品
表紙を見る
“AIR&WATER” 略してAW。
日本にはまだ珍しい秘密結社。
社長の唐澤明良は、15年間、
ボデイガードとして
アメリカで活躍してきた。
そんな唐澤が日本でチームを組んだ、
唐澤のこだわりが詰め込まれた
このチームは、全てにおいて
美しいビジュアルの人間の集まりだ。
顔、スタイル、マインド、
そして、身体能力は
群を抜いていなければならない
そして、今、AWのチームに、
五人の男性と一人の女性が所属している。
限りなく完璧に近いそのメンバーだが、
性格が素直じゃない奴らが多い気がする。
でも、唐澤は、
仕事さえしっかりこなしてくれれば
何も問題ないと思っている。
メンバーの私生活にまで
干渉しようなんて、
これっぽっちも考えていなかった。
法律の範囲内であれば。
そして、今回はそのメンバーの中で
絶対的エース、細谷翔のお話。
惚れられる事は数知れず、
でも、惚れる事は全くない。
そんな翔が今回の仕事では……
表紙を見る
…7月7日に天の川で待ってます
7月に入ったある日、
元カレから不可解なLINEがきた
天の川??
7月7日??
高校の時につき合っていた
心太からの突然の連絡
4年経った今でも心太が忘れられない
私を知ってて、もしや悪戯…?
でも、でも、どうしよう…
そもそも、天の川ってどこにあるの~~
表紙を見る
秋ちゃんの事好きになって、
本当によかった…
何年間も私の心を一人占めにした秋ちゃん
今日を私の記念日にするね
ありがとう…
そして、バイバイ秋ちゃん
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…