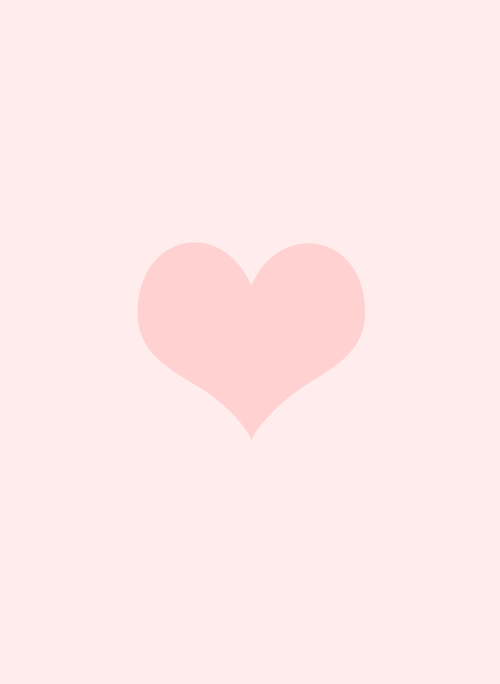「ミンジュン… よく考えろ。
今、俺達が新規事業として取り組み始めた事業がいくつあるか。
それは、全てお前のミンジュンという名前があってからこそ動いてるんだ。
確かにその分野ごとに優秀なブレーンを置いて、その専門家達が必死に会社を大きくしてくれてる。
でも、それもこれも全部、お前が社長で、そこに大きな信頼があるからなんだ。
お前に何もかも捨てられたら、今まで俺達がしてきた事は一瞬で水の泡だ。
もっと賢い方法を考えろ。
そういう極論じゃなくて…」
ミンジュンはジノの話を想定内の事として聞いていた。
ジノの言う通りだ。
もう俺は一人の体じゃない事くらい分かってる…
でも、それでも、何もかも捨ててでも詠美を側におきたいというこの衝動は、日に日に大きくなるばかりでどう対処していいのか分からないんだ…
「あ、それと、俺からの話だけど…
日本での仕事が予定より早く終わりそうだ。
もう何人かは韓国に帰ってるけど、一週間後の今日に、俺と残ってるスタッフは全員韓国へ戻る事にした。
ミンジュン、お前はどうする?」
ミンジュンはしばらく考えて小さく頷いた。
「俺も一緒に帰るよ…」
ジノはさずがにミンジュンが可哀想になった。
初めて人を愛して初めて人に愛されて、幸せというものをこの歳でやっと掴んだミンジュンにとって、何よりも酷な事だから。
「お前はギリギリまでいていいんだぞ。
そして、その他の方法をじっくり詠美と話し合え。
そんなこの世が終わったような顔をして帰って来られても、こっちがいい迷惑だよ」
ミンジュンはジノを睨みながら大きくため息をついた。
何も考えたくないというような疲れた顔をして。
「あ、それと、今朝、お前の母さんから電話がきた。
お前、全然電話に出ないそうじゃないか。
なんか明後日、東京に友達と来るらしいぞ。
ここのホテルのミンジュンの部屋番号を教えてっていうから、教えといた」
ミンジュンはゾッとした。
今のこの段階で母親と詠美を会わす方がいいのかと。
「マジか…
何しに来るんだ?」
「知らないよ、後で電話して聞けばいい。
とにかく、俺は、詠美のとの事は応援する。
でも、仕事を投げ出すなんていうのは、絶対認めない。
ちゃんと詠美と話しをしろよ。
いい方法が見つかるって。
でも、まずはオンマにちゃんと電話しろ、いいな」
ミンジュンはこれ以上悩みの種を増やしたくないのに、何故このタイミングで母親がやって来る?
ジノが食事を取っている間に、ミンジュンは韓国にいるオンマに電話をした。
「オンマ、久しぶり…
で、何しに東京に来るの?」
ジノは楽しそうにミンジュンと母親の会話を聞いていた。
ミンジュンにとって、母親はこの世の中のたった一つの愛だ。
でも、今のミンジュンには、それ以上に愛する人が現れた。
ジノはミンジュンの困った顔を見るのが好きだ。
電話口でジノに助けを求めるミンジュンは、最高に面白かった。
ミンジュンが部屋に戻ると、詠美は何か料理をしているのか、甘くて香ばしい匂いが部屋に漂っている。
ミンジュンはキッチンに立っている詠美を後ろから抱きしめた。
「おかえり、ミンジュンさん」
詠美はそう言うと、ミンジュンに軽くキスをする。
「ただいま…」
このままごとみたいな今の生活を俺はやっぱり手離したくない。
でも、これ以上欲張る事を神様は許してくれるのか…
「何を作ってるの?」
ミンジュンがキッチンを覗きこんでそう聞くと、詠美はペロッと舌を出した。
「今日、実家に帰ったら、お父さんが美味しいお餅が手に入ったからミンジュンさんに食べさせてって。
詠美おばちゃんが、きな粉や醤油や焼きのりやら全部持たせてくれたんだけど…」
ミンジュンは真っ黒に焦げた物体が餅だということが今気付いた。
「ここにあるオーブンが外国製だから全然加減が分かんなくて、もうこんなに焦がしちゃった…」
ミンジュンは適当にオーブンに餅をのせ、英語で書かれている説明書をパラパラと読んで、詠美が触った事のないボタンを2回押した。
「多分、これで大丈夫」
詠美は気持ちよく膨らんでいく餅を見て感動した。
「ミンジュンさん、すごい!
あ~、でも良かった…
お父さんからもらったお餅を全部台無しにするとこだったから」
詠美は焼き上がった餅をまずは持参した醤油に浸した。
そして、パリッとした焼きのりに巻いてミンジュンに渡す。
「この醤油は先祖代々伝わる、我が家の煎餅屋だけの秘伝の醤油なの。
ちょっと甘めですごく美味しいから。
それと、この焼きのりも、煎餅に使うものと一緒のものなんだ」
ミンジュンは詠美の説明を聞きながら、その餅を食べてみた。
「うん、すごく美味しい…
この間、詠美の家で食べた煎餅と同じ味がする」
詠美は顔をほころばせて自分もその餅を頬張った。
「変な話なんだけど、この味はきっと私とお兄ちゃんにとってはおふくろの味なんだ。
お母さんはいないけど、何て言うか、我が家の味みたいな…
良かった…
ミンジュンさんも気に入ってくれて…
でも、こんなに焦がしたってお父さん達には黙っててね。
もったいないって、絶対怒るから…」
ミンジュンは笑いながら頷いた。
部屋中に漂っているこの甘辛い醤油の味と匂いを、俺は一生に忘れないだろう。
こんなに幸せに満たされた時間を共有した全ての物を、俺はきっと死ぬまで忘れない。
「あ、そうだった… 詠美に相談があるんだ…」
詠美はドキっとした。
ミンジュンの深刻な顔は、迫りくる別れの時を嫌でも思い出させるから。
「実は、俺のお母さんが、明後日に東京に来るんだ…
友達との旅行だから、このホテルに泊まるとかはないらしいけど。
でも、俺の顔を見に来るって」
詠美は心臓が激しく高鳴る。
「じゃ、その日は、私は実家に帰った方がいいよね?
お母様も、親子水入らずで過ごしたいだろうし…」
詠美がそう言うと、ミンジュンは小さくため息をついて首を横に振った。
「それが、ジノが詠美の事を母さんに話したらしくって…
さらに、母さんが来るその日は、俺もジノも大切な仕事が入ってて昼間はいないんだ」
詠美の顔から見る見るうちに血の気が引いていく。
さっき食べ過ぎたお餅が胃の中で暴れ出し、最悪の気分になってきた。
「それで相談なんだけど…
明後日の昼過ぎに母さんはここにやって来る。
詠美がよければ、母さんにつきあって、食事なりショッピングにつき合ってもらいたいんだ」
ミンジュンは詠美の想定内の反応が可笑しくて笑ってしまいそうだ。
でも、いきなり、こんな事をお願いされたら、普通の女の子はこうなるだろう。
「え、でも…
ミンジュンさんのお母さんは、私の事をどこまで知っているの…?」
ミンジュンは目を閉じて大げさにため息をつく。
「ジノのバカ野郎が、ミンジュンはオンマ以上に愛する人を東京で見つけたって言ったらしい」
え~~、嘘でしょ…
韓国の年配の人は日本人をあまり好まないのに、それでいて、母一人子一人の絆が強い親子関係に、私の存在はただの邪魔でしかない…
「ミ、ミンジュンさん…
私… お母さんに、会わないとダメ?」
ミンジュンはさらに大きくため息をつく。
「どういう事か、母さんはぜひとも会いたいって言ってる。
詠美は韓国語が話せるし、東京の事を色々教えてもらいたいって」
「え? じゃあ、お母様は怒ってるとか不機嫌とかそんなんじゃないの…?」
ミンジュンはちょっとだけ首を傾げた。
「詠美も知ってると思うけど、韓国の女性は、基本強い女性が多い。
俺の母さんは、その中でも特に強い女性だと思うんだ。
そうじゃないと、あんな過酷な状況で女手一つで俺を育てられないと思うから。
でも、不思議なんだけど、母さんは俺のやる事成す事に一度も異を唱えた事がないんだ。
だから、今回も、俺の中ではそんなに心配はしてない。
それに結婚するとかそんなんじゃないって、ちゃんと伝えてあるから…」
詠美は、ミンジュンの最後の言葉が胸の奥深くに突き刺さるのを悲しいほどに感じた。
さりげなく流れていくその言葉は、詠美の心に引っかかり哀しみだけを置いていく。
分かってる、きっと、そう、二人とも分かってる…
私達の未来に希望はないという事を…
どんなに愛してるとお互い囁き合っても、現実と理想は違う事を、もういい大人の二人はちゃんと分かっている…
でも、もし、ミンジュンさんが結婚しようって言ってくれたら…?
韓国で一緒に暮らそうって言ってくれたら…?
本当はすごく嬉しくてミンジュンさんの胸に飛び込みたいけど、でも、私はきっとお父さんの事を捨てられない…
最愛の人を二度も亡くさせたくない…
私が韓国に嫁ぐっていう事は、私を亡くすということだから…
寂しがり屋のお父さんは、きっと、もう生きていけないよ…
お母さんを亡くした私達家族は、そうやって支え合って慰め合って生きてきたから…
「詠美? 大丈夫…?」
ミンジュンは詠美の顔が曇る原因を分かっていた。
それは、結婚という二文字を俺が会話の隅に出したから。
でも、これが今の現実の中の二人の状況だ。
考えている事を口に出すだけで、この世の終わりのような気分になる。
「あ、うん… 大丈夫、ごめんね。
それと、お母さんの件、私、引き受けてもいいよ…
ミンジュンさんのお母さんに、ちょっとだけ怖いけど、でも、会ってみたい気もするから」
ミンジュンはテーブル越しに詠美の頬を撫でた。
詠美は本当に優しい子だ…
「母さんが無事に帰ったら、俺から詠美にご褒美をしたい」
「何を…?」
ミンジュンは詠美の頬をまだ触っている。
つるつる滑らかな肌は、食べてしまいたいくらいに柔らかい。
「何でもいいよ。 詠美が望むものなら…
だから、考えといて。
どれだけお金がかかってもいいいから」
詠美はうんと頷いたが、別に欲しい物なんてない。
ミンジュンのお母さんに嫌われなければそれでいい。
そして、ミンジュンからありがとうって一言があれば、何も要らない…
この作家の他の作品
表紙を見る
“AIR&WATER” 略してAW。
日本にはまだ珍しい秘密結社。
社長の唐澤明良は、15年間、
ボデイガードとして
アメリカで活躍してきた。
そんな唐澤が日本でチームを組んだ、
唐澤のこだわりが詰め込まれた
このチームは、全てにおいて
美しいビジュアルの人間の集まりだ。
顔、スタイル、マインド、
そして、身体能力は
群を抜いていなければならない
そして、今、AWのチームに、
五人の男性と一人の女性が所属している。
限りなく完璧に近いそのメンバーだが、
性格が素直じゃない奴らが多い気がする。
でも、唐澤は、
仕事さえしっかりこなしてくれれば
何も問題ないと思っている。
メンバーの私生活にまで
干渉しようなんて、
これっぽっちも考えていなかった。
法律の範囲内であれば。
そして、今回はそのメンバーの中で
絶対的エース、細谷翔のお話。
惚れられる事は数知れず、
でも、惚れる事は全くない。
そんな翔が今回の仕事では……
表紙を見る
…7月7日に天の川で待ってます
7月に入ったある日、
元カレから不可解なLINEがきた
天の川??
7月7日??
高校の時につき合っていた
心太からの突然の連絡
4年経った今でも心太が忘れられない
私を知ってて、もしや悪戯…?
でも、でも、どうしよう…
そもそも、天の川ってどこにあるの~~
表紙を見る
秋ちゃんの事好きになって、
本当によかった…
何年間も私の心を一人占めにした秋ちゃん
今日を私の記念日にするね
ありがとう…
そして、バイバイ秋ちゃん
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…