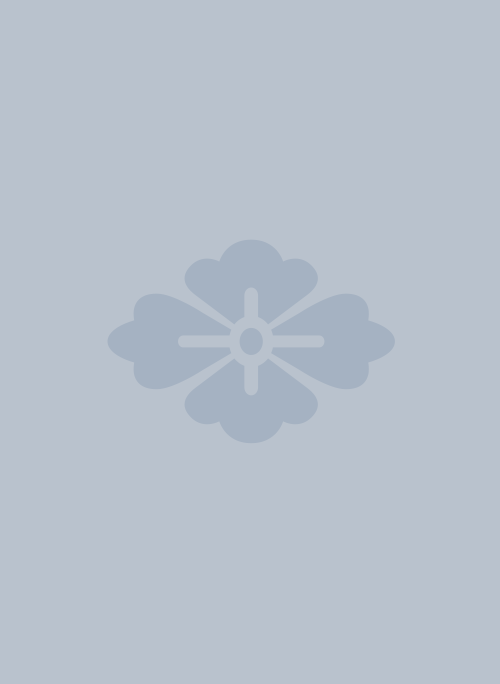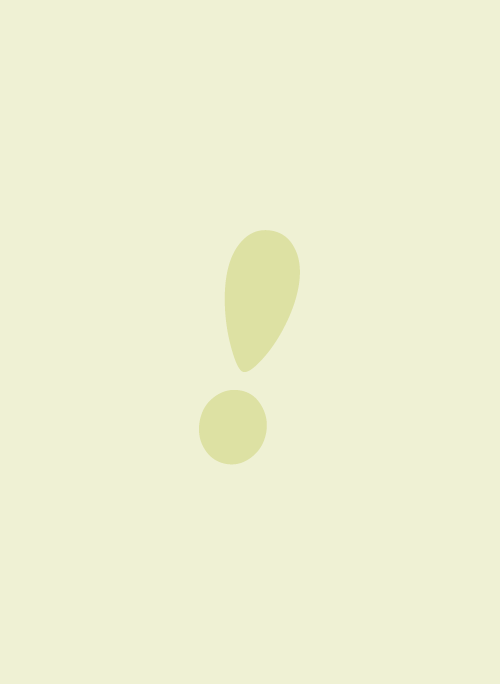普段、冷静な俺がこんな状況に陥って
しまったのは、すべて
あの男が原因だ。
それだけはハッキリと理解ができた。
☪︎⋆。˚✩ ☪︎*。 ☪︎⋆。˚✩ ☪︎⋆。˚✩ ☪︎*。 ☪︎⋆。˚✩
しまったのは、すべて
あの男が原因だ。
それだけはハッキリと理解ができた。
☪︎⋆。˚✩ ☪︎*。 ☪︎⋆。˚✩ ☪︎⋆。˚✩ ☪︎*。 ☪︎⋆。˚✩
「あぁ~。よく寝た。
あれ?私の部屋って薬のにおいしたかな?」
少しの違和感に目を覚ます。
情報量があまりにもすくないから、
自然と周りの様子を確かめるため、
身体を起こそうとする。
「ってか、背中痛いっつ。」
言うならば、足がつって起こされる朝みたいに
痛みがじわじわと残った。
「あぁーもう、何なのよ」
普段より数倍も重い身体を再びベットに
埋める。
「あれ?これ、私のベットじゃない!」
そこは以前、祖母のお見舞いで来た
白づくめの部屋に酷似していた。
「……ここは、病院?どうして私はここにいるの?」
ひとつひとつ理解していこうとしたが、
頭が割れそうで、自然と涙が出てきそうだ。
まるで何か大切なモノを忘れているようで……
これっていわゆる記憶喪失なのかな?
辛い現実から目をそらすために、
窓の外に目をやる。
埋める。
「あれ?これ、私のベットじゃない!」
そこは以前、祖母のお見舞いで来た
白づくめの部屋に酷似していた。
「……ここは、病院?どうして私はここにいるの?」
ひとつひとつ理解していこうとしたが、
頭が割れそうで、自然と涙が出てきそうだ。
まるで何か大切なモノを忘れているようで……
これっていわゆる記憶喪失なのかな?
辛い現実から目をそらすために、
窓の外に目をやる。
「カケル?」
窓の外から景色を確かめようと思ったが、
ベットの横の小さなイス……
そこには腕を組んだまま眠っているカケルがいた。
お世辞にも、整っているとは言えない顔。
日焼け跡、少しだけ長いまつげ、血色の悪い唇……
カケルの顔のすべてが私を掻き立て、
ただただ、愛おしい。
一晩中、一緒にいてくれたのかな?
カケルの髪や服の乱れ具合からすると
そうだろうなと推理して、勝手に胸が苦しくなる。
だが、心の奥底に悲しい出来事を閉じ込めて、
無知なふりをする。
私は本当に何も知らないのではないかと
自分自身を閉じ込め、そんな錯覚に陥る。
ふと、考えが浮かんだ。
声を出してみよう。
窓の外から景色を確かめようと思ったが、
ベットの横の小さなイス……
そこには腕を組んだまま眠っているカケルがいた。
お世辞にも、整っているとは言えない顔。
日焼け跡、少しだけ長いまつげ、血色の悪い唇……
カケルの顔のすべてが私を掻き立て、
ただただ、愛おしい。
一晩中、一緒にいてくれたのかな?
カケルの髪や服の乱れ具合からすると
そうだろうなと推理して、勝手に胸が苦しくなる。
だが、心の奥底に悲しい出来事を閉じ込めて、
無知なふりをする。
私は本当に何も知らないのではないかと
自分自身を閉じ込め、そんな錯覚に陥る。
ふと、考えが浮かんだ。
声を出してみよう。
「どうしてこんなところにいるんだろう?」
口に出してしまえば、頭の中で整理がつき、
この状況を少しは理解できるかもしれないと思ったのだ。
「もしかして、カケルが入院してるとこを
私がベットを占領していたりして……」
開いた口は止まらないで、動き続けていた。
それは彼の眠りを覚ますようだった。
にこっと笑ってみる。
それでも、記憶は変わらない。
いつものように、嫌いなものから逃げたいのに、
私は金縛りにあったかのように
一部分がカケた記憶
という設定に身体を縛られているのだ。
口に出してしまえば、頭の中で整理がつき、
この状況を少しは理解できるかもしれないと思ったのだ。
「もしかして、カケルが入院してるとこを
私がベットを占領していたりして……」
開いた口は止まらないで、動き続けていた。
それは彼の眠りを覚ますようだった。
にこっと笑ってみる。
それでも、記憶は変わらない。
いつものように、嫌いなものから逃げたいのに、
私は金縛りにあったかのように
一部分がカケた記憶
という設定に身体を縛られているのだ。
「ねぇ、カケル?」
どうしようもなくて、気付いたときにはそう嘆いていた。
ピクッとカケルの眉間にしわが寄った。
「ミチル?お前、目を覚ましたのか?」
カケルの三日月の目が開かれていた。
どうしようもなくて、気付いたときにはそう嘆いていた。
ピクッとカケルの眉間にしわが寄った。
「ミチル?お前、目を覚ましたのか?」
カケルの三日月の目が開かれていた。
「うん。今さっきね。
ねぇ、どうして私はここにいるの?」
私はいくらだってあなたが苦しまなくてもよい道を選ぶだろう。
「あ、それは……「なんか、背中がいたいんだよね~。
なんでだろう?
なぜか、記憶の一部がカケているようなそんな気がするの……」
彼があまりにも悲しい顔をするから
カケルの言葉を遮ってしまった。
彼はその話をしたくないに決まっている。
私はまだ、眠っていた方が良かったのだろうか?
「あっ、それより、私っていつから入院してるの?」
できるだけ、わざとらしくないように話題をそらす。
「あっ、えーと2日前からかな?」
「へー、じゃあ私は丸一日も寝ていたんだね。」
明るく、いつもの軽い口調で言った。
彼のいつもの笑顔が見て安心したいから。
ねぇ、どうして私はここにいるの?」
私はいくらだってあなたが苦しまなくてもよい道を選ぶだろう。
「あ、それは……「なんか、背中がいたいんだよね~。
なんでだろう?
なぜか、記憶の一部がカケているようなそんな気がするの……」
彼があまりにも悲しい顔をするから
カケルの言葉を遮ってしまった。
彼はその話をしたくないに決まっている。
私はまだ、眠っていた方が良かったのだろうか?
「あっ、それより、私っていつから入院してるの?」
できるだけ、わざとらしくないように話題をそらす。
「あっ、えーと2日前からかな?」
「へー、じゃあ私は丸一日も寝ていたんだね。」
明るく、いつもの軽い口調で言った。
彼のいつもの笑顔が見て安心したいから。
だが、カケルは
「どうして、丸一日だと分かった?」
と深刻な顔で言った。
「え?だって私は2日前の夕方に……」
私は、はっとなって口を手で覆った。
カケルはやっぱりという顔をして私をみつめた。
これだから頭のいい人は……
その時にはもう、眉間のシワはみていられないくらい
深くなっていた。
偏差値が80以上あるこの頭も、好きな人の前だと上手く働かないらしい。
「お前、何もカケてなんていないだろ?」
そんな冷たい声が病室内に響き渡った。
「どうして、丸一日だと分かった?」
と深刻な顔で言った。
「え?だって私は2日前の夕方に……」
私は、はっとなって口を手で覆った。
カケルはやっぱりという顔をして私をみつめた。
これだから頭のいい人は……
その時にはもう、眉間のシワはみていられないくらい
深くなっていた。
偏差値が80以上あるこの頭も、好きな人の前だと上手く働かないらしい。
「お前、何もカケてなんていないだろ?」
そんな冷たい声が病室内に響き渡った。
耳を塞ぎたくなったが、
彼に演技がバレたことよりも
カケルが私の名前を呼んでくれなかったことに
少し、腹が立った。
なぜか今更
病院の独特なにおいで鼻が満たされていることに気づいた。
それは、カケルに嘘が発覚しても、
私はまだ、彼の中で綺麗な存在であるだろう
自信と余裕からだ。
「どうして記憶喪失のふりをしたんだ?
それで、俺が楽になるとでも思ったのか?」
頭は落ち着き払っていたが、
少し時間が経ってからこたえた。
その方が余情があって綺麗な私を演出できると思ったから。
「思ったよ。」
私は穏やかな声でそう言い、
カケルの三日月の形をした目をとらえた。
彼に演技がバレたことよりも
カケルが私の名前を呼んでくれなかったことに
少し、腹が立った。
なぜか今更
病院の独特なにおいで鼻が満たされていることに気づいた。
それは、カケルに嘘が発覚しても、
私はまだ、彼の中で綺麗な存在であるだろう
自信と余裕からだ。
「どうして記憶喪失のふりをしたんだ?
それで、俺が楽になるとでも思ったのか?」
頭は落ち着き払っていたが、
少し時間が経ってからこたえた。
その方が余情があって綺麗な私を演出できると思ったから。
「思ったよ。」
私は穏やかな声でそう言い、
カケルの三日月の形をした目をとらえた。
この作家の他の作品
表紙を見る
近藤勇が、恋に焦がれる日々を描いた物語。
近藤勇はなぜ、最期に諦めたのか、それを作者の見解で展開していきます。
何とか完成することが出来ました。
読者さんの数は多いとは言えませんが、
それでも、私の作品を読んで下さったことに感謝します(*^▽^)/★*☆♪
作品中よく、貴方という言葉が出てきます。
貴女という表現もありますが、
貴女は、高貴な女性に言う言葉で、
作者は、葉月と近藤の仲がとても良いことを表現するために、わざと貴方を使用しています。
また、最初は、彼女や彼という言葉を使用していたのですが、
あの時代には、それらの言葉が、なかったことを思いだし、急いで貴方という表現にかえています。
そのため、幾分か読みにくい部分があると思いますが、ご理解をよろしくお願いします。
表紙を見る
浅葱の贖罪の続編です。
今回は土方目線でストーリーを進めたいと思います。
正反対の2人をテーマに描いた作品です。
前作を読んでいない方も楽しめるようになっています。
(前作を読んだ方が多少、分かりやすいかもです)
表紙を見る
三姉妹の末っ子目線の家族のストーリー
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…