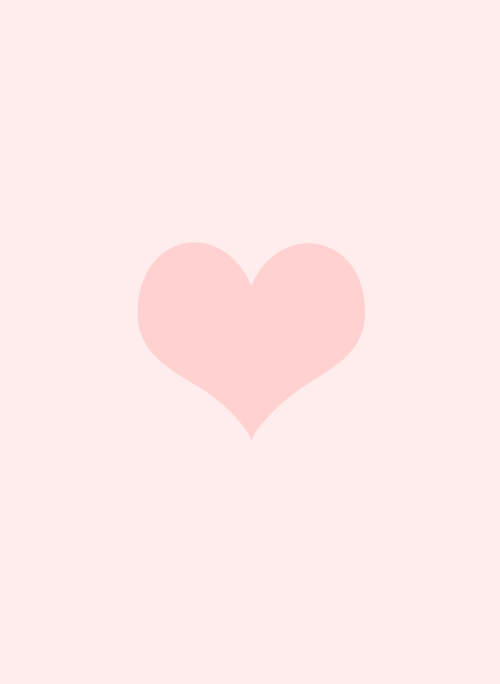翔太は何かとわたしに絡んでくる。
でも、なぜだか本物の嫌悪は感じない…
だって、わたし、知ってるから。
本当に嫌われる気持ち。
本当に嫌っている人のオーラ。知ってるから。
「おはよ。」
そう言って背後から声がした。
康介だ…
振り返らなくてもわかる。
きっと今は眠たそうに切り長の目を細めてて、ちいさくえくぼをくぼませているだろう。
さっきまで敷布団の上で眠っていた康介は、わたしに一応配慮してくれているのか、部屋の隅っこに布団を用意してくれている。
でも、わたしは汚い…純粋じゃないんだ…
こんなに素直で綺麗な康介たちのそばにいる資格は…ない。
康介は前に回ると寝癖のついた髪をくしゃっとしてわたしの前に屈み込むと、「だいぶ元気そうじゃん。」
そう言って目を細めて笑った。
康介の目をじっと見つめた。
今、康介の黒い、キラキラとした瞳にはわたししか映っていない。
わたしだけを見ている…
「な、なんだよ。」そう言って顔を引き離す康介は、今もわたししか見ていない。
なんともいえない気持ちが心を赤く染めた。
「康介。」
「お、おう。」康介は心なしかおどおどしている。
久しぶりに心が温かくなった。
くすぐったい気持ちになった。
「ありがと。」
わたしはそう言って、思わずふっと笑ってしまった。
康介は目を見開いて突っ立っていた。
その間抜けな表情にまた笑みが溢れる。
周りのみんなも驚いたような表情でわたしを見ている。
それがおかしくて、あははっと声を上げた。
「見てみてー!」
そう言ってかけてくる我が子を抱きしめると、初めて、喜びが湧き上がった。
「あーたん、大好き。」
そうつぶやいてあーたんの頬に口づけすると、ふわっと石鹸の香りがした。
彼女が笑った。
それはもう、世界で一番綺麗な笑顔だった。
ユリが風で揺れるなか、
そっと微笑む月のように、
彼女の笑顔は優しく、
美しかった。
俺は初めて、彼女のことが美しいと思った。
彼女の瞳の暗い、底なしの闇に宿る花が開花したと思った。
-----------
翔太の表情がパッと赤らむのがわかった。
翔太なんて、初めて彼女に会った時からあきらかだった。
でも俺からしたら、
彼女の中に闇しか見えなかった時から綺麗と思うなんて、どうかしていると思う。
もちろん、彼女、玲奈は、ありえないほど整った顔立ちをしている。
でも、俺は見てしまったんだ。彼女の瞳を。
あの日自転車にぶつかって立ち上がった、月光に照らされた彼女の闇を…
。
そんな中、優也は驚いたような顔はしたが、彼からは特に何も感じ取れなかった。
六月二十日。
雨。
気温は二十四度。
「留守番本当に大丈夫か?」
康介は足でサッカーボールを弄びながら何度目かに聞いてきた。
康介は部活に行くらしい。
たまたま今日は苦手な翔太も、そして珍しく優しい優也もいないから、心配してるらしい。
「ん。」
康介は何も言わないわたしにパンを押し付けてきた、「何も渡さなかったらお前家で餓死してそうだから。」
わたし、康介にとってどんなイメージなんだろ、なんて今頃思った。
梅雨。
天気予報では雨雲に注意。
傘を忘れないこと。
天気予報では雨雲に注意。
傘を忘れないこと。
「じゃあ行ってくるわ。」
そう言って玄関のドアを開ける康介、「餓死すんなよ。」
日に焼けた顔をほころばせて笑う彼は、常に笑顔だ。
「…じゃあね。」わたしは届かないくらい小さな声で言った。
康介は一瞬目を丸くすると、一層エクボをくぼませた、「おう!」
そう言って玄関のドアを開ける康介、「餓死すんなよ。」
日に焼けた顔をほころばせて笑う彼は、常に笑顔だ。
「…じゃあね。」わたしは届かないくらい小さな声で言った。
康介は一瞬目を丸くすると、一層エクボをくぼませた、「おう!」
この作家の他の作品
表紙を見る
私の運命の風向きを変えた男は、どこまでも強く、残酷で、ー…
闇色に底光りする彼の瞳はどこまでも黒く深い。
月光に浮き上がる彼の赤は、完全なるDEVIL。
彼に名など必要なければ、存在さえしない。
どんなに暗く濁った世界であっても、決して絶えない光を放つ彼に、いつの日かわたしもなれるのだろうか。
名はあるが光らない。
名はないが光る。
真っ暗闇の中、月光を浴びる彼になりたい。
想像を絶する物語が、今、幕をあける。
ー…………そして、どこまでも優しかった。
表紙を見る
-ーー桜の花びらの奥で芽吹いた青春を、きっと忘れないー---
毎朝寝癖が跳ねてるところとか、
上下ねずみ色の服を着ているところとか、
くだらない話ばかりしているところとか、
ちょっと猫背なところとか、
大きな声でくしゃみをするところとか、
マイペースなところとか、
冗談ばかり言っているところとか、
好きになる要素なんて絶対にない君なのに…
君のくしゃっとした笑顔で胸があったかくなったり…。
君なんて全然恋愛対象なんかに入らないのに…
君の冗談に笑ってしまうのはなぜ?
ねえ、この気持ちって…なに?
綾瀬穂花 (Ayase Honoka)
いつも一人で桜を見上げている少し変わった少女。
結城悠 (Yuki Yu)
冗談ばかり言っているマイペースなムードメーカー。
君の冗談の本当の意味、わたしはまだ知らなかった。
ー今だから届けたい。
わたしの大好きなヒーローにー--…
*タイトル:君じゃないとダメなんだ(完)→ HEROへエールを(完)→ HEROに花束を(完)
2018 START〜
表紙を見る
いつだったか君は言った。
みんなに合わせて笑うなんてバカだって。
みんなが楽しそうだから自分も楽しくなるんじゃない。
自分が楽しければそれでいい。
『俺のものは俺のもの。みんなのものも俺のもの。』
すごく自己中心で、わたしの存在をまるで否定するかのような言葉。
わたしには考えたことがなかったこと。
それを君は自信に満ちた笑顔で言ったんだ。
酷いと思った。
最低だと思った。
「俺の世界、見せてやろーか?」
だけどきっと…
たった一羽で、
広い天空を羽ばたく君が、
わたしはきっと、
羨ましかったんだ。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…