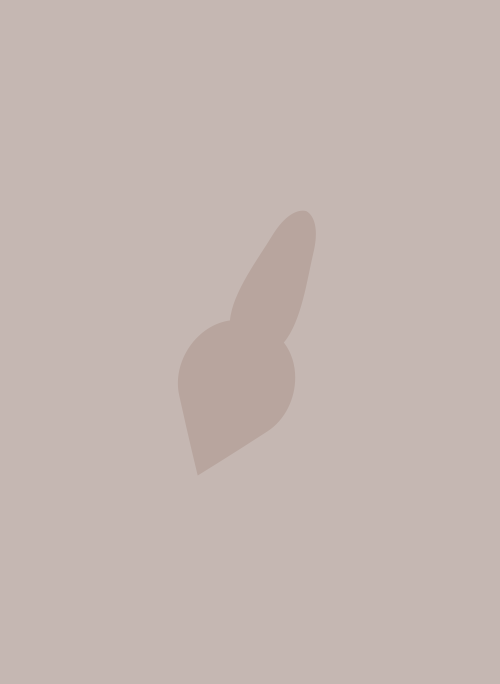いつも、一人で授業を受けていたわたしのクラスに転校生が来るとある日先生が告げた。
週に何度か他のクラスに授業を受けに行くことはあるが、普段はこの“支援学級”と呼ばれているところでわたしは一人、授業を受ける日々。
だから、『転校生が来る』と知らされたときはどんな子が来るのだろうとワクワクした。
「明日、来る子の名前は“小瀬 新汰(こせ あらた)”くんだ。仲良くしてあげなさい。」
帰りのHRでクラスの担任の先生があらかじめ、転校生の名前を告げて教室を出ていく。
中学1年だったわたしはイケメンとかアイドルとかに興味があった時期。
小瀬 新太という名前を耳にした瞬間、わたしはなんて格好いい名前なんだと胸が高鳴った。
“アラタ”という名前はよくある名前だが私はその名前の持ち主に会ったことがない。
多分、わたしの授業を受けに行く普通クラスには一人くらいいるんだろうけど、あまり関わることのないクラスだからまともに名前を覚えていられないのだと思う。
――きっと、優しくて話しやすい男の子なんだろうな
一人で軽く想像してみたりなんかした。しかし…
朝もいい天気で私の気持ちも晴れ晴れとしていたその日。
天気もいいことからか、鼻歌を歌いながら母が仕事で出かけたため溜まっていた洗濯物を洗濯機の中へ入れる。
洗濯機が回っている間にわたしは自分が学校へ行く準備をする。
寝相が悪くていつも寝癖がつく髪の毛をヘアアイロンで伸ばし、ハンガーに掛けてある制服を着て、朝食にグラノーラを食べて、顔を洗ったり。
洗濯が終わる音が聞こえると、洗濯物を干すが、身長が145センチしかないことなどからいつも洗濯物を干すのに一苦労。
すべてが終わるとバスの時間に合わせ戸締まりをして家を出ようとするがその日は少しバスが遅れているため、もう一度身だしなみを見る。
転校生が来るということもあり、いつもはつけたりなんかしないヘアピンで前髪を纏め鏡の前でクルリと一回転してみる
「よし、完璧だ。」
そして、また時計を確認した。
最後に腕にタオル製の黒いリストバンドをつけて家を出ていく。
わたしの通っている中学校まではバスに乗り約15分程度。
近くに指定の中学校はあるが、身体の弱いわたしは近くの中学でやっていけのるか不安でその中学校には行かず、少し遠い支援学級のある中学校に行くことを選んだ。
バスの中から見える景色はいつもとかわらないはずなのに、この日はなんだか少しだけ違うように見えたんだ。
いつもと同じ、お気に入りの特等席に座っているはずなのに...。
“転校生が来る”という心の中の魔法だろうか。
「次は・・・・・。次は・・・・・。」
バスのアナウンスが響きわたしはボタンを押しリュックを手に取り下りる準備をした。
バスが停止し、バスの定期券を取り出すとき、バスの運転手さんに『行ってらっしゃい』と言われた後、『今日はニコニコしてるけどなにかいいことでもあったの?』と言われた。
わたしは笑顔のまま『秘密です~』と言って定期券を通す、バスを降りていく。
バスを降りた直後、わたしは歩きながら一人運転手さんに言われたことを考え始め
る。
――そんなに顔に出てたかなぁ~。
確かにいつもはつけていないヘアピンつけてるし…
だけどいつもと違うのはそれくらい。
思い返してみればいつもはバスの後ろの方の席で一人ムスッとしているか、眠いとだらけている様子。
それが、今日の朝は窓の外をただ見つめている傍から見れば、恋する乙女オーラが出ていたのかもしれない。
本当は恋などしていないけど、まだ恋とかしたことはないけど...。
だけど、その恋は今日始まるかもしれないのだ。
考えただけでワクワクしていたのかもしれないのは否定できない。
今日、いつもより機嫌がいいのは事実だ。
だって、普段の生活でならできるはずのない憧れの恋愛というものがやっとできるかもしれないのだから。
恋愛は一人でできるものではない。相手がいなければできないんだ。
ヒトメボレでもない限り、まだまだ遠い話かもしれないが...
だって、彼は今日来る予定の転校生なのだ。
まず、わたしと二人だけのクラスに慣れていくことからはじめなければならない。
それから仲良くなっても遅くなんかないと思う。卒業まであと2年もあるわけだし。
恋はできなかったとしても、友達にはなれたらいいと思う。
支援学級と呼ばれているところにいるわたしは普通クラスには一応浅く仲のいい友達と呼べる女の子はいるが、少し離れたところから通うわたしと、近くに住んでいるという理由で指定の中学校に通う彼女とは帰りも別々で帰る。
だから、彼女は同じクラスの仲のいいグループの女の子たちといつも一緒に帰っている。
いつも、わたしは彼女に笑顔で『じゃぁね‼』と帰るとき一言言って帰るが、彼女はわたしの言葉を無視し、彼女のいつもいる教室の前を通り過ぎると嫌な笑い声が聞こえ、彼女のグループの一人が『アンタも大変だね~。先生に内申点上げてもらうためにあの子と仲良くしないといけないんだからさ』という。
彼女はグループの女の子の話を聞きニコリと微笑みうなずいたのだ。
その後、わたしは彼女たちの話をただ聞いてはいられなくなりその場を走り去ってしまった。
――バカだ。バカみたい、バカみたい...。
わたしに彼女が優しくしてくれたのは先生から頼まれたことだってことくらい最初からわかってた。
あんな態度、いくら陰口だとしても取らなくてもいいのに...。
あの頃のことを思い返すだけで今でも胸が苦しくなってしまう。
帰りのバスからはいつも彼女が彼女のグループの友人と楽しそうに話しながら帰る姿が見える。
彼女はいったいなにをそんなに楽しそうに話しているのだろうか。
もしかすると、わたしの悪口かもしれない。
そんなことを考えるといつも怖かった。
わたしのなにか気に入らないところがあったなら、直す。それとも、支援クラスにいるわたしと関わること自体が嫌だったとしたらもう関わってこなくてもいい。
そんなことを思い始めたのは1年の8月頃のことだった。
それから2か月くらいが過ぎ去った10月。
10月はきれいな赤い色をしていた葉もすっかり枯れ落ちてしまってわたしの心も孤独を感じ始めたある日。
担任が告げた転校生が来るという知らせ。
それが昨日の出来事だった。
そして今日はついに、転校生の男の子(小瀬 新太くん)がわたしのクラスに来るという日。
校門を通り抜け、教室に向かう途中、お手洗いにより普段はつけたりなんかしないリップ(無色透明)を塗ってみる。
無色透明だからあまり変化はないが、心にスイッチが入るんだ。
教室の中に入ると、机が2つ並べられているのが見えて、転校生が来る事実をわたしに告げている。
机の高さが違うことから、わたしがどちらの席に座ればいいのかが一目散によくわかる。
わたしは自分の席に腰を下ろし、いつものようにクラスの優等生を演じるように小説を手に取る。