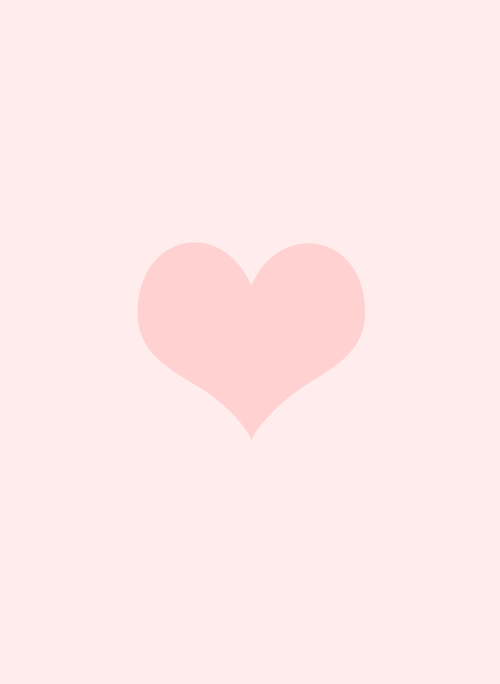ようやく一月の大震災の痛手から甦りつつあった大阪へ長橋一誠が戻ってきたのは、連休を前にした四月も半ば過ぎのことである。
「関東はどうやったん?」
「東京はてんやわんややったみたいやけど、うちがおったんは鎌倉の近くやったからなぁ」
新大阪の駅まで迎えにワーゲンのビートルで来てくれたのは、歯医者の倅の泉直也であった。
「なんや知らんけど、地下鉄でえらいことあったってニュースで言うてたやん」
長橋のやつ大丈夫やってんやろか、と仲間内で噂になっていたことを、助手席で初めて知った。
「あんだけの修羅場やってんやで、簡単には死なへんでぇ」
泉と一誠は東平野町とまだ呼ばれていた時代の幼稚園からの腐れ縁で、かれこれ十五年以上はつきあいがある。
「せや」
渋滞にはまった高速の車中で泉は、
「今度の連休、どっか行くんか?」
「取り敢えず一日は姫路に墓参りしなあかんけど、あとはずっと弁天町や」
「ほな、花見でもするか?」
「桜は散ってるし、造幣局の通り抜けは終わってるしで、吉野の山奥でも行く気か?」
「花は桜と限ったもんやあれへん」
泉は切り返した。
そういえば泉は専門学校を出たあとは、カメラマンのアシスタントとして京都で働いている。
「こないだグラビアで行ったんやけど、平等院って藤が見事らしいねん」
「平等院ねぇ」
「ほんで例の由美子ちゃんと行こうかなと思ったら、友達誘っていいかって」
「ガードかけられたな」
一誠はズケッと言い当てた。
「なぁ…おれ何でモテへんのかなぁ?」
「そんなんガツガツしとるからに決まっとるからやないか」
昔から一誠が厳しい物言いをするのを、泉は今更ながら思い出したようで、
「お前はどこ行っても生き残れそうやな」
「んな、人をゴキブリみたいに言わんといてや」
丁々発止のやりとりをする間に、弁天町の駅が見えてきた。
「ここから市岡の高校を裏に入ったとこが新しい実家や」
ビートルが信号を右折すると、左手に校舎らしき建物が見えてきた。
あれが市岡の高校なのであろう。
弁天町に再び泉のビートルがあらわれたのは、連休の初日である。
「おぅ」
「待たせたな」
見ると助手席には黒髪の綺麗な、水色のふわふわしたブラウスを着た女性が座っている。
「こいつ、おれの幼なじみで長橋一誠っていうねん」
「長橋です」
一誠はいつもの軽い会釈をした。
「取り敢えず後ろ空いてるから、カナやんの隣でえぇかな?」
後部に座っている、茶髪の子がどうやらガードでついてきたカナやんという友達らしい。
「うち、衛藤カナっていうねん、カナやんってみんな言うてるからカナやんでええわ。長橋くんは?」
「だいたい一誠やな」
「じゃあ一誠くんで決まりだね」
どうやらカナやんは仕切るのが好きな性分であるらしい。
乗り込むと車中は早速、一誠の話題になった。
「関東に疎開してたってホンマ?」
「まぁね、何せ西宮の家が半壊で、市役所からの指示で住めんくなって」
一誠が中学一年のとき、親が西宮に新しく家を買ったことから大阪を離れていたが、西宮の私立中学に通学していた泉との付き合いはそのままであったから、
「あの頃こいつ野球部やったから坊主頭で、今はその反動でロン毛にしよる」
と一誠は顎で運転席の泉を指し示した。
「お前ばらしなや」
「ほんまのことやもん、しゃあないやろ」
泉が露骨に嫌な顔をした。
高速を使わずに運転してきたので思わぬ時間は食ったが、昼前には宇治橋の側の駐車場に停めることが出来た。
「カナやん、お腹すいたね」
初めて長瀬由美子が口を開いた。
「泉くん、このあたりにレストランないの?」
「…確か橋の手前に、和食のレストランならあるはずやけど」
一誠は口を開いた。
「…このあたり知ってるの?」
「前にドライブ好きな親戚に連れてきてもらったことがある」
それは事実で、よく温泉や釣りに連れていってもらったこともある。
少し歩くと、瓦葺の平屋の食堂があった。
「確かここやなかったかなぁ」
空いていたのを見て、一誠が先に中へ入った。
「四人なんですけど大丈夫でっか?」
「ご案内します」
奥から声がしたので、
「良かった、すいてるってさ」
つられて続々と入った。
小上がりの座敷に案内されると、一誠の隣に由美子が座った。
泉はトイレに行っている。
「あ、自分は天ざるね。二人は決まった?」
由美子とカナに訊くと、
「私は天ぷら定食、由美子は?」
「同じでいいかな」
「あと一人来ますんで」
「では決まりましたらお呼びください」
店員がオーダーを伝えに行く。
「ところで一誠くんさあ」
すっかり打ち解けてたカナやんが、
「泉くんってさ、もしかしてあんまりモテない?」
「まぁずっと部活で女っ気はなかった」
「やっぱりなー」
カナやんは緑茶を一口飲んでから、
「なんかね、やたらに由美子に触ろうとするんだよね」
「…何を焦ってるんやあいつは」
「その点一誠くんあんまりそういうことないよね。もしかして彼女いる?」
「今はおらんけど」
「やっぱりね。なんかどっかで余裕があるっていうか、冷静やもんね」
「そうかな」
一誠は緑茶を含んだ。