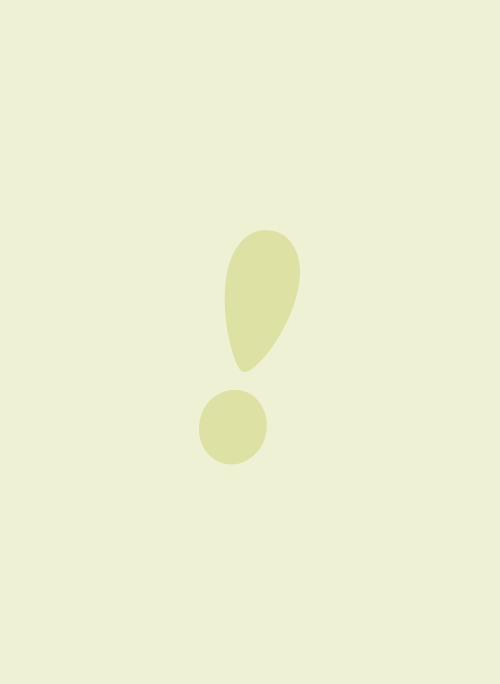そして…
「沖田惣次郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。」
後の愛弟子に逢った。初めて見た時、惣次郎には才覚が見てとれなかった。
また、義母(ぎぼ)の近藤ふでは惣次郎にきつく当たった。
「惣次郎、廊下の雑巾掛けは終わったの?」
「申し訳ありません。今、洗濯物をしていたため…」
「何を呑気なことを。いいですか?あなたは養われている身なの。いやなら、この道場から出ていきなさい。」
「沖田惣次郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。」
後の愛弟子に逢った。初めて見た時、惣次郎には才覚が見てとれなかった。
また、義母(ぎぼ)の近藤ふでは惣次郎にきつく当たった。
「惣次郎、廊下の雑巾掛けは終わったの?」
「申し訳ありません。今、洗濯物をしていたため…」
「何を呑気なことを。いいですか?あなたは養われている身なの。いやなら、この道場から出ていきなさい。」
義母(ぎぼ)は普段このような荒げた声はあげない。
どちらかといえば、穏やかで慈悲深いお方だ。
それなのになぜ、惣次郎にはきつく当たるのだろうか?
「惣次郎大丈夫か?」
いつしか、惣次郎を慰めるのは私の役目になっていた。
「大丈夫です。勝太さん。まったく私の要領の悪さには嫌気が差しますよ。」
無理して笑う惣次郎が痛々しかった。
「惣次郎…。」
なんと、声をかけたら良いのか分からず、惣次郎を慰めることも出来なかった。
どちらかといえば、穏やかで慈悲深いお方だ。
それなのになぜ、惣次郎にはきつく当たるのだろうか?
「惣次郎大丈夫か?」
いつしか、惣次郎を慰めるのは私の役目になっていた。
「大丈夫です。勝太さん。まったく私の要領の悪さには嫌気が差しますよ。」
無理して笑う惣次郎が痛々しかった。
「惣次郎…。」
なんと、声をかけたら良いのか分からず、惣次郎を慰めることも出来なかった。
惣次郎に何も出来なかったことを悔やみ、ただ無心で木刀を振っていると、
「勝太さん。今日はぶれていますよ。」
凜とした葉月の声だった。
「お前、分かるのか?」
「はい。剣術には全く詳しくないんですけどね…。」
少し照れたように言った。
「だったら、何故…」
葉月は少し不思議な顔をした。
「あれ?気づいていませんでしたか?私、いつも勝太さんの稽古向こうで見ているんです。」
そう言って葉月は庭を指差した。そこを目で追いやると物干し竿が目に入った。
「勝太さん。今日はぶれていますよ。」
凜とした葉月の声だった。
「お前、分かるのか?」
「はい。剣術には全く詳しくないんですけどね…。」
少し照れたように言った。
「だったら、何故…」
葉月は少し不思議な顔をした。
「あれ?気づいていませんでしたか?私、いつも勝太さんの稽古向こうで見ているんです。」
そう言って葉月は庭を指差した。そこを目で追いやると物干し竿が目に入った。
そして、意外なことを口にした。
「いつも、惣ちゃんと一緒に見ているんです。」
「惣次郎とか?」
私は思わず、聞き返した。
「ぇえぇ。惣ちゃんが教えてくれましたよ。勝太さんの剣術は凄いって。」
意外だった。惣次郎が、剣術に興味があったのだと。
「なぁ。なぜふでさんは惣次郎にきつく当たるのだろうか?」
葉月は顔をぎゅっと強張らせた。そして、言った。
「ふでさんは惣次郎が周助先生の隠し子だと、お思いなのです。」
「いつも、惣ちゃんと一緒に見ているんです。」
「惣次郎とか?」
私は思わず、聞き返した。
「ぇえぇ。惣ちゃんが教えてくれましたよ。勝太さんの剣術は凄いって。」
意外だった。惣次郎が、剣術に興味があったのだと。
「なぁ。なぜふでさんは惣次郎にきつく当たるのだろうか?」
葉月は顔をぎゅっと強張らせた。そして、言った。
「ふでさんは惣次郎が周助先生の隠し子だと、お思いなのです。」
私は、合点した。しかし、それではあまりにも惣次郎が不敏だ。
ふでさんは私達が何か言ったところで考えを変えてくれそうにもない。こうなったら…。
「あっ、」
私は、閃いた。惣次郎に剣術を教えれば、ふでさんと、接する回数も減り、惣次郎も剣術を学べるのではないか、と。
私が突然奇声を発したことに、葉月は驚いていた。だが、私の考えを話すと、彼女は同意してくれた。
「それはいい考えですね。勝太さん、私も出来る限りのことをします。」
彼女は笑顔で言った。
「あぁ。頼りにしている。」
私も、貴方に微笑んでみせた。
ふでさんは私達が何か言ったところで考えを変えてくれそうにもない。こうなったら…。
「あっ、」
私は、閃いた。惣次郎に剣術を教えれば、ふでさんと、接する回数も減り、惣次郎も剣術を学べるのではないか、と。
私が突然奇声を発したことに、葉月は驚いていた。だが、私の考えを話すと、彼女は同意してくれた。
「それはいい考えですね。勝太さん、私も出来る限りのことをします。」
彼女は笑顔で言った。
「あぁ。頼りにしている。」
私も、貴方に微笑んでみせた。
「惣次郎、剣術に興味はないか?」
私は向かい合って惣次郎と話した。
惣次郎は私の言葉に、目を輝かせたが、すぐにうつむいて言った
「私は、お世話になっている身です。だから…」
やはり、そう言うか、だが、今日の私はしつこいぞ。
「だから何だ?私は、剣術に興味はないか?と聞いたのだ。」
「興味はあります。ずっと、皆さんの稽古をみてきましたから。」
惣次郎はずっと、我慢していたのだろうな。何も言えず、ずっと…。
「そうか、では、明日の巳の刻、道場へ来い。稽古をつけてやる。」
惣次郎は嬉しそうな顔をしたが、
「私にはそのようなことをする時間はございません。」
私は向かい合って惣次郎と話した。
惣次郎は私の言葉に、目を輝かせたが、すぐにうつむいて言った
「私は、お世話になっている身です。だから…」
やはり、そう言うか、だが、今日の私はしつこいぞ。
「だから何だ?私は、剣術に興味はないか?と聞いたのだ。」
「興味はあります。ずっと、皆さんの稽古をみてきましたから。」
惣次郎はずっと、我慢していたのだろうな。何も言えず、ずっと…。
「そうか、では、明日の巳の刻、道場へ来い。稽古をつけてやる。」
惣次郎は嬉しそうな顔をしたが、
「私にはそのようなことをする時間はございません。」
惣次郎、もう我慢なんてするな。
そう言いたかったが、再び反論されそうだ。それならこっちは…。
私は大きく息を吸い込み、大きな口をさらに大きく開けた。
「惣次郎、そんなこととはなんだ?心外な。」
突然声を荒げた私に惣次郎は驚き、肩をピクリと震わせた。
「貴公(きこう)は剣術をそんなことと考えておるのか?剣術とは、国のため、故郷のため、愛する者を守るために必要なことだ。それをそんなことと貴様は侮辱する気か?」
ひどい剣幕で言った。一瞬、惣次郎は泣き出してしまうのではないか?と思った。
そう言いたかったが、再び反論されそうだ。それならこっちは…。
私は大きく息を吸い込み、大きな口をさらに大きく開けた。
「惣次郎、そんなこととはなんだ?心外な。」
突然声を荒げた私に惣次郎は驚き、肩をピクリと震わせた。
「貴公(きこう)は剣術をそんなことと考えておるのか?剣術とは、国のため、故郷のため、愛する者を守るために必要なことだ。それをそんなことと貴様は侮辱する気か?」
ひどい剣幕で言った。一瞬、惣次郎は泣き出してしまうのではないか?と思った。
しかし、惣次郎はそんなに柔ではなかった。
「侮辱など、してはいませぬ。私は剣術がどれ程今のこの国に必要なのか、分かっているつもりです。もしも、許されるものなら、私も剣を握りとぉ存じます。」
私は顔を綻ばせた。
「よく言ったぞ、惣次郎。よし、貴公に天然理心流を授けようじゃないか。」
「はい。勝太先生。」
惣次郎、あいつの目の輝きはこの日から変わらず澄んでいた。
「侮辱など、してはいませぬ。私は剣術がどれ程今のこの国に必要なのか、分かっているつもりです。もしも、許されるものなら、私も剣を握りとぉ存じます。」
私は顔を綻ばせた。
「よく言ったぞ、惣次郎。よし、貴公に天然理心流を授けようじゃないか。」
「はい。勝太先生。」
惣次郎、あいつの目の輝きはこの日から変わらず澄んでいた。
そう、惣次郎が死病にかかる、あの日まで…。
この作家の他の作品
表紙を見る
何気無い日々の中で起きる
それぞれの悪夢をきっかけに
四角関係の青春物語が
今、始まろうとしている。
悪者は誰ですか…?
表紙を見る
浅葱の贖罪の続編です。
今回は土方目線でストーリーを進めたいと思います。
正反対の2人をテーマに描いた作品です。
前作を読んでいない方も楽しめるようになっています。
(前作を読んだ方が多少、分かりやすいかもです)
表紙を見る
三姉妹の末っ子目線の家族のストーリー
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…