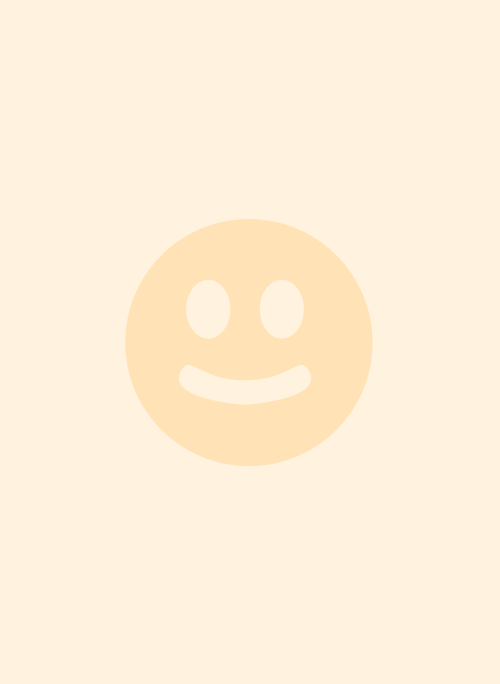俺と美幸は同じクラスだったが、一度も会話を交わした事がなかった。
お互いにイジメにあっていたし、下手に仲良くなろうものならイジメが更に炎上しかねない。
だから俺は彼女と話そうとはしなかったし、向こうも俺には近寄らなかった。
イジメについて先生に一度だけ相談した事があった。
だけど、先生は「イジメに合う方にも問題があるんじゃないのか?」
そう言い、深く踏み込まなかった。
親には頼らない。
俺の親は片親で母親しかいない。
女手一つで子供を養うのは大変だ。
これ以上、母親の負担にはなりたくない。
それが物心ついた頃からの俺のプライドであった。
だからこそ美幸の存在は俺の励みになった。
だから毎日の傷害にも耐える事が出来た。
(イジメに合うのはキツイ!でも独りじゃない。
一緒に頑張ろう。)
心の中でそう美幸に言っていた。
もしかしたら彼女もそう思っていたかもしれない。
もはや確かめる事は永久に出来なくなってしまったが・・・。
お互いにイジメにあっていたし、下手に仲良くなろうものならイジメが更に炎上しかねない。
だから俺は彼女と話そうとはしなかったし、向こうも俺には近寄らなかった。
イジメについて先生に一度だけ相談した事があった。
だけど、先生は「イジメに合う方にも問題があるんじゃないのか?」
そう言い、深く踏み込まなかった。
親には頼らない。
俺の親は片親で母親しかいない。
女手一つで子供を養うのは大変だ。
これ以上、母親の負担にはなりたくない。
それが物心ついた頃からの俺のプライドであった。
だからこそ美幸の存在は俺の励みになった。
だから毎日の傷害にも耐える事が出来た。
(イジメに合うのはキツイ!でも独りじゃない。
一緒に頑張ろう。)
心の中でそう美幸に言っていた。
もしかしたら彼女もそう思っていたかもしれない。
もはや確かめる事は永久に出来なくなってしまったが・・・。
季節は冬になり、受験シーズンがやって来た。
受験シーズンともなると流石にイジメをしてる場合じゃないのか、イジメに合う回数も減ってはいたが、イジメの濃度は濃さを増した。
俺と美幸は元々頭が良く、すんなり受験をパスする事が出来た。
あと少しで中学生活も終わる。
俺たちのイジメ抜かれた三年間ともおさらばし、新しい生活をスタートさせよう。
そう心から思っていた。
そんな矢先に事件は起きた。
ある日、中学を仕切っていた不良グループに呼び出された。
「おう、爆拳!今日19時にいつもの公園に来いや」
グループのリーダーが言った。
不良グループのリーダーの名前は諸見里 裕也(もろみざと ゆうや)。
彼は中学生ながら身長が高く180を超える大柄の男で、体重も90は超えていた。
他に下っ端の佐藤と鈴木がいた。
佐藤はすきっ歯で、鈴木はタラコ唇だった。
この二人は諸見里のコバンザメで諸見里が居なければ何も出来ない雑魚だった。
(またか!)
俺はそう思った。
俺はこいつらによく呼び出されては暴行を受けていた。
奴らは喧嘩慣れしており、容赦なく殴ってきたが、俺はその度に耐えた。
俺は諸見里に言われた時刻に中学校の近くにある寂れた公園に行った。
この公園は利根川沿いにある公園で、風車小屋が立っており、子供が遊ぶ為の遊具と休憩の為の東屋も立っている立派な公園なのだが、手入れがされてなく荒れ果てていて、浮浪者が1人住み着き、まさに廃公園だった。
公園の駐車場に着いた俺は自転車を駐輪場に停め、公園の奥へと歩いて行った。
受験シーズンともなると流石にイジメをしてる場合じゃないのか、イジメに合う回数も減ってはいたが、イジメの濃度は濃さを増した。
俺と美幸は元々頭が良く、すんなり受験をパスする事が出来た。
あと少しで中学生活も終わる。
俺たちのイジメ抜かれた三年間ともおさらばし、新しい生活をスタートさせよう。
そう心から思っていた。
そんな矢先に事件は起きた。
ある日、中学を仕切っていた不良グループに呼び出された。
「おう、爆拳!今日19時にいつもの公園に来いや」
グループのリーダーが言った。
不良グループのリーダーの名前は諸見里 裕也(もろみざと ゆうや)。
彼は中学生ながら身長が高く180を超える大柄の男で、体重も90は超えていた。
他に下っ端の佐藤と鈴木がいた。
佐藤はすきっ歯で、鈴木はタラコ唇だった。
この二人は諸見里のコバンザメで諸見里が居なければ何も出来ない雑魚だった。
(またか!)
俺はそう思った。
俺はこいつらによく呼び出されては暴行を受けていた。
奴らは喧嘩慣れしており、容赦なく殴ってきたが、俺はその度に耐えた。
俺は諸見里に言われた時刻に中学校の近くにある寂れた公園に行った。
この公園は利根川沿いにある公園で、風車小屋が立っており、子供が遊ぶ為の遊具と休憩の為の東屋も立っている立派な公園なのだが、手入れがされてなく荒れ果てていて、浮浪者が1人住み着き、まさに廃公園だった。
公園の駐車場に着いた俺は自転車を駐輪場に停め、公園の奥へと歩いて行った。
公園の中へ歩いて行くと「おう!爆拳」と公園の奥の東屋から諸見里の声がした。
俺は声の方に目を凝らすがこちらからでは見えなかった。
仕方なく更に奥へと歩いて行き、やがて東屋がぼんやりと見えてきた。
東屋の前まで行くとベンチに諸見里が足を広げて座っていた。
両脇に佐藤と鈴木。
下っ端らしい立ち位置だ。
そしてもう一人。
青柳美幸が諸見里の右側に顔を伏せたまま座っていた。
(何故美幸がここに?)
俺の脳裏に嫌な予感が走る。
「よう爆拳。よくきたな」
諸見里がそう言いながらセブンスターを口に咥え火を付けた。
「なに?俺に何か用なの?」
俺への暴行が要件である事は分かっていたが一応確認してみた。
「いやね!お前ら2人がデキてるって聞いたもんだから真相を確かめようと思ってさ」
ニヤニヤと下卑た笑みを浮かべながら諸見里が言った。
「デキてるもなにも俺は美幸と話をしたことすらないよ。諸見里君の勘違いじゃない?」
「げへへっげへへっ 隠す事はねーじゃねーか!お前らが出来てるって学校中の噂だぞ」
諸見里が言う。
下っ端の2人がニヤニヤと笑っている。
(こんな事をして何が楽しいのだろうか?しかも美幸まで巻き込んで)
俺はそう思っていた。
「それは単なる噂だよ。実際に話した事すらないんだから。もう帰っていいかな?親が心配する」
「まー待てよ。そんなに急いで帰らなくてもいいだろうがっ!ここは人影(ひとけ)のねー公園で今日はゲストも居るんだからよっ」
諸見里はそう言い美幸の乳房を鷲掴みにした。
「いや!やめてっ」
美幸が精一杯の声をあげた。
「おいっ!黙らせろ」
諸見里が言うと、下っ端の佐藤と鈴木が見事な連携で美幸の口を佐藤が抑え、両腕を鈴木が押さえつけた。
俺は、その光景を見つめながら恐怖の為動けなくなっていた。
俺は声の方に目を凝らすがこちらからでは見えなかった。
仕方なく更に奥へと歩いて行き、やがて東屋がぼんやりと見えてきた。
東屋の前まで行くとベンチに諸見里が足を広げて座っていた。
両脇に佐藤と鈴木。
下っ端らしい立ち位置だ。
そしてもう一人。
青柳美幸が諸見里の右側に顔を伏せたまま座っていた。
(何故美幸がここに?)
俺の脳裏に嫌な予感が走る。
「よう爆拳。よくきたな」
諸見里がそう言いながらセブンスターを口に咥え火を付けた。
「なに?俺に何か用なの?」
俺への暴行が要件である事は分かっていたが一応確認してみた。
「いやね!お前ら2人がデキてるって聞いたもんだから真相を確かめようと思ってさ」
ニヤニヤと下卑た笑みを浮かべながら諸見里が言った。
「デキてるもなにも俺は美幸と話をしたことすらないよ。諸見里君の勘違いじゃない?」
「げへへっげへへっ 隠す事はねーじゃねーか!お前らが出来てるって学校中の噂だぞ」
諸見里が言う。
下っ端の2人がニヤニヤと笑っている。
(こんな事をして何が楽しいのだろうか?しかも美幸まで巻き込んで)
俺はそう思っていた。
「それは単なる噂だよ。実際に話した事すらないんだから。もう帰っていいかな?親が心配する」
「まー待てよ。そんなに急いで帰らなくてもいいだろうがっ!ここは人影(ひとけ)のねー公園で今日はゲストも居るんだからよっ」
諸見里はそう言い美幸の乳房を鷲掴みにした。
「いや!やめてっ」
美幸が精一杯の声をあげた。
「おいっ!黙らせろ」
諸見里が言うと、下っ端の佐藤と鈴木が見事な連携で美幸の口を佐藤が抑え、両腕を鈴木が押さえつけた。
俺は、その光景を見つめながら恐怖の為動けなくなっていた。
この作品のキーワード
設定されていません
この作家の他の作品
表紙を見る
バイク事故に遭い、乳輪を無くした友達の生霊に呪われてしまった俺たち。
俺たちは友達の乳輪を見つける事が出来るだろうか!?
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…