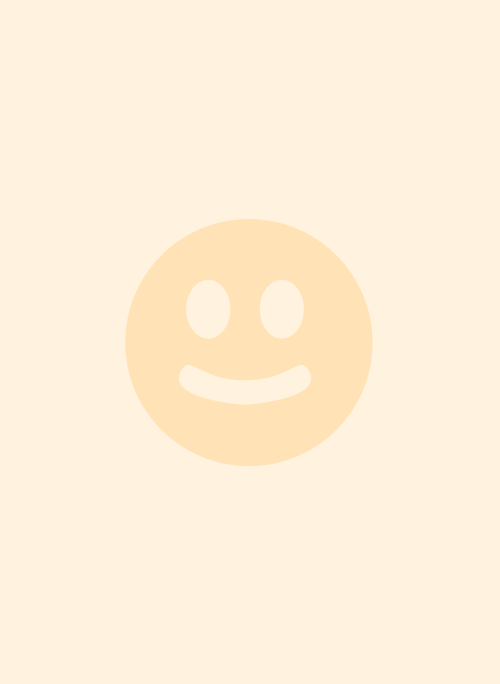俺の名前は弾間爆拳(だんまばっけん)。
爆発する拳と書いて爆拳だ。
大抵の人は俺の名前を見ると凶暴そうなイメージを抱く。
そのイメージは間違ってはいない。
俺はすぐに手を出すタイプの人間である。
だが、根っからの悪党ではない。
少し俺について説明しよう。
年齢は18歳。
身長175センチ 体重65キロ。
体脂肪、わずか8パーセント。
良く鍛えた筋肉の上にわずかに脂肪を付けてある。
スイマーの様な体型だ。
だが、スイマーではない。
れっきとした武道家だ。
正確に言えば柔術家である。
武道家は打撃に耐えねばならない。
だからボクサーの様に脂肪のない体にしてしまうと打撃に耐えられなくなる。
ボクサーは所詮スポーツであり、決まった階級で戦うが、俺のは無差別だ。
故に体重65キロ、体脂肪8パーセント。
これが俺のベスト。
以下でも以上でもダメだ。
目は奥二重で、髪の毛はサラサラのストレート。
髪の毛は短くカットしてある。
肌の色は白く、中々のイケメンである。
芸能人で言うなら小栗旬の様な甘い顔立だ。
この顔のお陰で女には困らない。
俺は生まれつき持病があり、激しい運動ができない。
紫外線にも弱く、炎天下の中外にいるとすぐにバテてしまう。
心身に多大な負荷が掛かると呼吸が苦しくなり、顔が干からびたカエルの様に皺がれてしまう。
この持病のせいで幼少期はイジメにあわされたものだ。
幼少期の俺は体が弱く、虚弱体質だった。
冬になると毎年マイコプラズマ肺炎になり、何日も寝込んだ。
夏になれば暑さの為、目眩を起こし、すぐに倒れたりした。
そういう状態になると決まって顔が皺がれて、爺さんの様な顔になってしまう。
それを周りの奴らは気味悪がったし、面白がった。
小学校時代の俺は、この特異体質のお陰で独り孤独を味わっていたし、またイジメの対象にもなった。
中学生になると孤独もイジメも激しくなっていき。
中学三年にもなると、イジメのレベルではなくなっていた。
もはや『傷害』である。
俺が孤独と傷害に耐えながら中学の三年生を過ごしていた頃、同じ学年の同じクラスに、俺と同じ様に孤独と傷害に耐えていた女の子がいた。
名前は青柳美幸(あおやぎみゆき)。
美幸と言う名前とは逆に不幸な毎日を送っていた。
彼女は小柄でストレートな艶のある髪をし、顔も可愛らしい子だった。
何故に彼女はイジメの対象になったのだろう?
それは親が熱心な宗教家で、同級生の家に布教活動をして回っていたからである。
「お前の母親がまたウチに宗教勧誘に来たぞ!迷惑なんだよテメーはっ」
そんな言葉が良く教室に響いた。
俺と美幸は同じクラスだったが、一度も会話を交わした事がなかった。
お互いにイジメにあっていたし、下手に仲良くなろうものならイジメが更に炎上しかねない。
だから俺は彼女と話そうとはしなかったし、向こうも俺には近寄らなかった。
イジメについて先生に一度だけ相談した事があった。
だけど、先生は「イジメに合う方にも問題があるんじゃないのか?」
そう言い、深く踏み込まなかった。
親には頼らない。
俺の親は片親で母親しかいない。
女手一つで子供を養うのは大変だ。
これ以上、母親の負担にはなりたくない。
それが物心ついた頃からの俺のプライドであった。
だからこそ美幸の存在は俺の励みになった。
だから毎日の傷害にも耐える事が出来た。
(イジメに合うのはキツイ!でも独りじゃない。
一緒に頑張ろう。)
心の中でそう美幸に言っていた。
もしかしたら彼女もそう思っていたかもしれない。
もはや確かめる事は永久に出来なくなってしまったが・・・。
季節は冬になり、受験シーズンがやって来た。
受験シーズンともなると流石にイジメをしてる場合じゃないのか、イジメに合う回数も減ってはいたが、イジメの濃度は濃さを増した。
俺と美幸は元々頭が良く、すんなり受験をパスする事が出来た。
あと少しで中学生活も終わる。
俺たちのイジメ抜かれた三年間ともおさらばし、新しい生活をスタートさせよう。
そう心から思っていた。
そんな矢先に事件は起きた。
ある日、中学を仕切っていた不良グループに呼び出された。
「おう、爆拳!今日19時にいつもの公園に来いや」
グループのリーダーが言った。
不良グループのリーダーの名前は諸見里 裕也(もろみざと ゆうや)。
彼は中学生ながら身長が高く180を超える大柄の男で、体重も90は超えていた。
他に下っ端の佐藤と鈴木がいた。
佐藤はすきっ歯で、鈴木はタラコ唇だった。
この二人は諸見里のコバンザメで諸見里が居なければ何も出来ない雑魚だった。
(またか!)
俺はそう思った。
俺はこいつらによく呼び出されては暴行を受けていた。
奴らは喧嘩慣れしており、容赦なく殴ってきたが、俺はその度に耐えた。
俺は諸見里に言われた時刻に中学校の近くにある寂れた公園に行った。
この公園は利根川沿いにある公園で、風車小屋が立っており、子供が遊ぶ為の遊具と休憩の為の東屋も立っている立派な公園なのだが、手入れがされてなく荒れ果てていて、浮浪者が1人住み着き、まさに廃公園だった。
公園の駐車場に着いた俺は自転車を駐輪場に停め、公園の奥へと歩いて行った。
公園の中へ歩いて行くと「おう!爆拳」と公園の奥の東屋から諸見里の声がした。
俺は声の方に目を凝らすがこちらからでは見えなかった。
仕方なく更に奥へと歩いて行き、やがて東屋がぼんやりと見えてきた。
東屋の前まで行くとベンチに諸見里が足を広げて座っていた。
両脇に佐藤と鈴木。
下っ端らしい立ち位置だ。
そしてもう一人。
青柳美幸が諸見里の右側に顔を伏せたまま座っていた。
(何故美幸がここに?)
俺の脳裏に嫌な予感が走る。
「よう爆拳。よくきたな」
諸見里がそう言いながらセブンスターを口に咥え火を付けた。
「なに?俺に何か用なの?」
俺への暴行が要件である事は分かっていたが一応確認してみた。
「いやね!お前ら2人がデキてるって聞いたもんだから真相を確かめようと思ってさ」
ニヤニヤと下卑た笑みを浮かべながら諸見里が言った。
「デキてるもなにも俺は美幸と話をしたことすらないよ。諸見里君の勘違いじゃない?」
「げへへっげへへっ 隠す事はねーじゃねーか!お前らが出来てるって学校中の噂だぞ」
諸見里が言う。
下っ端の2人がニヤニヤと笑っている。
(こんな事をして何が楽しいのだろうか?しかも美幸まで巻き込んで)
俺はそう思っていた。
「それは単なる噂だよ。実際に話した事すらないんだから。もう帰っていいかな?親が心配する」
「まー待てよ。そんなに急いで帰らなくてもいいだろうがっ!ここは人影(ひとけ)のねー公園で今日はゲストも居るんだからよっ」
諸見里はそう言い美幸の乳房を鷲掴みにした。
「いや!やめてっ」
美幸が精一杯の声をあげた。
「おいっ!黙らせろ」
諸見里が言うと、下っ端の佐藤と鈴木が見事な連携で美幸の口を佐藤が抑え、両腕を鈴木が押さえつけた。
俺は、その光景を見つめながら恐怖の為動けなくなっていた。