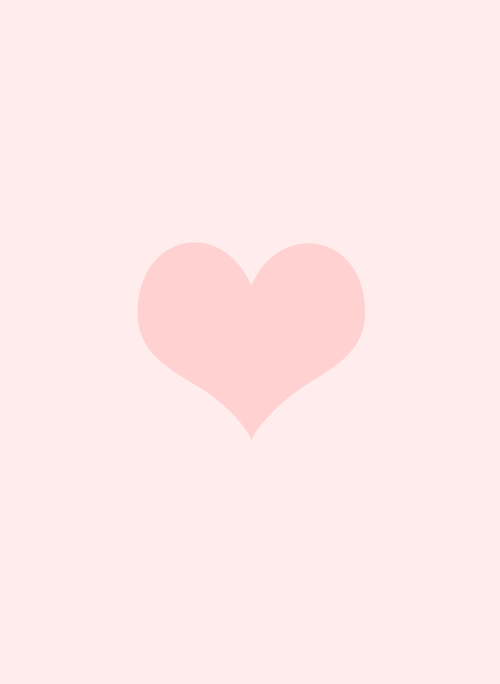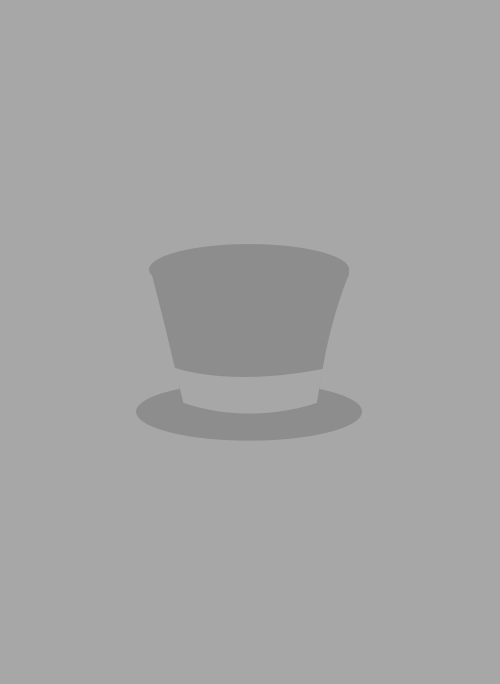そう思って、私は用意された料理を全部胃袋に詰め込んだ。
食事が終わるとみんなで片付けをした。
朔が食器を運んで、おばあさんがそれを洗って、私は卓を綺麗に拭いてから三人分のお茶を淹れた。
「ハナさん、お客様なのに手伝って貰っちゃってごめんなさいね。
でもとても助かったわ、ありがとう」
おばあさんは私が淹れたお茶を飲みながら労いの言葉をかけてくれた。
「いえ、こちらこそ急にお邪魔して朝ごはんまでご馳走してもらって。
あの、ありがとうございました」
「ハナー、このお茶苦いよー?」
静かな空間を突如破壊する朔の声に思わず汚い視線を投げかけそうになる。
「朔」
だけどおばあさんの手前そんなことはできない。
私は出かかった汚い部分を瞬時に隠してできるだけ落ち着いた声で抗議する。
「実は私、日本茶って初めて淹れたんだ。だから許してね」
自分でも気持ち悪くなるくらい、よそ行き用のトーンで話せた。
朔には不本意ながらも汚い部分も冷たい部分も弱い部分も見られているからなんだか少し照れくさかったけど、そこは一食の恩があるおばあさんの手前、何年も重ねてきた薄っぺらい声を出すのは至極簡単だ。
「ハナが変!」
なのに、朔は私のことを変だと言って笑い出す。
自分でも変だと思うけど、気持ち悪いと思うけど、それでも朔に笑われるとなんかムカつく。
だから。
もし私と朔の間に次があったら。
私は朔を一発殴ってやろうと思う。
とか思っていたらその次は速攻でやってきた。
朝ごはんを食べて、食後のお茶まで飲ませてもらって、さてどこに行こうかと考えを巡らせていたら朔は当たり前のように声をかけてきた。
「ハナ、この後は何したい?」
「え?何って何?」
「難しい質問だね。
何ってものはないんだけどさ、ハナはきっとまだお家には帰らないんでしょ?」
そっか。
朔には話してしまってた。
母親が出て行ったことを。
いまの私には居場所がないってことを。
だけど、
「帰るよ。散歩でもしてゆっくり帰る」
これ以上付きまとわれるのはごめんだ。
正直言ってこの場所はとても居心地がいい。
朔の隣はとても楽。
だけどそれに慣れてはいけないのだ。
私はこれから先を強く生き抜いていかなくちゃならない。
その為にはなるべく他人と距離を置いて、寄りかかるとか頼りにするとか信じるとか。
そう言った不毛なものとは縁を持たないようにしなくちゃいけない。
「そっか。じゃあ引き止められないね」
朔は言葉とは裏腹に嬉しそうに微笑みながらそんなことを言う。
出会った時から感じていたことだけど、朔ってやっぱり変なやつだ。
だって、朔が幸せそうで嬉しそうな笑みを浮かべるタイミングは他の人とはかなりずれている。
「あら、もう帰るのかい?残念だねぇ」
「はい。あの本当にごちそうさまでした」
「またいつでもいらっしゃいな。
歳だからたいしたおもてなしできないけど、ハナさんならうちはいつでも大歓迎だからね」
「ありがとうございます」
ここに来ることはきっともうない。
だけどそれをわざわざ言う必要はないし、そもそもおばあさんの言葉は社交辞令だろう。
それに素直に返事をするのも野暮ってもんだ。
「本当に突然お邪魔しました」
急な訪問にも嫌な顔一つせず、ご飯まで食べさせてくれたおばあさんに挨拶をして朔の家を後にする。
太陽はすっかり高い位置に移動していて、だけどやっぱり外は全然寒い。
その中を目的地もなくダラダラと歩き進める。
来るときは声をかけてきたお年寄りたちは畑仕事を終えたのかいまは外にはいなかった。
歩いていると誰かしらとすれ違いはしたけど誰も他人で、言葉を交わすことはなかった。
それが私の普通。
誰とも言葉を交わさないし誰も私に見向きもしない。
なのに……。
「日が出てても外はやっぱり寒いねー」
「あ、あの人近所のお兄さんだ」
「ハナ、見て見て。面白い形の雲!」
「ハナ?ハナはどこに向かって歩いてるの?」
空耳だと思い込もうとしたけど無理!
「ねえ、うるさい」
「あれ?さっきまでは名前で呼んでくれてたのに」
ああ、もう!
「朔、どうしてついて来るの」
「僕も散歩」
「じゃあ私はこの道を右に曲がるから、朔は左に曲がって。
じゃあね。さようなら」
「ふふ。分かった。じゃあハナ。またね」
「はいはい」
私は二股に分かれた道を右に曲がってさらに歩き進める。
もう朔の声は聞こえてこなくて、やっと解放されたのだと安堵する。
この作家の他の作品
表紙を見る
市瀬 コウ。
高校二年生。女。
飯田 モトハル。
高校二年生。男。
鈴原 エイ。
高校一年生。男。
思春期の高校生三人を軸に"人を好きな気持ちとは"についてストリート展開していきます。
きっと誰しもが悩んだことがある悩みの、なにかヒントになれますよう執筆して参ります。
※なお、タイトルはホラーチックですがおばけ幽霊の類は登場致しません。
2019.1.26
武井ゆひ
表紙を見る
都心のとある下町にひっそり佇むとある喫茶店。
そこの店主は少し変わり者。
そこに来るお客さんも変わり者。
偶然見つけたそのお店で、私が出会うことになる出来事の数々とは.......。
宜しければ御一読いただけますと嬉しいです。
2019.1.25~完
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…