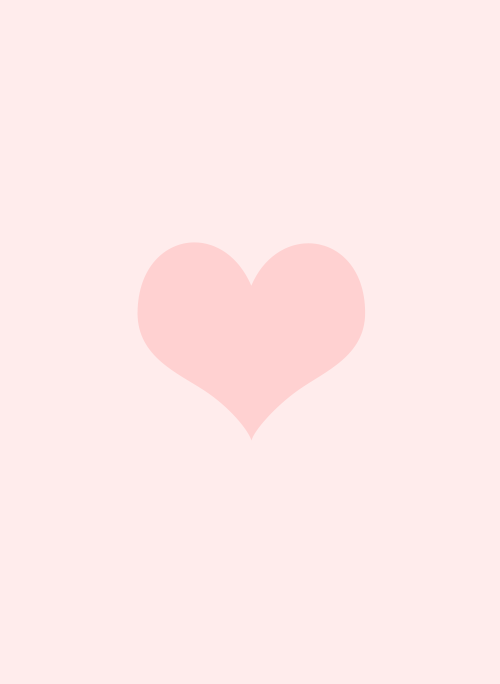「見上げればあの空浮かぶ雲
手を伸ばしても届かない」
どんなに届かなくたって。
「駆け足で跳ねても追いつけない
そんな遠いあの日の記憶」
今はもう、会えなかったとしたって。
「閉まっていた思い出が扉をノックして
“ 早くきかせて ” “ 歌わないよ ”
“ キミはいつも ” “ ひとりでいい ”
こだまする掛け合いにまた胸が痛む」
それでも、伝えたい気持ちがある。
「傷つくなら逃げたいなら もうこのままで構わない
光と影 夢と涙 手を取ることを拒んで」
私が今、できることは。
「永遠なんて誓えないよ 時間は過ぎゆくばかり
ねえ、キミはどうして?
本音はどこにあるの」
この空に向かって、声を響かせることだけだ。
曲が終わり、客席が静かになる。
それとは反対に、私の鼓動は激しくなる。
そして次の瞬間、わっと歓声があがった。
客席に大きなどよめきが溢れる。
良かった……。
私、歌えたんだ。
こんなに大勢の人の前で、また思いを届けられたんだ。
ねぇ、きっと聴いていたよね?
お姉ちゃん─────。
それから3曲を歌いきり、私達のライブは終了。
終わりを告げる爽快感は、心の中を一直線に駆けた。
次々とモチベーションが上がっていった私達は、少ししか合わせていないけれど息がぴったりだったと思う。
最後の方は、きっと見ている人まで巻き込んで盛り上がれていた。
そんな自信が湧いてくるのはどうしてだろうか。
「お疲れ様、陽葵ちゃん!」
舞台裏に戻るとすぐに駆け寄ってきたのは、日々ちゃん。
自分のことのように心配しながら、裏方の仕事をこなしていたらしい。
「すごかった」
「本当にいい歌だったよ!」
「音中さんなら大丈夫だって、思ってたぜ」
そう言って微笑んでくれるのは、一緒にバンドを組んでいた鶴本くん、月野さん、米田くんだ。
月野さんはバンドをしたいと言った張本人でもあるため、私が代理でボーカルを務めることになって責任を感じていたようだ。
あまり話したことはなかったけれど、みんな悪い人ではなさそう。
演奏中も後ろから私を支えてくれた。
「あの、音中さん……」
そんな中、今にも泣きそうな顔でこちらへ向かってきたのは相川さんだ。
まだフラフラしているようだけれど、本番前よりもスッキリとした顔をしている。
「歌ってくれてありがとう。
素敵な歌でし……った」
そう言っていきなり泣き出した彼女を、慌ててなだめる。
いつの間にか、私の制服にも涙が滲んでいた。
ありがとう、だなんて。
あまり言われ慣れていない言葉に少し胸が高鳴った。
「大丈夫です。
私こそ……ありがとうございます」
彼女はきっと、この言葉の意味は分からないだろうけれど。
相川さんのおかげで私は前に進めた。
彼女に歌ってほしかった。
でも、自分の思いをこうして他の人に伝えられたことは素直に嬉しい。
不格好に微笑むと、相川さんは私にしがみついて。
「音中さん、大好き!」と顔をすり寄せる。
その様子を見て、みんなで笑った。
空気は和やかなまま、私達の発表は幕を閉じた。
それから、日々ちゃんと一緒に文化祭を回って楽しんだ。
こんなにも親切な友達がいてくれることが、とてもありがたい。
錦戸くんはついてこようと必死に懇願していたけれど、最終的に米田くんと回ることになったらしい。
心から笑えていて、もう何も心配することなんてないと思っていた。
そんな幸せもつかの間、私をさらなる悲劇が襲う─────。
文化祭が終わった。
帰るときには文化祭実行委員として、そして代理ボーカルとして拍手に包まれた。
改めて、あの歌声がクラス全員に。
それどころか学校中の人に聴かれていたと思うと照れくさい。
片づけは明日行うため、今日はもう解散となった。
日々ちゃんや錦戸くん、今日仲良くなったみんなと一緒に話しながら廊下を歩く。
ちなみに、相川さんを見下していた女子ふたりは、ライブが終わった後に謝ってきた。
私に対しては、『すごい歌だった』『あんなこと言ってごめんなさい』と。
相川さんには、『可愛いから嫉妬していただけなの!』『本当に今までごめんね』と。
頭を下げて謝っていた。
その剣幕に圧倒されたのか、少し引き気味だった相川さんも『もう大丈夫だよ』と答えていた。
その後のことは知らないけれど、さっきは親しげに話していたからきっと関係は修復したんだと思う。
この文化祭を通して、少しでもクラスが一丸となれたなら。
私はそれだけでも委員を引き受けたかいがあった。
そんなことを考えている間にみんなは前へ進んでいたらしく。
「陽葵ちゃーん、早く早くー」
と呼ぶ日々ちゃんの声が聞こえた。
他のみんなも振り向いて、私を待っている。
────行かなきゃ。
彼女の方へ駆け寄ろうとすると、後ろから手首を掴まれた。
「え……?」
そこにいたのは、天音先輩。
なぜか真剣な目で私を捉えている。
どうして?
疑問だけが私の頭の中に浮かぶ。
「あ、ごめんね。
音中さんのこと、借りてもいいかな?」
そう言いながらみんなの前に歩み寄ると、私の手首をグッと掴みながら綺麗すぎる作り笑いを浮かべる。
突然の生徒会長の登場に驚いたのか、みんなは私に手を振ってそそくさと帰っていった。
「……なんですか?」
わざわざ他の人がいるときに呼び止めたということは。
本当に大切な用事があるのだろう。
今まで友達と一緒にいるときに話しかけてきたことなんて滅多になかったのに。
というか、私と知り合ったことは誰にも教えていないと思っていた。
心のどこかでそう安心しきっていた。
「お前、歌えるのか」
氷のように冷たい目。
そんな視線を向けられたことは今までにない。
一体何があったの?
何が悪いって言うの?
「……はい」
静かに答えると、天音先輩はどんどん近づいてくる。
え、何?
考えが回らないうちに、今おかれている状況を悟った。
これは、俗にいう壁ドン。
けれど甘い雰囲気なんかではなく、むしろ重い空気が流れている。
「陽葵」
「え……」
名前で呼ばれた理由はわからない。
そんなに苦しそうな表情をする理由もわからない。
でも確かに助けたいと思った。
手を差し伸べたいと思った。
それだけで、私が近づきたいと思ったことは説明がつく。
そんなに儚い彼を、守りたいと感じた。
「俺は、お前を許さない」
私が、悪いんだろうか。
あの日の言葉と、目の前にいる先輩が重なる。
────『俺の大切な人を奪ったお前を、一生許さない』
きっと、違う。
そんなわけがない。
そう思っているのに、体が動かない。
何しているの。
こんな風に固まっていたら、彼の思うツボじゃない。
ほら、早く何か言って誤魔化さなきゃ。
そうは思うけれど、体は一向に動いてくれない。
だって私は、彼のこの目を知っている。
「お前、似ているんだな。
“ お姉さん ” に」
お姉、さん……?
その言葉は、私の胸に決定的な痛みを感じさせる。
ねぇ、お願い。
やめてよ。
もうあの日のことにはフタをしたの。
「バレていないとでも思っていたか?」
ドクン、ドクン。
嫌な汗が止まらない。
これ以上、ここから先の言葉を聞いてはいけない。
一瞬で危険を察知したにも関わらず、やっぱり体は硬直している。
「天音奏汰。
この名前、忘れたとは言わせねえ」
もしかして……。
そう思っていたことが、確信に変わっていく。
そっか。
だから天音先輩も、弾かないの?
────『陽葵、助けて……っ』
「いやぁぁぁっ……!」
私の意識は、そこで途切れた。
この作家の他の作品
表紙を見る
本を読むことが好きな日野くんは。
なぜか今日も
私が持っている恋愛小説を読みます。
「……変なやつ」
「七草さんって、こういうことされたいの?」
「七草さんは、俺のだから」
口数は少ないのに。
その言葉に、行動に。
全てに、私の心はつかまれる。
ねぇ、なんでですか?
今、何を思ってますか?
私、日野くんの心が知りたいです。
ポジティブな真面目ちゃん
七草弥生(ななくさやよい)
×
口下手な隠れイケメン
日野大雅(ひのたいが)
☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆.。.:*・°☆
2019年6月18日~
野いちご編集部オススメ作品に掲載されました!
2019年6月20日
野いちご総合ランキングにランクイン!
本当にありがとうございます♡
表紙を見る
「大丈夫」
だなんて、なんて儚い言葉だろう。
今も君は俺のために。
苦しい気持ちを押し殺して
泣いているというのに。
ねぇ、この出会いは間違いだったかな。
恋なんてしなければ良かったかな。
後悔しても、泣いても、
明日は必ずやってくる。
また立ち上がることができれば
きっと笑えるから。
だから君も、最後に笑顔を見せてよ。
愛して、愛されて、それでも繋がらない心。
この恋の形は歪だった。
でも、誰もが懸命に恋をして、
不器用に今を走り続けていた。
これは、絶対に忘れられない、
俺の桜色の思い出。
表紙を見る
俺の住む世界には、いろいろな人がいる。
「よくここに来るの。
ひとりになりたいときにね」
傷つき、誰にも相談せずに、
自分を守ろうとする人。
「俺は、逃げてばかりなんだ……」
親とぶつかり、
自分の気持ちを見失いかけている人。
「アイツは知らねーよ。
言わないつもり」
誰かの幸せのために、自分の心を削って
守り抜こうとする人。
「……俺、ずっと後悔していた」
誰かを救うための優しい嘘で、
相手を逆に傷つけてしまった人。
「お前なんて……っ!
死んじゃえばいいのに!!」
そう言って─────俺の前から姿を消した人。
そして……。
「もう、わかんねーや……」
見えない過去に怯えて、
今日を歩けないでいる人。
ここにいる全員が “ 嘘つき ” で。
誰よりも懸命に、甘酸っぱい
青春時代を過ごそうとしていた。
だから、何があっても
神様のイタズラなんかに
負けちゃダメなんだ。
ヒミツの夜、蛍の光の中で。
俺達の嘘は全て、真実と交わる。
この作品を見ている人にオススメ
読み込み中…